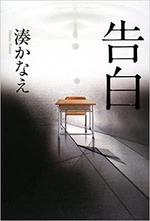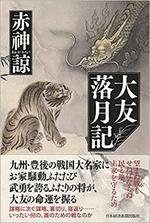 豊後の戦国大名・大友氏の「二階崩れの変」(1550年、天文19年)から6年、再び内紛・分裂の危機となる。当主・大友義鎮(後の宗麟)は、政より美と女に執着、とくに美貌となれば他の妻まで自らの正室や側室とした。家中の最高実力者の田原宗亀など一部の重臣たちが内政をほしいままにし、肥後方分の小原鑑元、"鬼"とあだなされる武将・戸次鑑連(後の立花道雪)などは、肥後や筑後・肥前の一部を平定して大友に服せさせていた。
豊後の戦国大名・大友氏の「二階崩れの変」(1550年、天文19年)から6年、再び内紛・分裂の危機となる。当主・大友義鎮(後の宗麟)は、政より美と女に執着、とくに美貌となれば他の妻まで自らの正室や側室とした。家中の最高実力者の田原宗亀など一部の重臣たちが内政をほしいままにし、肥後方分の小原鑑元、"鬼"とあだなされる武将・戸次鑑連(後の立花道雪)などは、肥後や筑後・肥前の一部を平定して大友に服せさせていた。
義鎮の近習頭・田原民部は謀略をめぐらし、本書の主人公である同じく近習の吉弘賀兵衛(二階崩れの変で失脚した吉弘鑑理の長子)は振り回される。後世に「氏姓の争い」とも「小原鑑元の乱」とも呼ばれるこの大乱は、なぜ起きたのか。肥後を善政によって蘇らせた小原鑑元はなぜ挙兵に追い込まれたのか。相次ぐ謀略、裏切り、寝返りのなかでの武将の苦哀と覚悟を描く。胸に迫る力作。
乱を鎮定した戸次鑑連が「この戦はいったい何のための戦だったのか」との吉弘賀兵衛のつぶやきに語る。「戦はしょせん人と人との醜い殺し合いにすぎぬ。正義じゃ何じゃと理由をつけてみたところで、双方に言い分はある。正しい戦なんぞありはせぬ。あるのは、いかなる戦でも勝たねばならぬという真理だけじゃ。このたび神五郎(小原鑑元)は生きるために兵を挙げた。わしは大友を守るために戦うた。正邪はない。あるのは勝敗だけじゃ」「神五郎は大友への忠義を貫いて死んだ忠臣じゃ。己が生と死をもって富める肥後の地と民と二万の精兵をそっくり大友に遺したではないか。月は落ちても、天を離れず。神五郎は大友に叛する己が運命に打ち克ったのじゃ。むろん、世の者は知るまい。されど天と、わしと賀兵衛が真実を知っておる」・・・・・・。「戸次鑑連は鬼だ。たしかに苛烈な鬼だが、情にあふれた鬼だと賀兵衛は思った」・・・・・・。
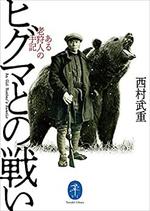 「私の叔父(北海道石狩郡当別村)が狩猟家であったので、私の家(札幌郡篠路村)へ訪れると、大きなガンやカモ、ウサギなどをおみやげに時々持ってきた。私はおとなになったら狩人になろうと思った」「徴兵検査がすみ、満21歳で狩猟免状を受けた」「私はついに、ヨローウシの出湯に魅せられて腰を据え、思う存分未開の林野内に鳥獣を追った」「私は、明治44年より今日に至るまでほとんど一生を、未開の森谷渓谷を探して、狩猟と釣りに費したようなもので、最早人生の終着駅にあり、気息奄奄たる老爺になってしまった。この本にあるものは、大正から昭和にかけての若き時代の思い出の昔話である」――。100年前の北海道の原野を縦横に駆け巡り、狩猟に釣り、温泉開発、鉱山発掘などフロンティアマンとして生き抜いてきた西村武重(1892年明治25年生まれ、1983年死去)が、1971年に上梓した代表作「ヒグマとの戦い――ある老狩人の手記」。養老牛温泉がある現在の中標津町が1916(大正5)年には2戸8名だったという。孫にあたる現町長・西村穣氏が「100年前の根室原野を駆け巡った祖父の冒険談の楽しさが伝わると幸いです」と語る。2021年7月5日文庫化。
「私の叔父(北海道石狩郡当別村)が狩猟家であったので、私の家(札幌郡篠路村)へ訪れると、大きなガンやカモ、ウサギなどをおみやげに時々持ってきた。私はおとなになったら狩人になろうと思った」「徴兵検査がすみ、満21歳で狩猟免状を受けた」「私はついに、ヨローウシの出湯に魅せられて腰を据え、思う存分未開の林野内に鳥獣を追った」「私は、明治44年より今日に至るまでほとんど一生を、未開の森谷渓谷を探して、狩猟と釣りに費したようなもので、最早人生の終着駅にあり、気息奄奄たる老爺になってしまった。この本にあるものは、大正から昭和にかけての若き時代の思い出の昔話である」――。100年前の北海道の原野を縦横に駆け巡り、狩猟に釣り、温泉開発、鉱山発掘などフロンティアマンとして生き抜いてきた西村武重(1892年明治25年生まれ、1983年死去)が、1971年に上梓した代表作「ヒグマとの戦い――ある老狩人の手記」。養老牛温泉がある現在の中標津町が1916(大正5)年には2戸8名だったという。孫にあたる現町長・西村穣氏が「100年前の根室原野を駆け巡った祖父の冒険談の楽しさが伝わると幸いです」と語る。2021年7月5日文庫化。
とにかく凄まじい。開拓時代に最も恐ろしかったヒグマ。打ち続くヒグマとの死闘。戦って命を落とした若者。組みついてヒグマが若者を弾防けにして撃てない。急所をはずした時のヒグマの暴れる姿。そして極寒、豪雪、猛吹雪との命がけの戦い。一転して晴れるや自然の美しさと清浄なる空気、アイヌの酋長である榛幸太郎、滝を登る何百尾ものサケやマス、大ヤマベ釣り、ガンやキネズミ・キツネ狩り・・・・・・。
異次元の壮絶な開拓時代に体当たりされた思いだ。
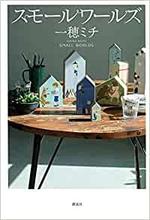 現代社会にありうる「ままならない現実」「内に抱える"秘密"」を鋭角的に、しかも優しく描き出す6篇。それぞれが全く違う状況・場面を鮮やかな文体でスパッと描き、爽快感まで漂う。
現代社会にありうる「ままならない現実」「内に抱える"秘密"」を鋭角的に、しかも優しく描き出す6篇。それぞれが全く違う状況・場面を鮮やかな文体でスパッと描き、爽快感まで漂う。
第1話「ネオンテトラ」――夫婦円満を装いつつも欝々と不妊に悩む相原美和は、家庭に恵まれない中学生の男子・笙一と出会う。孤独な二人は逢瀬を続けていくが・・・・・・。第2話「魔王の帰還」――鉄二は平和な高校生活を送っていたが、188cmもあり、"魔王"とも称されていた恐ろしい姉ちゃん(真央)が出戻ってきた。「あんたを嫁にもらおうなんて人類は後にも先にもきっとあの人だけよ」といわれて結婚。夫の勇と離婚話が出ているようだが、その裏にある"秘密""真相"とは・・・・・・。絶妙で面白い。
第3話「ピクニック」――初孫の誕生に喜ぶ祖母とその娘家族。だが、生後10か月のその初孫・未希が娘・瑛里子の留守中、突然不慮の死を遂げる。そして祖母・希和子が逮捕され、途方に暮れる。その真相はいったい・・・・・・。第4話「花うた」――これも不思議な物語。兄を殺され、天涯孤独となった新堂深雪は、弁護士に勧められて服役中の「兄を殺した加害者」の向井秋生に手紙を送る。漢字も書けなかった秋生が、手紙をやり取りするなかで、人間としても成長して、二人の心は次第に結びついていくのだった。罪とは、罰とは、反省とは、償いとは、そして赦しとは・・・・・・。
第5話「愛を適量」――中学教師の慎悟は、ある事件を境に教師としての情熱や意欲などとっくに涸れ果て酒びたりの"死んだ"ような毎日だった。そんな時、別れた妻が引き取っていた娘・佳澄が突然、戻ってきた。しかも男のようになって、「俺トランスジェンダーでFtMだって」というのだ。とまどいながらも親としての愛を注ごうとするが・・・・・・。またも過剰な押し付けがましい愛となって・・・・・・。愛の"適量"とは・・・・・・。第6話「式日」――高校時代から友達の少なった仲良しの先輩と後輩。その後輩から父親が死んだので、葬式に出てほしいと頼まれる。葬儀への道中、大切なことも言えずに別れてしまった二人の間の心中が語られていくことに・・・・・・。
いずれも巧妙な「えっ」と驚くストーリーの展開を見せつつ、心の中に潜む「秘密の芯」を探り当てていく。重い話が軽妙でユーモラスに感じさせる傑作。
 「先進国を超えるか、監視社会の到来か」が副題。デジタル技術の進展・加速化が、世界的に展開され、新興国・途上国を経済だけでなく、社会や政治にも大きな地殻変動をもたらした。変化は激しく、中国、インド、東南アジア、アフリカ諸国は、いまや最先端技術の"実験場"と化し、決済サービスやスーパーアプリでは、先進国を凌駕する勢いだ。従来の、先進国をキャッチアップして"履行型"で進むのではなく、明らかに"飛び越え型"展開だ。新興国がどうリスクを抱えているか、課題は何か、雇用はどうなるのか、中国が輸出する監視システムによる国家による取り締まり強化にどう立ち向かうか。可能性とリスクを追いつつ、デジタルを巡る世界の今日的な構造と問題点を、各国の現地点を探りつつ剔抉する。世界の変化が鮮やかに描かれ、"デジタル敗戦"とも言われる日本の課題とめざす方向性が浮き彫りにされる。大変刺激的な力作。
「先進国を超えるか、監視社会の到来か」が副題。デジタル技術の進展・加速化が、世界的に展開され、新興国・途上国を経済だけでなく、社会や政治にも大きな地殻変動をもたらした。変化は激しく、中国、インド、東南アジア、アフリカ諸国は、いまや最先端技術の"実験場"と化し、決済サービスやスーパーアプリでは、先進国を凌駕する勢いだ。従来の、先進国をキャッチアップして"履行型"で進むのではなく、明らかに"飛び越え型"展開だ。新興国がどうリスクを抱えているか、課題は何か、雇用はどうなるのか、中国が輸出する監視システムによる国家による取り締まり強化にどう立ち向かうか。可能性とリスクを追いつつ、デジタルを巡る世界の今日的な構造と問題点を、各国の現地点を探りつつ剔抉する。世界の変化が鮮やかに描かれ、"デジタル敗戦"とも言われる日本の課題とめざす方向性が浮き彫りにされる。大変刺激的な力作。
デジタルのもたらす世界の地殻変動と劇的変化を見せる新興国の可能性と脆弱性が示される。「2018年時点で世界人口78億人のうち半数超がインターネット・アクセスを得ている」「2030年までにアフリカ大陸全員がインターネット・アクセスを得るプロジェクトが始動した」「マレーシアで創業し、現在シンガポールに本社を持つグラブ――安全な"車(タクシー)"がなかったので、ライドシェアによって安全性と信用を得ようとした(日本の逆。新興国になかった信用をプラットフォームのもたらす信用に変えた)」「中国は現金や通販取引に対する不信をアリペイで解決した」「アフリカではケニアのM―PESAを筆頭に銀行口座は持たないがケータイを持つ人が通信会社の口座内にお金を預けるモバイル・マネーとして広げた(これもプラットフォーム企業による信用確保の取り組み)」「南アジアに広がるフリーランス経済(データ入力、文書作成等の業務)(国境を越えた業務委託の急増)」「携帯電話の爆発的普及(固定電話を飛び越える)(銀行も乗り越える)」「ラスト・ワンマイルは取りに来てもらう"菜鳥ステーション(アリババ)"で」「インドの個人認証と貧困層への直接給付(かつては社会保障補助金が中抜きされた)」――。ある意味では「後発性の利益(キャッチアップではなく飛び越す)」だ。そしてこれが「スーパーアプリ」としてタクシー配車から行政手続きまで行い、社会インフラとなる。そして「インドの閉鎖型工業化、開放型デジタル化戦略」と「中国の開放型工業化、閉鎖型デジタル化戦略」を採用する違いとなっている。「土台をつくり、後は競争に任せる」のがインドだ。
デジタル経済が成り立つためには3つの階層(レイヤー)がある。①最も基礎的な電話回線、送受信を支える設備と手順=プロトコルという物理層②最上層は人々が利用するアプリケーション層③その上下をつなぐ中間のミドルウェア層(OS)だ。新興国企業の活躍の場は主に②で、インフラでは中国と先進国の存在が圧倒的に大きく、進出・拡大は難しいし、③もプログラマー等の人材不足が悩ましい。また「雇用」も、製造業の雇用は減っていくが、一気には減らない。多くの作業は形を変えつつ必要となる。「自動化で失われる雇用は47%と言う説もあるが、OECDは9%という。機械化する投資額より、労働者を雇った方がコストがかからないこともある」「中国のフードデリバリー最大手の美団点許の配達員は399万人(2019年)、工場労働者より高賃金もある。しかしジェンダーや社会保障の問題が残る」・・・・・・。
「デジタル権威主義とポスト・トゥルース」――権力側はデジタルを活用し、監視や検閲の統治を行う"デジタル権威主義"が強化され、一方ではSNS上での情報戦が展開される。「米中新冷戦とデジタル化、世界の二者択一」が生ずる。加えて「米中対立の激化、中印対立の顕在化」が構図として現われる。そのなかで日本は「新興国がデジタルによって得られる可能性を拡大し、ともに実現し、同時に脆弱性を補うようなアプローチをとるべき。つまり『共創パートナーとしての日本』であるべきだ」と主張する。そしてそのためにも「遅れている日本の国内でのデジタル社会化を進めよ。アプリケーション層とミドルウェア層、物理層のレイヤーごとにもっと進めよ」という。