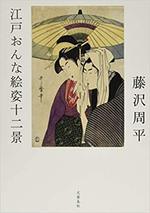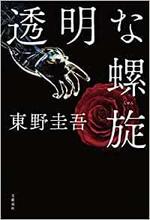 シリーズ第10弾、今、明かされる「ガリレオの真実」と銘打つ。湯川学の出生と湯川家に育てられた生い立ちが明かされる。
シリーズ第10弾、今、明かされる「ガリレオの真実」と銘打つ。湯川学の出生と湯川家に育てられた生い立ちが明かされる。
房総沖で銃弾を撃ち込まれた男性の遺体が発見され、同居していた恋人が失踪、関係者として天才物理学者・湯川の名が出てくる。草薙等が事件を追うなかで、湯川自身の出生・生い立ちまでが明かされるのだ。このシリーズ――科学者の目と警察・司法の目の違いは、どことなく"鬼平"の法的裁きと人情裁きの落差のような魅力が漂う。人情裁きは片目をつぶってのお見逃しだ。
若き女性・島内園香は母・千鶴子に大事に育てられた一人親家庭。園香たちには親戚と呼べる者はなかったが、千鶴子には心から信頼し慕っている年上の女性・松永奈江(絵本作家)がいた。ところが千鶴子が急逝。園香は一人きりの心細い生活が始まった時に辻中亮太という映像関係の仕事をしている男と出会い、同棲するが、これが激しいDV男だった。そして、房総沖で辻中亮太が遺体として発見され、園香は失踪。なぜか松永奈江が行動を共にしているようだ。その奈江が絵本を作るなかで接点があったのが湯川。一方、銀座のママ・根岸秀美には、乳児を捨てた過去があった。その時置いた「人形」を、園香が持っていたことを偶然発見し、秀美は千鶴子が自分が捨てた娘だと思う。そして園香を孫としてどうしようもない愛に包まれるのだった。親と子と孫、命のつながりの不思議なる因縁。そんななか事件は起きる。そして湯川の生い立ちも・・・・・・。
 「住宅」一筋に歩んできた竹中宣雄ミサワホーム会長。その人生は凄まじい。「人間いたるところに青山あり」「住宅営業は夜から深夜までは商談のゴールデンタイム(夜訪)」「駅のコンコースに寝て一夜を過ごしたこともあったホームレスもどきの泥臭い住宅営業」「管理職として必要な3つの能力――営業推進力、行動計画、受注残管理」「毎朝ミーティングが昼の1時、2時まで」「ついたあだ名がマムシ」「転職人生」「自動車事故で全身骨折、大量輸血でC型肝炎に」「走れ! Do Runを座右の銘に」「ミサワホーム経営危機、産業再生機構の支援」「敗者の惨めさ、火中の栗?」・・・・・・。しかしこれは単なる自伝の書ではない。激動する時代の変化の最前線で、人間生活の基盤であり根源である「住宅」は、それを映し出す鏡であり、「住宅(営業)」を語ることは時代と社会そのものを語ることであるからだ。その課題を打開していく先駆的役割りを住宅産業が担うという重要な意味をもつ。
「住宅」一筋に歩んできた竹中宣雄ミサワホーム会長。その人生は凄まじい。「人間いたるところに青山あり」「住宅営業は夜から深夜までは商談のゴールデンタイム(夜訪)」「駅のコンコースに寝て一夜を過ごしたこともあったホームレスもどきの泥臭い住宅営業」「管理職として必要な3つの能力――営業推進力、行動計画、受注残管理」「毎朝ミーティングが昼の1時、2時まで」「ついたあだ名がマムシ」「転職人生」「自動車事故で全身骨折、大量輸血でC型肝炎に」「走れ! Do Runを座右の銘に」「ミサワホーム経営危機、産業再生機構の支援」「敗者の惨めさ、火中の栗?」・・・・・・。しかしこれは単なる自伝の書ではない。激動する時代の変化の最前線で、人間生活の基盤であり根源である「住宅」は、それを映し出す鏡であり、「住宅(営業)」を語ることは時代と社会そのものを語ることであるからだ。その課題を打開していく先駆的役割りを住宅産業が担うという重要な意味をもつ。
「これからの住宅産業のカタチ」――。これからの時代と社会の変化をどう見るか。豊かな住生活を築くことが時代を切り拓くことになることを、俯瞰的に時間軸をもって語っている。その苦闘を「住宅という仕事の醍醐味」とポジティブに言うのが心地よい。
変容する不動産市場と住宅の「質」――。「人口減、少子高齢化」「都市回帰」「災害に強い耐震・免震」「南極の断熱、耐風、耐震、軽量化したミサワのプレハブ住宅・木質パネル接着工法」「ゼロ・エネルギー住宅」「二世帯住宅はひとつ屋根の下の近居」・・・・・・。更に「既存住宅流動市場の拡大」「空き家の抑制と活用」「外国人労働者も住宅確保要配慮者に」「長期優良住宅の促進と集合住宅の課題」「増え続ける"とりあえず空き家"」「二地域居住に空き家の活用」「環境時代にZEHの普及」「スマートハウスからスマートシティーへ」「太陽光発電(PV)と電気自動車(EV)の連結」「未来志向の複合拠点『ASMACI』モデル」「DX、テレワーク時代の住宅」・・・・・・。これからの時代変化の"見える化"は、住宅・都市づくりにあることを想起させる。
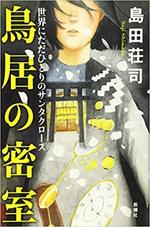 珍百景にもあげられる京都錦小路の錦天満宮の鳥居。参道の両脇ギリギリにビルが建てられ、なんと鳥居の両端がビルにめり込んでいる。その鳥居が刺さる建物で密室殺人事件が起きる。
珍百景にもあげられる京都錦小路の錦天満宮の鳥居。参道の両脇ギリギリにビルが建てられ、なんと鳥居の両端がビルにめり込んでいる。その鳥居が刺さる建物で密室殺人事件が起きる。
時は東京オリンピックが終わった39年の暮れ、クリスマスの朝。鳥居脇の1階で半井肇の妻・澄子が絞殺され、肇は早朝、京阪電鉄の始発に飛び込み自殺をする。鳥居がめり込んでいる2階には8歳の娘・楓が寝ており、枕元にはサンタクロースからの贈り物が置いてあった。夢にまでみた初めてのサンタからの贈り物と両親の死の悪夢。楓をとても可愛がってくれていた父の鋳物工場で働いていた国松信二が殺人犯として逮捕された。しかし、完全な密室。2階にはクレセント錠、1階にはスクリュー錠がしっかりかかっていた。誰も入れないはずの完全な密室に、サンタクロースと殺人犯、天使と悪魔が入ってきたというわけだ。
この謎に登場する御手洗潔。事件周辺に、不眠に悩まされたり、小さな物が朝動いているという不思議な現象が起きていることを知り、物体の「固有振動」と「共振」現象にたどりつく。私が京大土木工学科で、卒論・修論で取り上げた振動論だ。これが出てくるとは思わなかった。このミステリーは単なるトリックの謎解きでは終わらない。逮捕された国松の生い立ちと人生、楓の両親や育ての親、そして国松への思いなど、まさに人間ドラマが交錯する。「科学と人間」がミステリーのなかで包み込まれる感動傑作。
 「潮」の「令和に生きる日本人へ。」の中で、混迷の時代を生きる日本人に向けて、山崎正和さんは三つの遺言「過去と歴史の教訓から真摯に学ぶ(目の前のことで騒ぐのではなく、大きな歴史的文脈の中で考える)」「社交の技術」「読書の大切さ(時空を超えた社交そのもの)」を遺しているという。「鴎外 闘う家長」以来、日本の「知」を牽引し、「サントリー文化財団」を舞台に「知のサロン」を創造し、劇作家を文字通り演出してきた山崎正和さん。本書は山崎さんの思想と行動の骨格をくっきりと浮かび上がらせている。何度も事あるごとに話を聞きにおうかがいし、また著作もかなり読んできた私にとって、あの時、この時の言葉の意味がより鮮明になった。「山崎さんは、多くの人に大きな知的刺激と幸せの余韻を残して旅立たれた」と片山修さんは結ぶが、本当にそうだ。
「潮」の「令和に生きる日本人へ。」の中で、混迷の時代を生きる日本人に向けて、山崎正和さんは三つの遺言「過去と歴史の教訓から真摯に学ぶ(目の前のことで騒ぐのではなく、大きな歴史的文脈の中で考える)」「社交の技術」「読書の大切さ(時空を超えた社交そのもの)」を遺しているという。「鴎外 闘う家長」以来、日本の「知」を牽引し、「サントリー文化財団」を舞台に「知のサロン」を創造し、劇作家を文字通り演出してきた山崎正和さん。本書は山崎さんの思想と行動の骨格をくっきりと浮かび上がらせている。何度も事あるごとに話を聞きにおうかがいし、また著作もかなり読んできた私にとって、あの時、この時の言葉の意味がより鮮明になった。「山崎さんは、多くの人に大きな知的刺激と幸せの余韻を残して旅立たれた」と片山修さんは結ぶが、本当にそうだ。
「佐治敬三のDNA(彼は儲かるかどうかより、『おもろい』かどうかという感覚、感性を大事にした。経済的な損得よりも文化的な価値があるかどうかを判断基準)」「脱工業社会、モーレツからビューティフルの1970年代。山崎さんは人びとが時間を消費し、『社交』を楽しむようになるとして、ハードな組織集団から柔らかな集団に帰属する『柔らかい個人主義』の誕生を上梓した。消費は自己発見であり、社交の一環であり、文化そのものであり、知的な活動だ」「山崎は文化財団という戯曲の作者であると同時に、プロデューサー兼演出家でもあった」「私は根本的に文壇嫌いで小林秀雄という人について、非常に違和感があった。ああいうことはやるまいと。江藤淳は小林秀雄の跡継ぎになりますね。・・・・・・学芸賞において山崎はタコつぼを破壊し、国際性や学際性を重視して真のインターディシプリナリを復活させようとした」「論文に求められる『芸』――部分でなく全体でとらえる眼差し、一般の人たちの素朴な疑問や常識的な感覚からものを見ているかどうかを選考の重要なポイントとした。学術賞でなく、あくまで学芸賞とした(劇作家)」「地域文化賞――『文化』と言っているのは、言ってみたら『遊び』のこと、奇想天外で独創性がある(研究するのではなく、自らプレイヤーとして地域に参加する)」「学派、学党の集まる研究会でなく、日本の知的社会の構造改革、文化財団の『知のサロン化』、対話と論争の『場』、『社交』だ」「組織社会から社交社会へ――人間は社会的動物であるよりも、むしろ社交的動物だ」「『リズムの哲学』を考える――人生のリズム、孤独死と近代的自我」・・・・・・。
国家を支えるのは、文化である――戦後日本の成熟を信じた『知』の肖像」と帯にあるが、「ものを考え、それを文章にすることを生業にしてきました」と言う山崎正和さんの人格が迫ってくる。