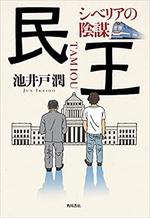 未知のウイルスに襲われた日本。武藤泰山総理と息子・翔が立ち向かう。そのウイルスはなんとシベリアの冷凍マンモスから飛び出したもの。かつて眉村紗英の父・古沢恭一がサハ共和国で起きたという集団感染の話を聞き研究。冷凍マンモスからのウイルスにたどり着いたようだったが突然、古沢恭一は自殺してしまう。
未知のウイルスに襲われた日本。武藤泰山総理と息子・翔が立ち向かう。そのウイルスはなんとシベリアの冷凍マンモスから飛び出したもの。かつて眉村紗英の父・古沢恭一がサハ共和国で起きたという集団感染の話を聞き研究。冷凍マンモスからのウイルスにたどり着いたようだったが突然、古沢恭一は自殺してしまう。
泰山は緊急事態宣言を発出するが、周りの政治家や都知事はそれに大反対、デモ・暴動にさらされる。一つはそのウイルスをめぐっての企業やテロ組織の陰謀、もう一つは武藤政権を倒そうと謀る政争。ともに武藤親子や紗英らが体当たりで解決する。とくにデモ・暴動自体が「大勢の人たちが疑心暗鬼になり、不寛容であり続け、大規模デモに訴える症状がウイルスを原因とする」「荒唐無稽な噂話を信じた人たちは、新種のウイルスに感染していた」というのだ。政治家としての信念をデモ隊に向かって身体を張って演説する武藤総理は痛快ではあるが、狂騒曲、マンガチックな展開。
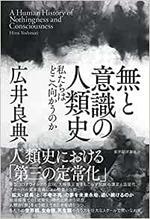 新型コロナ・パンデミックと大規模災害。それはグローバル資本主義の拡大・成長と気候の激変・地球温暖化が許容限界に達していることを表出している。無限拡大に対しての有限性、「生と有限性、地球環境の有限性」の自覚が今、突き付けられている。地球規模での「定常化」時代に向かっているとの自覚だ。
新型コロナ・パンデミックと大規模災害。それはグローバル資本主義の拡大・成長と気候の激変・地球温暖化が許容限界に達していることを表出している。無限拡大に対しての有限性、「生と有限性、地球環境の有限性」の自覚が今、突き付けられている。地球規模での「定常化」時代に向かっているとの自覚だ。
しかし、その「定常化」は人類の歴史から見て第3回目の「定常化」だという。人類は「有限性」を自覚した時に、「定常化」のなかに豊かな創造性を見出していたのだ。「第一の定常化――ホモ・サピエンスの増大→心のビックバンに転換」「第二の定常化――農耕と都市の拡大→枢軸時代、精神革命(世界での哲学・宗教の始源)」、そして現在の「第三の定常化――地球倫理へ」だ。人類は新たな「生存」の道への転換を図れるか。牧口常三郎初代創価学会会長の「21世紀を人道の世紀に」を想起させる。その「地球倫理」を人類の過去・現在・未来の壮大なパースペクティブの上から、またその根源を探ることから「有と無と空」「生と死」「時間と死生観」「仏教、老荘思想、キリスト教」「宇宙と生命」等、壮大なスケールで論述する。
「無と死を考える時代――生と死のグラデーション、無と科学」「有限性の経済学――資本主義と無限、人類史の拡大・成長と定常化、地球倫理の可能性」「超長期の歴史と生命――意識という開放定常系、共生と個体化のダイナミクスとしての生命」「無の人類史――無(ないし死)の人類史のスケッチ、心のビックバン(心の自立、無の自立)、農耕社会と"死の共同化"、枢軸時代・精神革命における"無"の概念化・抽象化、老荘思想・中国仏教における"無"、ギリシャにおける自然と生成・存在、ユダヤ・キリスト教の"永遠の生命"」「『火の鳥』とアマテラス――太陽の再生神話の起源、アマテラスの起源、死を含む生命」「有と無の再融合――無のエネルギー、生と死のグラデーションと死生観、認知症と老年的超越」「時間の意味――時間と死生観、時間・永遠・宇宙をめぐるモデルと現代物理学」・・・・・・。
断常の二見を超える「空」とエネルギー、人間の生と、己を超える大きな存在(宇宙、地球、共同性)との繋がりの覚知、第三の定常化時代の新たな思想・観念の形成、宇宙・地球・生命・人間の「共生と個体化のダイナミズム」、その到達理念としての「地球倫理」――。共鳴盤が激しく鳴った。
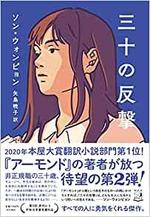 話題を呼んだ「アーモンド」の著者だ。本書のタイトルは当初、「普通の人」だったが「1988年生まれ」というタイトルで賞を受け、今回「三十の反撃」として刊行された。まさにそのタイトルどおり、1988年生まれで30歳になっても正規社員でもないインターンのままの女性・キム・ジヘ。日本でいう就職氷河期がこの世代にあたった。特に取柄があるわけでも、優れているわけでもない「普通の人」のキム・ジヘ。「どんな大人になりたい」「今の時間をどのように記憶し、刻んでいくか」を深く考える訳ではないが、職場でも言いたいことも言えず鬱積した不満・不安を抱え、かつては同級生にひどい仕打ちを受けながら"黙って我慢"した心の傷を引きずっている「普通の人」でもある。しかしそれは韓国社会にはびこるニセモノたちや、弱者を巧妙に搾取する構造的矛盾という"巨大な壁"に、"跳ね返され"たり、"沈黙"を余儀なくされている姿でもある。
話題を呼んだ「アーモンド」の著者だ。本書のタイトルは当初、「普通の人」だったが「1988年生まれ」というタイトルで賞を受け、今回「三十の反撃」として刊行された。まさにそのタイトルどおり、1988年生まれで30歳になっても正規社員でもないインターンのままの女性・キム・ジヘ。日本でいう就職氷河期がこの世代にあたった。特に取柄があるわけでも、優れているわけでもない「普通の人」のキム・ジヘ。「どんな大人になりたい」「今の時間をどのように記憶し、刻んでいくか」を深く考える訳ではないが、職場でも言いたいことも言えず鬱積した不満・不安を抱え、かつては同級生にひどい仕打ちを受けながら"黙って我慢"した心の傷を引きずっている「普通の人」でもある。しかしそれは韓国社会にはびこるニセモノたちや、弱者を巧妙に搾取する構造的矛盾という"巨大な壁"に、"跳ね返され"たり、"沈黙"を余儀なくされている姿でもある。
そのキム・ジヘが、新しくインターンとして入ってきた男性・ギュオクの"反撃の行動""いたずら"に触発されて、小さな「反撃」に出る。小さな"いたずら"のような「反撃」を行うこと、正しいこと、真実を言うことができるという「小さな勇気の反撃」だ。しかし、それが自分自身に変革をもたらし、成長していくことになる。我慢し、押し潰されても「沈黙」ではなく、「小さな反撃」に踏み出す勇気が、自分の人生を自覚的で確かなものにしていくのだ。沈黙ではなく行動、一人ではなく仲間がいること――そのことを駆け込み寺"ならぬ"仮空の人"のジョンジンさんが暗示する。
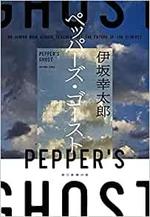 他人の明日の未来が見える「先行上映」という不思議な力をもつ中学校の国語教師・檀千郷。彼に迫り来る出来事・事件と、女子生徒・布藤鞠子の書く小説が交錯する。小説からロシアンブルとアメショーと名乗るネコジゴハンターが抜け出す。あたかも照明とガラスを使って別の場所の存在を観客の前に映し出すペッパーズ・ゴーストのよう。現実とバーチャルが入れ乱れるなか、"テロ事件"に彼等が巻き込まれていく。
他人の明日の未来が見える「先行上映」という不思議な力をもつ中学校の国語教師・檀千郷。彼に迫り来る出来事・事件と、女子生徒・布藤鞠子の書く小説が交錯する。小説からロシアンブルとアメショーと名乗るネコジゴハンターが抜け出す。あたかも照明とガラスを使って別の場所の存在を観客の前に映し出すペッパーズ・ゴーストのよう。現実とバーチャルが入れ乱れるなか、"テロ事件"に彼等が巻き込まれていく。
事件はまず、5年前に起きた「カフェ・ダイヤモンド事件」――。世田谷の洋風創作料理店「カフェ・ダイヤモンド」に5人の猟銃を持った男が、客やスタッフを人質にとって立てこもり、警察が突入。29人が亡くなり、犯人も自爆。テレビの人気のコメンテーター・マイク育馬の軽率な発言が自爆に追い込んだ最後の一押しとなった。被害者たちが秘かにサークルをつくる。庭野、野口勇人、成海彪子らは、警察やマイク育馬などへの復讐を図ろうとするが、その心の奥底には「人生そのものへの絶望」「生きる意味の喪失」「死にたい」「自暴自棄」が共有されていた。そして「やすらぎ胃腸クリニック」「後楽園球場」のテロ事件を起こす。ニーチェの「この世界の嘆きは深い、喜びのほうが、深い悩みよりも深い。嘆きが言う。『消えろ!』と。だがすべての喜びが永遠をほしがっている」との「ツァラトゥストラ」が通底音として全編に響く。
事件に巻き込まれた檀は、不思議な「先行上映」の力で、これらを何とかしのいでいく。そして最後の展開が・・・・・・。
 「草の花」「廃市」「海市」「北の島」など、「死」「河」「海」などを孕み、心層の暗部を描き出した福永武彦の1959年の作品。10年も昔の夏、大学生の「僕」は「卒業論文を書くためにその町の旧家で過ごした」。そして今、その水の町、運河の町が火事になって町並があらかた焼失したことを新聞記事で知る。「あの町もとうとう廃市となって荒れ果ててしまったのだろうか」と、もともと廃墟のような寂しさのある、ひっそりとした田舎町を想い、下宿先の旧家のこと、美しき姉妹(郁代さん、安子さん)のこと、そして姉の夫・直之さんの心中・自殺という衝撃的事件の記憶が蘇える。
「草の花」「廃市」「海市」「北の島」など、「死」「河」「海」などを孕み、心層の暗部を描き出した福永武彦の1959年の作品。10年も昔の夏、大学生の「僕」は「卒業論文を書くためにその町の旧家で過ごした」。そして今、その水の町、運河の町が火事になって町並があらかた焼失したことを新聞記事で知る。「あの町もとうとう廃市となって荒れ果ててしまったのだろうか」と、もともと廃墟のような寂しさのある、ひっそりとした田舎町を想い、下宿先の旧家のこと、美しき姉妹(郁代さん、安子さん)のこと、そして姉の夫・直之さんの心中・自殺という衝撃的事件の記憶が蘇える。
「安ちゃん、あなたは馬鹿よ。秀なんかにあの人を取られて・・・・・・直之はあなたが好きだったのよ」「お姉さんは間違っているのよ。兄さんが好きだったのはあなたで、わたしじゃないのよ」「あなたが、好きだったのは、一体誰だったのです?」・・・・・・。「この滅びたような田舎町」「運河がはりめぐらされた美しい水の町、しかし閉ざされた死んだような町」で起きた愛、誤解、邪推、その増幅・・・・・・。ゆったりとした時間のなか、厚みのある静寂と、人心の揺らぎを、自然の悠久さのなかに融け込む生命体のように描き出していく。中江有里さんの「万葉と沙羅」に突き動かされて読んだ。

