 プロ野球審判生活29年、通算出場2414試合、そのなかから70のエピソードを語る。審判という立場から見た選手たち。興味深い。
プロ野球審判生活29年、通算出場2414試合、そのなかから70のエピソードを語る。審判という立場から見た選手たち。興味深い。
「館山昌平はボールにこだわり、ボールの芯のズレを見抜いた。だからボール交換の要求が一番多かった」「3種類のフォークボールを投げ分けた上原浩治。コントロール抜群で四球は驚異的に少なかった」「打たせて取るピッチャーのお手本は吉見一起」「日本で一番ロジンバッグを使う石川雅規踏襲」「山井投手から岩瀬投手への継投はそうなると思った」「世界一のキャッチャー・谷繁元信」「レーザービームNo.1は現在オリックス監督の中島聡捕手」「守備範囲が2倍あった荒木雅博、一塁手のウッズの分まで捕った」「機敏で柔らかなグラブさばきの中村紀洋は最高だった」「広岡タイプで確実にアウトにすればいいという考えの井端弘和は意外とゆっくり1塁へ投げた」「トリックプレーを流行らせた福留康介」「外野のポジショニングといえば新庄剛志」「フライを補球する天才・飯田哲也、1993年の日本シリーズでの飯田のバックホームは、野村監督も俺の3冠王よりもすごいと言っていた」「ボールにバットをミートさせた時に焦げた匂いがした松井秀喜、広澤克実」「審判の体調を気遣う人間性の持ち主・大谷翔平」「日本人メジャーリーガーで内野手はなかなか成功しない。ランナーの当たりの強さが半端じゃない」・・・・・・。
大魔神・佐々木のフォークボールの落差も審判からは見えるという。乱闘とかビデオ検証「リクエスト制度」の功罪にも触れている。
 「漁民たちの国境紛争」が副題。漁業を通じて国際情勢の最前線、尖閣諸島のある東シナ海、日中台の国境紛争の現実を描き出す漁業経済学者による生々しい著作。「尖閣諸島の唯一の産業である漁業」の現実から見ると、東シナ海漁業が追い詰められ、日本の東シナ海権益が削られ、中国の漁業が著しく発展し、台湾漁業のプレゼンスが急拡大している危機感が迫ってくる。著者は日本漁業のリアルに接近し、国を挙げて打開しないと大変なことになると「漁業国有化論」を指し示す。
「漁民たちの国境紛争」が副題。漁業を通じて国際情勢の最前線、尖閣諸島のある東シナ海、日中台の国境紛争の現実を描き出す漁業経済学者による生々しい著作。「尖閣諸島の唯一の産業である漁業」の現実から見ると、東シナ海漁業が追い詰められ、日本の東シナ海権益が削られ、中国の漁業が著しく発展し、台湾漁業のプレゼンスが急拡大している危機感が迫ってくる。著者は日本漁業のリアルに接近し、国を挙げて打開しないと大変なことになると「漁業国有化論」を指し示す。
「東シナ海は、日本の運命を握る海にもかかわらず、課題は山積している」「日本の排他的経済水域(EEZ)は世界有数とされるが、東シナ海では関係国と相互承認している日本のEEZはほとんどない」「東シナ海だけではない。日本海でも、オホーツク海でも水域の画定はされていない」「中国漁船は条約に基づいて自由に操業。日本漁船の操業実績は落ち込んでおり、危機的状況だ」「東シナ海から駆逐される日本船団」「日本の漁業者は尖閣漁場でも追い詰められている(どんなに苦労して操業しているか)」「東シナ海で増す中国・台湾の存在感」「遠洋漁業は『流動的国土』。中国は遠洋漁業強国となった」「日台の漁業交渉で台湾側は尖閣諸島をめぐる問題について目をつむるが、代わりにこれまで利用できなかった優良な海域での操業権を獲得した」「尖閣漁場を失う八重山と九州の漁業者」・・・・・・。
「衰退する日本の漁業・漁村、遠洋漁業も沖合・沿岸漁業も疲弊」「人材も、1993年に32万人いた漁業就業者は2018年に15万人。外国人労働力に依存し、インドネシア人が日本漁業を支えている」「東シナ海の軍事化と『第二の海軍』の膨張。踏ん張る海上保安庁」「国境産業は国家の化粧である。国勢を推し量るリトマス試験紙ともなる。漁業は第三の海軍でもある」・・・・・・。
海洋国家・日本における漁業は、国民に食料を供給する使命とともに、安全保障に直結する産業であるとの認識が共有されなければならない。国民的議論を「日本漁業国有化論」として正面から行う必要があると訴える。
 訳者の岸本佐知子さんはいう。「ルシア・ベルリンの名を知ったのは今から十数年前・・・・・・。一読して打ちのめされた。なんなんだこれは、と思った。聞いたことのない声、心を直に揺さぶってくる強い声だった。行ったことのないチリやメキシコやアリゾナの空気が、色が、においが、ありありと感じられた。見知らぬ人々の苛烈な人生がくっきりと立ち上がってきた。彼らがすぐ目の前にいて、こちらに直接語りかけてくるようだった」と。とてもこんなにうまく表現できないので引用させていただいた。全くその通り。人生の起伏が、大いなる振幅が、感情豊かに、しかもラップのようなリズムで迫ってくる衝撃作だ。彼女の作品の多くは彼女の実人生に基づいているが、小説なのか実際なのかがよくわからない。それ以上に圧倒的な迫力でどっちでも良いと思ってしまう。
訳者の岸本佐知子さんはいう。「ルシア・ベルリンの名を知ったのは今から十数年前・・・・・・。一読して打ちのめされた。なんなんだこれは、と思った。聞いたことのない声、心を直に揺さぶってくる強い声だった。行ったことのないチリやメキシコやアリゾナの空気が、色が、においが、ありありと感じられた。見知らぬ人々の苛烈な人生がくっきりと立ち上がってきた。彼らがすぐ目の前にいて、こちらに直接語りかけてくるようだった」と。とてもこんなにうまく表現できないので引用させていただいた。全くその通り。人生の起伏が、大いなる振幅が、感情豊かに、しかもラップのようなリズムで迫ってくる衝撃作だ。彼女の作品の多くは彼女の実人生に基づいているが、小説なのか実際なのかがよくわからない。それ以上に圧倒的な迫力でどっちでも良いと思ってしまう。
ルシア・ベルリンは1936年アラスカ生まれ。鉱山技師だった父親の仕事の関係で幼少期より北米の鉱山町を転々とし、成長期の大半をチリで過ごす。3回の結婚と離婚を経て4人の息子を育てる。その間、学校教師、掃除婦、電話交換手、看護助手などをして働くが、アルコール依存症にも苦しむ。数少ない短編小説の中で、本書はその中の24の小説を選んでいる。いずれもこれほどの躍動感、洞察力、迫力、詩情、したたかな生命力、むき出しの言葉とユーモアはないと思わせる作品ばかりだ。とにかく庶民の泣き笑い、ズルさや怠惰、たくましさや怒り、死に直面する恐怖と寂寥が激しく迫ってくる。それらは、今の時代に最も欠け、隠蔽されているように思える。同時代を生きた者の一人として、感じることも多く、また日本と違って、荒々しい米国、チリ、メキシコの生々しい生活の実態に抱え込まれる。リズムある訳の素晴らしさにも感動する。拍手。
 外国人と共生する日本、外国人労働者が働きに来て良かったという日本――。今後の日本にとって重要なこの課題が、コロナ禍のなかでどうなっているかを心配している私にとって、貴重なルポだ。
外国人と共生する日本、外国人労働者が働きに来て良かったという日本――。今後の日本にとって重要なこの課題が、コロナ禍のなかでどうなっているかを心配している私にとって、貴重なルポだ。
劣悪で悲惨な技能実習生や留学生。そういった時代はこの10年、変革への途上にある。私自身も「建設」を中心にして課題克服に力を注ぎ、3年前からは「特定技能」の制度が始まっている。外国人を「都合のよい雇用調整弁」として使い捨てた歴史があるが、コロナ禍でも「クビを切られるのは、まず外国人から」という現実は今回でも起きていた。ゆえに「10万円給付が外国人も対象となったという喜びがあった」「東海地方に多い外国人労働者(1990年の入管法改正で日系2世・ 3世と配偶者に定住者の資格が与えられ急増)」「技能実習生が2年間を終え技能実習3号となると転職できる。しかし、コロナ禍で中小企業の仕事は激減して放り出され、パワハラにも遭い、名古屋イエス・キリスト教会に転がり込んだ」「2020年4月に襲った首切りの大波」「コロナ失職とともに外国人労働者の高齢化問題がある」「とくに留学生が母国で足止めを食らって新大久保の街からも消えた」「オンラインの授業は果たして留学なのか(現地で暮らし、人と交流し、友達ができてこそ留学)」「まだまだある技能実習生への不当な天引き、残業代不払い、暴力、セクハラ」「逃亡実習生が助けを求める埼玉県本庄市のベトナム尼僧の大恩寺」「ルールを優先する日本人、動く範囲が広く、ルール・法律よりも家族の縁や仏の教えが規範となる東南アジアの人々」「名古屋にもあるベトナム人の駆け込み寺」「留学生は都市出身で実家も裕福が多いが、実習生は地方出身で野生のような生き抜くたくましさがある。従順な労働力と思ったら大間違い」「何でも対象外の難民たち(10万円も)」・・・・・・。
しかし、悲惨とか「かわいそうな弱者」ではない。たくましく、したたかに「コロナをチャンス」としようとしている姿、「出店ラッシュ」「店舗に空きが出るとすぐ埋まってしまう」姿を描き出している。「この街はコロナに負けなかった」・・・・・・。「彼らはもうこの国にしっかり根づき、この社会の成員として生活を紡いでいる」という。
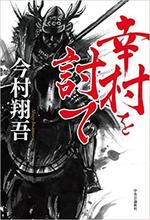 「そもそも人は何故、名を残そうとするのだろう」「鳥の如く、獣の如く、ただ飯を食らい、糞をして、眠りにつく。その繰り返しでよいはずなのに、人は何故か生に意味を見出そうとする。・・・・・・そしてそれを後世に何らかの形で残したいという願望を心の何処かで持っている」「真田の家を守りつつ、後世まで真田の名を轟かせる。父(昌幸)の死後、この壮大な計画を持ちかけてきたのは源次郎(真田幸村=信繁)であった」「兄・信幸は真田を守るために徳川につき信之と名を変えた。九度山を出て大坂城へ向かう砌、信繁は真田家累代が受け継いできた字『幸』を名乗リ幸村となった」「『信』の字は、御屋形様の俗世の名、武田晴信からきているのである」・・・・・・。
「そもそも人は何故、名を残そうとするのだろう」「鳥の如く、獣の如く、ただ飯を食らい、糞をして、眠りにつく。その繰り返しでよいはずなのに、人は何故か生に意味を見出そうとする。・・・・・・そしてそれを後世に何らかの形で残したいという願望を心の何処かで持っている」「真田の家を守りつつ、後世まで真田の名を轟かせる。父(昌幸)の死後、この壮大な計画を持ちかけてきたのは源次郎(真田幸村=信繁)であった」「兄・信幸は真田を守るために徳川につき信之と名を変えた。九度山を出て大坂城へ向かう砌、信繁は真田家累代が受け継いできた字『幸』を名乗リ幸村となった」「『信』の字は、御屋形様の俗世の名、武田晴信からきているのである」・・・・・・。
慶長19年、20年(1615年)の大坂冬の陣と夏の陣。大坂城には、魑魅魍魎、曲者たちが、それぞれの思惑と野望と人生をかけて集っていた。元大名や武将や浪人・・・・・・。長曽我部盛親、後藤又兵衛、織田有楽斎、南条元忠、毛利勝永・・・・・・。その中心の一人が真田幸村であった。これら武将や浪人も、それに対する徳川家康、伊達政宗ら周りのものも皆、何年にもわたって積み重ねられた真田父子の想像を絶する智謀に翻弄される。そして本書は、幸村と緻密に連携する兄・信幸の凄まじき用意周到なる深慮遠謀を浮き彫りにする。いつも新しい人物像を鮮やかに描く今村翔吾だが、今回は真田幸村の陰に隠れがちであった兄・真田信之の凄まじさを描いている。
「なぜ幸村と名乗ったのか」「兄は徳川、弟は豊臣、家康を翻弄した父・昌幸の父子三人は何を考え志したか」――。その智謀と尋常ならざる父子の情が描かれる。心の奥底からの重い情念だ。「これまで家康は、昌幸を、真田という家を問答無用に憎悪してきた。だが今回、真田家について、親兄弟の間に存在する尋常ならざる情の深さを知った。その根にある絆を」。そして戦国時代最後の戦いである大坂の陣、大坂落城、幸村の死後、家康と真田信之の壮絶な言葉による智謀の戦いを描く。攻める家康、凌ぐ真田信之。その生死をかけた尋問は息が詰まるほどの緊迫感に満ちたものだ。そして真田信之は語るのだ。「背後には乱世が。眼前には泰平が。・・・・・・悠久の歴史に己の名を刻むために生きるのか、それとも歴史に刻み込まれて生きるのか。どちらが正しいというわけではなく、どちらもまた人という生き物のあり方なのではないか。ただ弟は、少なくとも前者を求め、荒れ狂う時代を風のごとく最後まで駆け抜けた」と。本書もまた素晴らしき力みなぎる作品。

