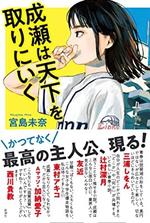 滋賀県大津市の同じマンションにずっと住んでいる成瀬あかりと島崎みゆきの絶妙のコンビ。成瀬は、幼稚園の頃から走るのは速いし、絵も歌もうまい。成績は超優秀、超然として他人の目を気にすることなく突き進み、他人を寄せ付けない。"男前"というやつだ。周囲から浮いてしまうが、島崎みゆきだけは、すっと成瀬を受け止める。この2人の中学、高校時代の物語だが、とにかくキャラが立っている。カラッと明るくて、破天荒で、面白い青春小説。
滋賀県大津市の同じマンションにずっと住んでいる成瀬あかりと島崎みゆきの絶妙のコンビ。成瀬は、幼稚園の頃から走るのは速いし、絵も歌もうまい。成績は超優秀、超然として他人の目を気にすることなく突き進み、他人を寄せ付けない。"男前"というやつだ。周囲から浮いてしまうが、島崎みゆきだけは、すっと成瀬を受け止める。この2人の中学、高校時代の物語だが、とにかくキャラが立っている。カラッと明るくて、破天荒で、面白い青春小説。
中二の夏、成瀬がまた変なことを言う。「島崎、わたしはこの夏を西武に捧げようと思う」・・・・・・。8月31日、西武大津店が閉店となる。これから毎日、野球のユニホーム姿で目立つようにして西武に通い、テレビに出ると言う。また「将来、私が出店する」とも。さらに「私の目標は200歳まで生きること」「わたしと島崎でコンビを組んで、M1グランプリ出る」・・・・・・。かつては、「大きなシャボン玉作り」で"天才シャボン玉少女"として有名になったり、大津市のけん玉チャンピオンにもなる。名うての進学校・膳所高校には坊主頭で入学。小倉百人一首かるた高校選手権で勝ち抜いていく。とにかく痛快、周りを気にしない。
さあ成瀬はどうなる。気になるところだが、大学受験で島崎と遠く別れるところで、精神的にがたつくところも面白い。新しい感性の話題の小説。
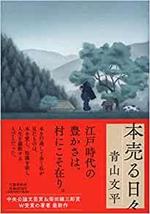 江戸時代、学術書を行商して歩く本屋「松月平助」が、村と村が発展した在郷町の住人たちとの接触で得た感動的な物語。生き生きとした暮らしや人情、見識ある人間が、じっくりと描き出される。青山文平さんらしい熟練の境地がとても良い。
江戸時代、学術書を行商して歩く本屋「松月平助」が、村と村が発展した在郷町の住人たちとの接触で得た感動的な物語。生き生きとした暮らしや人情、見識ある人間が、じっくりと描き出される。青山文平さんらしい熟練の境地がとても良い。
「私は本屋だ。本屋は本屋でも物之本の本屋で、漢籍や仏書、歌楽書、国学書といった学術周りの書物を届ける。とはいえ、医書に取り組んでからは、まだ日が浅く、城下の医者と十分に顔がつながっているとは言えない」という状況だが、書物好きが昂じて一念発起して本屋となっただけに、かなりの見識と情熱を持っている。1800年頃までの日本の書物は極めて貴重。丁寧に意欲を持って集めている。そして「開版」という夢を持つ。武家が困窮している時代――。得意先は、名主・庄屋、豪農など地付きの名士だ。イタリアの「モンテレッジォ」の本を担いで旅に出る本屋を思い出す。
連作3篇となっている。「本売る日々」――。得意先の小曽根村の名主・惣兵衛が71歳で17歳の後添いをもらったびっくりするような話。「今の惣兵衛さんには本に使う財布の持ち合わせは無いかもしれませんよ」といわれるが、そうではない。本も買うが、欲しがるものを何度も買い与えているというのだ。そして、持ち込んだ本がなくなっていた・・・・・・。
「鬼に喰われた女」――。杉瀬村の名主・藤助が語る八百比丘尼伝説のような女の話。和歌を通じて惹かれ合い、結婚寸前までいきながら、男は武家の娘を選ぶ。女は何年、何十年たっても歳をとらない。そして"復讐"を遂げる。しかし女の本当の心の中は・・・・・・。
「初めての開版」――。弟の娘の矢恵は喘病で苦しんでいたが、西島晴順という医者にかかって好転する。西島には良い噂もあれば悪い噂も。この土地で最も頼りになる医者は、城下の町医ではなく、近在の小曽根村の村医者・佐野淇一。名主の惣兵衛に聞くと、「世襲医の中でぴかいちなのが淇一先生。小曽根村の誇り」と言う。会うと、感嘆するほどの人物。この佐野淇一と西島には隠された出会いがあったのだった。この結末は「秘伝」なるものを公に分つことも含めてすばらしい。
江戸時代が武士の時代であった事は、紛れもない事実だが、庶民の中、村の中に、本を愛し、知識を欲し、人格を磨いた重厚感のある人物がいたことを描き出している。江戸の町や村には、そうした豊かさが着々と築かれていたことがよくわかる。心に染みいる素晴らしい作品。
 「普遍的な正義と、資本主義の行方」が副題。2020年から22年8月までに、月刊誌に連載してきた時事的な評論集。流動化する世界の中で、日本はどうすべきか。ロシアのウクライナ侵略を始めとする世界を揺るがす問題の核心に、俯瞰的に時間軸を持って大胆に迫る。その社会学的アプローチは、極めて刺激的だ。
「普遍的な正義と、資本主義の行方」が副題。2020年から22年8月までに、月刊誌に連載してきた時事的な評論集。流動化する世界の中で、日本はどうすべきか。ロシアのウクライナ侵略を始めとする世界を揺るがす問題の核心に、俯瞰的に時間軸を持って大胆に迫る。その社会学的アプローチは、極めて刺激的だ。
「ロシアのウクライナ侵攻――普遍的な正義への夢を手放さないために」が第1章。「ロシアがとったキリスト教は、東側のキリスト教、つまり正教。ヨーロッパを文化的に特徴づけているのは、西側のキリスト教であるカトリック(プロテスタンティズムが派生)」「プーチンには、非常に深いヨーロッパ・コンプレックス、ヨーロッパに対する憧れと劣等感がある」「ヨーロッパとははっきりと異なる大義をもつユーラシア主義?」「『ほとんどわれわれ』のウクライナは、ロシアよりもヨーロッパをとった」「フランシス・フクヤマの『歴史の終わり』の現在、戦争は、文明の衝突の様相を帯びる」「ロシアを非難しない国々がたくさんあり、反対5カ国、棄権35カ国から見える真の争点」「ロシアの一般の市民や民衆が『ヨーロッパ以上のヨーロッパ』たり得ることを行動で示すことこそ、真の問題の解決だ」と言う。愛国主義、ナショナリズムを通って普遍主義へ至る道があり、愛国的であるが故に、普遍主義に立脚することができることを、「日本人にとっての教訓」と言っている。
大きな論点は、第二章の「中国と権威主義的資本主義――米中対立、台湾有事と日本の立ち位置」だ。「中国のナショナリズムは、中華帝国のやり方をそのまま転用したものである。・・・・・・西ヨーロッパに出現した原型としてのネーションは、帝国的なるものの否定として成立した。中国は帝国をそのまま肯定的に継承し、ネーションとした」「台湾に執着するのは、中国が帝国の原理で動くネーションだからだ」と言う。中国は、国民国家の体をしながら、実質的には序列を非常に重視する帝国であり、法の支配よりも皇帝や共産党が上位に来る権威主義が資本主義と接合している。権威主義的資本主義は、①有能でつよい権限を持つ官僚・行政があること②法の支配が欠如していること③国家の民間部門に対する高度な自律性――としているが、金権腐敗は免れない。しかもこの権威主義的資本主義は、グローバルサウスに輸出されることはない。そして極めて面白いのは、「インターネットを主要な手段の場所として、現在の資本主義は、本来はコモンズであるべき『一般的知性』に私的所有権を設定するレント資本主義の形態を取ることになる。そして、レント資本主義は、それを担う人々のイデオロギーや思想とは関係なく、権威主義的資本主義へと漸近していく」と言っている。
「ベーシックインカムとその向こう側」「アメリカの変質――バイデンの勝利とBLMが意味すること」「日本国憲法の特質ーー私たちが憲法を変えられない理由」の各章がある。「私はあなたたちのために何ができるのでしょうか」との白人の女子大生の問いかけに、マルコムXが"N o t h i n g"と答えた。哀れな犠牲者である黒人を支援しようでは拒絶されるのは当然。人種主義の根源にも触れている。短く、一度も変えていない日本国憲法のなぜ。「創設」の行為がないことを指摘している。
 リベラル・デモクラシーを統治体制の最終形態だとした「歴史の終わり」から30年――。今、デモクラシーもリベラリズムも攻撃にさらされている。特にリベラリズムは、右派のポピュリストからだけでなく、新たに出てきた進歩的な左派からも挑戦を受けている。トランプ等の政治指導者は、リベラルな制度を攻撃。「司法省、情報機関、裁判所、主流メディアなどの組織を弱体化させる試みを行っている」のだ。「格差と移民」が欧米諸国の不満の背景にある事は明らかであり、リベラリズムとそれに結びつく資本主義システムへの批判となっている。「左派からの批判は、リベラルな社会が、すべての集団を平等に扱うという自らの理想に応えていないとする。・・・・・・この批判はやがて、リベラリズムの根本的な原理そのものを攻撃するような広がりを見せた。根本的な原理とは、集団ではなく個人に対し権利を認めることである。また人間は全て平等であるという前提である。これらは憲法や自由主義的権利の拠って立つ根拠となっている。さらには、真実を理解するための方法として重視されてきた言論の自由や科学的合理主義である。こうした原理を攻撃した結果、新しい進歩主義の正統から外れた意見には不寛容となり、その正統を実現するために様々な形態の社会的・政治的権力が用いられるようになった」と指摘する。このように右派からも左派からも、現在のリベラリズムへの不満が充満しているが、「原理に根本的な弱点があるからではなく、この数十年の間のリベラリズムの発展の仕方に不満を抱いているのだと私は考える」と言っている。プーチンが「リベラリズムは時代遅れ」と言い、欧米の方が多様性やマイノリティー問題など問題を抱え混乱してるではないか、とまでいう状況からいって、リベラリズムのもつ豊穣な価値を再構築、復権させることは、極めて重要であると思う。
リベラル・デモクラシーを統治体制の最終形態だとした「歴史の終わり」から30年――。今、デモクラシーもリベラリズムも攻撃にさらされている。特にリベラリズムは、右派のポピュリストからだけでなく、新たに出てきた進歩的な左派からも挑戦を受けている。トランプ等の政治指導者は、リベラルな制度を攻撃。「司法省、情報機関、裁判所、主流メディアなどの組織を弱体化させる試みを行っている」のだ。「格差と移民」が欧米諸国の不満の背景にある事は明らかであり、リベラリズムとそれに結びつく資本主義システムへの批判となっている。「左派からの批判は、リベラルな社会が、すべての集団を平等に扱うという自らの理想に応えていないとする。・・・・・・この批判はやがて、リベラリズムの根本的な原理そのものを攻撃するような広がりを見せた。根本的な原理とは、集団ではなく個人に対し権利を認めることである。また人間は全て平等であるという前提である。これらは憲法や自由主義的権利の拠って立つ根拠となっている。さらには、真実を理解するための方法として重視されてきた言論の自由や科学的合理主義である。こうした原理を攻撃した結果、新しい進歩主義の正統から外れた意見には不寛容となり、その正統を実現するために様々な形態の社会的・政治的権力が用いられるようになった」と指摘する。このように右派からも左派からも、現在のリベラリズムへの不満が充満しているが、「原理に根本的な弱点があるからではなく、この数十年の間のリベラリズムの発展の仕方に不満を抱いているのだと私は考える」と言っている。プーチンが「リベラリズムは時代遅れ」と言い、欧米の方が多様性やマイノリティー問題など問題を抱え混乱してるではないか、とまでいう状況からいって、リベラリズムのもつ豊穣な価値を再構築、復権させることは、極めて重要であると思う。
リベラリズムは「実践的な合理性。暴力を規制し、多様な人々が互いに平和で暮らせるようにするための手段であり、とりわけ科学的方法と強く結びついている」「道義性。人間の尊厳、特に人間の自律性(各個人が選択する権利)を守るものである」「経済。財産権と取引の自由を守ることで、経済成長とそれに伴うあらゆる良いことを促進する。新自由主義経済学の欠陥は、財産権や消費者利益を崇拝し、国家の活動や社会的連帯をあらゆる面で軽視したことであった」と指摘する。リベラリズムは、個人主義的であり、平等主義的であり、普遍主義的であって、人類という「種」の良心は皆同じであると主張し、特定の歴史的組織や文化形式には二次的重要性しか認めない。そして改革主義的である。人間の尊厳、平等、寛容、多様性がリベラリズムの中核である。特に、「寛容」の喪失が、現代社会の紛争と混乱をもたらしていることを危惧し、「中庸」の重要性を指摘している。同感である。「寛容」も「多様性」も、各人・各団体の都合の良いように偏って主張すれば社会は歪む。それを止揚するには、「中庸」の哲学が大事だと思う。
リベラリズムに代替案などない。
本書の最終章で「自由主義社会の原則」として、「リベラリズムの原則」が掲げられている。「まず、古典的リベラル派は政府の必要性を認め、経済成長と個人の自由にとって不可避の敵として国家を悪者にしてきたネオリベラリズム(新自由主義)の時代を乗り越える必要がある」「連邦主義を真剣に考え、権力を最も低い適切なレベルの統治機構へ移譲することである」「言論の限界を適切に理解した上で、言論の自由を守る必要があることである。リベラルな社会は、個人を取り囲むプライバシーの領域を尊重する必要がある」「人間の自律性は無制限ではないという認識と関係がある。リベラルな社会は、人間の尊厳、つまり個人は選択ができるのだということに根ざした尊厳が平等であることを前提としている。・・・・・・社会がまとまろうとするのであれば、公共心、寛容さ、開かれた心、公共問題への積極的な関与を優先させる必要がある」などと言う。
リベラリズムへの不満、リベラリズムの危機にある今、それらを再び甦らせる復権の作業、努力が人類には重要だと思う。
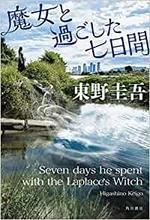 驚くべき特殊能力を持つ羽原円華が謎を解く「ラプラスの魔女シリーズ」第3弾。親子2人で暮らす中学生の陸真の父・月沢克司が、川で遺体となって発見される。克司は元警察官で、全国に指名手配されている犯人の顔写真を覚えて、街で見つけ出すスペシャリスト、「見当たり捜査員」だった。陸真は羽原円華と出会い、「あたしなりに推理する。その気があるなら、ついてきて」と言われ、一緒に動き始める。円華は美しい魅力的な女性だが、驚くべき特殊能力を持ち、危険をものともせず謎の解決に切り込んでいく。そして、17年前のT町一家3人強盗殺人事件に関係していることに至る。この事件は迷宮入りとなっていたが、10年以上経ってから匿名の情報提供があり、追い詰められた犯人が海に身を投げ終決していた。しかし、父親の克司は違和感を持って事件を追い続けていたようであった。円華は.「あのニ人――陸真と照菜ちゃんに、お父さんの本当の姿を見せてやりたい」と思う。照菜ちゃんは、円華が面倒を見ているエクスチェンジドで、声は出せないが極めて優れた記憶能力を持っていた。
驚くべき特殊能力を持つ羽原円華が謎を解く「ラプラスの魔女シリーズ」第3弾。親子2人で暮らす中学生の陸真の父・月沢克司が、川で遺体となって発見される。克司は元警察官で、全国に指名手配されている犯人の顔写真を覚えて、街で見つけ出すスペシャリスト、「見当たり捜査員」だった。陸真は羽原円華と出会い、「あたしなりに推理する。その気があるなら、ついてきて」と言われ、一緒に動き始める。円華は美しい魅力的な女性だが、驚くべき特殊能力を持ち、危険をものともせず謎の解決に切り込んでいく。そして、17年前のT町一家3人強盗殺人事件に関係していることに至る。この事件は迷宮入りとなっていたが、10年以上経ってから匿名の情報提供があり、追い詰められた犯人が海に身を投げ終決していた。しかし、父親の克司は違和感を持って事件を追い続けていたようであった。円華は.「あのニ人――陸真と照菜ちゃんに、お父さんの本当の姿を見せてやりたい」と思う。照菜ちゃんは、円華が面倒を見ているエクスチェンジドで、声は出せないが極めて優れた記憶能力を持っていた。
AIによる監視システムが強化されていく日本。「ゲノム・ モンタージュがあれば、今の世の中それがどこの誰かを付き止めるのは実に容易い」「社会システムに革命を起こす。その革命とは、全国民のDNA型データベースの構築だ」・・・・・・。しかし熟練の「見当たり捜査員」は、ゲノム・モンタージュを超えることが描かれている。
最後まで緊迫した攻防が続く。とともに、疑問が全てスッキリ解き明かされるのが心地良い。

