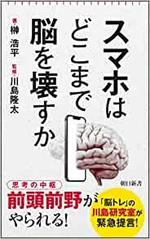 「人類は、オンライン習慣にどっぷり浸かってしまい、前頭前野の機能が失われ、滅びゆく運命をたどってしまうのか。それともスマホという危険で便利なものを使いこなし、前頭前野の機能を手放すこともなく生き延び、さらなる繁栄を遂げていくのか」「このまま対策を講じなければ、オンライン習慣によって前頭前野の機能が衰え、『ものを考えられない』『何かに集中することができない』『コミニュケーションが取れない』、そんな人たちで溢れかえってしまうのではないかと危機感を覚える」と言う。10年以上にわたって、数万人の小中学生を追跡調査し、脳科学の立場で分析した知見を示す。「脳トレ」の川島教授率いる東北大学加齢医学研究所の研究成果だが、大変恐ろしい結果の数々だ。
「人類は、オンライン習慣にどっぷり浸かってしまい、前頭前野の機能が失われ、滅びゆく運命をたどってしまうのか。それともスマホという危険で便利なものを使いこなし、前頭前野の機能を手放すこともなく生き延び、さらなる繁栄を遂げていくのか」「このまま対策を講じなければ、オンライン習慣によって前頭前野の機能が衰え、『ものを考えられない』『何かに集中することができない』『コミニュケーションが取れない』、そんな人たちで溢れかえってしまうのではないかと危機感を覚える」と言う。10年以上にわたって、数万人の小中学生を追跡調査し、脳科学の立場で分析した知見を示す。「脳トレ」の川島教授率いる東北大学加齢医学研究所の研究成果だが、大変恐ろしい結果の数々だ。
「前頭前野は、ものを考えたり、理解したり、覚えたりといった私たちが知的な活動をする上で必要な認知機能を支えている。さらに、感情をコントロールしたり、他人の気持ちを推し量ったりするなど、社会生活を営む上で必要なコミニケーションに関わる機能も支えている」「その前頭前野の成長期にあたる10代。勉強や仲間たちとの豊かなコミニュケーションを通して、前頭前野を鍛え、発達させていくことが重要だが、スマホはその反対で妨げる。大人にとっても仕事や日常生活のなかで、意識的に前頭前野を使い、認知機能を維持することが必要」「記憶を蓄える機能を持つ海馬は、成人後にも神経細胞が増加する」・・・・・・。その前頭前野は、どうしたら鍛えられるのかといえば、「使うこと」だと言う。
調査結果は恐ろしいものだ。「スマホの使い過ぎが、子供たちの学力を破壊している」「勉強してもよく寝ても『3時間以上のスマホ』で台なしになる」「浅い眠りのレム睡眠の時に記憶を定着させるが、睡眠不足はそれを奪う」「スマホ横目に3時間勉強しても、成果は30分(脳は複数の物事を並行して行うのが苦手)、集中が大事だが通知音が鳴るだけで集中力が低下」「スマホやタブレットでの学習は、脳が働かない(知らない言葉を調べるときに、紙の辞書を引いた場合は、脳の活動が急激に上がる)」「スマホを使い、脳にラクにさせていると脳の発達が損われる」・・・・・・。
「コミニュケーションが、脳の発達には欠かせない」「オンラインと対面ではコミニュケーションの質が違う。『つながっている』と感じる時、脳と脳も同期する」「オンライン・コミニュケーションでは『一人でボーッとしている状態と変わらない』」「脳の活動の同期という現象は、コミニュケーションの質と関係していて、人と人との共感や共鳴といったものを反映している」「なぜオンライン会話では、脳が同期しないのか。会話において目を合わせる視線が重要」・・・・・・。
そして、「前頭前野の『自己管理能力』で、スマホから身を守れ!」と言い、警告とともに対策を示す。
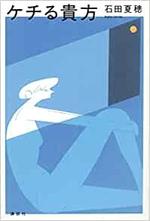 「冷え性」で悩む女性、「脂肪吸引」にはまる女性の心象。こういうテーマを、赤裸々に描いた小説はあまりない。しかも「語り」が、率直で明るく、いわば「男前」で、とてもいいテンポ。2つの短編で構成される。
「冷え性」で悩む女性、「脂肪吸引」にはまる女性の心象。こういうテーマを、赤裸々に描いた小説はあまりない。しかも「語り」が、率直で明るく、いわば「男前」で、とてもいいテンポ。2つの短編で構成される。
「ケチる貴方」――。「生まれてこの方、自分よりての冷たい人間に会ったことがない」から始まる。備蓄用タンクの設計と施工を請け負う中小企業に勤める女性。こんなことがあるかと思うほど、寒くて寒くてしょうがない。ぽっちゃりしているのに、なぜこの身体はかたくなに熱を生産しないのか。私の代謝機能はどうなっているのか。心臓の動悸が激しく打つが、心臓も冷え性も、意識してもどうしようもないものの異常は、自分にしかわからない苦悩だ。ところが温活が功を奏し、身体が温たかになり排便もあリ、体重が激減するという変容が・・・・・・。「ケチっては駄目だ。ケチな肉体は、ケチな魂に由来するのだから。私は迷いを振り払うように、ことさらご機嫌に振る舞った」「許す心、である。ここで怒ってはならぬ」・・・・・・。誰にもわからないようにしている自己を嫌悪する心への向き合い方。
「その周囲、五十八センチ」――。「脚が太いと、人生は、ものすごく難易度が上がる」「私の脚は、生来、人並み外れて太かった」――。脂肪吸引を始めて、次から次へとはまっていく。そして、「確かに私は人並みの体型になってからというもの、人に寛容になった。ごく自然のこととして、いちいち人を疑ったり嫌ったりせず世を渡っていけるようになったのだ。・・・・・・私は、この変化に自尊心というものの持つ力をまざまざと知り、それをつい最近まで自分が持っていなかったことに愕然とした」・・・・・・。見た目の判断。人は内面だ、などと無邪気に言う奴。これらの表現が絶妙。
 「科学と非科学の間に」が副題。昨年のノーベル物理学賞は、「量子もつれの実験、ベルの不等式の破れの確立、量子情報科学の先駆的研究」として3名に与えられた。最近は「量子コンピューター」が大きな話題を呼んでいる。本書は、アリストテレスの物理学から量子もつれまで、「宇宙とは何か」「時間とは、空間とは」「生命とは何か」を追い続けた科学者・哲学者の戦いの軌跡を描く。そして「ニュートン力学、アインシュタインの相対性理論」から「量子力学、量子もつれ」に至る世界を、科学者たちの研究・論争を通じて、わかりやすく(それでも難解だが)解説している。著者も訳者も極めてクリア。特に、アインシュタインとユングとパウリの交流など、人間模様は面白い。ユングは、精神的に不安定だったパウリの治療を行っていたようだが、心理学と物理学が触発しあい、非因果的な作用としてシンクロニシティという概念に到達する。パウリは量子力学の「量子もつれ」、ユングは深層心理学から「シンクロニシティ」に迫ったわけだ。
「科学と非科学の間に」が副題。昨年のノーベル物理学賞は、「量子もつれの実験、ベルの不等式の破れの確立、量子情報科学の先駆的研究」として3名に与えられた。最近は「量子コンピューター」が大きな話題を呼んでいる。本書は、アリストテレスの物理学から量子もつれまで、「宇宙とは何か」「時間とは、空間とは」「生命とは何か」を追い続けた科学者・哲学者の戦いの軌跡を描く。そして「ニュートン力学、アインシュタインの相対性理論」から「量子力学、量子もつれ」に至る世界を、科学者たちの研究・論争を通じて、わかりやすく(それでも難解だが)解説している。著者も訳者も極めてクリア。特に、アインシュタインとユングとパウリの交流など、人間模様は面白い。ユングは、精神的に不安定だったパウリの治療を行っていたようだが、心理学と物理学が触発しあい、非因果的な作用としてシンクロニシティという概念に到達する。パウリは量子力学の「量子もつれ」、ユングは深層心理学から「シンクロニシティ」に迫ったわけだ。
ニュートンは「重力」によるニュートン力学を示し、アインシュタインは「この世に光の速度より早く動くものは存在しない」「時間と空間は歪む」との相対性理論を提唱したが、量子もつれについては「幽霊のような遠隔作用」と断じた(アインシュタインはニュートンの「遠隔作用」を棄却した事が自身の主な功績の一つだと考えていた)。光などの伝達ではなく、瞬時に、それも遠い宇宙の彼方であっても相関する量子もつれは、不可思議極まりない現象であったのだ。それは幾世紀にもわたって考察されてきた原因が結果をもたらすという思考、原因の発生と同時に起こりうる現象など存在しないという思考に根本的な揺さぶりをかけることになる。昨年のノーベル物理学賞「量子もつれの存在」は、宇宙と小宇宙たる生命の真理について、またアインシュタインも認めなかった量子力学について、画期的な通過点(重要な一里塚)となるものだ。
20世紀初頭のアインシュタインの偉大な功績は、誰人も認めるものだが、ハイゼンベルク(1927年に不確定性原理発表、微視的な世界では位置と運動量、時間とエネルギーといった特定の組の物理量を同時に正しく測定することができない)、シュレーディンガー(電子が物質波であると想定し、その波動を力学的運動方程式・シュレーディンガー方程式の解であるとして表した)らの量子力学の一方で、パウリとユングの交流が、「量子もつれ」と「シンクロニシティ」が連関する思考を生んだ。1952年、ユングとパウリは2人の研究の集大成として共著「自然現象と心の構造」を発刊している。不思議なシンクロであり、もつれのような気がする。集合的無意識、対称性の力、スピンの謎めいた性質、光の速度よりも早く瞬時にシンクロする量子もつれーー量子論は物理学のみならず、宇宙論、生命論、化学や生物学、そして量子コンピューターなどの科学技術社会にも衝撃的なパラダイムシフトを生んでいる。研究の激流は速い。
 「アーモンド」「三十の反撃」のソン・ウォンピョンの八つの短編集。韓国に限らず、近代社会に内包される課題に、逡巡し懊悩する人々の心象、人間関係などの葛藤、人間存在への問いかけなどが描かれる。短い切れ味のある文章と表現は、冴え渡っている。「家」は安全地帯であるとともに、閉じこもりの拠点でもある。「楽しい我が家」といっても、一人ひとりの内面は孤立し複雑だ。8篇は極めて多彩だが、いずれも人間心理の深淵を突いている。吉原さんの訳もいいし、解説も見事。
「アーモンド」「三十の反撃」のソン・ウォンピョンの八つの短編集。韓国に限らず、近代社会に内包される課題に、逡巡し懊悩する人々の心象、人間関係などの葛藤、人間存在への問いかけなどが描かれる。短い切れ味のある文章と表現は、冴え渡っている。「家」は安全地帯であるとともに、閉じこもりの拠点でもある。「楽しい我が家」といっても、一人ひとりの内面は孤立し複雑だ。8篇は極めて多彩だが、いずれも人間心理の深淵を突いている。吉原さんの訳もいいし、解説も見事。
「四月の雪」――。別れを決めた夫婦に、フィンランドから民泊を求めてマリが来る。その"触媒"は何をもたらしたか。「怪物たち」――。ある言葉から生まれた夫婦の亀裂。何をやってもその憎悪と亀裂は閉鎖空間の中で増殖していく。そこに生まれた「怪物のような双子」の秘密の心象風景の恐ろしさ。
「z i p」――。結婚したが夫に望みを打ち砕かれ続ける女。「バカだったんだ。私がバカだった。バカな女だったんだ」・・・・・・。しかも儲け話だと信じて1億ウォンも失ったという事実を知ったとき。またライバル的な女の人生が気になるが・・・・・・。
「アリアドネの庭園」――。約50年後の未来の韓国。高齢者が住む住宅でも、保護施設のユニットDランクに住む女。少子高齢社会が進み、若者の負担が重く高齢者への嫌悪感が広がる。高齢者は尊厳死が夢となるというのだ。
「他人の家」――。部屋探しのアプリで、格安の超優良物件に出会った女。格安は訳あり物件だからだが、加えて本来2人で暮らすはずの部屋を4人で違法にルームシェアする。ある日、そこへオーナーが急遽訪れることに・・・・・・。さぁ、大変。「パラサイト 半地下の家族」を想い起こす。「箱の中の男」――。「僕は箱の中に住んでいる。きっちり閉ざされた安全な箱の中に」「心強い存在だった自慢の兄。トラックにはねられそうな子供を助け、自分はずっと寝たきり」となった。だから、自分は「わざわざ人に感謝されることなどしなければいい、絶対に絶対に、自分と関係のないことには関わってはいけない」と言っていた。兄は「ひとつだけ言えることがある。どっちをとったとしても、誰かは辛い思いをするんだよ。逆に言えば、誰かは喜ぶことになるんだ」・・・・・・。そして事件が起きる。
「文学とは何か」――。小説を書くということの意味と格闘。書けなくなる魔法の始まりと終わり。「開いていない本屋」――。閉まっているけれども、開いている本屋。今日も開いていなかった本屋が開店する。
末尾で、著者は言う。「私たちは異様な時代を生きている。・・・・・・ここでの大衆は、実体のない怪物に近いものだ。この怪物は、正義をまとった非理性とニセモノの道徳を武器としてかざし、決して鏡を見ようとしないために、逆に標的にした誰かを怪物に仕立て上げ、打ち負かさなくては気がすまないのだ。・・・・・・自分と他人をじっくり見つめるという行為をなおざりにすることがないようにしよう」と言っている。
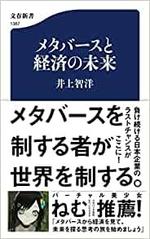 著者の2016年に出版した「人工知能と経済の未来」は刺激的で、特化型AIを超えて2030年頃から汎用AIが登場すると言っていた。シンギュラリティをはじめとする予測が一旦沈静化したが、今またチャットGPTが話題を呼んでいる。AI技術の進展はこれからも進む以上、課題に取り組む事は重要だが、同時に日本としては、デジタル遅れの現実を見て、進める力を加速する必要がある。熱い目が注がれるメタバース。著者は、すでにメタバース後進国になりつつある日本だが、「メタバースは日本経済逆転のチャンス(日本には、漫画やアニメなど、メタバースにふさわしいコンテンツがたくさんあり能力もあり有利)」「アニマルスピリッツを取り戻し、資金を思い切って投入して実行せよ」「先端技術と伝統文化を生かすサイバーオリエンタリズムと日本未来主義でエンジン全開で突き進もう」と呼びかける。
著者の2016年に出版した「人工知能と経済の未来」は刺激的で、特化型AIを超えて2030年頃から汎用AIが登場すると言っていた。シンギュラリティをはじめとする予測が一旦沈静化したが、今またチャットGPTが話題を呼んでいる。AI技術の進展はこれからも進む以上、課題に取り組む事は重要だが、同時に日本としては、デジタル遅れの現実を見て、進める力を加速する必要がある。熱い目が注がれるメタバース。著者は、すでにメタバース後進国になりつつある日本だが、「メタバースは日本経済逆転のチャンス(日本には、漫画やアニメなど、メタバースにふさわしいコンテンツがたくさんあり能力もあり有利)」「アニマルスピリッツを取り戻し、資金を思い切って投入して実行せよ」「先端技術と伝統文化を生かすサイバーオリエンタリズムと日本未来主義でエンジン全開で突き進もう」と呼びかける。
「メタバースの普及は、身体性の喪失や運動不足といった問題をもたらす可能性がある。一方で、通勤ラッシュ、都市部の高い住宅価格、地域間格差、地球温暖化といった問題を解消し得る力を持っている」「対人恐怖症やコミニュケーション障害を抱えた人たち、体が不自由で、寝たきりの人たちが、人と交流したり、自由に活動したりできるようになり、弱い立場の人たちのQOL(生活の質)を高めることもできる。仕事や教育の効率性、豊かな娯楽を享受し、経済、文化の新しい可能性にも満ちている」と言う。人間の本質とは何か。パスカルは「人間は考える葦である」と言ったが、考える機械・ AIが出現して、思考が人間だけではないとなると、「人間は意識を意識する動物である」。そこに動物やAIとの違いがあると言う。
「人類は、今から20年以内に、目覚めている多くの時間をコンピュータ上の仮想空間で過ごすようになる。私は本気でそう考えている」「この世界は、実空間をデジタル技術によってコントロールし、住み良い社会にしていく『スマート社会』と『メタバースの世界』に分岐する」「AIやロボットによる生産活動の自動化の果てにやってくる経済は『純粋機械化経済』で、AIやロボットを含む機械だけで、およそ生産活動が行えるようになる。2045年から60年ぐらい。人間の仕事はクリエイティビティー系、マネジメント系、ホスピタリティ系のCMH」「純粋機械化経済は実空間。メタバース内の経済は、労働者も機械設備もいらない『純粋デジタル経済』。その特徴は①資本財ゼロ②限界費用ゼロ③独占的競争――の3つ。そして、供給と空間と移動速度の無限性といった性質を持つ」・・・・・・。
さらに「メタバースとお金の未来」「資本主義はどう変わるか?」で、仮想通貨、DAOなどの分散型組織に論究する。「仮想通貨やDA O、NFTといったW e b 3・0的な技術は広く使われるようになり、メタバースも普及して、資本主義は新たな段階を迎えると思う」と言う。「頭脳資本主義」だが、実物財の世界では、AIなどの先端技術が生産性やイノベーションに与える影響は大きい。一方、デジタル経済の方では、資本財がほとんど必要ないので、デザインのできるクリエイター、面白いアイディアを出す人、イベントをプロデュースできる能力のある人などが活躍する世界になる。低所得層が増え、中間所得層も少ない。ゆえに「ベーシックインカムが必要」と言う。地球温暖化を防ぐために、最今は脱成長の「減速主義」を唱える者もいるが、著者は成長を目指し驀進する「反緊縮加速主義」を主張している。
「人類が身体を捨て去る日――メタバースの先にある未来」――。身体性の欠如は、今後の悩み深い問題だ。「BM I(脳と機械を通信させる技術)」は、障害や病気の人にとっては救いとなる技術。BB I(脳と脳を通信させる技術)は、自分と他人の脳をつなぐわけだから、極めて恐ろしい」と述べている。大変な問題であるだけに、早くからの議論が不可欠となる。人類の未来はユートピアでは無いのかもしれないし、ディストピアでもない。まさに人間にかかっている。

