 「きみがぼくにその街を教えてくれた・・・・・・ぼくは17歳で、きみはひとつ年下だった。・・・・・・『街は高い壁にまわりを囲まれているの』ときみは語り出す」「本当のわたしが生きて暮らしているのは、高い壁に囲まれたその街の中なの・・・・・・今ここにいるわたしは、本当のわたしじゃない。その身代わりに過ぎないの。ただの移ろう影のようなもの」と、いきなり不思議な世界に引き込む。実際の世界で恋をした「ぼく」は、突然消えた「きみ」を求めて幻想的な街に入り込む。「きみ」のいる図書館で、「ぼく」に託された仕事は「夢読み」だった。名前がなく、時がなく、単角獣のほかに動物はいない。驚くことに自分の影が引きはがされ別になっていた。・・・・・・やがて、影は街を出ようとし、私は残ろうと決断したのだが・・・・・・。
「きみがぼくにその街を教えてくれた・・・・・・ぼくは17歳で、きみはひとつ年下だった。・・・・・・『街は高い壁にまわりを囲まれているの』ときみは語り出す」「本当のわたしが生きて暮らしているのは、高い壁に囲まれたその街の中なの・・・・・・今ここにいるわたしは、本当のわたしじゃない。その身代わりに過ぎないの。ただの移ろう影のようなもの」と、いきなり不思議な世界に引き込む。実際の世界で恋をした「ぼく」は、突然消えた「きみ」を求めて幻想的な街に入り込む。「きみ」のいる図書館で、「ぼく」に託された仕事は「夢読み」だった。名前がなく、時がなく、単角獣のほかに動物はいない。驚くことに自分の影が引きはがされ別になっていた。・・・・・・やがて、影は街を出ようとし、私は残ろうと決断したのだが・・・・・・。
そして、「こちらの『現実の世界』にあって、私は中年と呼ばれる年齢にさしかかった」のだが、大学を卒業後、ずっと勤めていた書籍取次業の会社を突如として辞職。福島県の小さな町の図書館長となるが、そこで不思議な事象に遭遇する。面接し採用してくれた素晴らしい人格を持つ前の図書館長が実は死亡していた幽霊であったのだ。さらに、不思議な能力を持つ少年に出会い、少年は、「その街に行かなくてはならない」「<古い夢>を読む。僕にはそれができる」と言うのであった。
壁に囲まれた世界とその外側の世界。こちらの世界とあちらの世界。現実と非現実。意識と非意識との薄い接面。生きているものと死んだものとが一つになった混在。本体と影。壁に囲まれた街には、時間は意味を持たず、人の抱く迷い、嫉妬、恐れ、苦悩、憎しみ、懊悩、自己憐憫、夢、愛などの感情は無用のもので、害をなすものととして描かれている。人間の心の深層には、あらゆるものをため込む蔵のようなものがあるとする唯識論に小説として迫っていると思った。深層心理の深淵だ。また、有の世界と無の世界が、実は「空」の世界が、有と現れ、無と隠れることを示していることも想起した。さらにまた、昨年のノーベル物理学賞の「量子もつれ」が、小説の世界で表現すると、このようになるのかと思ったものだ。いずれにしても、人間の存在が宇宙生命のなかの小宇宙として存在し、可視の世界は、その一部分、一端であることを示しているといえよう。それゆえに「壁」は「不確か」であり、能の世界で言う「あわい」を生きるということなのかとも思った。
そうした面白さとともに、村上ワールドとして、私は、福島県の小さな町で知り合ったカフェの「彼女」との語らい。音楽を聴いて、ウイスキーを少し飲み、落ち着いて、深さと経験に満ちた洒落た大人の会話をする、あの描写は際立っていいと思う。こっちもまた私にとっての村上ワールドだ。
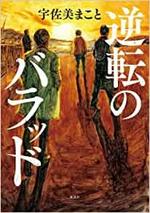 愛媛県松山市にある港町・三ッ浦町。定年間近の新聞記者・宮武弘之、銭湯「みなと湯」の主人・戸田邦明、そこで働く釜焚き係で元暴力団員の定本吾郎、骨董店「天狗堂」の小松富夫。「3匹のおっさん」とはちょっと違うが、仲間のおじさんたちが、「みなと湯」の融資に真剣に取り組んでくれていた瀬戸内銀行三ッ浦支店勤務の丸岡将磨が、溺死体で発見されたことから、悪に立ち向かうことになる。その背後には、松山西部病院の不正融資に大物金融ブローカーや暴力団などの反社会的勢力が絡むなど、かなり深い闇があった。本丸は松山西部病院理事長の坂上象ニ郎。
愛媛県松山市にある港町・三ッ浦町。定年間近の新聞記者・宮武弘之、銭湯「みなと湯」の主人・戸田邦明、そこで働く釜焚き係で元暴力団員の定本吾郎、骨董店「天狗堂」の小松富夫。「3匹のおっさん」とはちょっと違うが、仲間のおじさんたちが、「みなと湯」の融資に真剣に取り組んでくれていた瀬戸内銀行三ッ浦支店勤務の丸岡将磨が、溺死体で発見されたことから、悪に立ち向かうことになる。その背後には、松山西部病院の不正融資に大物金融ブローカーや暴力団などの反社会的勢力が絡むなど、かなり深い闇があった。本丸は松山西部病院理事長の坂上象ニ郎。
人生の後半のおじさんたち。野心も失せ後悔もあるが、突如飛び込んできたこの大事件に、色めき立つ。その姿を、ユーモラスに、そして痛快に描き出す。どんでん返しに次ぐどんでん返しは、まさに「逆転のバラッド」。その一方で、外ばかり見て家庭を顧みないおじさんの悲哀も身に沁みる。
「あなたには、何も見えていない。新聞記者なのに、人の心がわかってない。そんな人に良い記事なんか書けるわけがない」「事件は人間が起こすものだ。背後には人間の欲望、邪念、自己保身、傲慢さ、脆弱さなど、数々の感情が渦巻いている。ただ起こった事象だけを見ていたのでは、事件というものを真に理解できない。坂上は自ら命を絶ってしまったが、それで全てが許されるというものではない。最後に死という逃避を選んだ彼は、どんな心境だったのか。記事を読んだ人々に、そこまで思いを馳せてもらいたかった。正しい事はなされたのか、どうなのか」・・・・・・。
しぼみつつあるおじさんたちの逆転劇は、とても楽しい。
 「思考の座標軸を立て直す」が副題。時代の変わり目を表出する難問に直面してる今、「思考の座標軸」を立て直すことは極めて重要。「私たちは今こそ、近現代日本における『保守』と『リベラル』の議論の蓄積を再確認し、その意義を現代的に発展させていく時期に差し掛かっている」と言う。米英をはじめ保守・リベラルの意味合いは各国で異なるが、日本としての源流を探りつつ深めることは、政治的にも思想的にも意義深いと思う。
「思考の座標軸を立て直す」が副題。時代の変わり目を表出する難問に直面してる今、「思考の座標軸」を立て直すことは極めて重要。「私たちは今こそ、近現代日本における『保守』と『リベラル』の議論の蓄積を再確認し、その意義を現代的に発展させていく時期に差し掛かっている」と言う。米英をはじめ保守・リベラルの意味合いは各国で異なるが、日本としての源流を探りつつ深めることは、政治的にも思想的にも意義深いと思う。
「保守」は、伝統を尊重しつつ秩序ある漸進的な改革を目指す(急進的改革ではない)。「保守主義とは、伝統の中で培われた制度や慣習を重視し、そのような制度や慣習を通じて歴史的に形成された自由を発展させ、秩序ある漸進的改革を目指す思想や政治運動である」。「リベラル」は、個人の自由や寛容の原則、多様性を尊重する。「リベラル」と言う言葉は、「気前のいい」や「寛大な」を指すもので、他者への配慮や寛容の精神が含意されている。「リベラリズムは、他者の恣意的な意志ではなく、自分自身の意志に従うという意味での自由の理念を中核に、寛容や正義の原則を重視し、多様な価値観を持つ諸個人が共に生きるための社会やその制度づくりを目指す思想や政治運動」。従って両者は対立概念ではない。日本では、「保守」の伝統を考える場合、明治維新と第二次世界大戦というニつの断絶があり、歴史の基本的な継続性・連続性において大きな問題を抱えこんだ。また「保守」の対立概念として「革新」「急進」があるが、東西冷戦構造の崩壊と経済発展による豊かさの享受のなかで、鮮明な対立図式が崩れていっている。一方、リベラルコンセンサスのベクトルは間違いなくあるが、その「リベラル」自体の内実が煮詰められていない。本書は、その本質を源流から探り当てている。その論考に触れつつ、私は「中間大衆論」に先駆けて、庶民大衆を代弁する公明党が1964年結成されたことに思いをめぐらせた。
本書では、保守主義の系譜として、伊藤博文、陸奥宗光、原敬、戦後の吉田茂の「保守本流」などを丁寧に論述する。リベラルについても、福沢諭吉から石橋湛山、清沢冽、さらに戦後においても丸山眞男らにおいて、日本におけるリベラリズムのの重要な達成が見てとれると言う。日本のリベラリズムは政治勢力や幅広い裾野を社会に持つことはなかったが、福沢諭吉をはじめとするこれら人物の影響は大きいとする。「一身独立して一国独立する」の福沢諭吉は「魅力的な人物」「福沢ほどリベラリストの名にふさわしい人物は少ないのではないか」「大切なのは個人であり、その独立である。身分制秩序や、それに基づく人間関係から個人を独立させること、そして逆にそのような個人が自由に活動できるような社会を発展させることこそが、福沢の目指したものであった」「人はいたるところに序列を見出し、卑屈に従うがそれこそ独立自尊を説く福沢にとって我慢できないものであった。・・・・・・・豊臣秀吉が百姓から関白になっても、彼だけが偉くなったのであって、百姓一般の地位が高くなったわけではない。宗教も学問も等しく、『権力の偏重』に屈し、独立した宗教や学問は不在である。見られるのは『精神の奴隷』だけであると福沢は嘆く。果たしてこの福沢の嘆きは過去のものになったと言えるだろうか」と指摘している。
また、福沢諭吉を論述するとともに、丸山眞男(丸山眞男における3つの主体像)、福田恆存(福田恆存と保守思想)、村上泰亮(新中間大衆の時代)などについても力を入れて論述している。常に自ら責任を持って時代の変化の中で思考し続けた人達だ。保守合同してからの自民党は、自由主義的なハト派から、より国家主義的なタカ派まで抱え込んだが、その思想の系譜を、吉田茂、石橋湛山、岸信介、大平正芳とそれを囲む若い知識人に触れて語る。
まさに、「思考の座標軸を立て直す」という熱の伝わる著作だ。
 「ファスト映画・ネタバレ――コンテンツ消費の現在形」が副題。倍速視聴や10秒飛ばしが意外に多くの人の習慣となっていると言う。特に高齢者よりも若者、若者の中でも若年層に行くほどその傾向が大きいようだ。私自身も、「忙しい」「せっかち」「結論を早く得たい」ゆえか、飛ばして観ることがある。ストーリー中心のエンタメではそうする一方、藤沢周平の「花のあと」などの作品は、ほとんどセリフがなく、情景と心理描写が巧みで、そこにこそ味わいがある。飛ばして観るなら意味がない。北野武(ビートたけし)の名作「HANA-BI」の最後で、岸本加世子がたった一言だけを言うシーンが、いまだに心に残っている。「倍速視聴について調査をすればするほど、考察も深めれば深めるほど、この習慣そのものはたまたま地表に表出した現象の一つに過ぎず、地中にはとんでもなく広い範囲で『根』が張られていると確信した」「倍速視聴が現代社会の何を表していて、創作行為のどんな本質を浮き彫りにするかを突き詰めて考えることにした」と現代社会を剔抉したのが本書だ。
「ファスト映画・ネタバレ――コンテンツ消費の現在形」が副題。倍速視聴や10秒飛ばしが意外に多くの人の習慣となっていると言う。特に高齢者よりも若者、若者の中でも若年層に行くほどその傾向が大きいようだ。私自身も、「忙しい」「せっかち」「結論を早く得たい」ゆえか、飛ばして観ることがある。ストーリー中心のエンタメではそうする一方、藤沢周平の「花のあと」などの作品は、ほとんどセリフがなく、情景と心理描写が巧みで、そこにこそ味わいがある。飛ばして観るなら意味がない。北野武(ビートたけし)の名作「HANA-BI」の最後で、岸本加世子がたった一言だけを言うシーンが、いまだに心に残っている。「倍速視聴について調査をすればするほど、考察も深めれば深めるほど、この習慣そのものはたまたま地表に表出した現象の一つに過ぎず、地中にはとんでもなく広い範囲で『根』が張られていると確信した」「倍速視聴が現代社会の何を表していて、創作行為のどんな本質を浮き彫りにするかを突き詰めて考えることにした」と現代社会を剔抉したのが本書だ。
基底にあるのは、「映像作品の供給過多」「現代人の多忙に端を発するコスパ(タイパ)志向」「セリフで全てを説明する映像作品が増えたこと」の3点だと指摘する。現代人は膨大な映像作品をチェックする時間にとにかく追われている。映像メディアだけでなく、SNSも競合相手だ。しかも話題にはついていきたい。無駄は悪でコスパこそ正義。「見たい」のではなく「知りたい」。周囲が大絶賛している作品を知っておきたい。情報強者でありたい。知っているとグループの話の輪に入れる。若年世代にとって仲間の和を維持するのが至上命題、「共感強制力」があると言う。今の若者は、コミュニティで自分が息をしやすくするため、追いつけている自分に安心するために早送りで観るという。
これに加えて、1,980~1990年生まれのY世代(ほぼミレニアル世代)は、「デジタルネイティブ」で、SNSで叩かれたくないという「同調圧力」と「防御意識」が強かったのに対し、1990年代後半から2000年代生まれのZ世代は、「ソーシャルネイティブ」で、SNS上で周りと同程度に自己アピールしたいという「同調志向」と「発信意識」が強いという。Z世代が20歳前後となって社会に躍り出て、たったこの5年で変化しているわけだ。「とりわけZ世代を中心とした層に、『回り道』や『コスパの悪さ』を恐れる傾向が強い」と指摘する。常に"横を見ている"若者たちだ。
中身の濃い芸術的作品を目指す作り手の方と食い違うのは当然だ。「わかりやすく」「セリフで説明しすぎる」「過激で断定的だとネット上でフォロワーを集めやすい」「テレビではテロップが増える」ことになる。情報過多・説明過多・無駄のないテンポの映像コンテンツばかりを浴び続ければ、どんな人間でも「それが普通」と思うようになる。「わかりやすさ」と「作品的野心」の両立という難問に立ち向かうざるを得ないのだ。
SNSが発達し、同調圧力がストレスを生む社会。ブルシットジョブでストレスをため込んで帰り、LINEグループの人間関係にも疲れ果てているのに、考えさせられるドラマなんぞ観たくはない。だが、会話の輪には入りたい。テレビドラマでもスポーツ番組でも、話題とストレス解消を求めたい。それで倍速視聴に至るという。追われるのではなく、中身と情感を追い求めていく反転のサイクルはできないのか。AI、SNS社会の進展するなか、大事な局面に立っている。
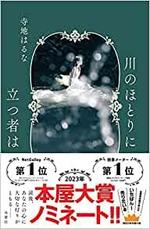 カフェ「クロシェット」の女性店長の原田清瀬は、客として来て知り合った松木圭太と恋人になる。しかし、松木は素直でまっとうで良い人物だが、自分のことについては全く話をせず、違和感が付きまとった。ある日、その松木が歩道橋から転げ落ちて意識不明と警察から連絡がある。親友と喧嘩をして共に転げ落ちたというのだ。親友の名は岩井樹(いつき)。不機嫌になって声を荒らげることもない松木が、なぜ親友と大喧嘩となったのか。なぜ親が駆けつけてこないのか。「いっちゃん」とはどんな関係なのか。松木の部屋に行くと、文字の練習をしている様子だが、これは誰に教えているのか。次々に疑問が噴き上がってくる。
カフェ「クロシェット」の女性店長の原田清瀬は、客として来て知り合った松木圭太と恋人になる。しかし、松木は素直でまっとうで良い人物だが、自分のことについては全く話をせず、違和感が付きまとった。ある日、その松木が歩道橋から転げ落ちて意識不明と警察から連絡がある。親友と喧嘩をして共に転げ落ちたというのだ。親友の名は岩井樹(いつき)。不機嫌になって声を荒らげることもない松木が、なぜ親友と大喧嘩となったのか。なぜ親が駆けつけてこないのか。「いっちゃん」とはどんな関係なのか。松木の部屋に行くと、文字の練習をしている様子だが、これは誰に教えているのか。次々に疑問が噴き上がってくる。
いろいろわかってくる。「小学校低学年の頃、いじめにあっていた松木がいっちゃんにいつも助けられたこと」「いっちゃんは極端に字が書けないが、ディスデクシア(発達性読み書き障害)であること」「親からも周りからも、いっちゃんはアホと言われるが、それは障害を全く理解していないからであること」「松木は母親から『あんたは将来ぜったいとんでもないことをしでかす』と乱暴者扱いをされてきたが、愚弄され続けるいっちゃんを助けるためだったこと」「カフェの従業員・品川さんは、だめな人ではなく、ADHDであったこと」・・・・・・。そして「いっちゃんが好きになった菅井天音に手紙を書こうとし、松木がその手伝いをしていたこと」「天音が乱暴者の小滝という男と同棲し、今逃げているということ」などがわかってくる。
人の本当の姿はわからない。近くで接していても、本当の心はわからない。障害もわからない。善意であっても、助けてもらう行為に、された方が苛立っていることもわからない。
周りを振り回し続ける菅井天音。「川のほとりに立つ者は、水底に沈む石の数を知り得ない」――。天音の心に流れる暗くて深い川。傷ついた人々が、他者に救われ、再生する物語に、幾度も涙を流してきた清瀬だが、「手を差し伸べられた人は、すべからく感謝し、他人の支援を、配慮を、素直に受け入れるべきだと決めつけていたが」・・・・・・。そうではないことを思い知るのだ。人の表面を見ても、内面はわからないし、内面の事は絶対知られたくないと思っている人が多くいる。まして、"善意"などで助けてもらいたくない。短いが重い小説。「あなたの明日がよい日でありますように」と素直に思えることが、最終メッセージと感じる。

