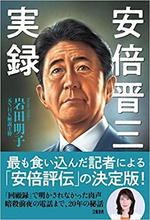 安倍元総理が亡くなって1年になる。「安倍元総理がいれば・・・・・・」と思うことが多くあったし、岩田さんと同じように衆議院第一議員会館1212号室に、ふっと身体が動いてしまう衝動に駆られることも多々あった。それだけ内外の情勢は複雑・混沌、重要案件は押し寄せてきている。「どう考え、どう行動するか。解決の道筋を探り当てるか」――安倍元総理は、「国を背負い」「戦略性を持った」「意欲あるリアリスト」「心優しい、笑顔の良い」政治家だった。帯に「最も食い込んだ記者による『安倍評伝』の決定版! 『回顧録』で明かされなかった肉声、暗殺前夜の電話まで、20年の秘話」とある。その通りだと思うが、長きにわたった激動の毎日を描くには、本書では短かすぎると岩田さん自身も思ったに違いない。
安倍元総理が亡くなって1年になる。「安倍元総理がいれば・・・・・・」と思うことが多くあったし、岩田さんと同じように衆議院第一議員会館1212号室に、ふっと身体が動いてしまう衝動に駆られることも多々あった。それだけ内外の情勢は複雑・混沌、重要案件は押し寄せてきている。「どう考え、どう行動するか。解決の道筋を探り当てるか」――安倍元総理は、「国を背負い」「戦略性を持った」「意欲あるリアリスト」「心優しい、笑顔の良い」政治家だった。帯に「最も食い込んだ記者による『安倍評伝』の決定版! 『回顧録』で明かされなかった肉声、暗殺前夜の電話まで、20年の秘話」とある。その通りだと思うが、長きにわたった激動の毎日を描くには、本書では短かすぎると岩田さん自身も思ったに違いない。
1993年の当選同期、2006年9月に自民党総裁と公明党代表の同時期、その後私は落選し、安倍元総理は失意の毎日という"地獄"の共有、2012年12月、第二次安倍内閣で国土交通大臣で閣内・・・・・・。率直に話し合い、大変にお世話になった。本書を読むなかで、思いが蘇った。9章にわたりまとめている。「第三次政権への夢(台湾有事は5年以内に起きる可能性も排除できない。日本を守るために、私が前線に出る必要が本当にあるかどうか。それは天が決めることだ。仮に、自分が望まれるなら、自然と機運が高まり・・・・・・)」「雌伏の5年間と歴代最長政権」「慰安婦問題と靖国参拝(戦後70年談話がもつ意味)」「トランプと地球儀俯瞰外交(直接差し向かいでのテタテの最大活用)」「拉致問題解決への信念(北朝鮮で殺されるかもしれない。政治家の妻として、覚悟しておいてほしい)」「習近平との対決」「生前退位と未来の皇室像」「スキャンダルと財務省」「岸家と安倍家の葛藤」・・・・・・。アベノミックス・デフレ脱却、平和安全法制、全世代型社会保障、防災・減災・ ・国土強靭化、観光立国日本、憲法論議などは少ない。
「日本再建」「政治とは、現実を直視した臨機応変の自在の知恵である」を共有したと思っている。
 中国、三国時代――。221年、劉備が蜀を建国する。魏の曹操、呉の孫権との長い攻防戦の中での最も小さな国の建国だが、「無垢な人」劉備を慕う関羽、張飛、趙雲、そして諸葛亮孔明は特に名高い。本書は「三国志名臣列伝」の「蜀篇」。この4人に加えて、李恢、王平、費褘の3人。7人を描いている。後の3人は特に劉備の死(223年)以降の活躍となる。「諸葛亮は魏を攻めながら、自分の後の為政の席は蒋琬に、その後は費褘に、という未来図を画いていたのであろう」「蒋琬が亡くなってからニ年後に、馬忠、王平という名将が逝去し、蜀の人材がさびしくなってきた」と言う。蜀の滅ぶのは263年と短い。劉備、それを関羽・張飛・趙雲らが支えて作った国、それを継いだ丞相・諸葛亮の国といって良いだろう。
中国、三国時代――。221年、劉備が蜀を建国する。魏の曹操、呉の孫権との長い攻防戦の中での最も小さな国の建国だが、「無垢な人」劉備を慕う関羽、張飛、趙雲、そして諸葛亮孔明は特に名高い。本書は「三国志名臣列伝」の「蜀篇」。この4人に加えて、李恢、王平、費褘の3人。7人を描いている。後の3人は特に劉備の死(223年)以降の活躍となる。「諸葛亮は魏を攻めながら、自分の後の為政の席は蒋琬に、その後は費褘に、という未来図を画いていたのであろう」「蒋琬が亡くなってからニ年後に、馬忠、王平という名将が逝去し、蜀の人材がさびしくなってきた」と言う。蜀の滅ぶのは263年と短い。劉備、それを関羽・張飛・趙雲らが支えて作った国、それを継いだ丞相・諸葛亮の国といって良いだろう。
戦にはどこまでも人材だ。それを惹きつけるリーダーの徳と質。「玄徳は珍しいほど無垢な人なのだ。関羽はここで劉備の本性を見たおもいで感動した。けがれるれる一方の世で、どこまで無垢をつらぬいてゆけるか、それをみとどけたくなった」「劉備ほどおもしろい人に遭ったことがない。どこにも欲がみあたらない」「劉備とはつくづくふしぎな人である。ここでも死ななかった」「自分の命運は、天が決めてくれる。おそらく劉備はそういう心胆のすえかたをしていたであろう。人の智慧などたかが知れていて、かえっておのれを縛るものになる。そうおもっていたふしがある」「これを徳の力というのだ、関羽は張飛にいったが、なるほどそういうしかあるまい。若いころから劉備の近くにいた張飛は、劉備から感じられる、心意気、が好きだった。劉備は早くに父を亡くしたので、母しかいないその家は貧しかった。それも張飛は知っている。ところが、なぜか劉備には吝嗇のにおいがしなかった」・・・・・・。
関羽も張飛も孫権を嫌った。「曹操は敵であるとはいえ、こんなうすぎたないことはせぬ」。張飛は関羽を兄と慕う。「人には表と裏がある。が、なんじには表しかない。めずらしい正直者ではあるが、敵を敵として見るばかりが能ではない。平定するということは、地を取るというよりも、人を取るのだ」と関羽は張飛を訓戒する。
諸葛亮のあざなは「孔明」――。「孔は、とても、たいそう、などの意味をもつ。つまり孔明とは、とても明るい、ということである」――。「王平」の章では「王平は残留の兵を拾い、逃げまどっている将卒を収めて、帰還した。天下に恥をさらし、蜀の全国民を失望させた大敗となった。すべてが順調であったのに、それを馬謖らがぶちこわしたのである。諸葛亮の嘆きも怒りもおさまらなかった。・・・・・・だが、街亭での大敗の原因は、諸葛亮が先鋒の将に馬謖を選定したことにある」と描いている。その3年後が五丈原だ。234年、諸葛亮は死ぬ。
 「脳科学者とマーケターが教える『買い物』の心理」が副題。マット・ジョンソンが脳科学者、プリンス・ギューマンがマーケター。いかに企業が広告などによって、消費者の思考や感情を刺激し、「欲しい」を導くか。消費社会の隠れた仕組みを明らかにする。大変興味深く面白い。「広告の時計の針はきまって、10時10分を指している。10時10分の位置にすると、時計の針が笑顔に見え、見る人の感情にプラスの影響を及ぼし、購買意欲を高める」「ファストフードのロゴは、赤か黄色。赤は生理的な刺激を生む色で無意識に切迫感を伝達し、黄色は無意識に親しみやすさや楽しい感情を伝達すると信じられてきた」「脳の神経活動を観察するf MRI装置を使ってワインを飲んだ時の快楽中枢の反応を調べたところ、『高価なワイン』と告げられて飲んだワインの方が『安価なワイン』と言われた時より快楽中枢は激しく発火した」「amazonのaの文字の下から zの下まで矢印が伸びているマークは笑顔の形を示している。矢印は輸送。それで購買意欲を高めている」・・・・・・。消費者が知らないうちに巧みな戦略があるわけだ。人間の心理には快と不快、論理と感情、知覚と現実という大いなる矛盾が潜み、人は、危険と安心のどちらにも惹きつけられる生き物だ。本書は、さらに、神経科学の観点からの記憶、意思決定、共感、つながり、ストーリー、サブリミナル効果、注意、体験とはどういうものかを消費主義という文脈から抉り出している。「見えていなかったものを見る力を手に入れたゆえに、乗客ではなく、パイロットとして消費の世界で舵をとっていけるはず」と消費者に呼びかけている。
「脳科学者とマーケターが教える『買い物』の心理」が副題。マット・ジョンソンが脳科学者、プリンス・ギューマンがマーケター。いかに企業が広告などによって、消費者の思考や感情を刺激し、「欲しい」を導くか。消費社会の隠れた仕組みを明らかにする。大変興味深く面白い。「広告の時計の針はきまって、10時10分を指している。10時10分の位置にすると、時計の針が笑顔に見え、見る人の感情にプラスの影響を及ぼし、購買意欲を高める」「ファストフードのロゴは、赤か黄色。赤は生理的な刺激を生む色で無意識に切迫感を伝達し、黄色は無意識に親しみやすさや楽しい感情を伝達すると信じられてきた」「脳の神経活動を観察するf MRI装置を使ってワインを飲んだ時の快楽中枢の反応を調べたところ、『高価なワイン』と告げられて飲んだワインの方が『安価なワイン』と言われた時より快楽中枢は激しく発火した」「amazonのaの文字の下から zの下まで矢印が伸びているマークは笑顔の形を示している。矢印は輸送。それで購買意欲を高めている」・・・・・・。消費者が知らないうちに巧みな戦略があるわけだ。人間の心理には快と不快、論理と感情、知覚と現実という大いなる矛盾が潜み、人は、危険と安心のどちらにも惹きつけられる生き物だ。本書は、さらに、神経科学の観点からの記憶、意思決定、共感、つながり、ストーリー、サブリミナル効果、注意、体験とはどういうものかを消費主義という文脈から抉り出している。「見えていなかったものを見る力を手に入れたゆえに、乗客ではなく、パイロットとして消費の世界で舵をとっていけるはず」と消費者に呼びかけている。
「脳の感覚で、ダントツでいちばん強いのは視覚だ。視覚は大脳皮質の大部分を支配し、視覚情報の処理と解釈だけに、脳の約3分の1が使われている」「ブランドは思いに基づくメンタルモデルに入り込む」「脳は常にアンカーを下ろす場所を探している。アンカーを固定する(比較の基準)」「感情の記憶とピーク・エンド効果(出来事のピークは、出来事の記憶に影響を及ぼし、最終的な印象を決定づける)」「YouTubeが自動再生機能を実装したすぐ後に、Netflixが『次のエピソード』を自動的に再生するというよく似た機能を採用し、シリーズ物を視聴すると、次の回が自動で再生される流れを初期設定とした」「この空腹による衝動買い狙いに特化したマーケティングを繰り返し行っている企業がある」「脳科学で衝動に耐える力を表す尺度・ Kファクターを利用した販売戦略が行われる。 Kファクターが下がれば購入意欲を抑えにくくなる。『期間限定』『数量限定』『送料無料』などはそれだ。脳科学や心理学の知見を応用しているのだ」「快・不快が購入にどう関わるか。快は①あっという間に消える②偶然性を好む③人が未来に得られる快を予測する能力はとても低い」・・・・・・。
脳は考えることや計算を嫌う。通貨にしても、日常生活においてもデジタル化がさらに進み、頭に入って来やすい情報で、自分を取り巻く世界を形作ってしまう。それが依存へと発展する。「共感と人間同士のつながりーーブランドが密かに使う言語。集団よりも、一個人のストーリーへの共感が強いことを広告は利用する。説得力のあるストーリーほど強力なものはない」「目で処理できないほどの短い時間のサブリミナルではなく、目の前のありふれた風景に溶け込ませる方がよほど効果的。ミドリミナル・プライシングだ」・・・・・・。
脳科学と心理学、マーケティングを駆使して、次から次へと具体例が示されて、極めて刺激的で面白い。果たして、私たちの「欲しい!」という感情は、本当の自分なのだろうか。
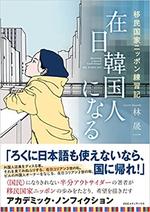 「移民国家日本練習記」が副題。戦後から今日までの在日の歩みを振り返り、その上で、日本人、在日、さまざまなマイノリティーがともに希望の歴史を編む努力が必要だと論じている。生々しく激しい壮絶な歴史を、自分の歴史と記憶に絡ませ、改めて感じ入った。
「移民国家日本練習記」が副題。戦後から今日までの在日の歩みを振り返り、その上で、日本人、在日、さまざまなマイノリティーがともに希望の歴史を編む努力が必要だと論じている。生々しく激しい壮絶な歴史を、自分の歴史と記憶に絡ませ、改めて感じ入った。
「45年8月の敗戦当初、日本には200万人以上の朝鮮人がいたとされ、翌3月末までに130万人以上が朝鮮に帰国。その後、日本に残り続けた在日の数は50〜60万人台で推移した。91年から彼らは『特別永住者』として、日本に住むようになったが、その数が減り続け、2021年にはおよそ30万人となった」「平和憲法は民主主義や基本的人権を高らかにうたったが、日本人からすれば、在日は内なる他者であり、日本国籍を剥ぎ取るべき『招かれざる客』であった」「日本国籍を失った在日は、郵便局員や国鉄職員などを含む公務員になれないし、公営住宅にも入居できない。生活保護を除いて、社会保障全般のかやの外に置かれ続けた」「戦後の日本人も食うに困ったが、日本国籍を奪われた在日の苦境はさらにひどかった。荒い手を使ったり、裏社会に飛び込むものだっていた」のである。
在日映画のパイオニアのひとつ「あれが港の灯だ」(61年)、「キューポラのある街」(62年)。そして江戸川区の小松川高校定時制2年の女子生徒が殺害された小松川事件(58年)。在日の民族意識を鼓舞した韓国民団と朝鮮総連。それに背中を押され、58年から始まった北朝鮮への移住(60〜61年がピークで両年で、7万人以上)。いかに日本での生活が過酷であったか、生活保護だけが命綱であった。「46〜65年生まれの在日2世は、ブルーカラー比率が高く、就職差別は深刻で、団塊の世代の日本人や後の世代の在日に比べ、確実にわりを食ってきた」ことが描かれる。同世代を生きてきた私として実感することだ。そのなか焼き肉屋やパチンコ店等で這い上がる在日の人々、日本人のヒーローとなった力道山は、「出自を隠して日本人を演じきる」姿勢を貫いたが、それ自体がナショナリズムと現実を生きることの苦悩を抱え込んでの戦いであった。日本が高度成長の波に乗り、団塊の世代が大学闘争に突入した68年に起きたのが、あの金嬉老事件。救いの手を差し伸べた知識人とその挫折。その軽薄さを茶化したのが、福田恒存の「解ってたまるか!」(浅利慶太演出)であったと描く。
高度成長、世界的な人権意識の高まりの中で、80年代には、在日韓国・朝鮮人を含む外国人にも、国民年金や児童手当などが適用されるようになり、86年にはついに国民健康保険が全面適用されるようになる。
「純」と「準」――。「在日の一部は薄れゆく民族意識を確かなものにしようと奮闘した」「通称名と本名、どちらを取ろうとわだかまりは残る。ジレンマを解消したところで、それは別のジレンマを生む。在日のアイデンティティーをめぐる戦いが行き着いた先は、必ずしもバラ色ではなかった」「民族意識を胸に、韓国や北朝鮮という祖国に貢献すべきか。将来の統一朝鮮を導く存在となるべきか。日本に定住する市民としての権利獲得に力を注ぐべきか。日本国籍取得は、憎き日本人との同化として責められるべきか。コリア系日本人として生きる道は否定されるべきなのか」――。70年代後半からアイデンティティーをめぐる様々な議論が盛んになっていく。本書が「在日韓国人になる」を表題としている問題意識が切実な生々しい問題として迫ってくる。そしてこの21世紀、社会は反転して分断とヘイトスピーチが跋扈し、平和と人権の21世紀とは全く異なる様相を呈している。著者は、その中で「敗北宣言はまだ早い」とし、冒頭に掲げた「ともに希望の歴史を編む努力が必要だ」と言うのだ。ぐいぐい迫ってくる著作。
 室町幕府の創設を成し遂げた足利尊氏、その弟で実質的に幕府を興した足利直義、足利家の執事で幕府樹立の影の立役者・高師直の3人の結束と戦い、数奇な運命を描く。鎌倉時代末期から建武の新政、室町幕府樹立、南北朝時代の攻防激しい動乱の十数年を、人物を中心にして立体的に描き切る熱量あふれる力作。
室町幕府の創設を成し遂げた足利尊氏、その弟で実質的に幕府を興した足利直義、足利家の執事で幕府樹立の影の立役者・高師直の3人の結束と戦い、数奇な運命を描く。鎌倉時代末期から建武の新政、室町幕府樹立、南北朝時代の攻防激しい動乱の十数年を、人物を中心にして立体的に描き切る熱量あふれる力作。
幼い頃より庶子の日陰者として、一心同体、信頼の絆で結ばれた尊氏と直義。しかし尊氏は、「やる気に乏しく、弱気で逃げ腰で無責任でお人好し。使命感なしで執着なし」「とにかく人に対する邪気と言うものが一切ない。見事なほどに人柄が丸い」という性格で、「腑抜けの棟梁」「極楽殿」と阿呆呼ばわりされている。しっかり者で生真面目一本の直義は、「一体何を考えているのか」と、兄の怠惰さ、無関心に呆れながらも、懸命に支えていく。高師直も執事の立場に徹し、懸命に支えていく。
鎌倉幕府の末期、北条得宗家の独裁で鎌倉幕府の信用は地に堕ち、怨嗟の声が上がっていた。三人は幕府の粛清から足利家を守ろうと必死の戦いをしていたが、後醍醐天皇から北条家討伐の勅命が下り、反旗・討伐の決断をする。足利一族が得宗家に成り代わって鎌倉府を引き継ぐと考えたのだ。しかし後醍醐天皇は幕府そのものを潰し、朝廷の世を作ろうとした。足利家に幕府を引き継がせる気などさらさらなかった。建武の新政。鎌倉府が行ってきたそれまでの制度や決まり事を全てひっくり返したのだ。曖昧な態度で後醍醐天皇に好意を寄せている尊氏に苛立つ直義と師直は、怒りのなか、新生幕府の樹立を画策する。
「やる気なし、使命感なし、執着なし」の尊氏だが、なぜか「足利殿は懐の深い御仁である。その御器量は、大海の如し」と赤松円心、楠木正成、新田義貞など、歴戦の強者は好意を寄せる。その後の攻防は複雑で激しい。"朝敵"とされるが、「今の帝である大覚寺統も皇室なら、われらは持明院統を正当な皇室として担ぎ上げ、新しき錦の御旗を掲げよう(赤松円心)」――。建武3年(1336)、後醍醐天皇を一時的に降伏させた尊氏と直義は持明院統の新しい朝廷を成立させ、新たな武家政治の基本方針「建武式目」を制定、実質的な室町幕府が誕生する。不満とした後醍醐天皇は吉野に遷幸し南朝を建て、建武4年(1337)から南北朝の動乱期に突入する。足利一門とそれに与する武門は、独力で各自の領国を切り取り、統治権と軍事指揮権を持つことによって、後年の細川氏、斯波氏、吉良氏、上杉氏、赤松氏、今河(今川)氏などが形成される。打ち続く戦乱のなか、次第に直義と師直の亀裂が生じていく。それはやがて、観応の擾乱(1350〜1352)へと突き進んでいく。朝廷と公家、武士と一族、領地と財と権力争覇――。心から信頼しあい、結束の固かった3人にしても、いかんともしがたい時代の波に翻弄されていく。時代そのものの人知を超えた宿命と言えるであろう。
「真の武士とは、修羅道に生きる覚悟ができたもののことを言う。何かを得るためには何かを捨てる。平然と我が命を懸け物にできる大将に率いられてこそ、成るものも成る」「世に最も恐るべきは、悪人にあらず。己の正義を譲らぬ頑固者である。唯我独尊の道を一緒に夢に突き進む、わしや相州殿のようなものである」「およそ人の世において、最も始末に負えず、対応に困るのは、他者からのむき出しの敵ではなく、逆にそこぬけの好意であることを、この時ほどしみじみと感じたことはない。完全に毒気を抜かれ、もはや手も足も出なくなる」・・・・・・。絶体絶命の中での言葉だけにずしりと重い。
「天下の政道、私あるべからず。生死の根源、早く切断すべし」「五十路まで 迷い来にける 儚さよ ただかりそめの 草の庵に」――。享年54。とても、うつけ者の歌ではない。

