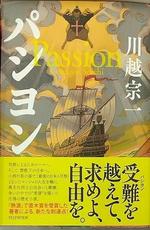 キリスト教が禁じられ、島原の乱に至った江戸時代――。最後の日本人司祭となった小西マンショの生涯を通じて、キリシタンへの迫害の凄惨な歴史が語られる。パシヨンとは受難。"受難の時代"を生き抜こうとする者の懊悩と魂の叫び、加えて弾圧をする幕府の総目付・キリシタン奉行の井上政重の心象が対比的に描かれ、緊迫の度が増す。ニ人はついに運命的な直接対峙の時を迎えるのだった。
キリスト教が禁じられ、島原の乱に至った江戸時代――。最後の日本人司祭となった小西マンショの生涯を通じて、キリシタンへの迫害の凄惨な歴史が語られる。パシヨンとは受難。"受難の時代"を生き抜こうとする者の懊悩と魂の叫び、加えて弾圧をする幕府の総目付・キリシタン奉行の井上政重の心象が対比的に描かれ、緊迫の度が増す。ニ人はついに運命的な直接対峙の時を迎えるのだった。
小西彦七(後のマンショ)はキリシタン大名・小西行長の孫で、対馬藩主・ 宗義智の子として生まれるが、関ヶ原の戦いで小西行長が西軍について斬首、母・マリヤは離縁される。長崎へ移り、小西家の遺臣・益田源介らの世話になりながら成長していく。江戸幕府が禁教令を強化し、キリシタンへの弾圧は強化され、それへの抵抗と小西家再興が画策されていく。逡巡する彦七は、司祭となるため、日本を出る決断をする。
そうしたなか、時代はますますキリシタン弾圧へと進み、40万にもなっていたキリシタンは、棄教か殉教かに追い込まれていく。そして島原の乱へと進んでいく。
一方、弾圧政策を強化していく幕府。少禄の幕臣から大目付に出世した井上政重は、幕府統治による太平の世を目指し、世を乱す不穏な動きをひたすら制止しようとする。政重は、なし崩しで禁制を指揮するようになり、厳しい拷問や火刑や斬首が相次ぎ、たちまち畏怖と嫌悪の対象となっていく。あたかも、ハンナ・アーレントの「エルサレムのアイヒマン」を想起させるが、彼の場合、心の中に潜む世への憤怒と空虚・孤独は深まっていく。
島原の乱に帰国が間に合った小西マンショ。餓死寸前の原城のキリシタン戦士に司祭となったマンショは叫ぶ。「逃げよ」「教えを棄てよ」「放免されて落ち着いたら棄てた教えを取り戻せばいい」・・・・・・。そして数年後、江戸時代最後の日本人司祭・小西マンショは捕われ、拷問のなか井上と対峙するのだが・・・・・・。
「生きる」ことと「自由」。「魂の自由」と「宗教」。弾圧する幕府の側の井上政重を出すことによって、本書は「受難の時代」を生きる魂の叫びを剔抉してみせた力作となっている。
 「米露中北の打算・野望・本音」が副題。「プーチン大統領に責任があるからといって、その不正義を指弾するため、すべての領土を奪還すべく戦い続けることがいいのか。停戦の機を見出して、ロシアとウクライナを話し合いのテーブルに着かせる外交努力を国際社会はしなくていいのか。無期限にして、無制限の戦争の果てに、核戦争が起こっていいのか。それでもウクライナに"正義の戦い"を続けさせるのか。今こそ、危険極まりない戦争を止めなければ――」と共通認識を持つ。
「米露中北の打算・野望・本音」が副題。「プーチン大統領に責任があるからといって、その不正義を指弾するため、すべての領土を奪還すべく戦い続けることがいいのか。停戦の機を見出して、ロシアとウクライナを話し合いのテーブルに着かせる外交努力を国際社会はしなくていいのか。無期限にして、無制限の戦争の果てに、核戦争が起こっていいのか。それでもウクライナに"正義の戦い"を続けさせるのか。今こそ、危険極まりない戦争を止めなければ――」と共通認識を持つ。
「ロシアが、ウクライナに侵攻した直接の目的は、ウクライナ東部に位置するルハンスク州、ドネツク州の住民の擁護であり、非軍事化だった」が、いまやハードルが上がってしまった。ウクライナが、クリミア半島も含め全領土の奪還を目指すとしたら、ロシアは2州にとどまらず侵略する。重要なポイントは、「ロシア国家の存亡が関わるいわば"核心的利益"が脅かされた場合だ。ウクライナ側が、特殊部隊を使ってクリミア大橋を爆破させたように、セヴァストポリを攻撃させようとすれば、核使用の危機が現実のものとなる恐れがある」と懸念する。「セヴァストポリが、ウクライナの実効支配下に入れば、それは1991年の時点に戻るのではない。18世紀後半のロシア全盛期に皇帝エカチェリーナ2世の時代に領有した土地の全てを失うことを意味する」と言うわけだ。
そこで、犠牲者をこれ以上増やさない方策として"まず撃ち方やめ"が鉄板のセオリー。「ロシア側に、開戦前の国境線まで撤退せよ、クリミア半島も返せと無条件勝利を掲げて戦いを続ければ、停戦の機をつかむ事は難しい」「ウクライナの強硬な姿勢を支えているのは米国をはじめNATO諸国の兵糧と武器だ」「西側陣営の首脳たちも、停戦を実現させる方策を真剣に探る時だ」「停戦のキーワードは"中立化"の外にはない」と言う。
ロシアのウクライナ侵略を言語道断としながらも、ロシアと米国を熟知する両者が、ウクライナの地勢と歴史を掘り下げつつ、米露中北の「嘘」と「本音」、「虚実」を赤裸々に語っている。
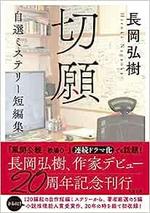 2003年に作家デビューし、発表してきた短編ミステリー小説は120編超。作家生活20年を記念して、著者自選の5編と本に未収録のデビュー作品を大幅修正したものを加えた選りすぐりの計6編。いずれも絶妙、緊迫感は凄いものがある。
2003年に作家デビューし、発表してきた短編ミステリー小説は120編超。作家生活20年を記念して、著者自選の5編と本に未収録のデビュー作品を大幅修正したものを加えた選りすぐりの計6編。いずれも絶妙、緊迫感は凄いものがある。
特に面白かったのは「迷走」――。消防の救急本部に属する消防官・蓮川とその上司・室伏隊長。腹部を刺され出血多量の男性被害者を救急車に乗せるが、対応できる病院がない。一刻を争う戦いのなか別の救急事案が発生、しかもこれに複雑な人間関係がからむ。緊迫感がぐいぐい迫る。電話中に倒れた人物の居場所をサイレンの音で突き止める救命士の迫力は、凄まじい。
「小さな約束」――。腎移植を待つ刑事の姉。主治医であり思いを寄せる相手でもあった男が海に転落死する。自殺の場合は、親族への優先提供はできないという問題が絡んでいるようだった。
「わけありの街」――。会社員殺害事件の捜査が難航するなかで、被害者の母親が田舎から出てきて、息子の住んでいたアパートを借りる。母親はなぜか「日本の刑法では確定裁判を経ていない二個以上の罪は『併合罪』とされ、まとめて審理にかけられる決まりになっている」ことをよく知っていた。そこで母親が打ったしたたかな手は?「あなたがわたしだったら、どうしていましたか」――。言葉を失う。
「黄色い風船」――。死刑囚を担当する刑務官の苦悩。担当する死刑囚は、顔と目が黄色で腹部に張りを覚えていた。「胸の中にある不安を風船の中に吹き込んで、全部ここへ吐き出せ」・・・・・・。世の中には、特定の匂いに強く反応する犬がいるようで、刑務官が奇想天外な手を考える。
「苦い確率」――。「ギャンブルの必勝法は、まるでツキのない奴を見つけて、その逆を張ること」――怖いが軽妙、ユーモアすら感じる作品。
「真夏の車輪」――。成績にこだわる高校時代。高校野球を応援に行った野球場で、自転車がパンク。そこで自転車を盗んだ高校生と、盗まれた高校生の焦りと苦悩。あるなぁ。こういう深みにはまることが・・・・・・。良い事はひとつもないのに。
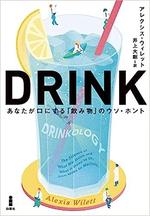 「あなたが口にする『飲み物』のウソ・ホント」が副題。著者は、ケンブリッジ大学で博士号を取得した人間生物学の専門家、サイエンス・コミュニケーター。あらゆる飲み物全般について、科学的なエビデンスに基づいた客観的な視点を提供する。とくに、世の中に流布されている健康飲料についての説明が、実はほとんど根拠のない無責任な売り文句であったり、科学的と称するエビデンスが、飲料メーカーがスポンサーとなるなかで行われたりすることを示す。「私たちはいかに踊らされているか(マーケティングの威力)」と末尾で述べ、「結局のところ、スーパードリンクに一番近いものを挙げるとすれば、答えはおそらく水と哺乳類のミルクだろう」「宣伝を鵜呑みにせず、健全な懐疑心を持っておいた方が賢明だろう」と言う。「糖質ゼロ」「特定保健用食品」「天然由来」などと宣伝されるが、しっかりとその成分を見て、効用ありとされる成分がドリンクにどの程度の量が入っているか、糖質など問題となっている他の成分がどの程度入っているのか見極めようと言う。私たちもこれほど翻弄されてきたから、相当賢くなってきてると思う。
「あなたが口にする『飲み物』のウソ・ホント」が副題。著者は、ケンブリッジ大学で博士号を取得した人間生物学の専門家、サイエンス・コミュニケーター。あらゆる飲み物全般について、科学的なエビデンスに基づいた客観的な視点を提供する。とくに、世の中に流布されている健康飲料についての説明が、実はほとんど根拠のない無責任な売り文句であったり、科学的と称するエビデンスが、飲料メーカーがスポンサーとなるなかで行われたりすることを示す。「私たちはいかに踊らされているか(マーケティングの威力)」と末尾で述べ、「結局のところ、スーパードリンクに一番近いものを挙げるとすれば、答えはおそらく水と哺乳類のミルクだろう」「宣伝を鵜呑みにせず、健全な懐疑心を持っておいた方が賢明だろう」と言う。「糖質ゼロ」「特定保健用食品」「天然由来」などと宣伝されるが、しっかりとその成分を見て、効用ありとされる成分がドリンクにどの程度の量が入っているか、糖質など問題となっている他の成分がどの程度入っているのか見極めようと言う。私たちもこれほど翻弄されてきたから、相当賢くなってきてると思う。
「雨水はもともと軟水。土の層を通過する時、ミネラルが溶けて硬水となる。硬水を飲むことで、心疾患による死亡リスクが下がる可能性が指摘されるが、説得力あるデータはない」「アルカリ水について謳われている健康増進効果には裏付けがない」「母乳の方が調合乳よりも優れているのかという問いに対しては、総合的に見てイエスと答えざるを得ない」「植物性ミルクは、動物性ミルクと比べて組成が全く異なり、栄養価も低い。その大半は、カルシウム、ミネラル、ビタミンが少なく、タンパク質の量と質が低いうえに塩分と糖分が多いからだ」・・・・・・。
「さまざまのお茶には、健康効果がある可能性の高い化合物が含まれ、おそらく健康に良い。ただどれぐらいが一杯のお茶に入り、体に吸収されて有益な効果もたらすかはまだよくわかっていない」「ソフトドリンクとは、ハードなアルコール飲料と対比される呼び方だ。私たちの食事には、ある程度の糖が絶対に必要だが、食事から十分過ぎる量の糖を摂っているので、飲み物でさらに摂る必要はない」「人工甘味料は砂糖の約200倍の甘さを持つ。砂糖という悪とされているものを追い払ったつもりが人工甘味料に置き換わっただけならどうなるか」「コカ・コーラの原材料は、100年以上にわたって秘密にされてきている。刺激効果のあるコカの葉とカフェインを含んでいるコーラナッツに由来しているが現在はどうか?」「果物そのものは食物繊維が含まれているために、吸収速度が遅くなり、血糖値の急上昇を起こさない。フルーツジュースには、満腹感をもたらす食物繊維が入っていないので、ジュースに含まれる果糖のせいで食べ過ぎてしまう恐れがある」「スポーツドリンクの有効性は説得力を持って証明されていない。高強度の運動する人に向けたスポーツドリンクを普通の人が飲めば、健康的に水分補給をしているつもりかもしれないが、ただ体重が増えるだけだ」「ソフトドリンクは健康効果がある化合物を入れているが、少量しか入っていない。大半は何の効果もないどころか、砂糖など害にもなる成分でできているのが多い。味が好きなので、高いお金を払っても良いと思うなら止めはしないが」・・・・・・。
「アルコール飲料」――。「アルコールの摂取がその量に関係なく、健康被害をもたらす可能性を示す証拠はたくさんある。たとえ少量のアルコールであっても、全体としては有益ではなく、害にもなり得るという可能性を示唆している。そのため、適度な飲酒は体に良いという考えは、科学的な見解ではなくなりつつある」「赤ワインを飲むと頭が痛くなりやすいという人がいたら、それはおそらく、単にアルコールの飲み過ぎである可能性が高い」「人間の体が1時間あたりに分解できるアルコールの量には限界がある」・・・・・・。そうだろうと思う。その上で、美味しいから飲む、楽しく飲む。ワインも「美味しいワインは美味しい」とは、私がワインの専門家から聞いた至言だ。
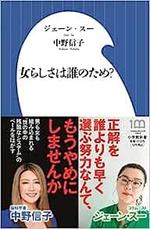 世間が考える「女らしさ」とは何か。「女らしさ」とは誰のために存在するのか。生き方の多様化が進行中だが、女性のみならず、男性もが知らず知らずのうちに組み込まれ、生き辛くさせている圧迫の構造について2人が対談する。「変化と進化によって、男も女も『らしさ』からどんどん解放されていけばいい」「みんながそれぞれに、自分なりの戦略を育てられる人になるといい」「女に生まれても、男に生まれても、それぞれ自分の選択を得にできるようになってほしい」「正解を選ばされる人生を強いられ、間違えることへの恐怖に怯え、失敗したと晒される人たちの姿を借りた、社会からの無言の脅迫に苦痛を感じてきた人が少なくないだろうと思う。でも、正解を誰よりも早く選ぶ努力なんてもうやめにしませんか(中野信子)」と言う。
世間が考える「女らしさ」とは何か。「女らしさ」とは誰のために存在するのか。生き方の多様化が進行中だが、女性のみならず、男性もが知らず知らずのうちに組み込まれ、生き辛くさせている圧迫の構造について2人が対談する。「変化と進化によって、男も女も『らしさ』からどんどん解放されていけばいい」「みんながそれぞれに、自分なりの戦略を育てられる人になるといい」「女に生まれても、男に生まれても、それぞれ自分の選択を得にできるようになってほしい」「正解を選ばされる人生を強いられ、間違えることへの恐怖に怯え、失敗したと晒される人たちの姿を借りた、社会からの無言の脅迫に苦痛を感じてきた人が少なくないだろうと思う。でも、正解を誰よりも早く選ぶ努力なんてもうやめにしませんか(中野信子)」と言う。
「女であることのメリット」「女だからこそのデメリット」が一覧となっている。「力が弱いため」――男性にフォローをしてもらえる場合があるというメリット、犯罪被害など常にセキュリティー面で注意が必要になるというデメリットもある。「美、モテ、若さは全て目減りする価値。今この瞬間があなたのこれから先の人生においては、一番若いことを実感してほしい。すべての人類は今日が一番若い(中野信子)」「若い頃は、美人の方が得という場面が多いが、美人はそれ以外が評価されづらい」「女性を取り巻く日本の今の空気には、LG BTに対するサポートが手厚過ぎると主張する人の声に似たところがある。LG BTに対する実質的なサポートなんて、ほぼゼロ、マイナスなのに『もっとみんな寛容になりましょうよ』という空気が流れる」「加齢がネガティブ要素にならない男システムは正直うらやましい」「仕事も家庭も完璧です的な女性像なんて『男性優位社会』が押し付ける幻想。仕事のできる、できないと、私生活のマネジメントはほぼ関係がない。仕事の場では仕事だけできれば良いはず」「私はクオータ制の導入には大賛成。クォータ制を採用すれば、ずば抜けて優秀ではない。女性にも役職に就く機会が訪れる(ジェーン・スー)」「新自由主義の風が吹き、ガラスの天井は傾いた。戦える武器を持った者と持たない者を分ける。天井に」「40歳は不惑といわれるが、道徳的なものではなく、ドーパミンがあまり分泌されなくなって扱いづらい感情が落ち着いてくる。不安がどんどん増幅するような回路が組まれている10代と、40代の脳は全然違う」「医学が発達し、卵子の凍結や代理母・・・・・・。生殖が変われば恋や結婚の形も変わる」「女が誰かの庇護下にいなくてもいい未来が来る?」・・・・・・。
大変率直な良い対談。

