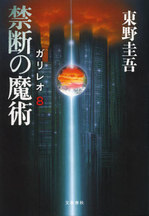10日、11日の土日、野球、サッカー、ソフトボール、アクアスロン大会など多くのスポーツ行事、華道、茶道、舞踊大会などの文化行事などが行われました。私も合唱に加わったりしました。
10日、11日の土日、野球、サッカー、ソフトボール、アクアスロン大会など多くのスポーツ行事、華道、茶道、舞踊大会などの文化行事などが行われました。私も合唱に加わったりしました。
先日来、私たちに野菜、果物、花などを提供してくれる東京各市場まつりが連続して行われ、地元の北足立市場(10/21)や板橋市場(10/28)、豊島市場まつりに参加しました。豊かな「食」は生活・文化の基本。「食育」という言葉もかなり定着。安全・安心の「食」の提供がスムーズに活発に行われることはとても大事です。 今年の市場まつりでは、どの会場にも福島のブースが設けられ、福島県庁からの職員も来て、「全て検査をしています。流通されているものは全て安全。おいしいです」と訴えていました。今年3月に佐藤雄平福島県知事にお会いした際、「風評も心配だが、これからは風化も心配」と言っていました。大変ななかで頑張っている人を応援する――全てに通じる大切なことだと思います。
今年の市場まつりでは、どの会場にも福島のブースが設けられ、福島県庁からの職員も来て、「全て検査をしています。流通されているものは全て安全。おいしいです」と訴えていました。今年3月に佐藤雄平福島県知事にお会いした際、「風評も心配だが、これからは風化も心配」と言っていました。大変ななかで頑張っている人を応援する――全てに通じる大切なことだと思います。
頑張ります。
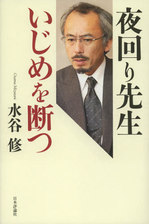 こうすればいじめを解決できる――"夜回り先生"水谷さんは、明確に示す。
こうすればいじめを解決できる――"夜回り先生"水谷さんは、明確に示す。
今の子どもたちがいかに追い詰められているか。大人と違ってストレス発散ができない。子どもたちには閉鎖された学校と家庭しかないうえに、その二つが追い詰められる場所となった時に、もう逃げ場はない。
"いじめ"の原因は家庭や学校、地域などの社会にある。だから閉鎖された学校空間の中の問題ではない。いじめる子もいじめられる子も交替もするし、生涯の傷を負う。水谷さんは、今の子どもに暴れ回るエネルギーや気力がなくなり、「目力」がなく、自己肯定感の希薄さ、自分への自信のないことを心配している。認められたり、ほめられたりすることなく、否定、否定で育てられればたしかにそうなる。
"夜回り先生"水谷さんはずっと、「死にたい、助けて」という子どもに体当たりで相談し続けてきた。本書にもその一端、実例が紹介されている。愛情のない、実情に迫らない、本質を探ろうとしない全てに対して憤りがあふれている。
いじめ現象は「不健全な人間関係(無視や悪口)」「人権侵害(死ね、学校へ来るな)」「犯罪」の三つに分かれるのに、文科省は曖昧な定義で、学校の内に抱え込ませている。人権侵害には人権擁護局などを、犯罪には警察との連携を、学校と教員は「不健全な人間関係」を直し、できなければ"いじめ"の責任を取ること――水谷さんの主張は明確だ。
いじめにどう対処するか――。「今いじめられている君へ」「いじめに気づいている君へ」「今だれかをいじめている君へ」「すべての親へ」「学校関係者へ」「関係機関の人たちへ」「すべての人たちへ」。皆、逃げているではないか。いじめ対策は、総がかりで、踏み込んでこそできるものだ。戦ってこそ解決の道がある――そうした叫びが伝わってくる。必読の本だ。
 内田樹さんの「街場シリーズ」だが、本書は神戸女学院大学での最終講義「クリエイティブ・ライティング」で文学と言語について語ったことを基にしたもの。
内田樹さんの「街場シリーズ」だが、本書は神戸女学院大学での最終講義「クリエイティブ・ライティング」で文学と言語について語ったことを基にしたもの。
「生成的な言葉とは何か?」というテーマが、あたかも宇宙のかなたに一気に行ったかと思うと、緻小の素粒子の世界に入り込むかのように自由自在。「僕らの身体の中心にあって、言葉や思想を紡いでいく基本にあるものは、かたちあるものではない。それは言葉にならない響きや波動や震えとか、そういうような非言語的な形態で、死者たちから生者へと手渡される。言葉というのは、『言葉にならないもの』をいわば母胎として、そこから生成してくる。それを『ソウル』と言ってもいいし、『生身』と言ってもいいと僕は思います。そこから発してくる言葉だけがほんとうに深いところで人を揺さぶる」といい、「響く言葉」「届く言葉」「身体に触れる言葉」とはどういうものか、を語ってくれる。とくに「届く言葉」だ。
それにしても、「人間の言語能力は、われわれが想像しているよりはるかに深く、複雑な仕事を信じられないほどの高速度でこなしている」し、人間の底知れなさは、言語と世界の底知れなさに行き着く。ソシュールのアナグラム研究、ロラン・バルトの「エクリチュール」理論、村上春樹の世界性と司馬遼太郎の日本人のための美学、「大日本帝国の瓦解を怜悧に切り捌く丸山眞男」と「トラウマを抱えた人、大日本帝国に半身を残した少年、吉本隆明や江藤淳」、階層と言語、階層再生産に強い力を発揮する教養・文化資本、階層がない日本と言語、PISAと「広めの射程で自分をとらえる」能力......。
言語、人間、世界、宗教、宇宙、日本、世間、地域、階層、演説、そしてiPS細胞と生命など、さまざま考えさせてくれた。
 うれしい起工式となりました。秋晴れの11月4日、足立区において、東武伊勢崎線(竹ノ塚駅付近)連続立体交差事業の起工式が参加者の喜びのなかで行われました。足立区、地元地域の方々、国会、都議会、区議会の熱意が実ったものです。いよいよ悲願であった工事に着手することになります。
うれしい起工式となりました。秋晴れの11月4日、足立区において、東武伊勢崎線(竹ノ塚駅付近)連続立体交差事業の起工式が参加者の喜びのなかで行われました。足立区、地元地域の方々、国会、都議会、区議会の熱意が実ったものです。いよいよ悲願であった工事に着手することになります。
この竹ノ塚の踏切は、竹ノ塚の東西を分断するだけでなく、ピーク時で1時間のうち58分が遮断される"開かずの踏切"。2005年3月15日、4人の歩行者が死傷する痛ましい事故が発生しました。私は翌16日には国会の衆院内閣委員会で対応を要請、夕方の事故発生同時刻に現場を視察、動きをただちに開始しました。足立区では同年4月に足立区議会鉄道高架化促進議員連盟、9月には竹ノ塚付近鉄道高架化促進連絡協議会が次々と結成され、約22万もの鉄道高架化早期実現を求める署名を集めるなど、課題克服に向けた運動が加速されました。
当時の北側国交大臣、続く冬柴国交大臣、金子国交大臣はじめとする国への要請には私自身常に働きかけを行なってきました。2006年4月の「連続立体交差事業の採択要件の緩和」、2007年4月の「連続立体交差事業の着工準備の採択」は大きな起点となるものでした。何度も何度も国交省と打ち合わせをしてきましたが、7年という異例のスピード、都内初の区施工という形で工事着工の日が迎えられたことはうれしいことです。足立区、地元住民、関係者の方々の並々ならぬ熱意とご協力の賜物です。心から感謝です。 事業は、最多箇所で8本ある線路を順番に高架化するという難工事。しかも昼間の列車を止めることなく行う行事であることなど、約10年を要することになりますが、安全第一で、また「線路工事が一本完了するたび、踏切の閉まっている時間が短くなる」(担当者)という喜びも加えて行われます。
事業は、最多箇所で8本ある線路を順番に高架化するという難工事。しかも昼間の列車を止めることなく行う行事であることなど、約10年を要することになりますが、安全第一で、また「線路工事が一本完了するたび、踏切の閉まっている時間が短くなる」(担当者)という喜びも加えて行われます。
さらにこの鉄道高架化にとどまらず、足立区の北の玄関口「竹ノ塚」周辺の街づくりをも視野にいれて行われます。足立区は大学が次々誘致されたり、鉄道網が拡充されたり、学校給食日本一のモデルとなったり、若者雇用へのキメ細かな対策が行われたりと、発展していますが、私はさらに頑張っていく決意です。