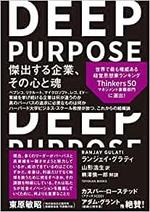 「傑出する企業、その心と魂」が副題。現在、多くのリーダーがパーパスと高業績を一致させようと努力している。その背景には、短期志向で株主の意向を極大化する株主資本主義から、ステークホルダー資本主義への転換という変化がある。長期的な企業価値を上げるためには、多様なステークホルダーの利害に目配りをし、かつ、気候変動や環境問題、人権や格差などの社会全体が抱える問題の解決に寄与することが企業にとっても重要となる。つまり「企業のパーパス(使命、目的、存在意義)」が重要であるとの考えだ。
「傑出する企業、その心と魂」が副題。現在、多くのリーダーがパーパスと高業績を一致させようと努力している。その背景には、短期志向で株主の意向を極大化する株主資本主義から、ステークホルダー資本主義への転換という変化がある。長期的な企業価値を上げるためには、多様なステークホルダーの利害に目配りをし、かつ、気候変動や環境問題、人権や格差などの社会全体が抱える問題の解決に寄与することが企業にとっても重要となる。つまり「企業のパーパス(使命、目的、存在意義)」が重要であるとの考えだ。
こうしたなか、パーパス経営を志向する企業は増えてきたが、実らせているとはいえないのが実情だ。著者は、ハーバード・ビジネス・スクール教授。広範なフィールドワークを行い、「パーパスを発見し、説明し、埋め込み、維持するにあたり、もっと先へ進み、ときにはそれを独特な方法でやってきた」という絞りに絞った企業を具体例を示し紹介する。多くのリーダーがパーパス経営を「単なるツール」「ブランド構築と評判改善の手段」「口先だけで、広報の手段」であることを紹介し、利潤だけでなく、パーパスを達成しようと努めるビジネスリーダーに何が必要かを提示する。「都合のいいパーパスではダメだ」と言っている。
「多くのリーダーたちは、形式的にしかパーパスを追求しない。ディープ・パーパス・リーダーは、4つの便益カテゴリーを指摘する。戦略立案の焦点を定める能力、顧客との関係構築、外部ステークホルダーへの対応、従業員啓発だ」「ディープ・パーパス・リーダーたちは、過去を振り返り、創業者や初期の従業員たちの意図に入り込んで、企業の不滅の魂や本質を捉える主題を探す(精神、本質、アイデンティティ)」「自社について、壮大で基盤となるような物語を語り、会社に深みと意義と、詩情さえももたらすのだ(ただのエピソードではない大きな物語)」「鉄の檻を逃れる、官僚制の打破」などを指摘する。
また「4つのパーパス脱線要因」として、「属人化のパラドックス(創業者が消えると魂を失いがちになる)」「(不適切な)計測による死」「善行者のジレンマ(不当に利潤を無視すれば、会社を社会的論理からあまりに遠く押し、やってしまう。商業と社会のバランス、カミソリの刃の上を歩く難しさ)」「パーパスと戦略の分裂」を指摘するが、パーパス経営者には難しい問題が突きつけられていることを痛感する。しかしそれを乗り越えなければ未来は見えない。

