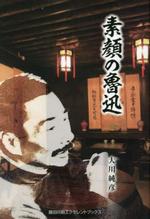 「筆者が食道癌で、余命宣告を受けたのは、本年8月22日・・・・・・」「翌日から『終活』に早速とりかかった」として出来上がったのが本書だという。仙台市生まれで、元国語教師、現在は釧路市に住む。仙台はまさに、魯迅の青春の地だ。
「筆者が食道癌で、余命宣告を受けたのは、本年8月22日・・・・・・」「翌日から『終活』に早速とりかかった」として出来上がったのが本書だという。仙台市生まれで、元国語教師、現在は釧路市に住む。仙台はまさに、魯迅の青春の地だ。
魯迅(1881~1936)は1904年に仙台医専に入学、あの藤野先生に会い、また「幻灯事件」で医学の道へ疑問を抱き退学。帰国して母の勧めで朱安と結婚。単身で日本に戻り、弟・周作人ら5人と本郷区西片町の漱石の旧居に住む。1911年に辛亥革命、1912年に同郷の紹興出身の友人・許寿裳の推薦により南京臨時政府教育部員になる。袁世凱の大総統就任により首都は北京に移転、魯迅も官吏として北京に移る。その後、時代の大激動の中で魯迅は、「狂人日記」「阿Q正伝」などを著し、反骨の思想家・文学者の道を突き進むが、本書はまさに「素顔の魯迅」を「魯迅日記」をひもときつつ語る。そこには生々しい生活実感や民衆への温かい眼差しや、許広平ヘの愛と逡巡、横暴な権力への怒りなどが溢れている。毛沢東による「空前の民族英雄」「現代の聖人」などの偶像化をかいくぐって、魯迅の実像を示してくれる。
時代も波瀾万丈だが、その中で生きる魯迅の感情の振幅が素直に伝わってくる。特に「藤野先生」での師弟や、知音の友・ 瞿秋白に送った詩句、「人生一知己を得なば足れり、斯の世まさに同懐以って視るべし」は有名だが、改めて心に響く。
同世代の著者の魯迅を通じての生き様を、感じさせられる。大変面白い著作だ。

