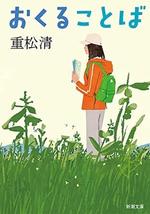 早稲田大学で教鞭をとっている重松さん。コロナ禍の3年余、若者はまた子供たちは、何を考えどう行動したか――。しかもこの期間には、本書の「夜明けまえに目がさめて」で語るように、「令和ちゃんは、なにごとも中途半端が嫌いで、白黒をはっきりつけないと気がすまないキツめの性格なのだろうか」「日本語にはせっかく『しとしと』『そよそよ』『しんしん』『さんさん』という素敵な言葉があるのに・・・・・・」「風が吹いたら暴風、雪が降ったら豪雪、天気が良ければ、猛暑日」と、「とにかく極端なのだ」。そして、ロシアによるウクライナへの軍事侵略、安倍晋三元首相が銃撃されて、白昼堂々、"衆人環視"のもとで、命を奪われる。コロナ禍では、人との会話・接触が奪われ、マスクに覆われた世界となる。
早稲田大学で教鞭をとっている重松さん。コロナ禍の3年余、若者はまた子供たちは、何を考えどう行動したか――。しかもこの期間には、本書の「夜明けまえに目がさめて」で語るように、「令和ちゃんは、なにごとも中途半端が嫌いで、白黒をはっきりつけないと気がすまないキツめの性格なのだろうか」「日本語にはせっかく『しとしと』『そよそよ』『しんしん』『さんさん』という素敵な言葉があるのに・・・・・・」「風が吹いたら暴風、雪が降ったら豪雪、天気が良ければ、猛暑日」と、「とにかく極端なのだ」。そして、ロシアによるウクライナへの軍事侵略、安倍晋三元首相が銃撃されて、白昼堂々、"衆人環視"のもとで、命を奪われる。コロナ禍では、人との会話・接触が奪われ、マスクに覆われた世界となる。
学生たちに日記を書かせ、それに触れつつ文を綴る。2022年2月24日、ロシアのウクライナ侵略――「ゼミ生の日記が変わった」と同時に、「なるほど、スマホで開戦を知る世代なんだなあ、テレビではなく」と思うのだ。重松ゼミの学生は幸せだと思う。世の中に出るといろんな壁にぶち当たる。しかし「まずは壁の前で絶望するな。小さな穴を開けることから考えよう」、そして「壁はそこにドアノブをつければ扉になる」「よくがんばったな」「またどこかで必ず会おう」と呼びかける。
中学校入学式までの忘れられない小学生の日々を描いた書下ろし作品「反抗期」も、小学6年生がどんな思いで、コロナ禍を過ごしたかがよくわかる。留めておきたい記録でもあると思う。
コロナ禍の子供たちや学生――。心にしみる豊かなメッセージの数々。改めて、この3年余を思い起こす。

