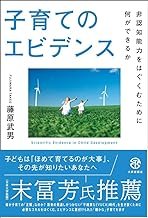 「非認知能力をはぐくむために何ができるか」が副題。現場での調査分析、エビデンスに基づくとともに、これまでの「子育て」についての世界の学術研究を踏まえた、極めて精緻かつ熱量溢れる著作。不確実な時代を生き抜くことができる子ども育てるために、これまでにわかっているエビデンスに基づく"確実な子育て"を詳述する。
「非認知能力をはぐくむために何ができるか」が副題。現場での調査分析、エビデンスに基づくとともに、これまでの「子育て」についての世界の学術研究を踏まえた、極めて精緻かつ熱量溢れる著作。不確実な時代を生き抜くことができる子ども育てるために、これまでにわかっているエビデンスに基づく"確実な子育て"を詳述する。
子育ての目的は、子どもを自立させること。まず土台となるのは「アタッチメント」、安全基地の形成だ。アタッチメントが確立されて「自分が生きていてもいいんだ」という自己肯定感が醸成される。その土台を作ってこそ、その上に構築する認知能力も非認知能力(社会情動的スキル)が育つ。認知能力とは知能、知性、学力だ。認知能力が高いからといって、将来が保証されるわけではない。非認知能力は、具体的には「セルフコントロール(自分を律する自律)」「モチベーション(内発的動機づけ)(何のために生きるのか、使命は何か)」「共感力(他者を理解できる力)」「レジリエンス(逆境を切り抜けるしなやかな強さ)」だ。それらは互いに連関し、不確実な時代においてもたくましく生き抜く人間力、生きる力が育まれていく。そして重要なのは、これらは「健康・体力」があってこそできるということだ。子どもの成長に必要なのは3つの能力、「認知能力」「非認知能力」「健康・体力」であることを指摘し、子育てにおいて、特に育てるべきスキルを具体的に論述している。さらにこれらは「するべきこと」だが、「してはいけないこと」がある。それが「虐待・ネグレクト」だと言う。
子どもの成長は「遺伝子か環境か」――この分析は極めて精緻で面白い。「大雑把に言って、遺伝子の影響は約50%、個別の測定できない環境要因が約50%を占めている」となるが、「母親の遺伝子と子育て」「遺伝によって犯罪者になるか」「遺伝子―環境要因交互作用」などが分析される。しかし遺伝子は変えられない以上、子育てにおいて必要な環境要因を整えることが重要ということになる。
「アタッチメント」――。「2歳までのアタッチメントが、脳活動に重要な影響を与えている」「アタッチメントと甘やかす(過保護)とは違う。子どもが本当に求めてるものを感じ取り与えることが大事」「足立区の野菜から食べる『ベジファースト』や歯磨きを1日2回以上する要求は子どもの自己肯定感を高める」「愛情ホルモンのオキシトシン、やる気ホルモンのドーパミンが親にも子にも重要」と言う。
「セルフコントロール」――。「セルフコントロールの必要性とは、我慢する力をつけよではなく、自らを使いこなす力をつけよということ」「早い時期のセルフコントロールが将来にも影響する」「親の幸福度が高いほど子どものセルフコントロールが高い」と言う。「モチベーション」――。「マズローの欲求5段階説(土台として生理的欲求、上位の階層に承認欲求、自己実現欲求)は、実はモチベーションの説明である」「何に対してモチベーションを持つか――自分らしさとは、使命とは何か、が重要」・・・・・・。
「共感力」――。「共感力とはエンパシー。他者の気持ちを想像して同じように理解し感じること。自分の目線で同情するシンパシーとは違う。共感力はその人の目線で状況を理解し感じること」「読書、小さい頃から挨拶をさせること、学校やニュースの話をすること、運動習慣をつけることなどが重要」と言う。「レジリエンス」――。「親の幸福度が高い。親子の関わりが多い。運動をする。歯磨きを1回より2回する」などがレジリエンスを促進すると言う。とても興味深いことだ。
「健康・体力」――。身体と精神の相互交流に基づく頑健性とバイタリティーが体力だ。私が文科省と一緒に推進した「早寝、早起き、朝ご飯」が大事であると改めて感じた。
地域社会も含め、本書の指摘は、極めて重要だ。

