 「増え続ける外国人とどう向き合うか」が副題。訪日外国人旅行客が今年、ついに4000万人の超え、在留外国人数も昨年末376万人、昨年1年で35.8 万人増加している。これに対し、治安や社会保障に関する不安の声も多く、「排外主義」まで台頭している。実際はどうなのか。本書は、これらの風聞の誤りを、エビデンスを基に指摘、移民政策の歴史と未来について考察する。現代日本の移民をめぐる最重要課題を明確に捉え、これからの日本の外国人問題のあり方を指し示す極めて重要な著作だ。
「増え続ける外国人とどう向き合うか」が副題。訪日外国人旅行客が今年、ついに4000万人の超え、在留外国人数も昨年末376万人、昨年1年で35.8 万人増加している。これに対し、治安や社会保障に関する不安の声も多く、「排外主義」まで台頭している。実際はどうなのか。本書は、これらの風聞の誤りを、エビデンスを基に指摘、移民政策の歴史と未来について考察する。現代日本の移民をめぐる最重要課題を明確に捉え、これからの日本の外国人問題のあり方を指し示す極めて重要な著作だ。
言われている風説は誤解だらけ。「地域の治安を悪化させるクルド人など。『経営・管理』の在留資格で滞在し、日本の義務教育や国民健康保険、高額療養費制度を濫用するリッチな中国人。出稼ぎのために来日する留学生。ゴミ出しや騒音問題を起こす外国人」などは、およそ荒唐無稽だと指摘する。
「今3%の日本だが、やがて10%になったら大変なことになる」と言うのも誤りで、先進国の外国人の割合は平均14.7% (フランス13.8%、米国14.5%、英国15.4%、ドイツ18.2%、カナダ22.0%)。「少子高齢化に直面する先進国の中で、日本だけは『隠された人口ボーナス』がある国」と指摘する。
「日本は『移民政策が不在』でなし崩しの受け入れがされている」――実際は「機能的・制度的に、日本は移民政策を有している。日本は『労働移民』を中心に永住型・ 一時滞在型双方で国際的に見ても相当規模の移民を受け入れている。他国と比較して、労働中心の永住型移民の占める割合が大きく、むしろ日本はリベラルな『労働移民国家』と評価される」「一時滞在型移民についても、技能実習など研修生、企業内転勤、留学生の受け入れが大きく、世界第6位の規模となっている」「日本は永住型、一時滞在型を合わせて年間約36万人の労働移民を受けており、先進国中第7位の規模となる」と言う。日本は移民政策を取らない特殊な国ではなく、国連の基準に基づけば移民政策の整備状況は進んでいる。労働移民を中心に据え、永住への道を特定技能制度等で開いている評価されるべき国だと言うのだ。
日本の歴史を見ると、「ハイスキル人材の受け入れ拡大(技術・人文知識・国際業務として1989年改正)(2023年から特別高度人材制度に拡大)」「技能実習制度の創設(1993年)」「特定技能制度(2019年)」などで拡大。特定技能制度は特定技能2号への移行によって在留期間の更新に上限がなくなり、戦後、「管理と排除」から始まった入管行政が「人手不足への対応と経済成長重視」に大きく変化したと言う。「技能実習制度から特定技能制度を通じて『技能形成を通じた永住』という国際的に見ても珍しいスキームを生んだ」「人口減少が本格化する2000年代以降に、本格的な労働移民政策を日本は欧米と違い、職の奪い合い、失業による貧困、社会保障への圧迫といった問題は、構造的に起こりにくい」と指摘する。
「日本は成長しない『選ばれない国』になる」と言うのも誤り。国際移住は「意欲ー潜在能力モデル」が最も包括的理論で、「貧しいから先進国に行く」ではなく、堅調な経済成長を遂げるなかで、個人の意欲や能力が高まっている故に、先進国を目指す。「日本の人気はアジア諸国で高く、特に経済発展が進む国や高学歴層からの支持が高い」と分析している。「アジアから産油国と日本に向かう」現実があるが、「産油国へは出身国の経済水準が高くなるほど急速に低下する」と言う。アジア諸国からは米国に次いで日本に移住する人気が高いと言うのだ。「選ばれない国どころか、人気を高めている日本」「アジアから来る留学生や技能実習生は、学歴の低い貧しい人たちではなく、人生のチャンスを掴もうとする勢いのある新中間層出身」「中国人の『日本侵略』も間違いで、国境を越えてチャンスをつかもうとする起業家精神の表れ」だと言う。
空前のペースで増加する国際移住。ハイスキル人材だけでなく、あらゆるスキルレベルでの人材不足が深刻化する現在の世界ーー。「排外主義が民主主義を破壊する」と言い、エビデンスを蓄積・整備し、効果的な政策の立案の必要性が心に迫る。「増え続ける外国人にどう向き合うか」ーー圧倒的説得力を持つ最重要の著作。
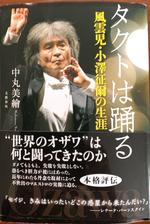 「世界のオザワ」の生涯。あのカラヤン、バーンスタインなどに愛され、認められ、ウイーン国立歌劇場音楽監督にまで上り詰めた小澤征爾。「セイジ、きみはいったいどこの惑星から来たんだい?」とバーンスタインは言ったという。まさに異次元。舞台も友人・知人も世界。指揮と同じように汗だくの全力疾走。「ダメでもともと。失敗を失敗としない」と描かれるが、目指す世界の次元自体が違っていたと思われる。
「世界のオザワ」の生涯。あのカラヤン、バーンスタインなどに愛され、認められ、ウイーン国立歌劇場音楽監督にまで上り詰めた小澤征爾。「セイジ、きみはいったいどこの惑星から来たんだい?」とバーンスタインは言ったという。まさに異次元。舞台も友人・知人も世界。指揮と同じように汗だくの全力疾走。「ダメでもともと。失敗を失敗としない」と描かれるが、目指す世界の次元自体が違っていたと思われる。
1935年満州生まれ。成城学園高校1年を中退、桐朋女子高校音楽科第1期生として入学、斎藤秀雄に師事。桐朋学園短期大学に入学。1959年2月、貨物船に乗り込み、マルセイユからパリまでスクーターで走る。まさに型破りだ。直ちに、数々の若手指揮者コンクールで受賞する。わずか20代半ばだ。
1962年の「N響事件」――。遅刻、振り間違い、若くて生意気もあったが、「NHKのやり方」との対立で、「小澤征爾ボイコット」「小澤はNHKを提訴」――。「征爾、燕尾服に着替えろ。文化会館に行くんだ」(浅利慶太)。一人で指揮台に立つ。N響を指揮したのは32年後の1995年だった。
本書は、「ニつの恋」「日本フィル分裂事件」「新日本フィルとボストン響」「サイトウ・キネン・ フェスティバル」「世界の頂点へ」「初心に戻る」の各章を立てて小澤征爾の疾風怒涛の人生を語る。
スピルバーグは「シューベルトやプロコフィエフや、ましてマーラーでもなく――もちろんそれはそれで素晴らしいのだけれどもーー指揮台の上にいる、まるでバレエでも踊っているようなスポーツ選手、驚くほど黒くてふさふさの髪をして、白いタートルネックのシャツにビーズのネックレスをしたすごい人物、のせいだった。これがセイジ・オザワその人だった。彼の溢れるエネルギーと優雅さとダイナミズムに、打ちのめされてしまった」と一文章を寄せる。「ヨーロッパへの客演指揮も増え続けた。小澤には20世紀の最も影響力のあるニ人の指揮者が後ろ盾となっていた。カラヤンとバーンスタイン。全く肌合いの違うこの両巨匠から弟子とされて可愛がられた指揮者は、小澤征爾だけだった」「しなやかな動物のような小澤の指揮はいつ見ても楽しい。だから、いつも聴衆は熱狂的な反応を返すのである。小澤が自信に満ち溢れる時、時に周囲を混乱に巻き込む。それは、小澤が主張をあくまでも完結しようとするからだった」と描く。それにしても小澤を助ける世界の音楽・政財界など各界の人々の多さは驚異的だ。凄い。
それは、小澤征爾の人間的魅力、挫折を乗り越え、世界の頂点を目指し続けた強烈なエネルギーの魅力であることを感じさせる圧倒的な著作。
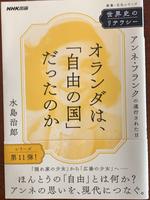 「アンネ・フランクの連行された日」が副題。「アンネの日記」は、1942年6月12日から1944年8月1日まで、ドイツ占領下のオランダの首都アムステルダムの隠れ家時代の記録が綴られている。その3日後の1944年8月4日、隠れ家に潜伏していた15歳の少女アンネ・フランクたち8名のユダヤ人が、ナチ親衛隊率いるドイツ当局に連行された。1930年代初め、ユダヤ人たちが相次いで目指した「自由の国」オランダに、まさに「自由」を求めて、ドイツから移り住んでいたのだったが・・・・・・。
「アンネ・フランクの連行された日」が副題。「アンネの日記」は、1942年6月12日から1944年8月1日まで、ドイツ占領下のオランダの首都アムステルダムの隠れ家時代の記録が綴られている。その3日後の1944年8月4日、隠れ家に潜伏していた15歳の少女アンネ・フランクたち8名のユダヤ人が、ナチ親衛隊率いるドイツ当局に連行された。1930年代初め、ユダヤ人たちが相次いで目指した「自由の国」オランダに、まさに「自由」を求めて、ドイツから移り住んでいたのだったが・・・・・・。
「アンネ・フランク一家は、なぜオランダで捕まったのか(事件の全容)」――。「広場の青春(アンネは一人じゃなかった) (広場の3人娘、アンネ、ハンネ、サンネ)」・・・・・・。オランダでは歴史的にユダヤ人が住民として受け入れられ、自主的に難民支援を開始していたが、1940年5月、ドイツ軍がオランダに侵攻、ユダヤ人の生活は一気に暗転した。
「ドイツ占領下のオランダで、ユダヤ人はいかに追い詰められたのか (事件の背景と結末)」――。華やかなオランダ劇場は接収され、収容所への移送拠点になってしまった。その向かい側に保育園があった。これがレジスタンスの有数の拠点となり、「闘う保育園」として子供たちを脱出(滞在した子供の1割の600人)させた。アンネは、ベルゲン・ベルゼン強制収容所の劣悪な待遇に苦しめられ弱っていったが、親友ハンネとのうれしい再会もあった。
「アンネつながった"ほんとうの"友だち(同時代へのインパクト)」――。オランダにアンネと同年の少女オードリー・ヘプバーンがおり、「魂の姉妹としての交歓」は衝撃的だ。1945年5月、父親のオットーが帰還、「アンネの日記」が刊行される。著者はここで「隠れ家での日記」を深掘りする。小川洋子とアンネの「閉じられた空間」「静かな孤独な空間のように見えて、この閉鎖空間の中にある人々は実に自由に、自分独自の方法で、語り、文章を綴り、他者と関わり、痕跡を残す。不自由に見える閉鎖空間が自由で創造的な空間に転化する」ことを語っている。「小川洋子さんの中に、どこかの時点で閉鎖空間を出て外の世界に出ること、そこで本当の自由に出会うことへの憧憬を感じる」と言っている。深いし納得する。
「自由な国オランダはなぜ、ホロコーストの犠牲者がユダヤ人住民の73%に達したのだろうか。他の国より格段に高い比率だ」――。それはオランダの行政機構や公営企業、民間団体が、占領当局の指示に忠実にし従い、「従順」に実行してしまった。そしてその背景には、オランダがユダヤ人を受け入れ、市民として平穏に暮らすことができる自由で寛容な国であったからでもある。
2020年1月、アウシュヴィッツ解放75周年でルッテ首相は謝罪演説。2023年7月オランダ国王は「奴隷制・奴隷貿易に対する国王の謝罪」が行われている。「アムステルダムの自由と寛容の背後には、大勢の他者の『不自由』があったのだ」と水島さんは言い、「この『他者の不自由の上に成り立つ自由』という問題は、難民が世界的に増加する現代の各国が向き合うべき重要な課題であり、日本も無縁ではない」と問題を提起している。
かなり人間の本質に関わる問題の根の深さを考える重い著作だ。
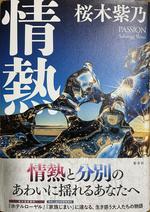 人生をたっぷり経験した熟年男女が織りなす6短編集。分別もあり、互いに相手を尊重、恋もあるが抑制的、プライドもチラッと覗かせつつ、これまでたどった人生の節を心に思い出しつつ、今を生きる。「情熱と分別のあわいに揺れるあなたへ」「あなたはもう、大人ですか」と帯にある。老けゆく男の心情が、実に穏やかな筆致で描かれる味わい深い大人の短編集。
人生をたっぷり経験した熟年男女が織りなす6短編集。分別もあり、互いに相手を尊重、恋もあるが抑制的、プライドもチラッと覗かせつつ、これまでたどった人生の節を心に思い出しつつ、今を生きる。「情熱と分別のあわいに揺れるあなたへ」「あなたはもう、大人ですか」と帯にある。老けゆく男の心情が、実に穏やかな筆致で描かれる味わい深い大人の短編集。
「兎に角」――。同級生だったカメラマンとスタイリスト。40年ぶりに片思いだった女性に会う。早期退職と離婚を同時期に体験した後、北海道に戻ってきた男。人生も円熟期だが、ふと蘇る40年前の記憶。半月に一度の撮影ペースで一緒に仕事をする。同性カップルの記念撮影、遺体を囲んでの家族写真・・・・・・。「淡々と降り注ぐ雪のように、人の幸福をひとつずつ心に溜めてゆく。兎に角----とにかく今日は、壁のジャッカロープが牧村を見て、微笑んだのを見逃さなかった」・・・・・・。
「スターダスト」――。とうを過ぎたサックス奏者と作曲家。若いディレクターに曲の作り直しをさせられる。「お互い時代を捉える瞬発力が落ちているのは明らかなのだ。『得意なところ抑えてほしい』などと若造に指摘されては、わかっているぶん憤慨もする」・・・・・・。「追い詰められた作曲家が、噛み付くように出してきた曲は、糸井を狂気させた」。老いの哀しみと意地が滲み出る。
「ひも」――。「ボケたら関係解消」が条件の70代ホストと美容室店長の中年女性。「体でお返しできないヒモ、江里子が言うところの『得がたい知恵袋』は、今日も女のために時間を使う」・・・・・・。ヒモという弱い立場の老人の気の使いようは尋常ではないが、哀れではなく人生が上品に見える。この2人、すっかり「寸借詐欺」に会うのはコメディー。
「グレーでいいじゃない」――。ジャズピアニストのトニー漆原が死んだ。ピアニストの母は、息子を本格的なピアニストにしたかった。「グレーでいいじゃない、突き詰めんなよ。どこからか、トニーの声が聞こえてくる」・・・・・・。
「らっきょうとクロッカス」――。順調に出世街道を歩いていたはずの札幌の裁判所職員の女性。突然、釧路に転勤させられる。小説家の妻を亡くした60歳を過ぎた弁護士と交流するうちに、次第に心が惹かれてメールのやりとりをする。「わたしずっと、百点を取り続けてきたんです。今までずっと、百点を取っていないと安心できなかったんです」「百点を手放した日々には、悔しさもなかった----この気楽さはなんだろうか。釧路に来てから、ほとんど、損得の計算をしなくなった」・・・・・・。
「情熱」――。60になる遅咲きの小説家が、同年代の女性大学教授と出会い、彼女のふるさと下関を案内してもらう。過去を明かさぬ彼女だったが、昔の恋人の話を聞く。「14で出会い、15のときには約束した場所で、5時間待つほど焦がれ、20歳を過ぎてから再び学ぶことを勧めた男は、彼女を置いて死んだ」「女の生きてきた60年を思うと、これ以上立ち入ってはいけない気がした」・・・・・・。
「なにが足りなかったのか。あのときどうかすれば、人生の潮目は変わったのか」――。人生の夕暮れの男には、それぞれの円熟と諦念があるものだ。
 「学問の常識を揺るがした思考実験」が副題。ガリレオ、デカルト、ニュートン、アインシュタイン、シュレディンガー、そして2022年のノーベル物理学賞は「量子もつれ」・・・・・・。人類は、それまでの「常識」「概念」を次々と打ち破る「思考実験」を繰り返し、新たな地平を切り開いてきた。ガリレオから量子力学まで、一冊の中に興味深く集結させる力技に感心した。「シュレディンガーの猫」についても、これだけわかりやすく解説されるのは有難い。
「学問の常識を揺るがした思考実験」が副題。ガリレオ、デカルト、ニュートン、アインシュタイン、シュレディンガー、そして2022年のノーベル物理学賞は「量子もつれ」・・・・・・。人類は、それまでの「常識」「概念」を次々と打ち破る「思考実験」を繰り返し、新たな地平を切り開いてきた。ガリレオから量子力学まで、一冊の中に興味深く集結させる力技に感心した。「シュレディンガーの猫」についても、これだけわかりやすく解説されるのは有難い。
思考実験は科学にとどまらない。「トロッコ問題」「臓器を分ける臓器くじ」「野戦病院でのトリアージ」・・・・・・。
「ガリレオの連続物体の落下(重いものも軽いものも同じ速さで落下する)」「アキレスと亀(到着までの過程の再分割、時間空間は無限に分割できない)」「サンクトペテルブルクの賭け」・・・・・・。
「クオリア」――「マリーの部屋(白黒の世界に住んだマリーが外に出た時)」「哲学的ゾンビはクオリア(感じ)を持たない」。
「コンピュータは考えているのか――チューリング・テスト」――当然、意味はわかっていない。「宇宙のファイン・チューニングから眠り姫問題へ」――宇宙は、奇跡的に人類誕生に都合が良かったのか、事あるごとに生ずる問題。
「ギャンブラーの誤謬」――9回連続で赤が出たのだから、さすがに次は黒か。これは錯覚。「モンティホール・ジレンマと3囚人問題。心理学でよく用いられる教材。「囚人のジレンマ」の心理実験をすると、裏切り戦略を取る人がほとんどと言う。「ケインズの美人投票ゲーム」は株式投資でも見られる話。
「マックスウェルの悪魔――取り返しがつかないことを元に戻せるか!?」。「ニュートンのバケツとマッハのバケツ――どちらが回っているのか」・・・・・・。
「光速度のパラドックス――光速度で、光を追いかければ」「通過する列車上での同時性の思考実験」「自由落下する瓦職人、自由落下するエレベーター」――落下する人から見ると、重力が消えている。アインシュタインは、屋根から落ちる瓦職人の思考実験からヒントを得て、重力と加速度は区別がつかないというアイディアを原理にして、重力の理論である一般相対性理論を構築した。アインシュタインーード・ブロイの関係式」・・・・・・。
「シュレディンガーの猫」――量子力学が、古典力学と根本的に違うのは「重ね合わせ状態」という概念。「量子力学は不完全か?――アインシュタインVSボーア(光子箱の中の時計の論争)」・・・・・・。
歴史に残る思考実験を20 選び興味深いが、難解な課題をわかりやすいイラストを使って説明してくれる。これがまたありがたい。

