 コロナ禍で、企業ではテレワーク、学校はGIGAスクール、日常の買い物等でもオンラインが急速度に進む。一方、若者の「活字離れ」や幼児的・情緒的言葉が蔓延し、中・高校生が教科書等の問いがわからないという「読解力」不足が指摘されている。「デジタル文化は『読む脳(読字脳)』をどう変えるのか」「『深い読み』は絶滅寸前?」「紙の本は『深く読む脳』を育む」「デジタルで読む脳は、連続で飛ばし読みになり、短絡的で真の理解ができない」・・・・・・。著者は読む脳(読字脳)の研究者として国際的に知られ、古今東西の哲学者・教育者・文学者・研究者と交わり行動している神経科学者だ。「紙の本などの印刷媒体からデジタル媒体へ」という劇的変化のなか、「紙とデジタルでは、読む脳の回路にどんな変化を及ぼすか」という根源的かつ重要な問題に真っ向から挑み、提示する。
コロナ禍で、企業ではテレワーク、学校はGIGAスクール、日常の買い物等でもオンラインが急速度に進む。一方、若者の「活字離れ」や幼児的・情緒的言葉が蔓延し、中・高校生が教科書等の問いがわからないという「読解力」不足が指摘されている。「デジタル文化は『読む脳(読字脳)』をどう変えるのか」「『深い読み』は絶滅寸前?」「紙の本は『深く読む脳』を育む」「デジタルで読む脳は、連続で飛ばし読みになり、短絡的で真の理解ができない」・・・・・・。著者は読む脳(読字脳)の研究者として国際的に知られ、古今東西の哲学者・教育者・文学者・研究者と交わり行動している神経科学者だ。「紙の本などの印刷媒体からデジタル媒体へ」という劇的変化のなか、「紙とデジタルでは、読む脳の回路にどんな変化を及ぼすか」という根源的かつ重要な問題に真っ向から挑み、提示する。
人間には、文字を読むための遺伝子が備わっていない。遺伝子でプログラムされている見る・聞く・話す・嗅ぐ等とは全く異なり、年代に合わせた大人・親からの忍耐強い文字教育があって「読む脳」の回路が育っていく。著者は「紙の本を『深く読む』ことの重要性」を指摘する。脳内に、文字・音・意味を結びつける複合的な神経回路を成長させる不断の努力が、とくに初等教育で重要となる。「深い読み」の回路が形成されるのは何年もかかる。しかし、「感じられる思考、イメージをつくる能力(俳句でも)」「共感――他者の視点を得る」「会わなくても他者とコミュニケーションを実らせる」「他人の人生に入り、自分の人生に持ち込む」「孤独を脱する」「他者の生活や気持ちに入り込む認知忍耐力をもつ(今の若者は同類でない人々への共感を失い、攻撃的、不寛容になる――トランプやメディア)」「過去の思い込みを忘れて、別の人、別の地域と文化と時代に対する知的理解を深め、高慢と偏見を消す」「推測、推論、思考と共感の基礎をつくる――フェイクニュースの犠牲を避ける」「文字から情報を取り込み、批判的結論を得て、未知の認識空間へと飛び込み、新しい世界へと開示する」――。熟慮、洞察の世界であり、物事の本質を見ることで、「読字脳」から進んだ到達点が「他者に共感したうえで自分の思想を築く『深く読む脳』」だ。それはゆっくり時間をかけて考える「紙の本を読む」ことで育まれる。他者を知り自己を磨く読書の意義だ。
一方、デジタル媒体は速読になり、「iPadは新手のおしゃぶり」で、どうも「恒常的注意分散」になるという。自ら考えず過多な情報を、最も速く、最も簡単に処理する。「斜め読み」で「目がF字やジグザグに動く」「文章全体ですばやくキーワードを拾い、最後の結論に突進する」「O・ヘンリーの小説の夫婦の"懐中時計と髪"のような情感は画面読みはわからなくなる」ようだ。また「自分が時間と空間のどこにいるかわからず"世界で道に迷う"」「キーワードを拾って斜め読みする21世紀の読み手は、意図的に配列された言葉と考えの美しさを見逃していること自体に気づかない」。そして「言語力と思考力が衰えるとき、複雑な社会を単純に幼稚な自己中心主義で断じてしまうことになる」と危惧する。ツイッターで育った若い世代は、難解な文構造や比喩には苦労し、離れていく。書くことも劣化し、難しい散文にはなじみが薄くなり「認知忍耐力」「認知的持久力」を獲得できないことになる。
しかし、デジタル化は更に進み後戻りはできない。本書では「2歳になる前」「2歳から5歳」「5歳から10歳まで」の段階に、「どう読むか」について詳細に、実践的に述べている。そして「読み書き能力ベースの回路」と「デジタルベースの回路」の両方の限界と可能性を理解し、「バイリテラシー読字脳の育成」を提唱する。バイリンガル学習者の育て方と同じ基盤だ。デジタル力も読み書き力と同様に上手く育てる。「デジタル媒体と紙媒体双方で、"深い読み"のできる"二重に読むバイリテラシー読字脳"を育む」「子供の時に多くの本に親しみ、デジタル媒体は意識的に注意深く読む習慣をつけ、それを続けて文章を分析・批判できる『バイリテラシー脳』を育む」ことを提唱する。「デジタルで読む脳×紙で本を読む脳」の「×」は掛け算。
 「良心と偽善のあいだ」が副題。「国民の九割は良心を持たぬ(芥川龍之介)」「自己ハ過去ト未来ノ一連鎖ナリ(夏目漱石)」「森林太郎として死せんと欲す(森鴎外)」「吾生の曙はこれから来る(島崎藤村)」「山椒魚は悲しんだ(井伏鱒二)(身の丈に合った国づくり)」「お父さんを呼び返して来い(菊池寛)」「風立ちぬ、いざ生きめやも(堀辰雄)」「夜の底が白くなった(川端康成)」「などてすめろぎは人間となりたまひし(三島由紀夫)」「私は何故か涙ぐんだ(泉鏡花)」「痰一斗糸瓜の水も間にあはず(正岡子規)」・・・・・・。西欧を受容して走った日本の近代、戦時下社会、昭和の戦争、敗戦とともに始まった戦後民主主義――。日本人は、どこで何を間違えたのか。昭和は何を間違えたのか。近現代の作家や評論家の作品中の一節を抜き出して、それを手掛かりにして日本近代、昭和史の本質を剔り出したユニークな試み。味わい深く、考えさせられた。
「良心と偽善のあいだ」が副題。「国民の九割は良心を持たぬ(芥川龍之介)」「自己ハ過去ト未来ノ一連鎖ナリ(夏目漱石)」「森林太郎として死せんと欲す(森鴎外)」「吾生の曙はこれから来る(島崎藤村)」「山椒魚は悲しんだ(井伏鱒二)(身の丈に合った国づくり)」「お父さんを呼び返して来い(菊池寛)」「風立ちぬ、いざ生きめやも(堀辰雄)」「夜の底が白くなった(川端康成)」「などてすめろぎは人間となりたまひし(三島由紀夫)」「私は何故か涙ぐんだ(泉鏡花)」「痰一斗糸瓜の水も間にあはず(正岡子規)」・・・・・・。西欧を受容して走った日本の近代、戦時下社会、昭和の戦争、敗戦とともに始まった戦後民主主義――。日本人は、どこで何を間違えたのか。昭和は何を間違えたのか。近現代の作家や評論家の作品中の一節を抜き出して、それを手掛かりにして日本近代、昭和史の本質を剔り出したユニークな試み。味わい深く、考えさせられた。
「戦後の、裸の王様たちよ――体がゆらゆらするのを感じた(開高健)」――。近代日本の最大の偽善とはどのようなものか。たとえば戦後のある時期に良心的だと評された教育評論家や新聞記者。戦時下で徹底した皇国史観の教育を行ったり、軍の提灯記事を書き、敗戦と同時に反省をする。そして戦争に反対する教育現場の先頭に立ったり、民主主義万歳の新聞を発行する。どんな時代になろうと常に「正義派」の側に位置して生きていく輩。「表向き誰も反対できない。しかしその言い分はまさに裸の王様ではないか」「戦時下社会は分析すればするほど、偽善が横行していたことがわかる。負けているのに勝っているとの国家的キャンペーンから日常のモラルまで、その全てが偽善化していた。その結果、どうなるのか。麻痺状態になるのである。客観的判断が失われ、主観的願望が社会の常識となる。まさに妄想性人格障害そのものの症状になっていく」「戦争に負けるというのは自己否定と考えていたのだ。自分が全否定された時、人は泣く以外に方法はない。なんのことはない。自立精神に欠けているという意味になる。もう一つは、戦争に負けるというのは自分たちの作ってきた神話が崩れるということだ。この場合の神話とは、不敗日本、神国日本、世界に冠たる帝国、そんな神話がまるで根拠もなかったと実証された。現実を知るのが怖いのである」「再び作った神話とは、経済大国日本という語に仮託されている日本人の団結力とか英明さである。やがてそれが思い込みと知った時に・・・・・・」「男子が本当に泣かなければいけないのは、信念のために生きる姿を見た時だ」「日本軍の軍事指導者は、日本文化、日本の伝統("戦"は存在しない)に対する背反者であり、無礼極まりない粗忽者である。・・・・・・痛切に思うのは、先達の残した文化的遺産を己が身に徹底してたたき込むことである」という。
 「『失敗の本質』と国家戦略」が副題。「なぜ戦前の日本は誤ったのか」「戦前の日本において、外交と軍事の総合調整、国務と統帥の統合がどのように形成され、破綻したか」――。世界の潮流を見誤まり、軍の暴走から大日本帝国の滅亡をもたらした"失敗の本質"に迫る。多くの歴史書と違い、熱を帯びた鋭い論考となっているのは、最近まで内閣官房副長官補、国家安全保障局次長として、国家戦略の中枢で重責を担ってきたことにあろう。加えて、戦前の体制が世界の激動と潮流を如実知見できず、体制は無責任、軍の暴走に帰着したこと、外交が国家の決定に関与できなかったことの悔恨が行間から滲み出る。それに比し、たとえば日露戦争を和平にまで持ち込むことができたのは「小村寿太郎のような傑出した外交官、大山巌、乃木希典、児玉源太郎等の名将とともに、桂太郎総理を陰から支えて外交と軍事を統括した元老・山縣有朋がいたからである」という。また日清戦争についても「伊藤博文総理が、陸奥宗光外相、川上操六陸軍中将という人を得て、政治、外交、軍事を統括することによって得た勝利である」という。
「『失敗の本質』と国家戦略」が副題。「なぜ戦前の日本は誤ったのか」「戦前の日本において、外交と軍事の総合調整、国務と統帥の統合がどのように形成され、破綻したか」――。世界の潮流を見誤まり、軍の暴走から大日本帝国の滅亡をもたらした"失敗の本質"に迫る。多くの歴史書と違い、熱を帯びた鋭い論考となっているのは、最近まで内閣官房副長官補、国家安全保障局次長として、国家戦略の中枢で重責を担ってきたことにあろう。加えて、戦前の体制が世界の激動と潮流を如実知見できず、体制は無責任、軍の暴走に帰着したこと、外交が国家の決定に関与できなかったことの悔恨が行間から滲み出る。それに比し、たとえば日露戦争を和平にまで持ち込むことができたのは「小村寿太郎のような傑出した外交官、大山巌、乃木希典、児玉源太郎等の名将とともに、桂太郎総理を陰から支えて外交と軍事を統括した元老・山縣有朋がいたからである」という。また日清戦争についても「伊藤博文総理が、陸奥宗光外相、川上操六陸軍中将という人を得て、政治、外交、軍事を統括することによって得た勝利である」という。
そうした「日清戦争、日露戦争と朝鮮半島」や「対華21ヶ条要求という愚策」「日英同盟の消滅がもたらしたもの」「ロンドン海軍軍縮条約を利用した統帥権干犯問題。政府から独立して動く統帥部の軍事作戦が外交と政治を壟断した日本憲政史上の最大の失敗(日本が道を誤ることになる最大の原因)」「満州事変は"下策中の下策"」「第二次上海事変こそが日中戦争の真の発火点」「独ソ不可侵条約でハシゴを外された日本」「松岡外相、ヒトラーに振り回される」「対日石油全面禁油の意味、連合国の逆鱗に触れた南部仏印進駐、恐るべき国際感覚の欠如」「日本を終戦に引っ張った鈴木貫太郎、陸軍を抑えた阿南惟幾大将の割腹自殺」「第二次世界大戦後の世界――民族自決、人種差別撤廃、共産主義の終焉」「米中国交正常化と戦略枠組みの変化」等々を剔抉して語る。
そして、「普遍的価値観と自由主義的国際秩序」「価値の日本外交戦略」「自由で開かれたインド太平洋構想」等について述べる。「日本が20世紀前半に大きく道を誤ったのは、欧州を中心とする弱肉強食の権力政治にとらわれて、人類社会の論理的成熟を待つことができなかったからである」「これからの日本に必要なのは、世界史的な次元でリーダーシップをとれるリーダーである」という。
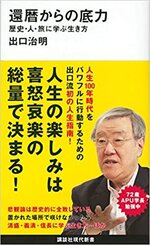 「『人・本・旅』で、いろいろな人に会い、いろいろな本を読み、いろいろなところに出かけていって刺激を受けたら、たくさんの学びが得られ、その分人生は楽しくなる。還暦だろうが古希だろうが年齢など関係ない」「定年を廃止し、健康寿命を延ばす」「根拠のない常識や不毛な精神論に縛られるな。数字・ファクト・ロジックで物事をとらえ、エピソードではなく、エビデンスで世界を見ることだ」「先進的な国では、もう年齢フリー社会、オール・サポーティング・オールの世界に入っている。年齢に関係なく、みんなが能力と意欲、体力に応じて働く。そして、シングルマザーなど本当に困っている人に給付を集中する。年齢で優遇するのをやめ、困っているかどうかで優遇する人を決める」「高度成長期の慣習が身体にしみついているが、ヤング・サポーティング・オールドという人口ボーナス期の特殊な時代の仕組みを前提にしてしまっている」「人生の楽しみは喜怒哀楽の総量で決まる(怒も哀もだ)」などという。人生哲学がビシッと柱となっていて、教養と経験、リアリズムに裏付けられ納得する。
「『人・本・旅』で、いろいろな人に会い、いろいろな本を読み、いろいろなところに出かけていって刺激を受けたら、たくさんの学びが得られ、その分人生は楽しくなる。還暦だろうが古希だろうが年齢など関係ない」「定年を廃止し、健康寿命を延ばす」「根拠のない常識や不毛な精神論に縛られるな。数字・ファクト・ロジックで物事をとらえ、エピソードではなく、エビデンスで世界を見ることだ」「先進的な国では、もう年齢フリー社会、オール・サポーティング・オールの世界に入っている。年齢に関係なく、みんなが能力と意欲、体力に応じて働く。そして、シングルマザーなど本当に困っている人に給付を集中する。年齢で優遇するのをやめ、困っているかどうかで優遇する人を決める」「高度成長期の慣習が身体にしみついているが、ヤング・サポーティング・オールドという人口ボーナス期の特殊な時代の仕組みを前提にしてしまっている」「人生の楽しみは喜怒哀楽の総量で決まる(怒も哀もだ)」などという。人生哲学がビシッと柱となっていて、教養と経験、リアリズムに裏付けられ納得する。
「グーグルやアマゾンを生み出せない日本の教育」「日本の仕組みは、製造業の工場モデルで、素直で我慢強く、協調性がある人が求められた。『飯・風呂・寝る』の低学歴社会。今からは、『人・本・旅』の高学歴社会。"変態オタク"が育つ教育を」「"仕事が生きがい"は自分をなくす」「北欧の先進国は定年なしで、社会保障がしっかりしている」「自分への投資と学び続けることの大切さ」「別府の町とAPU」「ダイバーシティーで栄えた国、逆の政策で没落した国」「必読の古典6冊」「理性にすべてを委ねるのは傲慢である」「男女差別が日本を衰退させている」「社会保障というセーフティネットを自ら壊してはいけない」「精神論を排除し、数字・ファクト・ロジックで語る」・・・・・・。
「高齢化社会の将来は暗くはないし、人はいくつになっても楽しい人生を過ごすことができる」と「還暦からの底力」の発揮をという。
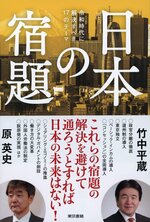 2020年代からの日本は厳しい山に差しかかる。①少子・高齢・人口減少社会②AI・IoT・ロボットの急進展③次元の変わった頻発する大災害――。これがコロナ禍によって更なるデジタル社会と感染症対策が加わる。構造変化が激しい。
2020年代からの日本は厳しい山に差しかかる。①少子・高齢・人口減少社会②AI・IoT・ロボットの急進展③次元の変わった頻発する大災害――。これがコロナ禍によって更なるデジタル社会と感染症対策が加わる。構造変化が激しい。
「令和時代に解決すべき17のテーマ」を副題として、「これらの宿題の解決を避けて通ろうとすれば日本の未来はない!」としたのが本書だ。「政治」においては「真の政・官分離を実現する――官僚主導のゆがみを是正せよ」「地方衰退を解決する――権限・財源を地方に移す、高齢者の地方移住を促進」「道州制を導入する」「東京を独立させる――東京を日本全体の戦略基地として特別行政地区とする」「令和の農地改革を実施する――企業の農地所有を認める」――。
「経済」では「ベーシック・インカムを導入する」「コンセッションを全面導入する――とりわけ当面、水道や林業」「シェアリング・エコノミーを推進する」「経済の新陳代謝を高める――総理主導の規制改革」「デジタル・ガバメントをつくる――マイナンバー制度と歳入庁」――。
「社会」では「働き方をさらに変革する――自由な働き方と自由な雇い方、同一労働同一賃金」「移民法(外国人労働法)をつくる」「脱原発を実現する」「少子高齢社会を克服する――特別養子縁組をしやすくする法改正、フランスの少子化対策」「東大を民営化し、教員資格制度を変える」「真のジャーナリズムを育成する」「政治・メディアの悪循環を糺す」――。
これまで論議してきたこと、私自身がかかわり具体的に進めてきたこと等々があり、問題を常に思考し続けることが大切!

