 今年はマックス・ヴェーバー(1864―1920)の没後100年――。「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」「職業としての政治」など、まさに「知の巨人」であり、高踏派の人物ととられがちだが、じつは政治的にも"血の気"の多い闘争的人物であり、衝突を常とした激しい人物であった。あまたあるヴェーバー研究のなかで、本書は時代と格闘したヴェーバーの人物像を描く「伝記論的転回」を意図した意欲作だ。
今年はマックス・ヴェーバー(1864―1920)の没後100年――。「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」「職業としての政治」など、まさに「知の巨人」であり、高踏派の人物ととられがちだが、じつは政治的にも"血の気"の多い闘争的人物であり、衝突を常とした激しい人物であった。あまたあるヴェーバー研究のなかで、本書は時代と格闘したヴェーバーの人物像を描く「伝記論的転回」を意図した意欲作だ。
「M・ヴェーバーは『鉄の歯』を持った男だった」とはソ連外相グロムイコがゴルバチョフに言った言葉だという。「強烈な主体性をもって何事でも自己貫徹をしようとしたヴェーバーには、この表現が相応しい」と今野さんはいう。世事を超越して知的に精進した「求道者」「人道家」、学会・大学運営への熱心な提言や官僚精神への抵抗、難題への集中力や弱者への義侠心をもつヴェーバーだが、一方では際限ない他者攻撃、プロテスタンティズムやドイツ・西洋などへの自分の側への極度の入れ込み、悪筆・難解な文体、社会ダーウィン主義への傾倒、カリスマ的政治指導への夢想、自身の言行不一致など、激しい二面性が同居していたことを指摘する。「主体性にも『独立自尊』という面と『傍若無人』という面がある」というのだ。本書の副題が「主体的人間の悲喜劇」であるのは、きわめて的確で納得する。
スペイン風邪で56歳の若さで死亡したヴェーバーは、ヒトラーのドイツには遭遇していない。"西欧派ドイツ・ナショナリスト" ヴェーバーとヒトラーは交わる面もあるが、本書でのヴェーバーの生涯から感ずるのは、宗教的倫理や人種など衝突は避けられなかったのではないかと思う。それは、師のシュモラーやアルトホフ体制批判の激しさや、生まれた家庭・生いたちの違いを見ても、時間を追うごとに亀裂を増していくと思われるからだ。
19世紀末の西欧の近代社会・産業社会への各国の攻防のなかでのドイツの興隆、そして第1次世界大戦とその敗北のなかでの疾風怒涛のヴェーバー。新興アメリカにも赴き、戦時となればプロイセン陸軍中尉として出頭したヴェーバーはきわめて人間臭い。
私にとってヴェーバーは青年時代、最も影響を受けた一人だ。京大相撲部に入部した時に、なんと相撲部部長が名著「マックス・ウェーバー」の著者・青山秀夫先生であった。この書を読むことは入部の必須事項のようなものだった。激しい学生運動、思想闘争、大学闘争へと大学は荒れた。常に論争はマルキシズムをめぐってのものだった。私は「経済の下部構造が上部構造を決定する」との論に、「経済等の根源に人間の生命があり、生命の変革・エートスの変革なくして社会変革はない」と主張した。ウェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」や大塚久雄先生の「社会科学の方法」などに感銘して、大胆にも仏法哲学と社会科学を架橋した。M・ウェーバーはそうした生きた思想だった。
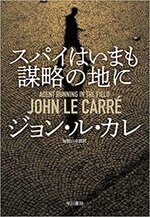 ブレグジット、トランプ、プーチン――。米・欧・露は日常的に頻繁な交流があり、利害・思惑が交錯する。巨匠ジョン・ル・カレの最新作。1931年のイギリス生まれだから88歳になる。それ自体が凄い。
ブレグジット、トランプ、プーチン――。米・欧・露は日常的に頻繁な交流があり、利害・思惑が交錯する。巨匠ジョン・ル・カレの最新作。1931年のイギリス生まれだから88歳になる。それ自体が凄い。
英国秘密情報部(SIS)のベテラン情報部員ナットは、ロシア関連の作戦遂行後、中年をすぎて引退が囁かれていた。英国はブレグジットで混乱、米国のトランプ政権の変化やロシアの情報部の脅威もあり、人員の吹きだまりのような部署「ヘイブン」支局長として異動になる。着任早々、ナットは新興財閥(オルガルヒ)の怪しい資産の流れを探る作戦の準備に忙殺される。息抜きは近所のスポーツクラブでのバドミントン。向かう所敵なしの彼に、エドという若者が挑戦してきて二人は親しくなる。そんな時、ナットのところに利用価値もないと思われていたロシア人亡命者セルゲイから緊急の連絡が入り、ロシアの大物スパイが英国で活動を始めるようだという。情報部全体が色めき立っていく。
登場人物は多彩。大きなアクションがあるわけではないが、各人物の思惑、本心の読み合い、読み取られないように細心の注意を払う言動や行動、個人と組織の相剋や忠誠心などが、人間存在の核心に迫るかのように繊細に描写される。息苦しいほどのスパイの日常、そしてその命の中に確立された信念や誇り、宿命というべきものが伝わってくる。
【私の読書録】
コロナ後の世界 ジャレド・ダイアモンド、ポール・クルーグマン、リンダ・グラットン、マックス・テグマーク、スティーブン・ピンカー、スコット・ギャロウェイ 大野和基(編) 文春新書
2020年9月 7日
 このパンデミックで人類の未来はどう変わるか。世界の知性6人への緊急インタビュー。それぞれの専門家に、率直に聞いているだけに、興味深い。
このパンデミックで人類の未来はどう変わるか。世界の知性6人への緊急インタビュー。それぞれの専門家に、率直に聞いているだけに、興味深い。
「独裁国家はパンデミックに強いのか」(ジャレド・ダイアモンド 生物学・生理学・地理学教授でピューリッツァー賞受賞)――。「日本は諸外国に比べて、よくやっているように思う」「未知の感染症は動物が持っているウイルスが人間にも感染するように変異したもの。なぜ中国は何年も前に野生動物市場を閉鎖していなかったのか」「日本の人口減少はアドバンテージになる。日本の高齢者は健康、問題は高齢化ではなく定年退職システム」「移民を受け入れ、女性を家庭から解放しよう」「何よりも大事なのは中国、韓国との関係改善だ。フィンランドを見よ」「21世紀は中国の時代か?」・・・・・・。「AIで人類はレジリエントになれる」(マックス・テグマーク AIの安全性を研究する『生命の未来研究所』を設立した理論物理学者)――。「パンデミックとの闘いは情報戦」「ワクチン・新薬開発にAIが活用できる」「汎用型AI(AGI)となると大量のデータを必要としなくなる」「AIによる自動兵器の脅威に国際禁止協定を」・・・・・・。
「ロックダウンで生まれた新しい働き方(リンダ・グラットン 人材論・組織論の権威で『ライフ・シフト』の著者)」――。「新型コロナは人生100年時代への大きな影響はない」「長寿社会とは"より長く働く社会"」「日本と企業を支配してきた"男女分担の考え方"を変えよ」「日本が戦後の再建に費やした経済成長へのエネルギーを、『個人』『家族』『健康』に注ぎ込め」・・・・・・。「認知バイアスが感染症対策を遅らせた」(スティーブン・ピンカー 進化心理学の第一人者のハーバード大教授)――。「中国の独裁主義が感染拡大を助長した」「いいニュースは報道されないジャーナリズムの罪」「我々の認知能力はバイアスの影響をすぐ受ける」「AIへの不合理な恐怖」・・・・・・。
「新型コロナで強力になったGAFA」(スコット・ギャロウェイ デジタルマーケティングを教えるニューヨーク大学スターン経営大学院教授)――。「パンデミックでビッグテックはますますパワフルに。企業統合の動きが続く」「GAFAはあたかも高速道路の巨大料金所」「GAFAを禁止する国が出てくる」「GAFAはパンデミックでパワフルになり、70~80%の企業は弱体化する」「オンライン教育となると二流大学は倒れていく」「在宅勤務のできる人とできない人の格差が広がる」「BATとGAFAのぶつかる場所はアメリカではなく、アフリカやインド」「GAFAの負の側面から目をそらすな」・・・・・・。
「景気回復はスウッシュ型になる」(ポール・クルーグマン 2008年ノーベル経済学賞)――。「労働人口の20%ほどが突然仕事を奪われ収入がなくなった"人工的な昏睡状態"」「ためらわずにバズーカ砲を撃て(強力な金融緩和策)」「景気回復のカーブはU字型でもV字型でもなくスウッシュ型になる。それも二歩進んで一歩下がる」「消費増税は税収を減らすだけ」「インフレ率を上げれば、実質金利が下がり、個人消費は喚起される。インフレ率が低迷しているのは、企業が賃金を十分に上げないことと、モノの価格を上げたがらないことにある」「インフレ目標を達成するには、減税や公共投資などの財政支出、爆発的財政支出が求められる」「ドイツはEUの"問題児"」「米中貿易戦争に勝者はいない」・・・・・・。
いずれもきわめて率直に語っている。

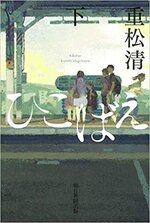 万博に沸く1970年、主人公の長谷川洋一郎が小学校2年の時に家を出て行った父親の記憶はおぼろげだ。48年たった現在、高齢者施設の責任者を務め、結婚した娘が臨月を迎えている彼のもとに、ある日突然、その後全く接触のなかった父親の訃報が届く。意外にも父親・石井信也は洋一郎とそう遠くない土地に住み、一人暮らしを続けていたという。洋一郎は父の住んでいた部屋を訪ね、付き合いのあった人々に出会い、「父はどういう人生だったのか」と、父親の姿を探り当てようとする。再婚した母親、迷惑をかけた父親を悪しざまに言う姉・宏子、父と親しかったトラック仲間・神田や行きつけのスナックのママ・小雪、「自分史」を残そうと相談されていた西条真知子・・・・・・。話を聞くうちに迷惑をあちこちにかけたが、憎めない親父、寂しさを抱え続けた親父の姿が見えてくる。そして、父―息子―孫、理屈を越えた血縁をしみじみ感じるのだ。
万博に沸く1970年、主人公の長谷川洋一郎が小学校2年の時に家を出て行った父親の記憶はおぼろげだ。48年たった現在、高齢者施設の責任者を務め、結婚した娘が臨月を迎えている彼のもとに、ある日突然、その後全く接触のなかった父親の訃報が届く。意外にも父親・石井信也は洋一郎とそう遠くない土地に住み、一人暮らしを続けていたという。洋一郎は父の住んでいた部屋を訪ね、付き合いのあった人々に出会い、「父はどういう人生だったのか」と、父親の姿を探り当てようとする。再婚した母親、迷惑をかけた父親を悪しざまに言う姉・宏子、父と親しかったトラック仲間・神田や行きつけのスナックのママ・小雪、「自分史」を残そうと相談されていた西条真知子・・・・・・。話を聞くうちに迷惑をあちこちにかけたが、憎めない親父、寂しさを抱え続けた親父の姿が見えてくる。そして、父―息子―孫、理屈を越えた血縁をしみじみ感じるのだ。
「ひこばえ」――。太い木の幹を切って切り株を土台にして、「ひこばえ」がいくつも芽吹く。「娘や息子には会えない。あわせる顔がないってことだな。だが孫には会いたいって言っていた」「自分の蒔いた種が、子どもの代をへて、孫の代にまで続いてるっていうのが、いいじゃないか」「思い出を勝ち負けで分けたらいけん。・・・・・・ええことも悪いこともひっくるめてひとはひとなんよ。あんたらのお父さんは、世間さまに褒めてもらえるようなことはできんかった。あんまり幸せにはなれんかったかもしれん。・・・・・・でもあんたらが幸せになって、あんたらの子どもも孫も、みんな幸せになってくれればええんよ。それでお父さんも・・・・・・お父さんが生きて、この世におったことが報われるんよ」「苦労やら気兼ねやら、ぜーんぶひっくるめて、うちは幸せな人生じゃったよ」・・・・・・。「母は最後にあらためて父の遺骨に手を合わせた」「洋ちゃん、お父さんを連れて来てくれてありがとうな。あんたの親孝行のおかげで、いろんな胸のつかえがとれた」という。人の心には「胸のつかえ」、「寂しさ」があり、それを埋めるには、人の血縁のつながりが不可欠のようだ。
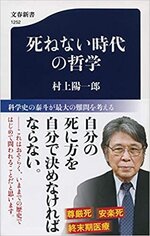 人生100年時代――それは、細菌やウイルスの攻撃によって「理不尽に」命を奪われる時代から脱し、老化によるさまざまな機能の劣化によって「必然的な、あるいは自然な死」を迎えるという流れにたどり着いた今の状況だ。しかし、私たちは「なかなか死ねない」時代に直面しているともいえる訳だ。歴史上はじめて、一人ひとりが自分の人生の終わり方を考えざるを得なくなったことでもある。科学哲学者・村上陽一郎氏が、「死」というものを考える道筋を示してくれている。生老病死、科学・哲学の世界を深く考えさせる必要不可欠、納得の書だ。
人生100年時代――それは、細菌やウイルスの攻撃によって「理不尽に」命を奪われる時代から脱し、老化によるさまざまな機能の劣化によって「必然的な、あるいは自然な死」を迎えるという流れにたどり着いた今の状況だ。しかし、私たちは「なかなか死ねない」時代に直面しているともいえる訳だ。歴史上はじめて、一人ひとりが自分の人生の終わり方を考えざるを得なくなったことでもある。科学哲学者・村上陽一郎氏が、「死」というものを考える道筋を示してくれている。生老病死、科学・哲学の世界を深く考えさせる必要不可欠、納得の書だ。
そこで立ち現れてくるのが永遠の難問である「死」をどう考え、どう迎えるのか。死は自己決定できるか。死生観、安楽死、尊厳死、終末期医療等々の問題だ。21世紀に入り、安楽死をめぐる世界の状況は大きく変わってきた。世界各国で安楽死、もしくは医師による自死支援(PAD)が認められるようになってきているという。安楽死は、医師が直接、死ぬための薬を投与する行為、PADは、死を希望する終末期の患者が、医師から死ぬための薬物、方法を与えられ、それを使って自ら死ぬこと。これを「積極的安楽死」と呼ぶ。一方で、延命治療を患者の意志で中止するのが「消極的安楽死」で、日本ではこれを一般的に「尊厳死」と呼ぶ。オランダ、カナダ、コロンビア等でPADと安楽死がこの20年程で認められ、1975年の「カレン事件」を受けアメリカでは「尊厳死」が容認され、アジアでも韓国と台湾で「尊厳死」(延命治療の中止)を認める法律が近年施行されているという。
しかし、これが"時流"などという軽いものではなく、「死は自己決定できるか」「安楽死の要件」という最大の哲学的・科学的問題に直面していることを語るのが、本書の凄い所。患者自身、医師の覚悟、死の関係者への広がりを含めて哲学、倫理と生死の現実の葛藤が濃密に語られる。思索の深さが心に浸透してくる。「死を避ける方法がなく、死期も間近い。患者に耐え難い、見るに忍びないほどの肉体的苦痛がある」――。医療現場、司法等々、ギリギリの模索がこの50年、世界で続けられている。「米のカレン事件(1975年)」「米の医師キヴォキアンの点滴タナトロン(1987年)」「オランダのポストマ事件(1971年)」「名古屋安楽死事件と司法の安楽死要件(1962年)」「東海大安楽死事件(1991年)」「川崎協同病院事件(1998年)」「7人の終末期患者が生命維持装置を外され死亡した富山県の射水市民病院の事件(2006年)」・・・・・・。法制化はこのデリケートな問題については難しい。「オランダ等のようには法的に安楽死を認める方向には、日本社会は進まないだろう」「私はあくまでも原則としてですが、PADや安楽死は常に否定されるべきものではない、という個人的な意見を持っている」という。なだいなださんは「法律になじまない問題だと考えてきた。安楽死が法的に認められてしまうと、権利や義務の意識でこの問題に対処するようになるのではないか、と危惧する」といっており「私も全く賛成です」と村上さんはいう。自己決定については、「本人の意志は欠かすことのできない必要案件であるが、十分案件とは言えない。本人はそう考えているけど、どうしましょうか、という所から初めて議論が始まる。・・・・・・自己決定の原理そのものが最大限尊重されるべきであることに異論は少ないでしょう。ただしその中に死も含まれるか、ということになると、人それぞれ思いは違ってくるはず」ともいう。「自分の運命は自分のもの」という考え方について、また「自己決定と自己決定権の違い」についても述べる。生命倫理学者の小松美彦氏の著書「『自己決定権』という罠」の「死は関係のなかで成立し、関係のなかでしか成立しない事柄なのだから、人は死を権利として所有も処分もできない」を引きつつ、「自分の人生ですから、それをどうするかについて、刻々自己決定を迫られる。けれどもそれは、権利として、その人の生あるいは死を覆うわけではない、という彼の主張にはうなずかされるところがある」という。さらに「安楽死で逝きたい」「周りの人に迷惑をかけたくない」という思いが、その時の自己決定であっても、「人間の意志は変わりうる」ことも事実だ。この長寿社会、死ねない時代、そして安楽死や尊厳死、終末期鎮静、自己決定、個人主義と民主主義社会の問題は、現前する難問であるが、その問題の提起する深さを剔抉している。

