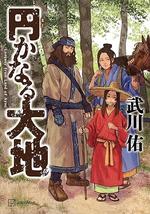 16世紀の蝦夷地。アイヌと和人とが激しく激突した今でいう函館、松前などの北海道南部先端。シリウチコタン(アイヌ集落として最南端)、大館(後の松前)、勝山館、エサウシイなど、和人とアイヌが混在する嶋南が舞台。アイヌの壮年シラウキは、この地の支配を目論む大館の蠣崎季廣の娘・稲を、とあることから攫ってしまうことになり、紛争の引き金を引く。
16世紀の蝦夷地。アイヌと和人とが激しく激突した今でいう函館、松前などの北海道南部先端。シリウチコタン(アイヌ集落として最南端)、大館(後の松前)、勝山館、エサウシイなど、和人とアイヌが混在する嶋南が舞台。アイヌの壮年シラウキは、この地の支配を目論む大館の蠣崎季廣の娘・稲を、とあることから攫ってしまうことになり、紛争の引き金を引く。
この地は、これまでも何度も和睦と称して相手を皆殺しにするという悲惨な歴史が繰り返され、アイヌと和人との間には不信と憎しみが充満していた。そうした絶望的な過去を抱えるシラウキ、領袖の娘として純粋な責任を背負う稲、蠣崎家家臣で稲の許婚の下国師季、泊村を支配する無頼の女傑・小山悪太夫、女真族で蠣崎二郎基廣(シラウキの友であった)の「有徳党」の一員の男・アルグンの5人は、紆余曲折を経たうえ結束し、和睦を成立させるために仲裁を求めて海を渡り、出羽国の檜山屋形(安東家当主・安東舜季)へと旅立つ。命をかけた難行苦行。それぞれが過去を背負い向き合いながら、ひたすら自分の内に秘すものを秘しながら、「アイヌと和人のとこしえの和睦」「円かなる大地」を目指して突き進む。
暴れる羆、過酷な自然、異文化の攻防――最初から、最後まで、息苦しいほどの戦いのなか、一筋の光芒が鮮やかに描かれ、一息つく思いがする。2019年の「アイヌ新法」「ウポポイの民族共生象徴空間」を想起する。
 「台湾有事のリスクと日本が果たすべき役割」が副題。台湾をめぐる米中軍事衝突は世界戦争へ直結する危険がある。「台湾をめぐる米中戦争の可能性は『起こりうるが回避も可能、もし起きたら世界が終わる』というのが現時点の評価だ。関係諸国の間で、それが、『世界の終わりは避けられないが、そんな未来はありえない』に変われば、筆者は枕を高くして眠れるだろう」と結論する。
「台湾有事のリスクと日本が果たすべき役割」が副題。台湾をめぐる米中軍事衝突は世界戦争へ直結する危険がある。「台湾をめぐる米中戦争の可能性は『起こりうるが回避も可能、もし起きたら世界が終わる』というのが現時点の評価だ。関係諸国の間で、それが、『世界の終わりは避けられないが、そんな未来はありえない』に変われば、筆者は枕を高くして眠れるだろう」と結論する。
「インド太平洋地域の内外で、多くの国が終末戦争の危険を減らそうと力を注いでいる」と、著者はその様子を伝え、各国の努力の評価を行い、抑止戦略の相関図を開示する。抑止努力は、「自由で開かれたインド太平洋vsアジアの安全保障はアジア人の問題だ」「台湾は中国人が解決すべき『国内問題』であるvs台湾は安定と人権と制海権をめぐる地域と世界の問題だ」との言説の報酬は危険な誤解を招きかねない。「台湾をめぐる紛争は、通常兵器しか使わない局所的な衝突なのか、それとも世界への波及が避けられず、核の使用まで想定する必要があるのか」――その損失と危険は容認しがたいと言う。過去の冷戦と違い、今の世界は2つのブロックにしっかり分かれているわけではなく、緊密かつ複雑な関係が絡み合っている。「今求められているのは、従来型の抑止戦略に加えて、その良い面を現代の外交と政治に再現することだ。新しい冷戦を始めなくとも、かつての冷戦から外交の枠組みが持つ価値を学べば良いのである」・・・・・・。
バイデン大統領の介入発言が「台湾とウクライナのリスクの差を鮮明にした」が、著者は米国が断固として介入する意思を持てるかどうか、それが台湾有事の焦点になると言う。米国が中国と向き合う意思を強固にし、日本が新防衛方針に沿って抑止力を高め、同盟国・パートナー国との連携を促進することの重要性を指摘する。アジア諸国のそれぞれの事情の違いを説明している。日本の安全保障政策と政局との関わりについては、正確ではない。
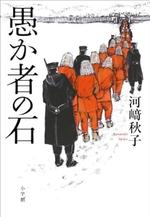 北海道の厳しい自然環境のなか、人と獣の業と悲哀を圧倒的な迫力で描き続ける河﨑さんの最新作。
北海道の厳しい自然環境のなか、人と獣の業と悲哀を圧倒的な迫力で描き続ける河﨑さんの最新作。
明治18年初夏、瀬戸内巽は政治活動をした国事犯として徒刑13年の判決を言い渡され、北海道の樺戸集治監に収監される。21歳だった。劣悪な5人部屋の雑居房。そこで一緒になったのが山本大二郎30歳。極寒、劣悪、過酷な日々が始まるが、この大二郎、女の話や食い物など囚人の欲望を膨らませる夢のような話で周りを巻き込む法螺吹き男だった。巽は親しくなるが、大二郎は、「俺の宝物なんだ」と小さな水晶の石を大事に隠し持っていた。あまりにも厳しい極寒の冬を何とか乗り切るが、翌春、2人は硫黄採掘に従事するため、道東の釧路集治監へ移送される。吹雪で仲間が命を落とすなか、中田看守と2人は、やっとたどり着くが、そこでの労働は、これまで以上に過酷、硫黄のために体を壊し死ぬものも多かった。大次郎は体をやられ、目を悪くする。
2年に及ぶ苦役を何とかしのぎ、明治21年暮れ、3人は再び樺戸へ戻ってきた。大二郎は明治22年1月末、収監されていた屏禁室が火事となり、脱走する。
「山本大二郎はどこの出身なのか、何の罪を犯したのか」「あの石は一体何なのか」「法螺話や大仰な話をして場を楽しませていた男の真実の正体とは」「火災はなぜ起き、大次郎はどこへ行ったのか」・・・・・・。明治30年1月、恩赦もあって、刑期を終えた巽だが、脳裏にはその疑問がつきまとう。中田看守から大二郎はかつて幼子2人を殺した男だと聞くが・・・・・・。
絵の名人であることを隠していた大二郎。「囚人というのは徹底して、看守に従順であることを課せられる。ならば、本当の自分を晒さないこと、それは当人にとってはささやかな抵抗として機能し得るのではないか」「山本大二郎は、相棒にまで絵の趣味を隠し、密かに集治監の体制に抵抗していた」・・・・・・。しかし普通の勝利への抵抗では全くない。地獄の中に住み続ける男の諦念の境地が、真実に迫るなかで心奥に伝わってくる。
 「ソーシャル・アバランチを防ぐには」が副題。データ改竄、不正会計、品質不正など、なぜ有名企業の不正はあとを絶たないか。派閥の「政治とカネ」の問題もそうだ。その組織不正が続いていることの原因について考察する。
「ソーシャル・アバランチを防ぐには」が副題。データ改竄、不正会計、品質不正など、なぜ有名企業の不正はあとを絶たないか。派閥の「政治とカネ」の問題もそうだ。その組織不正が続いていることの原因について考察する。
「組織不正は、いつでも、どこでも、どの組織でも、誰にでも起こりうる。なぜなら、組織不正とは、その組織ではいつも『正しい』と言う判断において行われるものだからだ」「個人が『正しさ』を追求することによって、個人的雪崩、組織的雪崩が起き、ひいては社会的雪崩が起きる」「とりわけ組織不正に着目すれば、組織的雪崩をいかに防ぐかが大事である」「重要なことは単一的=固定的な『正しさ』を相対化するための複数的=流動的な『正しさ』をいかに確保して行くかである。とりわけ役員レベルにおいては、女性役員の登用のように、性差、年齢、国籍、経験など多様性が保たれることが重要である」と言う。特に組織不正の発生とその広がりを「社会的雪崩(ソーシャル・アバランチ)」として説明し、個々の不正行為がどのようにして、組織全体に雪崩のように影響及ぼすかを示している。多くの研究では、組織不正が「危うさ」によって引き起こされるとされてきたが、本書はそうではないとする。「誰もそのことには気づかずに長い間状態化してきてしまった」とよく言われるが、「組織にいる多くの人々が、何かしら『正しい』と考えている状態があって、それを疑うことなく、長い間続けてしまったというのが組織不正の本質ではないか」と考察している。それが積もれば積もるほど雪崩となるのだ。
具体例が示される。まず三菱自動車・スズキの燃費不正。国交省、経産省と自動車企業との「正しい」とされる燃費基準の差異が問題を生んだと指摘する。
東芝の不正会計問題――。経営陣が事業部に対して過度な利益達成目標を押し付け、それに耐えかねた社員が、利益の水増しなどを行ってしまったもの。無理を強制して現場を追い込んでいる。トップの経営陣がミドルの事業部に利益目標を一方的に伝えるのではなく、ミドルに権限を与えて、自ら利益目標を計画させ行動できるようにすることの重要性だ。どの組織にも「会社のため」と「部門のため」の「正しさ」があるわけだ。
医薬品業界の品質不正――。ジェネリック医薬品の増産を求める「骨太方針」の下で「国―都道府県―製薬業界」に何が起きていたか。
そして大川原化工機を襲った軍事転用不正の疑い――。これは「閉じられた組織の中の『正しさ』」が次々と雪崩を生んでいく怖さだ。さらに「倫理的な『正しさ』もまた組織的雪崩を生む」を指摘する。
どの組織にもある権力構造の歪みが、組織不正を生み出してしまう。それを「組織不正はいつも正しい」と言う表題で抉り出している。
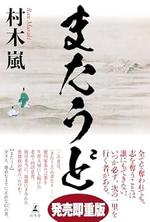 田沼意次は賄賂にまみれた悪徳政治家だったのか――その実像を第9代将軍徳川家重に見出され、第10代将軍徳川家治の信頼の下、邪念なく戦い続けた改革者として描く。意次の胸に常にあったのは、「この者は<またうど>の者なり」と家重からいただいた言葉(あの動かぬ手で懸命に書き付けてくれたもの)であった。「またうど」とは「全き人。愚直なまでに正直な信(まこと)の者」ということだ。
田沼意次は賄賂にまみれた悪徳政治家だったのか――その実像を第9代将軍徳川家重に見出され、第10代将軍徳川家治の信頼の下、邪念なく戦い続けた改革者として描く。意次の胸に常にあったのは、「この者は<またうど>の者なり」と家重からいただいた言葉(あの動かぬ手で懸命に書き付けてくれたもの)であった。「またうど」とは「全き人。愚直なまでに正直な信(まこと)の者」ということだ。
田沼意次が家治に仕え舵取りを任されたこの時代――江戸の大火、浅間山の噴火、飢饉に打ち毀し、商人の台頭と貨幣経済の黎明期。困難と激動が続いた。「意次には確信がある。五十年後か百年後か、意次のやりかけたことはいつか必ず実を結ぶ。蝦夷地の開発も印旛沼、手賀沼の干拓も、貸金会所も南鐐ニ朱銀も――。そのとき意次はこの世にはいない。だが、己のしようとしたことは間違っていない。その未来が意次にははっきりと見える。だから罵られ、禄を奪われても意次はへこたれるまい。意次はまたうどだ」・・・・・・。
身分の低い者も実力さえあれば登用し、交易に役立つ俵物を手に入れるため、蝦夷地開発に乗り出す。江戸税制の改革者として商人にも課税。新しい5匁銀を鋳造し金貨と銀貨が同じ曲尺の上にある貨幣だとする貨幣経済の道を開く。「付け届け」は多かったが、全く無頓着で開封することさえなかった。そこには"まいまいつぶろ"家重に仕え、何一つ受け取らなかった大岡忠光の姿を目のあたりにしていたからだった。
汚職政治家の汚名を着せられた田沼意次は思う。「人はなぜ身に余る位や物を望むのか。この世には御役を果たすほど愉しいことはない」と。この嘆息こそが意次の本心であったと本書は描く。懸命にただただ仕事をし、「付け届け」を放置していたのだ。これが後に仇となるなるのだが・・・・・・。
しかし突然、家治の死によって、老中を罷免され領地まで失う。家治の嫡男・家基が18歳で事故死しており、権政は一橋家の治済の子息が第11代将軍・徳川家斉となる。これに白川藩の松平定信が老中としての実権を握り、意次らの改革を何から何までひっくり返したのだ。
意次は逍遥として受け止める。「全てを奪われても、志を奪うことは誰にもできない。いつか必ず、次の一里を行くものがある」と。

