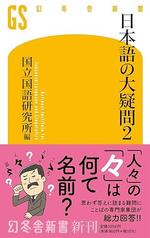 2021年に刊行された「日本語の大疑問」の続編。「ことばの正しい使い方や美しい言葉遣い」を示すものではなく、「私どもの研究は、日本語という一言語がどのような構造をもっているか、母語話者および非母語話者による日本語運用の実態はどのようなものか、日本語の多様性、歴史的変化などの問題を、客観的な手法で解明することを目指している」と言う。何気なく使っている日本語の構造を知ることができる。
2021年に刊行された「日本語の大疑問」の続編。「ことばの正しい使い方や美しい言葉遣い」を示すものではなく、「私どもの研究は、日本語という一言語がどのような構造をもっているか、母語話者および非母語話者による日本語運用の実態はどのようなものか、日本語の多様性、歴史的変化などの問題を、客観的な手法で解明することを目指している」と言う。何気なく使っている日本語の構造を知ることができる。
「若者ことば・話しことばのナゾ」――「『上から目線』の『目線』はもとは映画業界用語だった」「置いてけ堀は『置いてけ、置いてけ』と魚を返せという幽霊(?)の声からのことば」「地域によるアクセントの違い――平安時代の標準語アクセントが各地で変遷した」「東と西では人を起こす言い方でも微妙に違う(『起きたらどうだ』と『起きなあかん』)」・・・・・・。
「どうにもモヤッとすることば」――「『感謝しかありません』という表現に違和感を持つ人は少なくない。『感謝の思いしかない』とすれば違和感はなくなる」「社外の人に対し、上司を呼び捨てにするのは違和感があるという人がいる。優先順位は<上下>関係よりも<内外>関係」・・・・・・。「文字にまつわるミステリー」――「人々の『々』は何という名前? 」「平仮名は空海が作ったのではない。だいぶ後の11世紀ごろにいろは歌はできている」・・・・・・。
「そろそろ決着をつけたい日本語」――「原則として表記に『づ』『ぢ』は使わない。『稲妻』は『いなずま』と書く。『稲』と『妻』の関係がわかりにくいから。『鼻血』は『鼻から出る血』で『はなぢ』」「『ムショ』は、監獄のことを言う盗人仲間の隠語で『虫寄場』の略。『刑務所』よりも前にあった言葉」・・・・・・。
「ことばの歴史を探る」――「現代の高校生が戦国時代にタイムスリップしたら言葉は通じるか。戦国時代は『古代語』と『近代語』のはざま」。「外国人学習者がとまどう日本語」――「『ら抜き言葉』を学習者が使う危険性」「用事があります『から』『ので』の違い。『ので』の方がより丁寧な印象になる」「日本語が上手ではない留学生とコミュニケーションを取るコツ――短い文で言葉を省略しない言い方をする」・・・・・・。演説などでも短く切って話をする方がわかりやすいと実感している。
大変面白い解説が続く。

