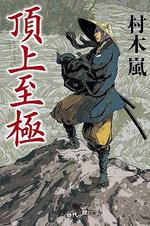 第9代将軍徳川家重の時代――。宝暦3年(1753)師走、幕府は薩摩藩に200もの支流をもつ天下の暴れ川・ 木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)の治水工事を命ずる。家老の平田靱負は総奉行として美濃に向かう。鹿児島組は、靱負と十蔵二手に分かれ、江戸組も合わせると1000人を上回る藩士が妻子と別れ、従容として美濃へ向かったのだ。
第9代将軍徳川家重の時代――。宝暦3年(1753)師走、幕府は薩摩藩に200もの支流をもつ天下の暴れ川・ 木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)の治水工事を命ずる。家老の平田靱負は総奉行として美濃に向かう。鹿児島組は、靱負と十蔵二手に分かれ、江戸組も合わせると1000人を上回る藩士が妻子と別れ、従容として美濃へ向かったのだ。
江戸開幕以来、薩摩に積もり積もった借財は既に40万両、幕府は14万両ほどというが何倍にもなることは間違いない。その工面から始まるが、美濃では想像を絶する毎年のように荒れ狂う洪水の凶暴さに直面する。輪中の人々も、それぞれの輪中の思惑もあり、繰り返される普請にも不信感が募り狡猾さを身に付けていた。さらに郡代や交代寄合との確執も露骨。「関ヶ原で負けた薩摩」と愚弄されるなかで、絶対不可能に近い難工事に挑んだのだ。あるのは、関ヶ原の島津義弘公が、家康相手に一歩も退かなかった「島津の退き口、苛烈な捨て奸戦術」以来の薩摩の誇りと意地であった。靱負らの捨て身の覚悟と本気度は、次第に人々を味方に惹きつけていき、宝暦5年(1755)春、ついに三川分流の難工事をやり遂げる。
使った金子は40万両、材木が13万本、蛇籠に編んだ竹は170万本、石は俵にすれば280万俵、土はその5倍。この1年余で藩士は33人が病に倒れ、53人が腹を切った。「あの波間に沈む石は、薩摩の米どころではない。薩摩の藩士たちの命そのものなのだ」・・・・。
「感服つかまつった。人にこれほどのことができようとは。薩摩はいかばかり精励したことであろう」「この地の百姓どもにとって、これほどの喜びはございませぬ」との声を受け、靱負は「己は頂上至極ではないか」と思う。そして薩摩に帰る前に命を断つ。「まいまいつぶろ」の村木嵐さんの2015年の作品。今、将軍家重を絡めて書いてくれたら、そして膨大な借財を抱え込んだ薩摩を描けばどうなるだろう、と思ってしまう。

