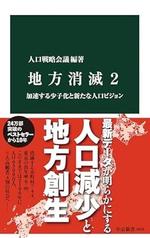 「加速する少子化と新たな人口ビジョン」が副題。2014年刊行の「地方消滅」では、896の「消滅可能性都市」リストが出され衝撃を与えた。それから10年――消滅する市町村は744となったが、東京の出生率は0.99、このままでは2100年に人口6300万人、そのうち高齢者が4割の社会になる。本書は、全国1729自治体を9つに分類。「ブラックホール型自治体」の特性なども分析し、持続可能な社会へ向かうための戦略とビジョンを打ち出す。
「加速する少子化と新たな人口ビジョン」が副題。2014年刊行の「地方消滅」では、896の「消滅可能性都市」リストが出され衝撃を与えた。それから10年――消滅する市町村は744となったが、東京の出生率は0.99、このままでは2100年に人口6300万人、そのうち高齢者が4割の社会になる。本書は、全国1729自治体を9つに分類。「ブラックホール型自治体」の特性なども分析し、持続可能な社会へ向かうための戦略とビジョンを打ち出す。
「消滅可能性都市」が減ったのは、「外国人入国者数がかなり増加したためで、危機的状況は全く改善されていない」(増田寛也)と言う。ただし、東京豊島区は消滅可能性都市と言われ、高野之夫区長を中心に区全体が一丸となって反転攻勢の戦いを始めた。私の地元でもあって、その懸命の戦いを目の当たりにした。若い女性が住み続けられるように、様々な手を打ち、待機児童ゼロを実現。「国際文化都市」をキーコンセプトにし、池袋は「文化」の街へと大変貌した。大塚、巣鴨も変わった。その熱量はすごいもので、地域の創生はやればできるのだ。
人口減少の要因は、「自然減」と「社会減」。自然減に対してはまさに異次元の少子化対策。非婚、晩婚、晩産、少産の4つの壁を打ち破ることだ。そのためには、「若い世代の給料を上げて、かつ女性の非正規労働を減らし、出産後も復帰しやすい体制を整え、安心して子どもを産み育てられるような環境を整備すること」(三村明夫)だ。「共働き共育て」社会であり、本書で言う「子どもをみんなで育てる『共同養育社会』」だ。この10年、女性のM字カーブは解消してきたが、L字カーブ問題(女性の正規雇用率が20代後半をピークに急低下する)は残っている。
社会減については、地方に仕事を作り、東京への若者の流出を食い止めようとしたが、「地方自治体は自らの住民数を増やすことに躍起になり、近隣自治体との移住者の奪い合いに終始してしまった」(増田寛也)。取り組みはバラバラで「空回り」と指摘する。政府も官も民も国民全体での対策の盛り上がりが絶対不可欠となっている。
人口戦略会議の緊急提言「人口ビジョン2100」では、「安定的で、成長力のある『8000万人国家』へ」を目指している。そして総合的、長期的な戦略として「定常化戦略(人口減少のスピードを緩和させ、最終的に人口を安定させること)と「強靭化戦略(質的に強靭化を図ることにより、多様性に富んだ成長力のある社会を構築していく)」を目指している。
大事なことは総合的に、持続的に、強力に、具体的に推進することだ。本当に待ったなしだと思う。

