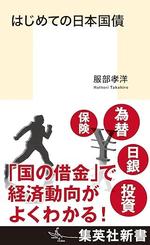 国債と言うと「1100兆円の国の借金」とか、「令和7年度歳出115兆1978億円で、国債費28兆2179億円、社会保障38兆2938億円、防衛関係費8兆6691億円、地方交付税交付金等18兆8728億円、公共事業6兆858億円・・・・・・」。一方、「令和7年度歳入は、所得税22兆6660億円、法人税19兆2450億円、消費税24兆9080億円、特例公債21兆8560億円・建設公債6兆7910億円・・・・・・」などがすぐ頭に浮かび、「長期金利が上昇している」などが話題となる。
国債と言うと「1100兆円の国の借金」とか、「令和7年度歳出115兆1978億円で、国債費28兆2179億円、社会保障38兆2938億円、防衛関係費8兆6691億円、地方交付税交付金等18兆8728億円、公共事業6兆858億円・・・・・・」。一方、「令和7年度歳入は、所得税22兆6660億円、法人税19兆2450億円、消費税24兆9080億円、特例公債21兆8560億円・建設公債6兆7910億円・・・・・・」などがすぐ頭に浮かび、「長期金利が上昇している」などが話題となる。
本書は「国債の基礎知識について包括的に解説する」としたもの。表題の通り、日本の国債の仕組み、債券や証券、日銀の市場操作などの金融政策、銀行や生命保険の運用等を通じ、日本経済の変化を理解できるようにと丁寧に解説する。
「『金利』は利子(クーポン)を意味するのではなく、債券のリターンを指す」「だから、金利が上がると債券価格が下がる」「イールドカーブ(年限と金利の関係、利回り曲線)」・・・・・・。「証券会社と国債市場の重要な関係(財務省による国債の入札、証券会社は国債の営業を担う)(国債のマーケット・メイク)」・・・・・・。「日銀の役割と公開市場操作(オペレーション)」・・・・・・。
「国債からわかる日本の金融政策史:量的・質的金融緩和から、量的縮小へ」ーー2013年4月の量的・質的金融緩和(QQE)(マネタリーベースを年間60兆〜70兆円程度増やす目標)。2016年1月のマイナス金利政策(日銀の当座預金の1部にマイナス金利を付す)。イールドカーブ・コントロール(YCC)。そして「2024年3月、YCCを撤廃するとともに、マイナス金利政策を解除、利上げ」・・・・・・。
「銀行や、生命保険会社と国債投資の関係」「日本国債はどのように発行されているか(60年償還ルールと借換債)」「デリバティブを正しく理解する(レバレッジと証拠金)(金利スワップ)」「短期金融市場と日銀の金融政策(国債購入の減額と量的引き締め:QT) (短期国債の大部分は外国人投資家が保有) (大部分の日本国債は現在国内投資家に保有されているが、2024年時点でも日銀の保有割合を除くと、外人投資家による保有割合は3割弱で増える可能性も)」・・・・・・。
複雑で、デリケートな国債の世界から経済の動向を見る。

