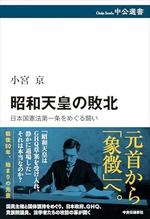 「日本国憲法第一条をめぐる闘い」が副題。大日本帝国憲法における天皇の地位は、「国ノ元首」であり、「統治権ヲ総攬」すると書かれていたが、日本国憲法では「象徴」となる。1946年2月3日の「マッカーサー三原則」の1つ、「天皇は国家の元首の地位にある」は、2月13日のGHQ憲法草案では、「symbol」となる。「昭和天皇は、幣原喜重郎首相の奏上に対し、これを承諾し、自らが統治権の総攬者を降りることを了解した」「陛下親ら『象徴でいいではないか』と仰せられた(吉田茂『回想十年 上』)」という「聖断」があったとされる。著者は「聖断は事実なのだろうか」「戦後の始まりとして信じられてきた"事実"が所詮は物語に過ぎなかったのではないか」と問いかける。憲法制定過程を徹底して調べ上げ、昭和天皇の真意を明らかにするとともに、「象徴天皇」「国民主権と国体護持」をめぐり展開される幣原喜重郎、松本烝治ら日本政府とその官僚、マッカーサー、ケーディスらGHQ、衆議院・貴族院議員、宮沢俊義、佐々木惣一、南原繁ら学者たちの激しい攻防を描いている。
「日本国憲法第一条をめぐる闘い」が副題。大日本帝国憲法における天皇の地位は、「国ノ元首」であり、「統治権ヲ総攬」すると書かれていたが、日本国憲法では「象徴」となる。1946年2月3日の「マッカーサー三原則」の1つ、「天皇は国家の元首の地位にある」は、2月13日のGHQ憲法草案では、「symbol」となる。「昭和天皇は、幣原喜重郎首相の奏上に対し、これを承諾し、自らが統治権の総攬者を降りることを了解した」「陛下親ら『象徴でいいではないか』と仰せられた(吉田茂『回想十年 上』)」という「聖断」があったとされる。著者は「聖断は事実なのだろうか」「戦後の始まりとして信じられてきた"事実"が所詮は物語に過ぎなかったのではないか」と問いかける。憲法制定過程を徹底して調べ上げ、昭和天皇の真意を明らかにするとともに、「象徴天皇」「国民主権と国体護持」をめぐり展開される幣原喜重郎、松本烝治ら日本政府とその官僚、マッカーサー、ケーディスらGHQ、衆議院・貴族院議員、宮沢俊義、佐々木惣一、南原繁ら学者たちの激しい攻防を描いている。
GHQ案に基づいて、日本側が起草した三月ニ日案――「天皇ハ日本国民至高ノ総意ニ基キ日本国ノ象徴及日本国民統合ノ標章タル地位ヲ保有ス」。そして4月17日の憲法改正草案では、「天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であつて、この地位は、日本国民の至高の総意に基く」――。そして8月24日の衆議院修正で、「天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」となる。「象徴」「元首」「君民共治」「国民主権の明示」「国体護持」等をめぐる攻防が、GHQの圧力や公職追放の危機迫るなか展開される。想像を絶する国を負う攻防が伝わってくる。
はたして天皇はどう考えていたのか――。1946年6月7日の第2回両議院有志懇談会。これは衆議院本会議上程に向けての最重要会議だ。「この回は政府の憲法草案により、国体が維持されたか否かで紛糾した」「国体変革という結論に至らない文章にせねばならないと、国体維持が最重要視されていたことがわかる」と言い、馬場恒吾(読売新聞社長)の発言に注視する。
「陛下はKing in Parliamentを希望して居られるから其処へ持って行けば良い」(参議院事務局所蔵の記録)――。「これまで昭和天皇は『第三の聖断』により、第一条の『象徴』を了解したと描かれてきた。しかしながら、馬場が伝えた『昭和天皇の希望』発言は、第一条に関して、昭和天皇が具体的な要求を行ったという驚天動地の内容に他ならない。端的に、馬場発言は聖断神話を真っ向から否定するものであり、これにより、従来の憲法史や昭和天皇像は、根本的な見直しが必要となる」と言う。「希望」があり、それも英国型の「外交使節の接受・条約締結などの外交大権を有する国王の存在を前提とし、君主主権でも国民主権でもない英国型の君民同治」の考えをしていたと言うのだ。「英国憲法では、『強いて言えば"キング・イン・パーラメント"が主権者』であり、『主権は在君か在民かなどという愚問』(猪木正道)」であり、「英国のような立憲君主国がよい」「国民主権を断言しないかたちでの元首型君主」との意向を昭和天皇は持っていたことを徹底した調査分析によって検証しているのだ。「聖断」によって「口をつぐんできた」歴史の闇を、著者は、「天皇自身の心」に迫ることによって剔抉する。凄まじい迫力ある論考に、引きつけられた。
「GHQを恐れ、天皇の宸襟を畏れ」、敗戦日本から立ち上がろうとした先達。それが日本国憲法第一条の文言の変遷に滲んでいる。昭和天皇の「敗北」でもなければ、「加工」「変節」「保身」の政治家・学者たちの「成功・失敗」でもない。この憲法制定から戦後が始まった。昭和天皇にとっても「象徴天皇」を模索する旅が始まり、その現実の行動によって権力ではない「権威」を実感させ、平成から令和の時代を迎えている。本書に出てくる一人一人の「攻防」という以上に「苦衷」に思いを馳せた。

