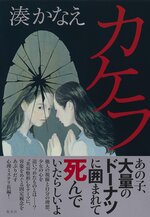 美容クリニックに勤める医師の橘久乃は、久し振りに訪ねてきた幼なじみから、故郷の同級生・横網八重子の娘・有羽が自殺したことを聞く。母の手作りのドーナツが大好きで、太っていても運動神経がよく、明るく人気者の少女が、高校2年から学校に行かなくなり、なぜ死に至ったのか。母親の八重子は小学校の頃、太っていて"横綱"と呼ばれ、今回の自殺では「娘を激太りさせた"虐待親"」など責めたてられているという。大量のドーナツに囲まれて死んだという意味はいったい何か。
美容クリニックに勤める医師の橘久乃は、久し振りに訪ねてきた幼なじみから、故郷の同級生・横網八重子の娘・有羽が自殺したことを聞く。母の手作りのドーナツが大好きで、太っていても運動神経がよく、明るく人気者の少女が、高校2年から学校に行かなくなり、なぜ死に至ったのか。母親の八重子は小学校の頃、太っていて"横綱"と呼ばれ、今回の自殺では「娘を激太りさせた"虐待親"」など責めたてられているという。大量のドーナツに囲まれて死んだという意味はいったい何か。
他人の視線と自分の理想、外見の美しさと内面の価値、長所と短所、好きなものと苦手なもの。ジグソーパズルはピースに違いがあってこそのもの。自分というカケラとカケラがはまって家族ができ、町ができる。しかし、時として自分だけがはまらず浮いてしまう。無理に押し込むと周囲のバランスを失う。「居場所」を失わないということの大切さ。「ピースがぴったりとはまる場所は必ずある」と結ぶのだから、"イヤミス"ではない。
社会は「外見」が大きな部分を占め、固定観念を形成する。しかし、一人一人が求めるのは、その奥に潜む「承認欲求」であり「自己肯定感」だ。そこに生じるズレを、「美容整形」と「誰しも喜ぶ母自作のとびきりおいしいドーナツ」で、悩みながら架橋して物語は進む。人間の本性に迫る心理ミステリー長編小説。
 1980年代まで、アジアを圧倒的な存在感でリードしてきた日本経済。「日本一極」の20世紀、アジア最初の先進国となった日本の技術や産業がアジアに伝播し、「雁行形態型発展モデル」が進行。NIEsが躍進、中国が計画経済の挫折を経て「南巡講話」等で発展への本格的スタートを切る。そして90年代後半のアジア通貨危機の苦難を越えた21世紀のアジアは大きく変貌した。日本経済の地盤沈下がいわれるなか、どう活路を見出すのか。そのためには、そのアジア経済の地殻変動をまず正確に把えることが不可欠だ。副題にある「躍進のダイナミズムと日本の活路」を示す。
1980年代まで、アジアを圧倒的な存在感でリードしてきた日本経済。「日本一極」の20世紀、アジア最初の先進国となった日本の技術や産業がアジアに伝播し、「雁行形態型発展モデル」が進行。NIEsが躍進、中国が計画経済の挫折を経て「南巡講話」等で発展への本格的スタートを切る。そして90年代後半のアジア通貨危機の苦難を越えた21世紀のアジアは大きく変貌した。日本経済の地盤沈下がいわれるなか、どう活路を見出すのか。そのためには、そのアジア経済の地殻変動をまず正確に把えることが不可欠だ。副題にある「躍進のダイナミズムと日本の活路」を示す。
アジア経済のダイナミズム。その中心軸は、国際的な生産分業体制、グローバル・バリューチェーンの展開だ。安い労働力を求めて工場を移すという時代を越えて、今やほとんどの工業製品はグローバル・バリューチェーンのなかで作られ、その展開は特にアジアで顕著となっている。競争力のカギは、他国の企業といかに効率的な生産ネットワークを築くことができるかだ。中所得国の台頭はめざましく、アジア経済の多極化が眼前にある。もう一つの軸は、「ものづくりのあり方が、これまでの日本企業が得意としてきた『擦り合わせ(インテグラル)型』から、アジアの新興企業が新たに参入しやすい『組み合わせ(モジュラー)型』へとシフトしたこと」だ。この「グローバル・バリューチェーンの時代」「モジュラー化による地殻変動」には、ICTの加速度的進展が拍車をかける。そして国境を越えての生産フローの分断・分散立地(フラグメンテーション)と工程ごとの集積(アグロメレーション)という二つの異なるダイナミズムの相互作用が進み、グローバル・バリューチェーンの展開を支える。
後藤さんは「日本の後退・没落」などと悲観するのではなく、日本をある局面では超える国・地域が出てきていること、その地殻変動を正確に把え、例えば「"選ぶ日本"から"選ばれる日本"」へ積極的に踏み込むこと、「アジアとともに未来を築こう」という。
 ウィズコロナ、ポストコロナの世界。「言葉+身体接触」で信頼の世界をつくってきた人類。それが逆襲された。人間は"人と人の間"、社会的人間であったものが、遮断される。落合さんは「しかし今は、"人と人の間"にはインターネットがある。その意味では『人間=インターネット』と言ってもいい。インターネットは人間そのものだ。人間とインターネットは、区別がつかない。つまり、人間とコンピュータの区別のつかない時代に近づきつつある。だから『デジタルネイチャー』なのだ」「システム知能のもたらす悲観的なディストピアではなく、個々人の幸福感と目的意識を親和させ、対話可能になった自然の形だ」「今までと"自然"のあり方が根本的に違う。コンピュータやインターネットなどのデジタル情報があふれ、人工物と自然物が垣根なく存在する環境が、人間にとっての『新しい自然、デジタルネイチャー』の世界だ」という。
ウィズコロナ、ポストコロナの世界。「言葉+身体接触」で信頼の世界をつくってきた人類。それが逆襲された。人間は"人と人の間"、社会的人間であったものが、遮断される。落合さんは「しかし今は、"人と人の間"にはインターネットがある。その意味では『人間=インターネット』と言ってもいい。インターネットは人間そのものだ。人間とインターネットは、区別がつかない。つまり、人間とコンピュータの区別のつかない時代に近づきつつある。だから『デジタルネイチャー』なのだ」「システム知能のもたらす悲観的なディストピアではなく、個々人の幸福感と目的意識を親和させ、対話可能になった自然の形だ」「今までと"自然"のあり方が根本的に違う。コンピュータやインターネットなどのデジタル情報があふれ、人工物と自然物が垣根なく存在する環境が、人間にとっての『新しい自然、デジタルネイチャー』の世界だ」という。
そこで「人間のやるべき仕事とは何か」――。当然、人材の価値が変化していく。これまでホワイトカラーがやってきた仕事のほとんどは、システムが代行するになる。求められるのは、機械では代替されにくく創造的な専門性を持つ知的労働者(クリエイティブ・クラス)だ。むろん「機械の下請け」のような労働も、けっして不幸ではなく、人間でなければできない、人間がやる方がいいという部分もある。しかし、「デジタルネイチャー」「AI・ロボットとともに働く働き方5.0」の時代は、「言語化する能力」「論理力」「思考体力」「世界70億人を相手にすること(ニッチで小さなビジネスモデルでも70億人を相手にするならば成立する)」「経済感覚」「世界は人間が回しているという意識」「物事を回しているキーマンの考え方や見方に影響を与える、その判断力と説得力あるロジック」「何よりも専門性」が人材の価値だ。「システムに得意なことと、人間に得意なことの違いを考えよう。システムの効率化の中に取り込まれないために持つべきなのは何か。それはモチベーションだ。システムにはこれをやりたいという動機がない。モチベーションを持ってコンピュータをツールとして使う"魔法をかける人"になれるか、"魔法をかけられる人"のままになるのか」「クリエイティブ・クラスになるためには、コンピュータの使い方に習熟することではなく、自分が何を解決するか、プラットホームの外側に出る方法を考え抜くことが大切だ。その思考体力を持つことだ。自分の問題、人生の問いについて、一点を考え抜いて深めていくことだ」と徹底して語る。
「世界に変化を生み出すような執念を持った人に共通する性質を、私は『独善的な利他性』だと思っている」「いまできる人類の最高到達点に足跡を残す」ともいう。「これからの世界をつくる仲間たちへ」が副題。
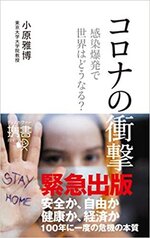 「感染爆発で世界はどうなる?」が副題。新型コロナウイルスとの闘いが世界で続いており、各国の国民意識が当然、変化している。ただでさえ、「一国主義的傾向が強まっている世界」「米中の衝突」が懸念されている時での「コロナ後の世界」はどうなるのか。外務省、上海総領事も務めた小原東大教授が、問題と課題を抽出する。中国にも詳しいだけに知見は生々しい。
「感染爆発で世界はどうなる?」が副題。新型コロナウイルスとの闘いが世界で続いており、各国の国民意識が当然、変化している。ただでさえ、「一国主義的傾向が強まっている世界」「米中の衝突」が懸念されている時での「コロナ後の世界」はどうなるのか。外務省、上海総領事も務めた小原東大教授が、問題と課題を抽出する。中国にも詳しいだけに知見は生々しい。
「健康危機から経済危機へ」「経済と感染症のジレンマ」が語られる。中国の「武漢戦疫」――。初動の遅れ、地方政府の失態と大衆の批判、李文亮医師の叫びと当局の隠蔽、政権による空前の検疫と封鎖、"中国の権威主義体制"の強みと弱み、中国が世界に展開した"支援"の狙いと成否......。そしてトランプの米国――。欧米民主主義の失態、米国の軍事力・経済力の状況、普遍的価値に基づくガバナンスが生み出す国際的正当性や公共財を提示する意志と能力などのグローバルな指導力の陰り・・・・・・。それらが米中の相互不信と非難合戦をもたらしている。「米国は、自国第一や単独行動主義ではなく、世界の価値を共有する諸国との結束、民主主義や自由資本主義の再生に努めよ」といい、「米中、そして世界にとって存在感のある日本でありたい」という。
コロナ後の世界――。中国の友人100人以上に聞くと、①生活様式の変化(オンライン化の加速や健康と衛生への認識)②価値観の変化(安全や自由といった基本的価値の大切さと再考)③世界の構図の変化(米中関係悪化による衝突への危惧)――が語られ、小原さんの友人であるだけに「日本との良好な関係」への言及がされたという。
末尾に「感染症一口メモ」「感染症の歴史小話」が簡潔に示されている。
 「心を耕す名言100」が副題。小説、随筆、詩集、映画、漫画から墓碑まで、長年拾い集めた100の名言。じつに味わい深く、面白く(目の前がパッと明るくなって新しい世界が開けるとの意)、感動の100編のエッセーが綴られる。古今東西の「名言」を集めて解説したものではない。岡崎さんが自ら読んで、接して、同苦して得た「キメの一言」「心に沁みる鮮やかな"イッポン"」が次から次へと続く。知識ではなく、知慧の「人間学」の開示だ。
「心を耕す名言100」が副題。小説、随筆、詩集、映画、漫画から墓碑まで、長年拾い集めた100の名言。じつに味わい深く、面白く(目の前がパッと明るくなって新しい世界が開けるとの意)、感動の100編のエッセーが綴られる。古今東西の「名言」を集めて解説したものではない。岡崎さんが自ら読んで、接して、同苦して得た「キメの一言」「心に沁みる鮮やかな"イッポン"」が次から次へと続く。知識ではなく、知慧の「人間学」の開示だ。
「順風が吹き凧はうまく揚がるとは限らない ――『まず小さな凧から揚げることである』(水原秋櫻子)」「谷川俊太郎が作った詩の校歌――『わたしがたねをまかなければ はなは ひらかない』」「任された仕事に関しては、すべて自分の責任――『人生ってそもそも自営業だからね』(みうらじゅん)」「『小さいことについては悩め、大きなことについては即断しろ』――内田樹・平川克美・名越康文の鼎談でニーチェの言葉らしい」「男の子から"きたない"と誹られた少女が言いかえした――『北がなければ日本は三角』(谷川雁)」「反対意見、消極意見を聞く方が公演はうまくいく――『もめるというのは大事なことなんですね』(山田洋次)」「リツイートの数も振り返らない――『"物言わぬ支持者"を俺は支持する』(つぶやきシロー)」「"禅"のサーファーとも呼ばれるジェリー・ロペスの言葉――『挑むのではない、待つのでもない。波そのものになる』」「三木卓の矜持に生きるサムライ――『他者は認めてもらう相手ではなく、納得させるものである』」・・・・・・。
「『誤解されない人間など、毒にも薬にもならない』――小林秀雄」「灘校で半世紀も国語(中勘助の「銀の匙」)を教えた橋本武――『すぐ役立つことは、すぐ役立たなくなります』」「社会は建前でできている――『私はホンネで生きている。なんて、かなり甘い台詞だよな』(詩人の田村隆一)」「勝海舟の妻――ジジババ合戦、最後の逆転(富士正晴)」「漱石の妻――『夫婦は親しきを以て原則とし、親しからざるを以て常態とす』(夏目漱石)」「今東光と川端康成――『たとえドロボウをしても手伝わねばなりません』(川端康成)」「種茂と岩本勉、そして藤浪晋太郎――『この1イニングを彼にあげてくれ』(種茂雅之)」「『正直に生きるということは、それだけでもいいものだぞ』――山本周五郎の『主計は忙しい』」「『使ってりゃ錆びねえよ』――彫刻家・船越保武」「山崎方代の歌――『今日は今日の悔を残して眠るべし 眠れば明日があり闘いがある』」「寒い日など1日ずっと庭の見える部屋で座っていた画家の熊谷守一――『"退屈"っていう気持ちがわからない』」「『ふたりでみると すべてのものは 美しくみえる』――サトウハチローの墓碑銘」・・・・・・。
たしかに、この百編百言は、また歩き始める「言葉のたいまつ」になる。

