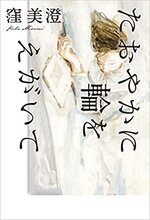 家族というもの、結婚というもの、男という生き物、そして女性の幸せ・・・・・・。静かに、優しく、心の襞、心奥の不安や嵐を濃密に描く。イプセンの「人形の家」を想起させ、現代を浮き上がらせる力作。
家族というもの、結婚というもの、男という生き物、そして女性の幸せ・・・・・・。静かに、優しく、心の襞、心奥の不安や嵐を濃密に描く。イプセンの「人形の家」を想起させ、現代を浮き上がらせる力作。
結婚して約20年、穏やかな暮らしをしていた主婦・酒井絵里子。ある日、離婚した妹の芙美子がいう。「お姉ちゃんみたいに、20何年も結婚生活が続いている人は、やっぱり結婚に向いている人なんだよ。私、結婚しているとき、ほんとうに息苦しかったよ・・・・・・あと、何十年もこんな生活が続くのかって。地獄みたいだった・・・・・・」「お姉ちゃんみたいな人にはわからないって。お父さんが浮気していたことも、お父さんとお母さんが離婚したことも、私が離婚したことも、多分、お姉ちゃんにはわからない。・・・・・・お姉ちゃんが考えているより、人間ってもっと不可解なもんなんだよ」・・・・・・。
そして清廉潔白、大好きだった父の浮気、よりによって夫が風俗に通っていたこと、一人娘の萌がいかがわしい場所で年上の男と遊んでいたという衝撃の事実に絵里子は打ちのめされる。「何も知らないで主婦として過ごす日常とは何であったのか」「家族とは何なのか、結婚とは何なのか、男という生き物っていったい何なのだろう」・・・・・・。しかし、同窓会で再会した整形し店を持って生きる詩織、いっしょに暮らす女性みなも、その友人の風俗嬢、乳癌を患った美しい老婦などと出会って新たな世界に目覚め、自己を変えていく。絵里子は「新しい自分に生まれ変わりたかった」のだ。自分の人生を生きていく。自分の人生でいつも闘っている。自分の人生を歩み出すことの嬉しさが、最後の締めの一行まで息つくことなく描かれていく。とてもいい。
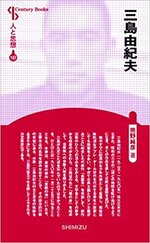 1970年11月25日――。三島由紀夫が自決して今年で50年になる。あまたある三島由紀夫論のなかでも、本書は「戦後民主主義の擬制」「天皇(制)」「日本文化の防衛」や「政治的計画」「私生活」などは除かれ、ひたすら小説等を読み解き、その生と思考の軌跡を明らかにしている。三島由紀夫として、文学者として、小説家として、作家として、芸術家として、キメ細かく書き分けている。眩いほどの"天才"が、何に憧憬し、何に渇え、何に苦悩し、何を究めようとしたかを、作品を関係者の証言も含めて時系列的に読み解いていく。「花ざかりの森」「岬にての物語」「仮面の告白」「潮騒」「金閣寺」「鏡子の家」「憂国」「午後の曳航」「春の雪」「豊饒の海」――。
1970年11月25日――。三島由紀夫が自決して今年で50年になる。あまたある三島由紀夫論のなかでも、本書は「戦後民主主義の擬制」「天皇(制)」「日本文化の防衛」や「政治的計画」「私生活」などは除かれ、ひたすら小説等を読み解き、その生と思考の軌跡を明らかにしている。三島由紀夫として、文学者として、小説家として、作家として、芸術家として、キメ細かく書き分けている。眩いほどの"天才"が、何に憧憬し、何に渇え、何に苦悩し、何を究めようとしたかを、作品を関係者の証言も含めて時系列的に読み解いていく。「花ざかりの森」「岬にての物語」「仮面の告白」「潮騒」「金閣寺」「鏡子の家」「憂国」「午後の曳航」「春の雪」「豊饒の海」――。
はじめに高橋和巳の三島論「仮面の美学――三島由紀夫」が出てくる。「清冽な処女作『花ざかりの森』」「夭折の美学」「硬質の知性」を語っている。私の大学時代、同じキャンパスにいた高橋和巳、そして三島由紀夫は、左右両翼の"教祖"にも似た存在であった。三島の自決が70年、高橋の病死が71年、翌72年は三島を守った川端康成の自殺。私の学生時代は三人の総仕上げの時だったわけだ。そして戦後の思想、論争はこの時一つの区切りとなってることを今、しみじみ思う。
三島の小説に投影される心象は、「美と死」「精神と身体」「絢爛たる才能と危険なまでの激情の純粋昇華(川端康成)」「太陽と海」「有と無」「存在と非存在」「永遠と瞬間」「認識と行動」「破壊と創造」を時を経るごとに掘り詰めている。そして三島は「表現者は死を暗示するだけではなく、じっさいに死んでみなければならない」と主張する。「金閣寺」では、世界からはじき出される「世界との隔絶」「この世への拒絶」「世界を変貌させるのは行為」、認識の境地から行動へと踏み出して世界を破壊するとともに創造し直す。瞬時の三変土田であり、「決定的なものとは時間の流れを堰き止めてなにごとか、瞬間のうちに永遠をやどし、永遠を瞬間のなかに封じ込めるなにものかとなるはずである」というのだ。「豊饒の海」の大尾に「この庭には何もない。記憶もなければ何もないところへ、自分は来てしまったと本多は思った。庭は夏の日ざかりの日を浴びてしんとしてゐる。・・・・・・」とあることを、著者は「三島由紀夫の生涯でおそらく最高の美文である。小説家は、これといって奇巧はない。しかし、このうえなく閑雅な一文を最後の作品として、文学者としての生涯を閉じることを望んだのである」と語っている。この最後の一文の境地に向けて、なるほど三島は走り続けたのだと納得する。すばらしい評伝。
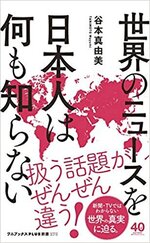 「日本のメディアが非常に閉鎖的」「そもそも日本人は海外のニュースに興味を持っていない」――。だから、世界の変化にも、日本が世界からどのように評価(酷評)されているかも、日本人は知らない。ネットではノイズが多すぎる。正しい情報、信頼性の高い情報へ能動的にアクセスすることが大切だという。「移民・難民」「格差の増大」は世界の構造を大きく変化させているが、現場の最前線の変化を紹介し、日本人のもつ"先入観"を打ち破ろうとしている。かなり現実的に、大胆に、率直に、"乱暴"ともいえるほどの表現で剔抉し語る。
「日本のメディアが非常に閉鎖的」「そもそも日本人は海外のニュースに興味を持っていない」――。だから、世界の変化にも、日本が世界からどのように評価(酷評)されているかも、日本人は知らない。ネットではノイズが多すぎる。正しい情報、信頼性の高い情報へ能動的にアクセスすることが大切だという。「移民・難民」「格差の増大」は世界の構造を大きく変化させているが、現場の最前線の変化を紹介し、日本人のもつ"先入観"を打ち破ろうとしている。かなり現実的に、大胆に、率直に、"乱暴"ともいえるほどの表現で剔抉し語る。
「日本のメディアのトップニュースに外国人は驚いている」「アフリカのメディアを買収する中国」「アメリカは映画を通してソフトパワーを駆使(ハリウッド)(韓国も)」「所得格差が激しくなる一方のアメリカ(貧困層の拡大)」「移民に対して意見が欧州で二極化(揺れるスウェーデン)(受け入れ増のカナダ)」「国連は町内会のよう。国連のお仕事は無謀国家への"ガン付け"」「EUは修羅場の町内会」「難民騒ぎで崩壊寸前! 無責任過ぎるドイツにサヨナラ」「日本は治安も格差も医療も住宅も恐ろしく恵まれている国」「国を豊かにするには『高学歴移民』」「イスラムとイギリス・欧州」「ゴーン氏の汚職事件は新興国の感覚では甘すぎる」「ビジネスでも政治でも意思決定を左右するようになった『感情の動き』(エモクラシー)」「世界の富裕層は複数の国籍を入手する」「何が人間を幸福にするか――自分の能力を最大限発揮できて、自分の行動や人生を自分で選択できること」・・・・・・。
「世界の国民性――アメリカの信仰心、アメリカでのアジア人の高収入、欧州の読み書きの劣化、日本の教育の良さ、イギリス人の借金生活、イタリア人のお風呂嫌い」・・・・・・。
信用できる情報へのアクセス、クリティカルシンキングを身につけよ、という。
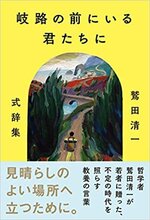 哲学者・鷲田清一さんが、大阪大学総長、京都市立芸術大学学長として、入学式・卒業式で、新しい世界に踏み出す若者へ贈った不定の時代を照らすメッセージ、式辞集。
哲学者・鷲田清一さんが、大阪大学総長、京都市立芸術大学学長として、入学式・卒業式で、新しい世界に踏み出す若者へ贈った不定の時代を照らすメッセージ、式辞集。
不定の時代――。「人生もこの社会も、すぐに答えが見つかるような問題だけから成り立っているのではない。政治の領域でも不確定な状況のなかで不確定なまま迅速で的確な判断が求められる。・・・・・・何らかの決定をしなければならない。・・・・・・大事な問題は、答えがすぐに出ないものばかり。すでにわかっていることよりも、わからないまま、見通しのきかないまま、どう的確に処するかの知恵やスキルであるということだ」・・・・・・。そこで大事なのは「教養」「価値の遠近法」だ。「教養があるというのは、ものごとの軽重をわきまえているということ。生きていくうえで①なくてはならないもの(絶対に見失ってはいけないもの)と②あってもいいけどなくてもいいもの③端的になくてもいいもの④絶対にあってはならないもの、起こってはならないこと。この4つの"価値の遠近法"をわきまえるということだ」「不確かな状況のなかで不確かなまま的確な判断と決断ができる、そのための基盤となるのが教養」「教養というのは『複眼をもつ』こと。複眼のなかでこそ、世界はある奥行きをもって浮かび上がってくる」「教養とは、一つの問題に対して必要ないくつもの思考の補助線を立てることができるということ。問題を複眼で見ること、いくつかの異なる視点から問題を照射することができるということだ」「サーヴィス会社というのは、皮肉にも、市民をどんどん受け身にしてゆく、そして市民としての責任の意識を低下させていくものである。課題の根を発見し、自ら解決する力を回復してゆかねば、脆弱なシステムとともに自身が崩れる」「梅棹忠夫さんは、いつも全体を気遣いながら、自分にできるところで責任を担う。そういう教養のあるフォロワーシップについて語っていた。『請われれば一差し舞える人物になれ』と」「自分がこれまで育んできた個性らしきものに閉じこもるな。大切なものだけれど、それは小さすぎる」「異変の徴候への鋭い感受性と、どんな状況にも手業でそれに対応できる器用さ。この二つが人がしたたかに生き延びるために不可欠。微かな異変の徴候を、人より先に感知すること、そしてそれを『掘り下げる』こと。それが芸術の仕事だ」「わからないけどこれは大事という、そんな『余白』を拡げてゆくのが芸術ではないか」・・・・・・。
大事なことが指摘され、有意義で深い。
 データの争奪戦が激しい。ヒト・モノ・カネが生み出すデータ資源が世界を激変させている。GAFAやBATが世界を席巻し、GDPのかなりの部分を食い、そしていつの間にか個人のデータが吸い上げられ、それ自体が価値となって売買される。データの世紀、データエコノミーの時代だが、当然、光と影がある。一昨年、フェイスブックから8700万人の個人データが流出し、政治にも影響を与えたのではないかといわれたり、日本でも昨年、就活サイト「リクナビ」が内定辞退率の予測という重要かつデリケートな個人データを企業に販売していた問題が発覚したり、GAFA等の規制に慎重だった米国も、規制強化に転じ始めている。本書は、同種の本のなかでも、より現場から、より現実的に、取材班がそれこそ自ら体験(「やってみた」コラム)をして現状を浮き彫りにしたなどの特徴がある。リアルに迫って緊迫感がある。
データの争奪戦が激しい。ヒト・モノ・カネが生み出すデータ資源が世界を激変させている。GAFAやBATが世界を席巻し、GDPのかなりの部分を食い、そしていつの間にか個人のデータが吸い上げられ、それ自体が価値となって売買される。データの世紀、データエコノミーの時代だが、当然、光と影がある。一昨年、フェイスブックから8700万人の個人データが流出し、政治にも影響を与えたのではないかといわれたり、日本でも昨年、就活サイト「リクナビ」が内定辞退率の予測という重要かつデリケートな個人データを企業に販売していた問題が発覚したり、GAFA等の規制に慎重だった米国も、規制強化に転じ始めている。本書は、同種の本のなかでも、より現場から、より現実的に、取材班がそれこそ自ら体験(「やってみた」コラム)をして現状を浮き彫りにしたなどの特徴がある。リアルに迫って緊迫感がある。
「リクナビ問題」の衝撃――自分の内定辞退率が算出されて販売されている。違法であり、プラットフォーマー規制にも一石が投じられた。「世界が実験室」となり、新たなイノベーションがデータ資源の使い道や価値を問い直す。「エコーチェンバー(共鳴室)現象」――SNSで自分と似た意見を持つ人につながると次々に同じ意見が跳ね返って偏見を増幅していく。政治観を変えられてしまうし、「いいね!」の世論操作がされていく。「GAFA規制」――①プライバシーを守る個人情報保護②健全な競争環境を保つ為の独禁法③適切に課税するための法人税、のあり方の3分野だ。データ資源が爆発的に増え"私"が奪われる――利便を取るか"私"を守るかだが、「ターゲティング広告」は凄まじい。またAIが人を格付けするスコアリング技術が急速に発展している。偽動画のディープフェイク、AIによる美人認定ソフト。一方で、スコアに一喜一憂するウーバー運転手。不正出品に対する審査の甘さがアマゾンの足をすくう。
「AIの56%がデータ不足で苦悩」、しかも保存形態がバラバラで、企業が苦しんでいるという現実も明らかにされる。使えるAIへ、学ばせ方の模索だ。また、データと利益が一握りのIT巨人に集中する「新たな独占」が出現したが、放置すれば市場がゆがみ、過剰な規制は成長を阻むというジレンマに世界は悩む。またIT巨人に対して、企業が悪質な情報漏洩を起こせば賠償請求できるという消費者プライバシー法がカリフォルニア州で今年施行されるなど、個人が立ち上がる動きが始まった。データ版TPPなどデータ経済圏の動きもある。
「テクノロジーを鍛え、正しく進歩させる」――新ルールも混沌とするなか、とてつもない課題に直面している。

