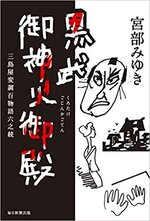 巧妙というか、絶妙というか、スルスルと宮部みゆきの世界に引き込まれていく。「三島屋変調百物語の六之続」だ。今度は、第一話から聞き手を務めてきた「おちか」が嫁に行ったので、三島屋の主人・伊兵衛の次男・富次郎が聞き手となる。百物語の守り役・お勝と古参の女中・おしまの3人で語り手を迎えることになる。4話ある。
巧妙というか、絶妙というか、スルスルと宮部みゆきの世界に引き込まれていく。「三島屋変調百物語の六之続」だ。今度は、第一話から聞き手を務めてきた「おちか」が嫁に行ったので、三島屋の主人・伊兵衛の次男・富次郎が聞き手となる。百物語の守り役・お勝と古参の女中・おしまの3人で語り手を迎えることになる。4話ある。
「黒武御神火御殿」――。小伝馬町の質屋、二葉屋の女中・お秋の印半天を三島屋は手に入れるが、そこには何かまじないのような言葉が書いてあった。語り手の梅屋甚三郎とお秋と亥之助爺さんの3人は、だだっ広い屋敷に迷い込んでしまう。そこにあと2人、そして更に武士が1人加わり、翼のある化け物に襲われたりする。化け物の潜む森に囲まれ、広さも造りも判然としない屋敷。手掛かりとして残るのは「黒武」の名の入った印半天のみ。6人の囚われ人に6枚だけある印半天。さらに屋敷を進むと広間には赤黒色の火山が襖絵から溶岩を転げ出している。なぜに屋敷に閉じ込められたのか。どうすれば解き放たれるのか。「悔い改めよ、罪ある者よ」との野太い声。神が宿る大島三原山の御神火だ。屋敷に囚われた6人のそれぞれの罪とは何なのか。そしてこの屋敷の謎とは、そして"ひらがな文字"の謎とは・・・・・・。バテレン追放、大島への流罪、そのなかでの噴火・御神火と領主の憤怒という真相に突き当たる。
「泣きぼくろ」――語り手として来たのは、幼なじみの豆腐屋「豆源」の八太郎だった。家族の女性に突然"泣きぼくろ"が付いて「てろり~ん」不貞を犯してしまう。それが続いて一家はバラバラの離散、店もなくなってしまったという。「姑の墓」――恨みをもった姑が「絶景の丘」に葬られ、嫁が来ると突き落とす。登ってはならないという丘。「同行二人」――妻子を失い走っていれば忘れることができると飛脚をする。道中いろいろな怪異に巡り合うが・・・・・・。
人間の欲望と苦悶と失意、憤怒と怨念の世界が実に巧妙に描かれる。火山はその業火だ。変わり百物語――人は「打ち明けて、これが本当にあったことだと、自分たちの身の上に襲いかかったことだと、すっかり吐き出して楽になりたい。慰めてほしい。共に恐れてほしい」と思うものだ。せめて一人だけでも。
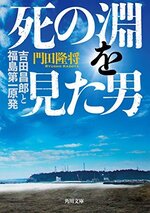 3.11東日本大震災から9年。新型コロナ感染症との戦いで、「追悼の式典」も中止された。しかし、本書原作の映画「Fukushima50(フクシマフィフティ)」がこの3月6日に公開され、書店には本書が店頭に並んでいる。「吉田昌郎と福島第一原発」「現場に残った勇気ある50人を世界はこう呼んだ」とあるが、本書を読み、「東日本大震災」「原発」に対して、多くの被災された方々、これに戦いを挑んだ方々に思いを致し、人間の「慢心」を戒め、復興に努めることが大事だと思う。
3.11東日本大震災から9年。新型コロナ感染症との戦いで、「追悼の式典」も中止された。しかし、本書原作の映画「Fukushima50(フクシマフィフティ)」がこの3月6日に公開され、書店には本書が店頭に並んでいる。「吉田昌郎と福島第一原発」「現場に残った勇気ある50人を世界はこう呼んだ」とあるが、本書を読み、「東日本大震災」「原発」に対して、多くの被災された方々、これに戦いを挑んだ方々に思いを致し、人間の「慢心」を戒め、復興に努めることが大事だと思う。
迫真のギリギリの局面が次々と甦る。大地震、大津波の襲来、そして全電源喪失。「人命と原子炉を守る」――吉田昌郎所長、伊沢郁夫中央制御室当直長(1号機、2号機)らの死に物狂いの戦い。原子炉へ水のラインを開けるべく突入。格納容器の圧力の異常上昇とベント。「俺が行く」――誰が原子炉建屋に突入するか。「われを忘れた官邸」と菅首相の乱入、「なんでベントをやらないんだ!」。自衛隊の消防車への"出動要請"。原子炉建屋への突入、ベント操作。ベントへの再チャレンジ。1号機で水素爆発、建屋の5階が吹き飛ぶ。海水注入。海水注入中止の命令(官邸の介入と混乱)。3号機の原子炉建屋で水素爆発。水が入っていかず最大の危機を迎えていた2号機。「全員撤退」問題と菅首相の東電での発言。2Fへの退避と残った69人(フクシマフィフティ)。協力企業のなかにも現場に戻る必死の男、決死の自衛隊。凄まじい執念の注水作業で暴走するプラントも冷却へ。「家族」「七千羽の折鶴」「運命を背負った男・吉田昌郎と地涌菩薩。チェルノブイリ事故×10」・・・・・・。
「決死の仲間」「人間の"慢心"と"侮り"」「現場のわからない中央のリーダー」「人間には命を賭けなければならない時がある。その命を賭けて毅然と物事に対処していく人がいる」・・・・・・。土壇場における「現場の底力と信念」が日本の本当の力である。そして日本を救った。感謝。
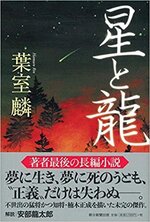 葉室麟の最後の長編で、未完のもの。楠木正成を描く。後醍醐天皇の建武の新政までは描いたが、足利尊氏らの九州への駆逐、反撃に転じた足利軍と楠木・新田義貞連合軍との湊川の戦い、正成の最後は書かれていない。本当に残念だ。
葉室麟の最後の長編で、未完のもの。楠木正成を描く。後醍醐天皇の建武の新政までは描いたが、足利尊氏らの九州への駆逐、反撃に転じた足利軍と楠木・新田義貞連合軍との湊川の戦い、正成の最後は書かれていない。本当に残念だ。
北条得宗家の命を受け、同じ悪党を討伐することで正成は名を上げる。築城・籠城・情報戦・電撃戦と縦横無尽の軍才をもった正成だが、その精神の骨格を成したものが、夢窓疎石の弟子・無風から受けた朱子学であった。中国・南宋の「夷敵を撃つ精神」「帝によってこの世を作り替える」「天子は徳によって世を治めてこそ天子なのだ」「悪党であるがゆえに正しきことをなそうと若きころ心に思い定めた」「正成の生き方は生涯で正しきことをなしたいということであった」――。
安部龍太郎が、末尾に「夢と希望と作家の祈りと」との心に浸み入る解説を載せ、「複雑怪奇な南北朝時代・・・・・・。そのシンボルとして葉室さんが選んだのが、理想の象徴としての星である後醍醐天皇と、天に駆け昇ろうとする龍に見立てた楠木正成だった」と言っている。正成は後醍醐天皇を隠岐島から脱出させ、反幕勢力の布陣を整え、自ら千早城に幕府の大軍を引きつけ、ついに倒幕を成し遂げる。しかし、理想と現実は当然異なる。足利によって護良親王は殺害され、その背後には帝自身がいる。足利尊氏の台頭、新田義貞の巻き返しがある。「楠木ならばいずれ足利を退治いたすこともできよう。朕をしのごうとするものは護良であれ、尊氏であれ、天罰を被るのじゃ。後醍醐天皇は満足げに嘯いた」と描いている。正成と志を共にした鬼灯には「どのような敵にも打ち勝つ、魔神のごとき戦上手の楠木様の一番の弱みは正しき道を求めるところでございますな」と語らせている。「天と天皇」「朝廷と武士」「南宋における朱子学と貿易」「日宋、日元貿易と宋銭」など、根源的問題が自然のうちに剔り出されている。
 「SNSが変えた1400年の宗教観」が副題。「日本人はイスラム教を危険だ、怖いと思っているが違う。イスラム教は平和な宗教なのだ」ということが通説となっている。しかし現実には、ヨーロッパなどで性犯罪や暴力、価値観の違いに由来する問題が多発している。「なぜ」との問いも「平和の宗教」という通説がその思考を遮断している。飯山さんは「2000年以降、ジハード主義が世界中で急速に拡大した背景にあるのはイスラム2.0であると考えている」「2000年初頭からIT、SNS、動画サイトが登場。一部の宗教エリートのものだった『コーラン』『ハディーズ』の知識が、容易に直接触れられるようになり、ここ10年ほどのイスラム教徒たちの行動を大きく変えた」「イスラム2.0時代は、一般信徒が徐々に啓示に忠実な『真に正しい』信仰に覚醒し、原理主義化していく時代。多くのイスラム教徒が近代的価値観に違和感を持ち、異議を唱え、よりイスラム的な価値の実現を求める時代だ」という。
「SNSが変えた1400年の宗教観」が副題。「日本人はイスラム教を危険だ、怖いと思っているが違う。イスラム教は平和な宗教なのだ」ということが通説となっている。しかし現実には、ヨーロッパなどで性犯罪や暴力、価値観の違いに由来する問題が多発している。「なぜ」との問いも「平和の宗教」という通説がその思考を遮断している。飯山さんは「2000年以降、ジハード主義が世界中で急速に拡大した背景にあるのはイスラム2.0であると考えている」「2000年初頭からIT、SNS、動画サイトが登場。一部の宗教エリートのものだった『コーラン』『ハディーズ』の知識が、容易に直接触れられるようになり、ここ10年ほどのイスラム教徒たちの行動を大きく変えた」「イスラム2.0時代は、一般信徒が徐々に啓示に忠実な『真に正しい』信仰に覚醒し、原理主義化していく時代。多くのイスラム教徒が近代的価値観に違和感を持ち、異議を唱え、よりイスラム的な価値の実現を求める時代だ」という。
そして、「ヨーロッパのイスラム化とリベラル・ジハード(移民人口が急増、定住すれども同化せず、ポピュリズム政党は極右?、教育現場でも激しい対立)」「インドネシアにみるイスラム教への『覚醒』(世俗法よりもイスラム法、州知事が冒瀆罪で実刑判決、宗教マイノリティへの寛容度低下)」「イスラム・ポピュリズム(ジョコウィ大統領の選挙戦略、反LGBTが活発化、男と女と夫婦)」「イスラム教の『宗教改革』(エジプトの状況、コプト教徒への迫害と融和策、女性と子供)」など、ヨーロッパ、インドネシア、エジプト等の問題の複雑さ、困難さが述べられる。
最終章「イスラム教徒と共生するために」で、対立・衝突を避けて「どうにか共生を成立させること」「多様性社会への粘り強い知的営為」の努力を求めている。
 児童精神科医として精神科病院や医療少年院に勤務していた宮口さん。「ここに丸いケーキがあります。3人で食べるとしたらどうやって切りますか? 皆が平等に」と紙に丸い円を描いて提示すると、凶悪犯罪に手を染めていた少年たちはそれができないのに驚愕する。「計算ができず、漢字も読めない」「計画が立てられない、見通しがもてない」「反省といわれてもそもそも反省ができず、葛藤すらもてない」のだ。認知力が弱く、反省以前の子どもが沢山いるという現実を直視しないといけないと、宮口さんは行動する。
児童精神科医として精神科病院や医療少年院に勤務していた宮口さん。「ここに丸いケーキがあります。3人で食べるとしたらどうやって切りますか? 皆が平等に」と紙に丸い円を描いて提示すると、凶悪犯罪に手を染めていた少年たちはそれができないのに驚愕する。「計算ができず、漢字も読めない」「計画が立てられない、見通しがもてない」「反省といわれてもそもそも反省ができず、葛藤すらもてない」のだ。認知力が弱く、反省以前の子どもが沢山いるという現実を直視しないといけないと、宮口さんは行動する。
非行少年に共通する特徴5点セット+1――。「認知機能の弱さ」「感情統制の弱さ」「融通の利かなさ」「不適切な自己評価」「対人スキルの乏しさ」、そして「身体的不器用さ」。「見る力」「聞く力」「想像する力」が弱い。自己肯定感が低く、怒りをため込む。対人スキルが弱く、嫌なことも断れず、イジメに遭っても他者に助けを求めることができない。身体的不器用で力加減がわからず物をよく壊す。社会に出ても、仕事ができず、人間関係もうまくいかない。「知的障害はIQが70未満」だが、IQ70~84の「境界知能」の子どもたちは、およそ14%ほどいて、知的障害者と同じくしんどさを感じていて、支援を必要としている。困っている人たちだ。保護者などにも気づかれないまま、イジメに遭い、中学に入った頃から全くついていけなくなり、大きなストレスをかかえる。非行に走って加害者になり、警察に逮捕され、少年鑑別所に回され、初めて「障害があった」と気づかれる。軽度知能障害や境界知能の人には支援が必要だが、気づかれないゆえに非行、犯罪まで行く。
認知行動療法に基づいたソーシャルスキルトレーニングがあるが、それは認知機能に大きな問題がないことが前提となり、考え方を変えるトレーニングだ。しかし、聞く力、言語を理解する力、見る力、想像する力などの認知機能に問題がある人には身につかない。矯正教育や学校教育の現場では対象者の能力が考慮されていない。
「ではどうすれば? 1日5分で日本を変える」「学習の土台にある認知機能をターゲットにせよ」――。ワーキングメモリを含む認知機能向上への支援として有効な「コグトレ(認知機能強化トレーニング)」が紹介される。

