 凄い、けれん味がなく真っすぐ、ぶっ飛ぶ、破天荒な喜怒哀楽、エネルギッシュで面白い。島田雅彦の自伝的青春私小説。「埴谷さんは暗黙裡に自らの異端性を弟子が受け継ぐよう促した、と君は受け止めた。彼は戦後派のみならず文学一般に受け継がれてきた価値観を守れとはいわなかった。文学なんか解体しても一向に構わないから、果敢に新しい心の露呈に対面せよと迫ったのである。つまり、伝統を保守する正統なんか目指さず異端のままでいよ、と」「君は滴り落ちる汗を拭いながら、遠くに見える遺影(中上健次)に向かって、『路地の荒くれ男たちの短命にして波瀾万丈の物語をなぞらず、自己申告ではない、正真正銘の文豪になる手もあったじゃないですか』と虚しく呼びかけた」「島田を守れ。オレが死んだら、誰もあいつを守ってやれない――。君はその時初めて、弟分に惜しみなく注がれた中上の慈しみを痛感した」「君が出会ったのは全て偉大な異端者たちばかりだ。君は幸か不幸かその系譜に連なるよう仕向けられた。君は疲れを知らずにナンパにかまける体力はあったが、まだ偉大な先輩たちの屈折や情熱、思想を表面的にしか理解できないバカだった・・・・・・」「すでに時効を迎えた若かった頃の愚行、恥辱、過去の数々を文書化しておくことにした。それにうってつけの形式は私小説をおいてほかない。正直者がバカを見るこの国で本当のことをいえば、異端扱いされるだろうが、それを恐れる者は小説家とはいえない」・・・・・・。
凄い、けれん味がなく真っすぐ、ぶっ飛ぶ、破天荒な喜怒哀楽、エネルギッシュで面白い。島田雅彦の自伝的青春私小説。「埴谷さんは暗黙裡に自らの異端性を弟子が受け継ぐよう促した、と君は受け止めた。彼は戦後派のみならず文学一般に受け継がれてきた価値観を守れとはいわなかった。文学なんか解体しても一向に構わないから、果敢に新しい心の露呈に対面せよと迫ったのである。つまり、伝統を保守する正統なんか目指さず異端のままでいよ、と」「君は滴り落ちる汗を拭いながら、遠くに見える遺影(中上健次)に向かって、『路地の荒くれ男たちの短命にして波瀾万丈の物語をなぞらず、自己申告ではない、正真正銘の文豪になる手もあったじゃないですか』と虚しく呼びかけた」「島田を守れ。オレが死んだら、誰もあいつを守ってやれない――。君はその時初めて、弟分に惜しみなく注がれた中上の慈しみを痛感した」「君が出会ったのは全て偉大な異端者たちばかりだ。君は幸か不幸かその系譜に連なるよう仕向けられた。君は疲れを知らずにナンパにかまける体力はあったが、まだ偉大な先輩たちの屈折や情熱、思想を表面的にしか理解できないバカだった・・・・・・」「すでに時効を迎えた若かった頃の愚行、恥辱、過去の数々を文書化しておくことにした。それにうってつけの形式は私小説をおいてほかない。正直者がバカを見るこの国で本当のことをいえば、異端扱いされるだろうが、それを恐れる者は小説家とはいえない」・・・・・・。
少年時代、高校時代、大学時代、そしてその後の煩悶や葛藤、文士・思想家との格闘の遍歴。戦争を経て戦後を背景にして躍り出た世代、次に団塊の世代、そして島田雅彦氏らの世代の感性は当然異なる。しかし在前する世界を突破し、脱出しようとする力は世代を超え魅力的だ。"異端"と称される天才たちの生命力・エネルギーに心持良さを感ずる。それはかなり本質的なものだ。
 「DNA全解析とクリスパーの衝撃」が副題。ゲノムとは「DNAに記された全遺伝情報」を意味し、遺伝子はその重要な一部を成す。今、DTCと呼ばれる一般消費者向け遺伝子検査(DNA検査)が急速に普及しているというが、それは、「がん等をどう発見し、どう治療するか」「自分とは一体何なのか(ルーツ探し)(自分の外見や才能、性質や病気)」などに多くのユーザーが惹き付けられているからだ。そして、遺伝子操作の基礎研究や技術基盤はかなり確立され、実社会に応用されるのを待つばかりとなっている。ゲノム編集「クリスパー」と呼ばれる超先端バイオ技術だ。遺伝子検査サービスDTC、がんゲノム医療、知らぬ間に食卓に上るゲノム編集食品、生殖医療、刑事事件の科学捜査、生態系を改変する遺伝子ドライブ・・・・・・。各分野にゲノム編集技術が浸透しているが、光もあれば影もある。その実態と課題を解説する。
「DNA全解析とクリスパーの衝撃」が副題。ゲノムとは「DNAに記された全遺伝情報」を意味し、遺伝子はその重要な一部を成す。今、DTCと呼ばれる一般消費者向け遺伝子検査(DNA検査)が急速に普及しているというが、それは、「がん等をどう発見し、どう治療するか」「自分とは一体何なのか(ルーツ探し)(自分の外見や才能、性質や病気)」などに多くのユーザーが惹き付けられているからだ。そして、遺伝子操作の基礎研究や技術基盤はかなり確立され、実社会に応用されるのを待つばかりとなっている。ゲノム編集「クリスパー」と呼ばれる超先端バイオ技術だ。遺伝子検査サービスDTC、がんゲノム医療、知らぬ間に食卓に上るゲノム編集食品、生殖医療、刑事事件の科学捜査、生態系を改変する遺伝子ドライブ・・・・・・。各分野にゲノム編集技術が浸透しているが、光もあれば影もある。その実態と課題を解説する。
とくに医療と農業、生態系との関連だ。1970年代に始まった「遺伝子組み替え」の時代と違っているのは、特定の遺伝子を狙って操作できるクリスパーの時代となっていることだ。奇跡の世界に突入するとともに、根本的な懸念が出されるのはそのためだ。また米国、欧州、日本、中国などの対処方針の違いが浮き彫りにされる。「ゲノムから私たちの何が分かるのか?――遺伝子検査ビジネスの現状と課題」「ゲノム編集とは何か?――生物の遺伝情報を自在に書き換える技術の登場」「見えないゲノム編集食品」「科学捜査と遺伝子ドライブ、そして不老長寿――ゲノム技術は私たちの社会と生態系をどう変えるか」の各章がある。
ゲノム革命がひたひたと浸透している。進行途上であるだけに課題は重い。
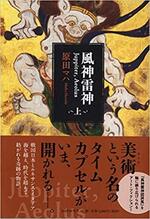
 16世紀末、九州のキリシタン大名の名代としてローマに派遣され、ローマ教皇に謁見した少年たち、いわゆる天正遣欧使節団。イエズス会の巡察師、アレッサンドロ・ヴァリニャーノに導かれ、はるばる海を渡った4人のキリシタンの少年たち。伊東マンショ、千々石ミゲル、中浦ジュリマン、そして原マルティノの他にもう一人、俵屋宗達がいたというアート・フィクション。スケール、テンポ、冒険心、ダイナミック。抜群に面白い。
16世紀末、九州のキリシタン大名の名代としてローマに派遣され、ローマ教皇に謁見した少年たち、いわゆる天正遣欧使節団。イエズス会の巡察師、アレッサンドロ・ヴァリニャーノに導かれ、はるばる海を渡った4人のキリシタンの少年たち。伊東マンショ、千々石ミゲル、中浦ジュリマン、そして原マルティノの他にもう一人、俵屋宗達がいたというアート・フィクション。スケール、テンポ、冒険心、ダイナミック。抜群に面白い。
「風神雷神図屏風」で名高い琳派の祖・俵屋宗達は卓越した技術と新しい視野をもち独特の様式を確立したが、いまだ生没年すら確定せず、謎多き存在だ。それが、狩野永徳とともに宗達が仕上げた「洛中洛外図屏風」を、キリシタンの王たる教皇に届けるためにローマに行ってこい、そしてローマの"洛中洛外図"を描いて見せてくれ――これが織田信長の直々の命であった。天正十年の本能寺の変の直前だ。宗達たちはついにローマにたどり着く。そこで、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロの絵画に驚愕、衝撃を受け感動し涙する。バロックの巨匠となる少年・カラヴァッジョとも出会う。出会いの奇跡、東と西、芸術家たちの魂が時空を超えて邂逅する。「風神と雷神」「アイオロスとエピテル」の異形のダイナミックさが物語となって躍動する。
 これぞSF小説。しかもAI・IoT・ロボットの急進展を目のあたりにすると、描かれた世界が現実となるのも時間短縮されるかも知れない。それは楽しい豊かな社会とは異なるものではないか。世界の未来と秘密に迫るコンピュータ・サイエンス専攻のテッド・チャンの17年ぶりの刊行となる最新作品集。SF界のヒューゴー賞受賞作など9篇が収録されている。
これぞSF小説。しかもAI・IoT・ロボットの急進展を目のあたりにすると、描かれた世界が現実となるのも時間短縮されるかも知れない。それは楽しい豊かな社会とは異なるものではないか。世界の未来と秘密に迫るコンピュータ・サイエンス専攻のテッド・チャンの17年ぶりの刊行となる最新作品集。SF界のヒューゴー賞受賞作など9篇が収録されている。
「商人と錬金術師の門」――。タイムトラベル、しかも現代科学と矛盾しないで、「千夜一夜物語」風に話が展開する。くぐると20年前と20年後に移動できる門がある。「過去と未来は変えられるのか」と「過去や未来は変えられなくても不幸ではない。知ることの意義とは何か」は永遠のテーマだ。その人生の根源的課題に、緻密に温かく迫る。「予期される未来」は予言機の普及と自由意志の問題が語られる。
「息吹」――。毎日、空気が空になった肺を、吸気口にセットしていっぱいになった肺と取り替えるという今の人間とは異なる世界が登場する。そのなかで、脳と意識と生命の源としての空気(アルゴン)の存在や不死を探究していく。「わたしがこうして存在するのは宇宙のゆるやかな息吹から生まれた」「存在するという奇跡についてじっくり考え、自分にそれができることを喜びたまえ」・・・・・・。「オムファロス」も"若い地球"創造説、成長輪を持たない木々、縫い目のない頭蓋骨などと、現代物理学、考古学等による世界の探究を大胆に問題提起する。
「ソフトウェア・オブジェクトのライフサイクル」――。動物園の飼育係をしていた女性が、ディジエントと呼ばれる人工生物の子育てをし、教育し成長させていく。そのなかで生まれる飼い主との感情移入、絆。さらにはディジエントの虐待、性的関係、社会との関係等々が広範に描かれる。「デイシー式全自動ナニー」や「偽りのない事実、偽りのない気持ち」でも機械による子育てや父娘の葛藤、言葉と文字と気持ちの本質的問題等が描かれる。
人類の未来は、科学の急進展のなかで、とてつもない課題を突き付けられる。
 「牢人医師はなぜ謀反人となったか」が副題だが、通常の「本能寺の変」をめぐる小説タッチのものではない。日本中世史を専門とする関学教授のものだけに、きわめて実証的に織田政権の実態等から光秀の実像に迫る。新鮮な感がする。
「牢人医師はなぜ謀反人となったか」が副題だが、通常の「本能寺の変」をめぐる小説タッチのものではない。日本中世史を専門とする関学教授のものだけに、きわめて実証的に織田政権の実態等から光秀の実像に迫る。新鮮な感がする。
生まれに二説ある。1528年と1516年、ここでは1528年をとる。天正10年(1582年)の本能寺の変の後に没するから数え55才となる。「光秀は土岐一家の人物で牢人だった」「越前の長崎称念寺の門前で明智十兵衛尉という牢人として10年暮らしていた」「足利義昭の足軽衆となる」「元亀元年(1570年)、信長の越前朝倉攻め、窮地の信長の反転攻勢のなか宇佐山城主となる」「延暦寺焼き討ちの功績で滋賀郡全体が与えられる」「義昭・信長連合軍で目立ち坂本城を築城する」「天正元年(1573年)、義昭と信長が離間し、信長方につく」「天正元年、朝倉義景敗北、浅井長政自刃・滅亡。光秀は激務の日々、京都代官を兼任する」「天正3年、武田を破る長篠の合戦後、信長の推挙で惟任日向守になる。丹波攻めを命じられるが、難しく挫折」・・・・・・。
興味深いのは「天正2年末以降、信長は道路を拡張する大土木工事を敢行し大規模な動員をした。それによって信長軍の圧倒的機動力が確保され(皮肉にも本能寺の変でも山崎の戦いでも)荘園領主の縄張り意識をも形骸化させた」「光秀の家格は土岐家の当主ではなく、土岐氏の庶家であった。身分の問題は彼の行動を規定した」「信長は道路をつくり、兵粮を把握する枡の規格統一など斬新な戦略を貫いた」「光秀は随一ともいえるスピードで伸し上がったが、織田家中からの風当たりが強かった。もめた場合に信長にとりなしてくれた信長側室の御妻木殿(光秀の妹)が天正9年8月に死亡したのが痛かった」「信長は部将たちに激務を強いる一方、一族を優遇する人材配置を積極的に進めた。側室となっていた妹を亡くした光秀は、信長から一族に準ずる扱いも期待できなくなっていた(不満と不安)」「急激に膨張した織田分国を統治しきれる人材を賄いきれていない、織田政権の官僚制度の整備が追いつかなかった。光秀もつらい出陣、家康の饗応など多忙を極めた。信長への過酷な労働奉仕のスパイラルが生じていた」等々・・・・・・。「道路整備」「側室の妹・御妻木殿の死」など、きわめて面白い。

