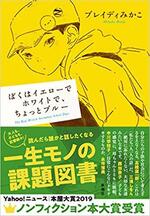 「ブレグジットがどうとか、EUがどうとかいう、大きく華々しいニュースの見出しの遥か下のほうで、一つ、また一つと子どもたちの小さな写真の数は増え続けている」――。人種差別や貧富の差が広がるイギリスの元"底辺"中学校に通う息子の「毎日が事件の連続」の日常。その葛藤と成長の姿を、ブレイディみかこさんが息子の考え、親の考えを交えて率直に綴る。激しく、ユーモアをもって繊細に、痛快に、赤裸々に描く。
「ブレグジットがどうとか、EUがどうとかいう、大きく華々しいニュースの見出しの遥か下のほうで、一つ、また一つと子どもたちの小さな写真の数は増え続けている」――。人種差別や貧富の差が広がるイギリスの元"底辺"中学校に通う息子の「毎日が事件の連続」の日常。その葛藤と成長の姿を、ブレイディみかこさんが息子の考え、親の考えを交えて率直に綴る。激しく、ユーモアをもって繊細に、痛快に、赤裸々に描く。
ロンドンの南にあるブライトン、そこの公立中学に通う息子さん。貧しい白人の子どもが多く、移民が多いこともあって人種差別はかなりデリケートで大きな問題。学力的には底辺校であったが、音楽や演劇、スポーツ競技などにも積極的で学力も向上してきた。イギリスの最前線を生々しく伝えてくれて、刺激的で面白い。LGBTQも、かなり改善、深化している。「多様性はややこしい。衝突が絶えないし、ない方が楽だ」というが、日本とは及びもつかない多様性の現実があり、その格闘の日常が描かれる。「楽ばっかりしてると、無知になる」という。2010年から保守党の行った緊縮財政がいかに貧しさと分断を加速させているか、昨今のEU離脱をめぐる紛糾が庶民生活の現場にどう投影されているか。「ポリティカル・コレクトネス」「エンパシーとシンパシー」など、イギリス社会は日常の隣接の所で思慮されていることを感ずる。
それにしてもブレイディみかこさんの知性ある"肝っ玉母ちゃん"と、エンパシーとは「自分で誰かの靴を履いてみること」と即答する息子さんの聡明さが快い。
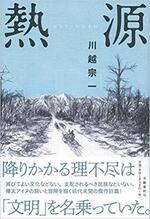 舞台はサハリン島、樺太。時代は明治初期から1945年8月、昭和の戦争。もとは無主の島であったサハリン島。やがて帝政ロシアと日本が共同で領有。その後、ロシアの単独領有となり、日露戦争で島の真ん中、北緯50度以南が日本へ割譲されていた。ロシアと日本のあわいで揺らぎ続けた島に、樺太アイヌ等の先住民がいた。
舞台はサハリン島、樺太。時代は明治初期から1945年8月、昭和の戦争。もとは無主の島であったサハリン島。やがて帝政ロシアと日本が共同で領有。その後、ロシアの単独領有となり、日露戦争で島の真ん中、北緯50度以南が日本へ割譲されていた。ロシアと日本のあわいで揺らぎ続けた島に、樺太アイヌ等の先住民がいた。
樺太出身のアイヌ、幼少時に北海道に移住していたヤヨマネクフ(山辺安之助)、同じ年のシシラトカ(花守信吉)、幼なじみの千徳太郎治・・・・・・。ロシア皇帝暗殺を謀った罪でサハリンに流刑されていたポーランド・リトアニアのブロニスワフ・ピウスツキは、テロ組織の残党でサハリンに住む民族学者レフ・シュテンベルグやロシアのアイヌ民族調査のため北海道を訪れるヴァツワフ・コヴァルスキらと交わり、アイヌの民族調査の道に入る。そしてブロニスワフは、アイヌの女性と結婚をする。
大激動する世界、国内の動乱。挟撃されるポーランド、日露戦争、文明の猛威のなか、凍てつく島で異民族が交差する。その国難のなかで生きる熱を与えたものは何か。文明が進歩の名の下に弱小民族を押し潰す。民族の幸せとは何か。弱肉強食のなかで国家は、なかでも人間は何をもって生きるのか。アイヌ民族を中心にしながら文明の理不尽、国家主義になだれる人間の愚かさを剔り出しつつ、人間の生存と生活の根源的な問いを発する。
私も関わった今年4月に本格オープンする「民族共生の象徴空間」――。白老町のアイヌ民族博物館には、ブロニスワフ・ピウスツキの銅像がある。本書には、二葉亭四迷、アイヌ語研究の金田一京助、南極探検隊の白瀬矗らとの交わりも描かれる。生きる「熱源」「誇り」が"受動の力"として骨太に伝わってくる。
 「『トランプ・ドミノ』が誘発する世界危機」が副題。世界各地でのこのところの危機は、アメリカ・ファーストを掲げて突き進むトランプの想定外の"禁じ手"に要因がある。「米中衝突」も「日韓激突」も「中東」もという。二人の対談。
「『トランプ・ドミノ』が誘発する世界危機」が副題。世界各地でのこのところの危機は、アメリカ・ファーストを掲げて突き進むトランプの想定外の"禁じ手"に要因がある。「米中衝突」も「日韓激突」も「中東」もという。二人の対談。
朝鮮半島を取り巻く情勢の激変――。日韓の未曾有の対立と予想外の米朝の接近の2つのファクターが朝鮮半島の新たな相貌を見せ始めた。「米朝対話に進んだトランプが設けた日韓亀裂の舞台」「自らの首を絞めた韓国の戦線拡大」「日韓の水面下の3つの下部構造、①植民地支配と旧宗主国の責務②日韓の国力の接近③38度線が消えて韓国は海洋国家から半島国家に変貌」「中国という後ろ盾を得て大陸を志向する韓国」「日米韓同盟の綻びを衝く中露両国」「日韓基本条約の改定の可能性」などが語られる。
ホルムズ海峡「日本タンカー攻撃」の真の狙い――。「米大使館のエルサレム移転の強行」「首相のイラン訪問が誘発したタンカー攻撃」「イランも手を焼く? 攻撃の"真犯人"」「トランプは"オバマの政治的遺産"を潰した(イラン核合意からの離脱、制裁の再開・強化)」・・・・・・。「日本とイランの絆が武力衝突を回避した」「平和を語ったイランの最高指導者と安倍外交の功(金星)」「大きい日本の役割」など、注目の発言がある。
米朝蜜月と米中衝突の果てに劣化する日米同盟――。「米朝シンガポール会談と板門店会談の意味」「米に二正面作戦の余力なし」「トランプ政権の北朝鮮の"落としどころ"と、日米安保への考え」「降りる米と中国の"宇宙の一帯一路"」「イデオロギー喪失の中国はどこへ」「安倍流の"下品力"(返す力)」・・・・・・。最後に「トランプの"日米安保廃棄論"に日本はどう立ち向かうか」が論じられる。そして、「トランプの後も『アメリカ・ファースト』の潮流は消えるのではない。構造変化を見よ」「大陸国家(軍事力を背景に領域拡大で国益を得る)と海洋国家(領域拡大よりも貿易によるネットワークによって国益を得る)の基本・地政学から国際政治・世界経済を見よ」「米朝関係の改善に伴い韓国が地政学的に大陸と再結合しつつある」という。「トランプ・ドミノが誘発する世界危機」「北東アジアに生じた不気味な地殻変動を見逃すな」ということだ。
 「妻のトリセツ」の第二弾。男性脳と女性脳がテーマだが、「この本は『この人と一生を生きる』と決心した女性のために書いた。・・・・・海に出るなら羅針盤が要る。結婚に乗り出すなら、妻には『夫のトリセツ』、夫には『妻のトリセツ』が要る。私から見ると男女脳のありようを知らずに結婚するなんて、羅針盤なしに素人が深夜に大海に乗り出すようなものだ。命知らず」という。「男女の脳の認識フレームが絶望的にすれ違っている」ことを指摘する。
「妻のトリセツ」の第二弾。男性脳と女性脳がテーマだが、「この本は『この人と一生を生きる』と決心した女性のために書いた。・・・・・海に出るなら羅針盤が要る。結婚に乗り出すなら、妻には『夫のトリセツ』、夫には『妻のトリセツ』が要る。私から見ると男女脳のありようを知らずに結婚するなんて、羅針盤なしに素人が深夜に大海に乗り出すようなものだ。命知らず」という。「男女の脳の認識フレームが絶望的にすれ違っている」ことを指摘する。
「長らく狩りをしてきた男性脳は、『遠く』を見て、とっさに問題点を指摘し合い『ゴール』へ急ぐようにチューニングされている。目の前の人の気持ちや体調の変化に鈍感で、優しいことばも言わず、いきなり相手の欠点を衝いてくる」「問題解決を急ぐ、結論を急ぐ男性脳と、経緯を語りたがる、共感してほしい女性脳」「男性脳は定番に忠実、約束を守るのが彼らの愛だ。気を利かせて察して優しくね、というのが難しいのだ」「男性脳はおしゃべりが苦手。男性脳の緊張を解くためには、安寧な沈黙が必要不可欠。おしゃべりにストレスを感じる男性脳だから、べらべらしゃべり続ける女性の好感度は低い」「男性脳はゴールはどこか(どこを狙うか)を常に探っている。結論のわからない話に耐性が低く疲弊する」「"夫は気が利かない"は濡れ衣。妻の所作をうまく認知できていない」・・・・・・。
「男性脳は、身体拡張感覚が強い。車や道具を、自分の身体の一部のように扱う感覚が鮮明。妻や母親を手下のように扱うにはそうしたわけがある。だから褒めないし、お礼も言わないのだ。妻は"なんでもしてあげたい"病に気をつけて」「男性脳には、空間を把握する習性が刷り込まれている。レストランでは女性を壁際に座らせること。男性が壁を背にして座ると店全体を眺めてしまう」・・・・・・。
「私の話を聞いていない」「話が通じない」「気が利かない」「思いやりがない」といわれる訳だが、「私は、男性脳にも大いに同情している」「21世紀、男はつらいよね」という。
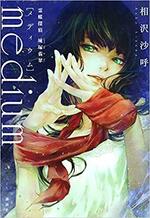 推理作家・香月史郎は城塚翡翠という霊媒の若き女性の助けを借り、様々な難事件を解決してきた。香月の大学の後輩・倉持結花が殺害された事件、作家の黒越篤が閉鎖空間で殺害される"水鏡荘の殺人"。そして女子高生連続絞殺事件。翡翠が死者の言葉を伝え、それを香月は論理の力を組み合わせて解決するという訳だ。
推理作家・香月史郎は城塚翡翠という霊媒の若き女性の助けを借り、様々な難事件を解決してきた。香月の大学の後輩・倉持結花が殺害された事件、作家の黒越篤が閉鎖空間で殺害される"水鏡荘の殺人"。そして女子高生連続絞殺事件。翡翠が死者の言葉を伝え、それを香月は論理の力を組み合わせて解決するという訳だ。
そんな時、同一犯と思われる姿なき8件もの連続殺人事件が起きていた。手口も異常だが、何の手がかりも残さない。全員が20代の女性会社員、一人暮らし、失踪届が出されていることを後で知る。犯人は狡猾で、警察の捜査手法にも詳しいようだ。事件は予想外の展開に。「大ドンデン返し」と「緻密な推理」に身体ごと持っていかれる本格ミステリー。

