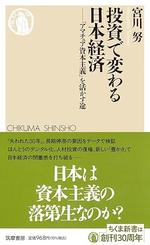 「『アマチュア資本主義』を活かす途」が副題。日本はなぜ30年もの長期停滞から抜け出せないのか。それは時代に合った果敢な「投資」をしてこなかった当然の帰結だ。設備投資額の低迷、人的資本への投資不足、デジタル化の遅れに見られる投資の質の低下。要するに供給サイドの政策不足であり、日本は「開発独裁」から「プロフェッショナル資本主義」への切り替えに失敗したとデータを徹底検証して解き明かす。
「『アマチュア資本主義』を活かす途」が副題。日本はなぜ30年もの長期停滞から抜け出せないのか。それは時代に合った果敢な「投資」をしてこなかった当然の帰結だ。設備投資額の低迷、人的資本への投資不足、デジタル化の遅れに見られる投資の質の低下。要するに供給サイドの政策不足であり、日本は「開発独裁」から「プロフェッショナル資本主義」への切り替えに失敗したとデータを徹底検証して解き明かす。
なぜ日本の投資はここまで増えなくなったのか。「日本企業は需要に合わせて設備投資を行う傾向が強く、バブル崩壊後の低成長期には過剰設備となった」「1997年からの金融システムの崩壊で、日本企業は単独で投資リスクを超えなくなった」「2010年代初頭の円高で、製造業は内需の成長ではなく生産拠点を海外に移した。円安となっても戻ってこない」「デフレが続き、実質金利の高止まりは設備投資を減少させ、収益を実物投資に回すより現預金の蓄積に向かった」とし、最大の要因は「日本企業が収益率の高い投資機会を見出せず、米国のICT革命の時期はリストラの最中。新たなビジネスチャンスとなる技術革新に乗り遅れた」と分析する。日本は新たな分野への挑戦なしに既存設備の削減がダラダラ続いてきた、需要を掘り起こす進取がない。資本蓄積が極端に低下して供給力低下した。その背景には、日本企業の躍進を支えたメインバンク制などの資金面、長期雇用・年功賃金制など労働面の慣行の崩壊がある。日本の個人レベルの行動よりも「ムラ」レベルの意思決定が優先される「アマチュア資本主義(意思決定は遅く、人間関係の協調性が重視され、労働者の満足度も専門的な能力が賃金に反映されず低い)」だと断言する。それが中途半端なデジタル投資に反映してしまっているし、人の配置にも改革が行われていないと言う。
そこで「日本経済の選択肢」を示す。2000年以降、マイルドなデフレ現象が経済の停滞をもたらしたということから「財政金融政策」に関心が集中したが、それは基本的には短期的な政策である。大事なのは真の成長戦略。そのために「デジタル化なくして真の成長なし」と強調する。「ソフト面での遅れが顕著な日本のデジタル化は、ビジネス面だけでなく、安全・安心面での進化にとっても必要である」と言う。
もう一つは「人材への投資」だ。デジタル投資はハードの投資に対して、ソフトウェア投資の比率が高いがゆえに、優秀な人材をいかに集められるかにかかっている。そこでは「少子化が人手不足時代に入った」「キャリアの上昇が図れる労働市場の流動化」「学校教育と企業内外の人材育成システム」の重要性を示す。
そして「市場経済では『プロフェッショナル資本主義』に基づく競争を徹底させ、非市場経済については『アマチュア資本主義』で運営すべきである」「日本では、市場経済でも、アマチュア的な考え方が入り込んでいることが問題」「豊かさで、経済的豊かさ以外の部分がクローズアップされることはあるが、経済的豊かさが維持されなければ、全体の『豊かさ』も低下していく」と述べる。
いずれにしても、幅広い新たな「投資」の重要性を指摘する。金融・財政政策が強調され論議されることが多いが、「投資」「成長」「生産性」「日本企業」にデータを示しながら迫る大事な著作。

