 「月まで三キロ」など6つの短編集。なんとも魅力的、感動的、新鮮で、いずれも天文学や考古学、宇宙物理、気象など科学が主旋律となって響く。苦悩に沈んだ主人公が、宇宙のリズムや自然に接し、包まれ、苦悩の世界から脱出する。宇宙即我、我即宇宙の入り口、その衝撃、飛躍の威力なのか。珍しい理系の小説だが素敵な話が続く。
「月まで三キロ」など6つの短編集。なんとも魅力的、感動的、新鮮で、いずれも天文学や考古学、宇宙物理、気象など科学が主旋律となって響く。苦悩に沈んだ主人公が、宇宙のリズムや自然に接し、包まれ、苦悩の世界から脱出する。宇宙即我、我即宇宙の入り口、その衝撃、飛躍の威力なのか。珍しい理系の小説だが素敵な話が続く。
「月まで三キロ」――。事業に失敗、奥さんとも離婚、母が急逝、父は認知症が進み介護も限界・・・・・・。死を求めてさ迷いタクシーに乗った男。運転手が連れて行ってくれた所が「月まで三キロ」の標識のある所。運転手は、天文学の教師だったこと、月の裏側は見えないこと、それには孤独があり、化石の渦には哀しみがあること、天文好きの自分の息子が自殺したこと等をしみじみと語るのだった。「星六花」――。気象庁に勤務する男に出会ったアラフォーの女性。共に独身。会話は降雨や降雪の専門の話になる。雪結晶の美しさ、その数なんと40種類などの話に驚く。気象少年であった男は「美しい花も、美しい鳥も、美しい人も、生殖のためにそうなっているにすぎない。・・・・・・しかし雪結晶は、雲の中で完全に物理プロセスのみで生まれる。・・・・・・掛け値なしにただ美しい」という世界を語るのだ。女の心に大きな変化が生ずる。「アンモナイトの探し方」――。中学受験を控えた小学6年生が、父母の別離等で潰されてしまいそうになり、祖父母の北海道に行く。そこでアンモナイトを河原でハンマーで発掘し続ける戸川という男と出会う。
「天王寺ハイエイタス」――。前3作とは違って大阪丸出し、笹野家随一のトラブルメーカー哲おっちゃんと娘ミカちゃん。だが、この哲おっちゃんがじつにいい。兄貴は過去数万年の気候の変遷を復元して、今の温暖化を研究する古気候研究者。「エイリアンの食堂」――。夜の日替わり定食を売りにしている味自慢のつくばにある「さかえ食堂」。身内を失った謙介・鈴花の父子のもとに高エネルギー加速器研究機構の女性科学者"プレアさん"が毎日、食べに来る。「実はわたし、138億年前に生まれたんだ。宇宙といっしょに生まれた水素で」と"宇宙人"だったという。
「山を刻む」――。火山研究者と学生と家を出て山に来てある決断をする私。「溶岩だけ調べてもダメ。その間にどんな火山灰層、軽石、火砕流堆積物などが挟まれているか。僕ら火山研究者は、できるだけ細かく、山を刻むんです」という話に、「いつも間にかわたしは、家族にとって、切り刻んでも構わない相手になっている」と思う私。大きな決断をし、自分の感動を他に伝染させる人間へと突き進もうとする。
 幸福度2年連続世界一位、ワークライフバランス世界一位のフィンランド。ムーミン、オーロラ、サウナ、私の好きなシベリウスのフィンランド。教育や社会福祉の進んでいる幸せな国・フィンランド。冬にマイナス30度、太陽の出ない時期もある寒いフィンランド。フィンランドの大学院を出て、企業勤めのあと、フィンランド大使館で広報を担当している堀内さんが、住んでみた実感のなかで語る。
幸福度2年連続世界一位、ワークライフバランス世界一位のフィンランド。ムーミン、オーロラ、サウナ、私の好きなシベリウスのフィンランド。教育や社会福祉の進んでいる幸せな国・フィンランド。冬にマイナス30度、太陽の出ない時期もある寒いフィンランド。フィンランドの大学院を出て、企業勤めのあと、フィンランド大使館で広報を担当している堀内さんが、住んでみた実感のなかで語る。
幸福度をランキングしても、あまりの環境と生活の違いで意味がないとまず思う。同時に、こういう暮らし、働き方があるということを新鮮に思う。それを知ることは大変いいことだ。「身近に自然があり、楽しむ」「定時に家に帰り、夏は1か月も休みをとる。『ゆとり』があり、『ゆとり』に幸せを感ずる」「仕事、家庭、趣味とそれぞれを楽しむことができるワークライフバランスがとりやすい」「自分らしく生きていける選択の自由度がある」「最近はヨーロッパのシリコンバレーと言われるほど、様々なアイデアを融合させたスタートアップがたくさん生まれている」・・・・・・。夜遅くまで働いたり休みも返上したりの"一生懸命感"や"疲労感"が漂う日本とは全く異なり、休みも睡眠時間もきちっととり、プライベートや趣味も充実させるワークライフバランスが整っている国がフィンランドだという。
働き方は柔軟、週に1度以上の在宅勤務をしている人は3割になる。1日2回のコーヒー休憩がある。「ウェルビーイング」という言葉をよく使うが、「心身共に健やかな状態」だ。接待は夜というのではなく、コーヒーやサウナ。ランチミーティングやブレックファーストミーティングが盛んだという。就業時間以外に自分のプライベート時間を犠牲にしてまで外出しない。趣味に家庭に忙しくそんな暇はないというわけだ。週末は店は閉まり、ベリー摘み・猟などの趣味・スポーツ・DIY・掃除などに精を出す。「心身ともにしっかり休み、次に頑張る」という姿勢は、ボーっとしたり、休んだことのない私などとは全く違う世界だといってよい。しかし一方で、こうしたなかにも、フィンランドのシス(内に秘めた強さ)に世界の注目が集まっているという。"灰色の岩さえ突き破る"シスは、不可能に思えても立ち向かいやり遂げるフィンランド人の精神の核だ。自立して生きる強さであり、おぜん立てされる日本とは違う自力で何でもやる、どうにかする力だ。シンプルな生活、シンプルな服装、人間関係もシンプル、コミュニケーションもシンプル。そして最後に教育、生涯学習のスタイル、フィンランドの貪欲な学び方が紹介される。
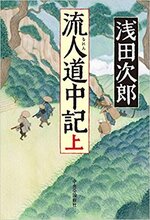
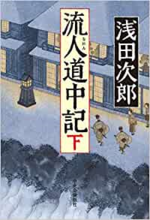 「どうして青山玄蕃は不実の訴えに抗おうとせず、冤罪に甘んじたのか」「玄蕃が対馬守の非道を暴かなかったことには合点がゆかぬ」――。時は幕末、黒船来航から安政の大獄、桜田門外の変、世情騒然たる万延元年(1860年)。姦通という破廉恥罪を犯したという旗本・青山玄蕃は、切腹を拒んで蝦夷松前藩への流刑に処せられる。その押送人に選ばれたのが19歳の石川乙次郎。鉄炮足軽の次男坊だったが町方与力に一躍出世、結婚したばかりであった。流人と押送人の旅。奥州街道を北へと進むが、貧しさが民を襲い、政を担う武士の儀礼と慣習と道徳は硬直していた。口も態度も悪い玄蕃だが、道中で遭遇する様々な出来事を情によって包み込み、奇想天外な解決をもたらしていく。乙次郎は、このろくでなしの男の徳と罪の断絶に驚く。抜群に面白い。
「どうして青山玄蕃は不実の訴えに抗おうとせず、冤罪に甘んじたのか」「玄蕃が対馬守の非道を暴かなかったことには合点がゆかぬ」――。時は幕末、黒船来航から安政の大獄、桜田門外の変、世情騒然たる万延元年(1860年)。姦通という破廉恥罪を犯したという旗本・青山玄蕃は、切腹を拒んで蝦夷松前藩への流刑に処せられる。その押送人に選ばれたのが19歳の石川乙次郎。鉄炮足軽の次男坊だったが町方与力に一躍出世、結婚したばかりであった。流人と押送人の旅。奥州街道を北へと進むが、貧しさが民を襲い、政を担う武士の儀礼と慣習と道徳は硬直していた。口も態度も悪い玄蕃だが、道中で遭遇する様々な出来事を情によって包み込み、奇想天外な解決をもたらしていく。乙次郎は、このろくでなしの男の徳と罪の断絶に驚く。抜群に面白い。
道中でめぐり逢う人々。「杉戸宿のおかみ」「中田関所の御番頭」「佐久山宿の按摩」「芦野宿での稲妻小僧と賞金稼ぎ」「7年も父の敵を探し旅する侍」「故郷の水が飲みたいと願う"宿村送り"の女」・・・・・・。
「昔は法がなかった。礼はひとりひとりが自らを律した徳目だ。人間が堕落して礼が廃れたから御法ができたんだぜ・・・・・・。青山玄蕃は無法者にはちがいないが、もしや無礼者ではないのではないか」「俺は町人に生まれついて、なりたくもねえ武士にさせられた。・・・・・・武士道というわけのわからぬ道徳を掲げ、家門を重んじ、体面を貴び、万民の生殺与奪を恣にする武士そのものに懐疑したのだ」「俺は俺のなすべきことを悟った。二百数十年の間にでっち上げられた武士道をぶち壊し、偽りの権威で塗り固めた『家』を潰してやる。それは青山玄蕃にしかできぬ戦だった。大勇は怯なるが如く、大智は愚なるが如しという。ならば俺は、破廉恥漢でよい」「俺はのう、乙次郎。われら武士はその存在自体が理不尽であり、罪ですらあろうと思うのだ。よってその理不尽と罪とを背負って生きようと決めた。非道を暴くのは簡単、ただ義に拠ればよい。・・・・・・そのうえ腹を切って死ぬれば、あっぱれ武士の誉よとほめそやされるであろう。だが、それでは俺も糞になる」「武士が命を懸くるは、戦場ばかりぞ」・・・・・・。
「武士の本分とは何か」「家とは何か」――。"奇怪な武士"の世の終末期、青山玄蕃の心に抱えたマグマ、問いかけたものを鮮やかに描く。
 江戸の文化は庶民の文化だ。大坂夏の陣(1615)から70年、元禄年間(1688~1704)に、庶民文化の成熟を迎える。平和であったればこそ、そして大災害や飢饉、火事等の危険にどう立ち向かうかが、切実な問題としてあった。江戸暮らしの内側を見ると、副題にある「快適で平和に生きる知恵」があふれている。「生活文化」「暮らしの文化」の基層には思想がある。「物的資源の有効利用」「近隣住民との長屋等での適度な付き合い」「倹約」「地域共同体の重視」・・・・・・。その深層にある道徳思想、「石門心学」と呼ばれる庶民哲学を生み出した石田梅岩の思想。日常を大事にし、平安や治安の良さを感受し、それを維持するための「道徳」「修身斉家治国平天下」の浸透だ。抜群に面白い書。
江戸の文化は庶民の文化だ。大坂夏の陣(1615)から70年、元禄年間(1688~1704)に、庶民文化の成熟を迎える。平和であったればこそ、そして大災害や飢饉、火事等の危険にどう立ち向かうかが、切実な問題としてあった。江戸暮らしの内側を見ると、副題にある「快適で平和に生きる知恵」があふれている。「生活文化」「暮らしの文化」の基層には思想がある。「物的資源の有効利用」「近隣住民との長屋等での適度な付き合い」「倹約」「地域共同体の重視」・・・・・・。その深層にある道徳思想、「石門心学」と呼ばれる庶民哲学を生み出した石田梅岩の思想。日常を大事にし、平安や治安の良さを感受し、それを維持するための「道徳」「修身斉家治国平天下」の浸透だ。抜群に面白い書。
「秩父流平氏の一族・江戸氏に由来する江戸」「家康の利根川の東遷、荒川の西遷」「井の頭池を主たる水源とする神田上水(飲料水の確保は最重要課題)」「明暦の大火(1657)で3分の2が灰燼と帰し、木造密集の弱点克服の為に道幅を広げる大江戸の誕生」「大江戸をつくる為に男性が流入、18世紀になると100万都市(北は千寿、南は品川)」「流入者に長屋を借家として提供、間口2.7m、奥行3.6m(2間)と狭く、上水道の上水井戸を共有。汚水は下水道へ。管理するのは大家」「余所者が集う小さな共同体に生きる庶民が魅力あふれる文化をつくり上げた」――。
「朝夕2食だった日本人が朝昼夕の3食に変わったのは、明暦の大火で流入した肉体労働者の体力維持の為だった」「江戸の茶漬け文化と上方の粥文化の意味」「関東の蕎麦と関西の饂飩(醤油も先進地域は関西だった"下り物""下り醤油"が、野田・銚子で安い地廻り醤油が出回るようになった)」「"江戸の前の海"の江戸前の鰻、屋台で揚げた天麩羅、大ヒット握り鮨と稲荷鮨の工夫」「"さっぱり"したい江戸っ子の服飾文化と銭湯・共同浴場」――。
「庶民の教育、寺子屋で学ぶ子ども(江戸後期で男性50%、女子20%)」「道徳教育を施した寺子屋という装置」「人足寄場という再教育施設(天明の飢饉と長谷川平蔵)」「石門心学と心学講舎」「活発だった出版と本の流通」「与えられた場で懸命に生きるということ、江戸庶民の生老病死」「天災地変と笑い――庶民の人生哲学」「過ぎ去ったことは悲しんでも始まらぬ。悲嘆の代りに陽気を選びとる放れ技、できるだけ楽しんでやろうという心性」――。
「与えられた場で懸命に生きる」――江戸庶民の日常生活が活写される。
 "老後資金2000万円"問題――その提起したことを冷静に把握・分析し、真正面から「人生100年代の生活」「日本の社会保障と財源」「高齢者の働き方や生活」を考える。
"老後資金2000万円"問題――その提起したことを冷静に把握・分析し、真正面から「人生100年代の生活」「日本の社会保障と財源」「高齢者の働き方や生活」を考える。
日本の人口構造は今後も高齢化が進行するので、社会保障の抜本的見直しが必要となる。まず年金――。2019年の財政検証で「年金財政はおおむね維持できる」というが、「マクロ経済スライド」「実質賃金効果」「非現実的な経済前提」の3つのトリックがあり、このままでは年金財政は破綻する可能性が高い、という。保険料収入が減少して給付が増加する、そのギャップをどう埋めるか、ということだ。「保険料率引き上げ」「マクロ経済スライド強化」は政治的にも困難だから、「支給開始年齢引上げ」が可能性が高い。しかし、70歳支給開始となれば、9割の人々が老後生活資金を賄えないという。
労働力不足のなかで、「女性労働力率の引上げ」「外国人労働者の活用」の2点以上に大事なのが高齢者の労働力を引上げること。社会保障の給付と負担の双方、労働力の確保などあらゆる面で高齢者の就労を進める必要がある。しかし高齢者の就労はなかなか進まない。働くことが損になってしまう制度となっていることが大きな要因で、とくに「在職老齢年金制度」と「高齢者医療制度、医療費の自己負担」「介護保険」の現状を改革する必要がある。「働くと年金が削減される」「働くと医療費の自己負担がぐっと増える」「介護保険でも前年の所得が一定限度を超えると自己負担率が高まる」というわけだ。「所得ではなく資産を勘案して自己負担率を決めるべきだ」と主張する。
高齢者はどう働けばよいか――。「定年延長の問題点」「企業のアウトソーシングによっての可能性」「ITで広がる高齢者の働く分野」「高まるフリーランサーの可能性(フリーランサーの時代が来た)(フリーランサーになるには早くからの準備が必要)(フリーランサーで働ける税制改革を急げ)」などを提唱している。

