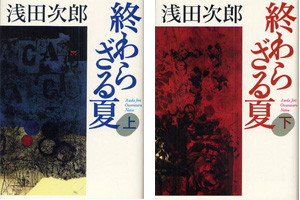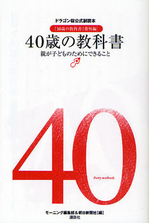広瀬さんは相当怒っている。「地球は温暖化しており、犯人はCO2だ」ということに、真正面から異を唱えている。目をさませ、といっている。
広瀬さんは相当怒っている。「地球は温暖化しており、犯人はCO2だ」ということに、真正面から異を唱えている。目をさませ、といっている。
もう20数年前になる。広瀬さんの衝撃的な本を何冊も読み、誌上対談もしたことがある。広瀬さんはエネルギーの問題をずっと、研究し続け、今日に至っている。
前半は、科学的データを駆使して、二酸化炭素温暖化論を批判する。都合のよいようにするデータの取り方、短兵急な時間軸で気温というものの上下をうんぬんすべきでないこと。
偏西風やエルニーニョとラニーニャの影響、現われている寒冷化と温暖化の分析、氷河・山火事・ハリケーン・台風の分析、ヒートアイランド問題、原発の温排水問題、太陽活動と黒点の増減、水蒸気などの多要因を冷静に分析せよ、といっている。
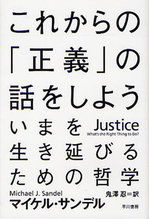 「いまを生き延びるための哲学」と副題にある。ハーバード大学史上空前の履修者数を記録する大人気講義「Justice(正義)」をもとにしたもの。
「いまを生き延びるための哲学」と副題にある。ハーバード大学史上空前の履修者数を記録する大人気講義「Justice(正義)」をもとにしたもの。
「金持ちに高い税金を課し、貧しい人々に配分するのは公正なことか」「徴兵と傭兵、どちらが正しいか」「自殺・食人」「戦後補償」から「妊娠中絶・幹細胞・同性婚」に至るまで、これをどう考えるか。
前提とする考え方を突き詰めると「正義」「自由」「道徳・哲学・倫理」の問題にぶち当たる。道徳的問題を解決することなしに、法の支配を決しえない。「幸福」「自由」「美徳」の視点からベンサムの功利主義、ミル、リバタリアニズム、カント、ロールズ、アリストテレス等を中心に「正義」に迫る。
福利の最大化と自由の尊重――ベンサムやミルとリバタリアニズムは論議の中心だが、重いし、講義が熱を帯びることがわかる。