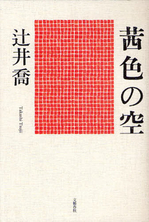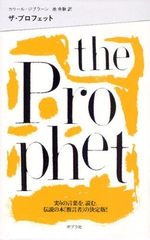環境・エネルギー、医療や介護や住宅、そして教育・・・・・・。日本は課題先進国であり、それを意識し、挑戦し、切り開いていくことによって新しい国家は築かれる。全くその通り。
環境・エネルギー、医療や介護や住宅、そして教育・・・・・・。日本は課題先進国であり、それを意識し、挑戦し、切り開いていくことによって新しい国家は築かれる。全くその通り。
「21世紀の国家像を示せ、ビジョンを示せ」という言葉を何度聞いただろうか。今を打開せずしてどうして未来があろう。しかも、直面している課題は、世界的だ。課題の克服は、世界のフロントランナーとして新しい社会システムを創造することになる。
小宮山さんは21世紀の環境とエネルギーのビジョンとして、ビジョン2050を提起している(物質循環システムの構築〈分別と最小限の廃棄、紙・プラスチック〉、エネルギー効率3倍にする。それはエネルギー消費を3分の1にすること〈自動車・エアコン・照明4倍、転換(高炉→新電炉、キルン→副成セメント)〉、自然エネルギー2倍(太陽電池・バイオマス・風力発電・水力・輸送・蓄電・グリッド)。
副題に「詭弁・逃げ・だましの倫理なき菅政治は日本を滅ぼす」とある。斬れている。
鳩山・菅両氏が小沢幹事長を非礼きわまりない斬り方をした「人情紙よりも薄い民主党人間関係」から始まる。どこにも人間哲学がある。
「巧言令色鮮し仁」「君子は本を務む。本立ちて道生ず。(本とは基本)」「利して利する勿れ(国民の利益のためにのみ働き、自分の利益をはかるな)」「選挙至上主義と自分さえよければ主義の執行部」――。
そして、後半は労働組合についてだ。「労働組合は政治権力の番犬になってはならない。あくまで独立自尊を貫くべし」とし、「君子の交わりは淡きこと水の若し。小人の交わりは甘きこと醴(れい)の若し。君子は淡くして以て親しみ、小人は甘くして以て絶つ」を示す。