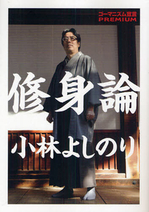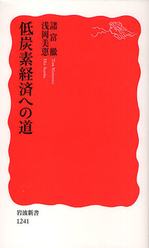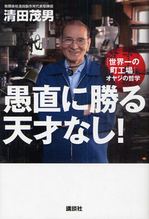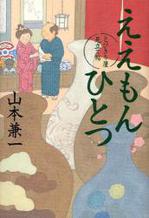宮本常一(つねいち)氏は、1907年(明治40年)の生まれ。昭和14年以来、全国の離島や辺地をくまなく歩き、独自の民俗学を築いた。
宮本常一(つねいち)氏は、1907年(明治40年)の生まれ。昭和14年以来、全国の離島や辺地をくまなく歩き、独自の民俗学を築いた。
文化を築き支えてきた伝承者・老人達自身が語ることを、丁寧に克明に描き、生き生きと蘇らせている。1960年の本で、宮本民俗学の結晶だ。
私の生まれたすぐ近くの北設楽郡旧名倉村が「名倉談義」として出てくるが、地名も土地柄もなるほどと思わせるもので、当時の田舎の生活そのものが描き出されている。民衆史、民俗学そのものだ。
「私の一ばん知りたいことは今日の文化をきずきあげて来た生産者のエネルギーというものが、どういう人間関係や環境の中から生まれ出て来たかということである」と宮本氏はいう。
「中央的・権威的な匂いのする既成の民俗学に抗して、泥にまみれた庶民の生活そのものの中に、人の生きる明るさ、たくましさをとらえようとする宮本氏の民俗学」(網野善彦氏)だ。
多くの人が圧倒的に基本にすえるすぐれた一書だ。
プロフィール

太田あきひろ(昭宏)
昭和20年10月6日、愛知県生まれ。京都大学大学院修士課程修了、元国会担当政治記者、京大時代は相撲部主将。
93年に衆議院議員当選以来、衆議院予算委・商工委・建設委・議院運営委の各理事、教育改革国民会議オブザーバー等を歴任。前公明党代表、前党全国議員団会議議長、元国土交通大臣、元水循環政策担当大臣。
現在、党常任顧問。