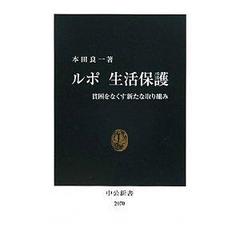 生活保護受給者は近年、急増。80人に1人、150万人にも及ぶ。一方、全ての人が雇用情勢の厳しさや生活苦、低い年金にさらされ、さらには不正受給者もあり、生活保護世帯への納税者の目は厳しい。地方財政の厳しさもある。
生活保護受給者は近年、急増。80人に1人、150万人にも及ぶ。一方、全ての人が雇用情勢の厳しさや生活苦、低い年金にさらされ、さらには不正受給者もあり、生活保護世帯への納税者の目は厳しい。地方財政の厳しさもある。
経済的、財政的視点から自立が要請されるが、生活保護受給者になるのは、まさに貧困、病気、教育(親の貧困、低学歴)、低賃金、雇用・失業、非正規労働、低年金など、日本社会の構造的問題の帰結である。たんなる経済・財政の視点のみで生活保護の問題を考えてはならない。社会に参画し、生きがいをもって人と交わるという次元からこの問題を考えないと、社会はつらいものになる。
本田さんは生活保護を、現場を丹念に歩くなかでルポし、問題の深刻さを剔り出している。そして北海道釧路市の地道な活動は、突き放されがちな生活保護受給者を、社会の中に抱きかかえようとする心の政治をみせてくれている。
「貧困をなくす新たな取り組み」という副題だ。
副題に「グーグルとメディア崩壊」とある。その通り。まさに大きくいえば人類が今、直面している社会の問題は、グーグル・ワールドと報道そして報道機関、
グーグル・ワールドと個人情報、さらに再考を余儀なくされるジョージ・オーウェルの「1984年」の社会――そうした問題だ。テレビ・新聞が消えるかどう
か、という次元を越えた、社会の本質的問題が提起されており、そのなかでの報道再生問題だ。
この本は面白い。税のプロ中のプロ、大武さん。本当にわかっている人は、やさしく語れるものだ。企画立案と税務行政の両方を担当しただけに具体的だし、日
本の地域現場や世界を駆けめぐって仕事をしているだけに、「高齢社会」「グローバル化」「資源制約時代」の3つの構造変化にどう税制をつくり直すかという
意欲があり、根源的、本質的だ。「国家の大宗は租税なり」と言われるように、国家戦略的に税を考え、骨太に再建しなければならない。
アジアの時代といわれる。低迷する世界経済のなかで、上昇するのはアジアだ。後藤さんはそのアジアの「今」を直視せよという。
「人件費の安い生産拠点」「汚職・腐敗・非効率」のアジアへの先入観は捨てよ。製造業と製品輸出のアジアから、消費するアジアへと「双発の成長モデル」へ と変わった。それも富裕層・中流層・BOP(ボトム・オブ・ピラミッド、アジアで20億人の年収3000ドル未満)の三層で新しい需要を考えよ。上から目 線ではなく、協調・共栄のアジアの一員として日本がいい役割りを演じることが、日本のためにもなる――こうしたことを後藤さんは現場を見、数字をあげて活 写する。今のアジアの熱気を教えてくれている。
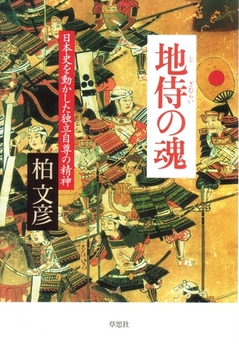 鎌倉時代の末から南北朝の時代、武装した有力農民・地侍が多く歴史の表に出てくる。源流は古代の力田の輩だが、農耕技術、農業経営にもすぐれた者が力を蓄
え、権力や権威の衰えに乗じて武装して自立する。室町時代に入って農業生産力の高まりで更に力をつけた地侍。応仁の乱のあとの戦国時代、戦国大名は勢力拡
大のため、圏内の地侍を動員した。徳川家康、真田昌幸の家系自体がそうだし、第一章「天地を開く」で紹介される市川五郎兵衛、大梶七兵衛、亀井茲矩(これ
のり)から高田屋嘉兵衛に至るまで、全国各地で活躍した人々のルーツを本書は表している。
鎌倉時代の末から南北朝の時代、武装した有力農民・地侍が多く歴史の表に出てくる。源流は古代の力田の輩だが、農耕技術、農業経営にもすぐれた者が力を蓄
え、権力や権威の衰えに乗じて武装して自立する。室町時代に入って農業生産力の高まりで更に力をつけた地侍。応仁の乱のあとの戦国時代、戦国大名は勢力拡
大のため、圏内の地侍を動員した。徳川家康、真田昌幸の家系自体がそうだし、第一章「天地を開く」で紹介される市川五郎兵衛、大梶七兵衛、亀井茲矩(これ
のり)から高田屋嘉兵衛に至るまで、全国各地で活躍した人々のルーツを本書は表している。
豊臣秀吉の兵農分離政策や島原の乱には地侍対策があるが、独立自尊、勤勉、剛直、忍耐を背景とする地侍の魂が、下級武士、有力農民、商人となって、日本を現場の中で切り拓いてきている。地域の吃立した地力と自力の戦さ人の歴史群像だ。
柏さんは「大地を自分の足でしっかり踏みしめ、汗を流し掌に血まめを作りながら荒野を切り拓き、創意工夫を重ねて自分の生活を確立する者、それが地侍である」「荒野を開拓して独立し、武装して自由と尊厳を守る――日本人よ、そういう地侍であれ、といいたい」と言う。

