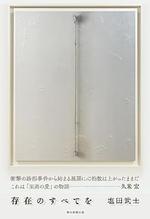 前代未聞のニ児同時誘拐事件といえば、犯人をめぐっての激しいアクションか、理詰めの知的攻防戦の展開と思うが、全く違う。子供を思う清冽な「家族愛」ともいうべき切なく温かい一途な心情に感情が揺さぶられる。涙と感動の傑作。
前代未聞のニ児同時誘拐事件といえば、犯人をめぐっての激しいアクションか、理詰めの知的攻防戦の展開と思うが、全く違う。子供を思う清冽な「家族愛」ともいうべき切なく温かい一途な心情に感情が揺さぶられる。涙と感動の傑作。
1991年12月、厚木で小学校6年の児童・立花敦之が誘拐される。そして翌日、横浜市山手で4歳の内藤亮誘拐事件が発生。その母・瞳は不思議なことに全く無関心。育児放棄と児童虐待の疑いがあり、身代金の要求は、実家の木島茂(海洋G会長)・塔子夫妻にされる。厚木の事件は、翌日には児童が帰り、こちらはどうも捜査を撹乱させる囮と思われた。可愛い孫を助けようと、1億の現金を犯人の指定する場所へ必死に届ける木島。しかし警察は犯人を取り逃がす。警察の失態と批判され、1億円は遺失物扱いとして戻ったものの、事件は迷宮入りとなる。そして3年、1994年12月に突然、7歳となった亮が祖父母のもとに帰ってくる。なぜか亮も祖父母の木島夫妻も、口を閉ざし全くしゃべらない。
事件の真相は――。空白の3年間に何があったのか――。誘拐事件から30年たった2021年。当時警察担当だった新聞記者の門田次郎は、事件を担当していた元刑事・中澤洋一の葬儀に出る。そこで事件を担当していた同僚刑事から、誘拐事件の被害者・内藤亮が今、如月脩という人気の写実画家となっていることを知らされる。既に時効となっているこの事件ーー。門田は再取材に入るが、中澤たち元刑事も粘り強く調べ続けていたことを知る。そしてある不遇の天才的写実画家の存在が浮かび上がる・・・・・・。
「空白の3年間に何があったのか」「祖父母のもとに帰った亮は、その後どのように過ごし、人気の写実画家となったのか」――。祖母の木島塔子は、仲良くなった刑事に「情けないけど、産みの親より育ての親っていうのは本当ね」と漏らしたという。「空白の3年」を経て帰ってきた少年は、読み書きができ、きちんと挨拶ができる子供になっていた。虫歯だらけの育児放棄にあってきた少年が、驚嘆すべき写実画家の才を身に付けて・・・・・・。単なる誘拐事件として、表面的に語られ忘れられる「虚」の世界と、写実画に象徴される「実」の世界の対比。3年間の「空」の世界と、実際の濃密な「実」の世界。門田は元刑事に言われた「何でブンヤをやってるの」と言う問いかけを、事件を探るなかで考え続けるのだ。そして現代の社会に蔓延する安易で軽薄な表層的な世界であるからこそ、奥にある「存在」「秘めたる力」「写実の如き洞察」が大事であることを浮かび上がらせる。犯罪の背後に、なんと清洌な人間ドラマがあったか――感動的な傑作。
波騒は世の常である。この世は、表層で流れ続いて行く。だが、その事象の裏には必ず人間ドラマがある。それを見ないで、どうして人生と言えようか。その深さを求めて政治家も、きっと記者(ブンヤ)も、黙々と現場にこだわり戦う。その真実と人間ドラマに触れる喜びを見出して。
 2020年から始まった新型コロナ禍。学校が休校となり、緊急事態宣言が発せられ、メディアも毎日コロナで覆い尽くされた。まだワクチンはなく、有名人の死亡が恐怖を与え、「三密」「ステイホーム」「濃厚接触者」は、日常用語となり、生活が一変した。その春から夏、登校や部活動が制限されるなか、全国の中高校生は、どのように生きたか。「この夏の星を見よう」と連携するいい話。
2020年から始まった新型コロナ禍。学校が休校となり、緊急事態宣言が発せられ、メディアも毎日コロナで覆い尽くされた。まだワクチンはなく、有名人の死亡が恐怖を与え、「三密」「ステイホーム」「濃厚接触者」は、日常用語となり、生活が一変した。その春から夏、登校や部活動が制限されるなか、全国の中高校生は、どのように生きたか。「この夏の星を見よう」と連携するいい話。
茨城県砂浦第三高校の2年生の溪本亜紗は、同級生の飯塚凛久などとともに、顧問の綿引先生のもとで天文部で活動しているが、コロナ禍の行動制限に悩んでいる。渋谷区のひばり森中学校の1年生の安藤真宙、なんと新入生のなかでたった1人の男子であることにショックを受ける。同級生の男子のいない中学生活を送ると思うと「コロナ、長引け、学校、ずっと休みのままになれ」とまで思う。そんな時、クラスメイトの中井天音に理科部に誘われる。長崎県五島列島の旅館の娘の佐々野円華は泉水高校の3年生。旅館には、東京などからコロナを持ち込まれるのではないかという目で見られ、憂鬱の日々を送っている。そんな時に、クラスメイトに五島列島にある天文台に誘われる。
それぞれが辛い気持ちになっている夏だったが、それぞれが天文活動に出会い、オンライン会議を通じてつながっていく。そして望遠鏡で星を捕まえるスピードを競う「スターキャッチコンテスト」を開催することに発展する。しかも天体望遠鏡をそれぞれが作ることから始めるというのだ。難易度1の月は1点、難易度2の木星、土星などは2点、難易度5の天王星、海王星、ファインダーで見づらい星団・星雲は10点・・・・・・。夢がある。人がつながり宇宙につながる。そのイベントが大成功に終わり、つながった中高校生は、12月には、国際宇宙ステーション、通称ISSの日本実験棟「かなた」の合同観測会を開くまでになる。
コロナ禍の不安や、葛藤のなかから、中高生たちが新しい絆と新しい風景を築ていく。鬱々としたコロナを、宇宙へと突き抜けていく友情あふれる青春小説。
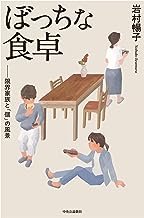 「限界家族と『個』の風景」が副題。「日本の家庭の食卓はどうなっているのか」――「食卓」を定点観測の場として、同一家庭の10年後、20年後を追跡調査、驚愕の現実を明らかにしている。これほどまで家庭が崩れてしまっているのか、恐ろしい。生きる基本としての「衣食住」も家庭だし、学校教育といっても家庭が大事で、「早寝、早起き、朝ごはん」運動を私は推進してきた。朝ごはんを食べているかどうかは、子供の学校教育に決定的な影響を与えるからだ。その家庭の食卓がどんどん崩れていると調査は示す。
「限界家族と『個』の風景」が副題。「日本の家庭の食卓はどうなっているのか」――「食卓」を定点観測の場として、同一家庭の10年後、20年後を追跡調査、驚愕の現実を明らかにしている。これほどまで家庭が崩れてしまっているのか、恐ろしい。生きる基本としての「衣食住」も家庭だし、学校教育といっても家庭が大事で、「早寝、早起き、朝ごはん」運動を私は推進してきた。朝ごはんを食べているかどうかは、子供の学校教育に決定的な影響を与えるからだ。その家庭の食卓がどんどん崩れていると調査は示す。
追跡調査は、厳しい現実を浮き彫りにしている。バラバラに食事をしている家庭、好きな食べ物を子供自身に選ばせて出している家庭、家族一緒の食卓がない、朝昼晩3食のリズムがない家庭が増えていると言う。なぜそうなるかと言えば、「家にいると、子供が邪魔でとてもストレスだった」「子供を複数の塾などに入れて、自分の自由な時間を確保しようとする親が珍しくない」「2017~2018年頃、朝の家事や子供の身支度ではなく、携帯チェックやメール交換をする親が増えてきた」「子供に食べさせる煩わしさで、家族バラバラの勝手にさせる食事となっている」「家には、カップ麺や冷凍のピザなどがたくさん買い置きしてあり、家族は頻繁にそれらを『自分の分だけ』勝手に食べている」と言う。さらに問題は、これらの家には経済的困窮や親の不在や物理的居場所がないというのではない。深夜に帰宅する子供を心配したり、食事を用意しておく「案じる親」がないということだ。親自身に「自由とお金と無干渉」の考え方が広がってしまっている。自分の自由、自分の勝手、自分のペースを大事にする傾向が極めて強くなっていると言う。
そして10年後になると「2005年以降、乳幼児期の子供との共食を疎ましいと語った家の約半数に『家に帰らぬ子』が出現した」「中学生の頃から部屋に引きこもり学校にも行ってない子、高校の時から無断外泊が多く今もたまにしか家に帰らない子、高校を中退して親と没交渉、今も半家出状態の子が、2005年前後から目に見えて急増している」・・・・・・。そして家族が壊れ、家庭内離婚や離婚が増えているというのだ。ダイニングテーブルさえもない家族や「独りベッド飯」の夫が増えるという家族の変化が指摘されている。身体の具合が悪くなった高齢者は同居を望むかもしれないが、本書の調査によれば、逆に「没交渉」「ノータッチ」にされる可能性が強いという。衝撃的事実だ。
これまでの日本の論調では、「貧困」による家庭破壊、子供の貧困などが問題となったが、そのさらなる底流に、「家庭のバラバラの食卓」「限界家族と個」があり、「主婦の『自分一人の時間』志向」という意識の変化に「家族共食を蝕むブラック部活とブラック企業」などが追い打ちをかけていることが指摘される。主婦も、家族も「自分の時間」「自分一人の時間」を生きるようになった。「個化する家族」は、旧来の家庭が担ってきた様々なものを内側から無用化している。
一方、この調査を通じ、きちっとした「家庭の食卓」をしてきた家庭は、円満家庭として崩れない。家族が減っても「共食」を維持している。家事協力も崩れていないことが示される。しかしこの調査では、10年後に「円満」「多少の問題を抱えながらも、円満を保っている」という家庭は、36%であったという。恐ろしい現実が、日本社会の底流で進行している。
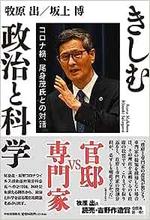 「コロナ禍、尾身茂氏との対話」が副題。3年に及んだ新型コロナウィルスとの対決。尾身茂・新型コロナウィルス感染症対策分科会長と計12回、24時間を超える対話を行い、政治と科学、政府と専門家がどう考え、ぶつかり、協力してコロナと戦ってきたかを語る。
「コロナ禍、尾身茂氏との対話」が副題。3年に及んだ新型コロナウィルスとの対決。尾身茂・新型コロナウィルス感染症対策分科会長と計12回、24時間を超える対話を行い、政治と科学、政府と専門家がどう考え、ぶつかり、協力してコロナと戦ってきたかを語る。
試行錯誤の戦いであり、政府も専門家も悩みつつ決断した様子がドキュメントのようによくわかる。「コロナ禍の3首相」の序章から「謎の肺炎 過去の教訓生かされず」――。加藤厚労相に提出した対策案、専門家会議の発足、PCR検査の『抑制』批判などの第1章。第2章「前のめり ルビコン川を渡った専門家会議」では、「これから1〜2週間が瀬戸際」と専門家が、「ルビコン川を渡るような思い」で前のめりの発言をしたことを赤裸々に話す。わが国のクラスター対策が奏功、北海道の危機、エビデンスなき一斉休校、官邸官僚による3密(密閉、密集、密接)など一つ一つ思い起こす。第3章「緊急事態宣言発令 42万人死亡推測の衝撃」――。2020年4月7日の緊急事態宣言、「最低7割、極力8割」の表現をめぐる攻防、休業要請をめぐる足並みの乱れ、アビガンへの否定的意見、解除基準を作る苦悩などが語られる。世界がロックダウンや死者増大のなか、日本が微調整をしながらしのいだことがよくわかる。
第4章は「専門家会議の『廃止』 政府に向かうべき批判が専門家に」――。専門家会議を発展的に解消し、20年7月、尾身氏が会長に就任した「新型コロナウィルス感染症対策分科会」が発足する。経済の大竹文雄氏や小林慶一郎氏、鳥取県知事の平井伸治氏らが入る。政府と専門家、その役割分担という難しい問題が表面化するが、これからも問われる難問だ。
そして第5章「GoTo 経済かコロナ対策か」――。2020年7月22日、GoToトラベルのスタート、安倍首相の辞任表明と菅首相・・・・・・。専門家がGoToに常に危機感を持っていたこと、コロナの最初から担当の西村大臣とずっと毎日のように会っていたことが語られる。そして2021年1月7日に2度目の緊急事態宣言、「急所」と狙い撃ちされたという飲食店の反発、待望のワクチン登場(進まぬ国産ワクチン開発)などの攻防が語られる。
第6章は「東京五輪 官邸と専門家の衝突」だ。「五輪開催自体で感染拡大に影響したのかを証明するのは難しい」と語っている。ワクチン接種を徹底して進めた菅首相の退陣。第7章は「看板倒れの『聞く力』 平時への移行に前のめり」――。分科会が開かれなくなったり、国会にも呼ばれなくなり、専門家と距離が開いていったと言う。「4つの考え方」に政府は困惑、行動制限を行わない方針、待機期間短縮は事前相談なし、全数把握の見直しを発表、2類相当から5類への動き・・・・・・。そして第8章「感染症対策の司令塔 専門家助言組織のあり方を問う」「終章 コロナとの共生」について語る。
「新型コロナウィルスと向き合ってきて、浮き彫りになった、あらゆる課題を洗い出す必要がある。医療提供体制の問題、感染症法や新型インフルエンザ等対策特別措置法の問題、国と自治体の関係等を検証すべきだ。新型コロナウィルスにより23年5月時点で約7万5000人の尊い命が失われているのですから、二度と同じ過ちを犯してはなりません」と締めくくっている。大変な3年間をかなりくっきりと思い起こしつつ読んだ。
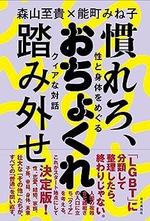 きわめて率直で大胆で面白く、世界が広がる。帯に「『LG BT』に分類して整理したら、終わりじゃない。人間の複雑さと繊細さの入り口に立ち、『クィア』を考える。これがスタート地点にして決定版!」「性、恋愛、結婚、家族、子孫、幸福、身体、未来・・・・・・壮大な『その他』たちが、すべての『普通』を問い直す」とある。LGBTQの当事者である二人が、全くその通り語り尽くしている。「差別」の繊細さについても、「普通」を押し付け、「多様性」を上から目線で論ずることの違和感と嫌悪感が率直かつ緻密に語られる。これまで小説も含めて様々な本を読んだり、直接話を聞いてきたが、本書は特にパワフルで圧倒され、世界がクリアになる。
きわめて率直で大胆で面白く、世界が広がる。帯に「『LG BT』に分類して整理したら、終わりじゃない。人間の複雑さと繊細さの入り口に立ち、『クィア』を考える。これがスタート地点にして決定版!」「性、恋愛、結婚、家族、子孫、幸福、身体、未来・・・・・・壮大な『その他』たちが、すべての『普通』を問い直す」とある。LGBTQの当事者である二人が、全くその通り語り尽くしている。「差別」の繊細さについても、「普通」を押し付け、「多様性」を上から目線で論ずることの違和感と嫌悪感が率直かつ緻密に語られる。これまで小説も含めて様々な本を読んだり、直接話を聞いてきたが、本書は特にパワフルで圧倒され、世界がクリアになる。
「私たち『その他』は壮大なんですけど? ――LGBTQ+、分類して整理したあとの、その先の話(クィアは強烈な侮蔑語から始まった)(あなたはLG BTですか?は老若男女ですかと?と同じ) (名前をつけられない人たち) (壮大なその他)」「基準を疑え、規範を疑え――性、性別、恋愛ってなんだろう?(男と女っていうニ通りじゃない)(『早い段階で決まる』は違う)(恋愛至上主義規範)」「いい加減、そろそろ慣れてくれないかな――マイノリティとマジョリティのあいだ(『マイノリティだから素晴らしい』がやばい)(ゲイと言えばオネエみたいなステレオタイプがセクシュアル・マイノリティ一般に拡張されてしまった) (弱者を救うと言う政治家を弱者はなぜ支持しないか)」が1〜3章。
「制度を疑い、乗りこなせ――結婚をおちょくり、家族像を書き換える(侮蔑語を逆手に取る) (なんで友達同士で結婚しちゃいけないの?)」「そんな未来はいらないし、私の不幸は私が決める――流動する身体、異性愛的ではない未来(『見える差異』に依存していいのか) (『ありのまま』がとにかく嫌だ)(身体は変わるし変えられる)」「『出過ぎた真似』と『踏み外し』が世界を広げる――『みんな』なんて疑ってやる(聞いたこともない性的指向の人に会ってみたい)(ずるい、図々しい、厚顔無恥!)」が4~6章。
「男性でも女性でもない性別の人間であるという自認をもって生きる方はいっぱいいる。Xジェンダーを自称してる人はけっこう多い」「男か女か、そのあいだかという一直線の基準自体を疑っていいと思う。『男度20%、女度80%』みたいな2つの基準で計れるのではなく、直線上ではない、平面上、あるいは立面上のグラデーションとも言ったらいいのかな」「そもそもゲイの場合、カミングアウトしなければ、トランスの人みたいには困らないという点で、就職とか仕事に関して不利な点が少ない」「私は寛容だから受け入れるというのはものすごく上から目線。『理解する』『受け入れる』ではなく、『もう慣れてくれ』ということ」・・・・・・。
「クィアを使うための三本柱」が示される。「みんな一緒ではなく、いろんな人の違いを違いとして保持したまま一緒にやっていく」「アイデンティティをプロセスとして捉える」「喧嘩を売るとか、逆手に取るぞという好戦性」の3つだ。また「『体が男(女)だけど、心は女(男)』という言い方が広まったのはよくない。そんな単純に分けていいのか疑問がある。そういうバキッとした言い方があると、結構当事者も乗ってしまう。男か女かなんて個人個人でグラデーションであるはずなんだけど」・・・・・・。
まさに性と身体をめぐるクィアな対談。

