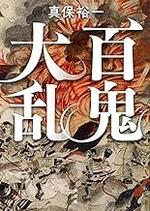 なるほど「百鬼大乱」の大変な時代、大変な関東だったと思う。太田道灌(1432〜1486年)は「江戸城築城」「山吹伝説」などが名高いが、人物像そのものはあまり伝わっていないようだ。しかし本書は、「戦国時代はいったいいつから始まるのか」の問題意識から、歴史関連の文献を読み込み、「応仁の乱に先駆けること13年、関東の戦乱は、実に30年にわたり、応仁の乱が収束した後も続き、戦国時代の幕を開けた」ことを明らかにする。その血みどろの30年を駆け抜けた名将が、太田道灌であることを描く。「太田道灌こそ、まさしく名将と呼ぶに相応しき漢であった。長引く関東の戦乱をほぼ一人で平定してみせ、自ら指揮を執った戦で負けたことは一度たりともなかった」「諸葛孔明の如き人物」と言う。
なるほど「百鬼大乱」の大変な時代、大変な関東だったと思う。太田道灌(1432〜1486年)は「江戸城築城」「山吹伝説」などが名高いが、人物像そのものはあまり伝わっていないようだ。しかし本書は、「戦国時代はいったいいつから始まるのか」の問題意識から、歴史関連の文献を読み込み、「応仁の乱に先駆けること13年、関東の戦乱は、実に30年にわたり、応仁の乱が収束した後も続き、戦国時代の幕を開けた」ことを明らかにする。その血みどろの30年を駆け抜けた名将が、太田道灌であることを描く。「太田道灌こそ、まさしく名将と呼ぶに相応しき漢であった。長引く関東の戦乱をほぼ一人で平定してみせ、自ら指揮を執った戦で負けたことは一度たりともなかった」「諸葛孔明の如き人物」と言う。
足利幕府が衰え混迷する15世紀中頃。関東では鎌倉公方・足利成氏、それを支える簗田持助等と、関東管領・上杉家との激しい戦いが絶え間なく繰り返されていた。上杉家は、上杉宗家の家務・長尾景仲(昌賢)、扇谷分家当主の上杉持朝(道朝)、扇谷分家の家務の太田資清(道真)の3人の猛者、そして道真の嫡男・太田資長(道灌)が強い結束のもとで戦いを進めていた。1454年、成氏による関東管領・上杉憲忠の殺害をきっかけにして、享徳の乱が勃発。上杉援軍の今川範忠は鎌倉を制圧、敵が町中に火を放って逃げ250年にわたって、坂東の都として栄えた鎌倉は、無惨にも灰燼と帰す。室町幕府は、足利政知を新たな鎌倉公方として派遣したが、伊豆の堀越を拠点とした(堀越公方)。足利成氏は鎌倉を追われ古河を拠点とする(古河公方)。ここから再びおおよそ利根川を挟んで両陣営二分の激突となる。昌賢は古河の対岸に砦を構え、資長(太田道灌)は長禄元年(1457年)、江戸に城を築く。品川や神奈川の湊に出入りする商人の船が江戸に集まってくる。河越などにも砦が築かれる。一進一退の攻防が激しく繰り返されるなか道真・資長親子の活躍はめざましく、資長は獅子奮迅の戦いとなった。京では、山名と細川等による応仁の乱(1467〜1477)が起き、関東にもその影響が及んだ。
しかし、そうしたなか、上杉家内の抗争が始まり、上杉顕定の重臣・長尾景春が謀反(長尾景春の乱)を起こし大混乱。これを太田道灌が鎮めたのだった。ほとんどの戦いで勝利し、上杉家の危機を救った太田道灌であったが、妬み、讒言にもあい、直言も用いられないことが多かった。そして文明18年(1486)8月、上杉定正の刺客によって暗殺される。「当方滅亡」――太田道灌の残した言葉通りの上杉家となり、北条早雲によって付け入られる関東となってしまう。
「お家の為、一門の為、命を賭して戦に挑む。しかし何のための戦いなのか」・・・・・・太田道灌の胸中には、外の敵ばかりでなく、内の敵とも戦わねばならない悔しさがあったと思う。まさに「百鬼大乱」の関東、そのなかでの太田道灌。せり上がってくるような苦衷がよく描かれている。
 「キラーロボットの正体」が副題。中国、ロシア、イスラエル、米国など、世界で広がるAI搭載型兵器の現状を紹介し、AI兵器戦争、「人工知能は、人を殺すのか」を語ってはいるが、それ以上きわめて丁寧に、そもそも人工知能とは何か、意識とは何か、生物とは何か、「人工知能はどのような技術であり、何ができて何ができないのか」を語っているのが本書だ。
「キラーロボットの正体」が副題。中国、ロシア、イスラエル、米国など、世界で広がるAI搭載型兵器の現状を紹介し、AI兵器戦争、「人工知能は、人を殺すのか」を語ってはいるが、それ以上きわめて丁寧に、そもそも人工知能とは何か、意識とは何か、生物とは何か、「人工知能はどのような技術であり、何ができて何ができないのか」を語っているのが本書だ。
第三次ブームは、人間が持つ学習能力を機械(コンピュータ)学習、ディープラーニングの高い性能を発揮できる環境が整ったことによって起きている。「現在、人工知能と呼ぶさまざまな技術は、人工知能と呼ぶよりも、高度情報処理技術と呼んだ方が実態に合致している」とまず言う。
そして「知能とは何か」――。「生物と低汎用型人工知能搭載ロボットの決定的な違いは、生きる目的を持っていることと、その目的を達成させようとする自律性、能動性である」「生物は、行動マニュアルでは乗り切れない状況に対し、試したり工夫したり、調べたり、他人の真似をしたりと、生きるために、知識や経験を総動員し打開する。これが生物であり、知能である」と言う。「我々が意識と呼ぶ意識は、顕在意識である。しかし、その行為を意識して実行する少し前に、潜在意識にてその行為の実行が開始されている」・・・・・・。
人の体は、数十兆にもなる膨大な数の細胞から構成される。トップダウン型の設計で、これだけのパーツで構成される製品は存在しない。航空機でも数百万パーツ。しかも生物は、ボトムアップ型で生み出されており、脳自体が神経細胞の巨大なネットワークだ。しかも、蟻の群れの行列や、ホタルの同期の創発など、「生命のような複雑なシステムをゼロから構築するのはまだまだ難しい。そう簡単に人を超える人工的な知能ができるわけがない」と言う。
さてキラーロボット――。道具型人工知能であれば制御できるが、問題は自律型人工知能だ。ホーキング博士らは危険性を指摘し、人のクローンを作らないようにと同じように、ガイドラインが必要となる。科学技術のレベルに準じて兵器を分類すると、①半自動型兵器②自動型兵器(用途限定の人工知能を搭載した兵器、低汎用型人工知能を搭載した多機能型の自動型兵器) ③集団自動型兵器(連携機能が付加された集団・編隊作戦) ④自律型兵器(人と同じレベルの臨機応変な問題解決能力を持つ) ⑤集団自律型兵器――と分類する。あくまで「人がトリガーを引くタイプの開発に留めておかなければ、人類に未来はなく、新しいルールが極めて重要だ」と言う。そうした国際基本ルールが動き始めている。
「人工知能は、人を殺すのであろうか」について、「私の答えは、当面の人工知能のレベルにおいては、NOである。人が人工知能を使って人を殺すのである」「自動運転車にしても自動であって自律ではない。自動運転車が事故を起こした際は、製造メーカーに責任が生ずる」「そのために、作る側と利用する側の双方に対するガイドラインの作成及び道徳教育が特に必要だ」「求められるのは、人間力であり、人間力を高めるべきだ。これこそが、人工知能にとって最も苦手とする能力だからである」と主張する。しかし、その人間力が若者を始めとして衰退していることを懸念し、「日本にある東洋的感性に期待する」と言う。
キーワードは「自動か自律か」。科学の発展により「意思を持つ自律のように感じさせる人工知能」のように見えても、それは人間のような「自律」ではない。それゆえに、人間力を鍛え磨き、しっかりしたルールを国際的に作り上げなければならないということだろう。
 「G O(柴咲コウ)」「世界の中心で、愛をさけぶ(長澤まさみ)」「春の雪(竹内結子)」「北の零年(吉永小百合)」「劇場(松岡茉優)」、そして「リボルバー・リリー(綾瀬はるか)」など・・・・・・。デビュー以来、25年にわたって、映画史に直刻む作品を撮り続けてきた映画監督・行定勲。身近で接してきた名だたる女優たちの挑む姿をエピソードを交えて語る女優論、映画論。映像でしか見たことのない我々だが、女優の奥行きと葛藤、凄さを知ることができ面白い。それを引き出したのが映画監督・行定勲と言えるだろう。行定勲は成瀬巳喜男監督を尊敬し、その成瀬監督が最も敬愛していたのが女優・高峰秀子だった。根っこはそこにあるようだ。
「G O(柴咲コウ)」「世界の中心で、愛をさけぶ(長澤まさみ)」「春の雪(竹内結子)」「北の零年(吉永小百合)」「劇場(松岡茉優)」、そして「リボルバー・リリー(綾瀬はるか)」など・・・・・・。デビュー以来、25年にわたって、映画史に直刻む作品を撮り続けてきた映画監督・行定勲。身近で接してきた名だたる女優たちの挑む姿をエピソードを交えて語る女優論、映画論。映像でしか見たことのない我々だが、女優の奥行きと葛藤、凄さを知ることができ面白い。それを引き出したのが映画監督・行定勲と言えるだろう。行定勲は成瀬巳喜男監督を尊敬し、その成瀬監督が最も敬愛していたのが女優・高峰秀子だった。根っこはそこにあるようだ。
ヒロインをいかに組み立てるか――。凄い、無敵の松岡茉優――ストーリーを理解するだけでなく、この映画が社会に存在する上でどうあるべきかがわかっている末恐ろしい技巧派。女優としての重力、重い色っぽさがある有村架純――清楚でありながら、強烈に匂い立つものがある。自分をさらけ出すことに達成感を見いだすことができる人は期待できる。成熟した裸体を堂々と見せた二階堂ふみ――無鉄砲で自分が動けば何でも実現すると信じ、現実に成立させてしまう。台本を500回も読んできた8歳の芦田愛菜――現場で感情をプラスしてしまう天才。自分で考え、細かい芝居を加えてくる。美しさだけでなく、喜怒哀楽の陰影が豊かな薬師丸ひろ子――気の強さも儚さも、可愛らしさも全てを携えている。緊張すると腕組みをする癖があった沢尻エリカ――すごくわかりやすい子で、僕の演出は彼女の腕組みをほどくところから始まった。削ぎ落とした末に風格が立ち現れる竹内結子――存命だったら今も指名していた女優だ。美人で意志があって、でも柔らかくて、しっとりしていて、アグレッシヴでもあるそんな女優はなかなかいない。
誰が見ても大女優だが、ご本人はあくまでもニュートラルであろうとされている吉永小百合――できるだけ監督の話を聴こうとし、監督が望んでいることに近づけようとする人。次はもっと、その次はもっとと本気で思ってる人。人と仕事をする際の敬意を教えてもらった。相手との距離感や踏み込みには唸らされた大竹しのぶ――均衡が壊れると新鮮さが誕生する。圧倒的なヒロイン綾瀬はるか――初々しさと独特の透明感があり、肉感的でありながら、身体能力が突き抜けていた。被写体としての綾瀬はるかの説得力は、まず体幹の良さにある。めちゃめちゃ暗く全然しゃべらなかった長澤まさみ――自分から坊主にし「坊主に、なっちゃったぁ」と明るく笑った。真っ直ぐな眼差しの柴咲コウ――もし壊そうとしても、絶対壊れない何か。打ち勝ってしまう何か。それがあった。
長澤まさみにも、柴咲コウにも語らなくても伝わってくる「存在の雄弁さ」「芯の強さ」があった。だから、女性を脇役にはできない、と言う。我々が見ている映像とも違和感がないが、奥行きと深さが感じられ迫ってきた。
 「あの人物に嘘は通用しない」――加賀恭一郎がきちっと理詰めで攻めていくシリーズ最新刊。8月の別荘地に裕福な家族が集まってくる。総合病院を経営する櫻木洋一と妻・千鶴、そのわがままな一人娘・理恵と婚約者・的場雅也。大企業の会長・高塚俊策とやり手の妻・桂子と会社の部下の小坂家3人。公認会計士の栗原正則と美容院経営の妻・由美子と中学生の娘・朋香。6年前から別荘地に移り住んだ未亡人の山之内静枝と姪夫婦で病院に勤務する鷲尾春那・英輔。そこで今年も恒例のバーベキュー・パーティが行なわれた。その夜、連続殺人事件の惨事が起きる。閑静な別荘地で、ある意味では、閉鎖された密閉空間での恐るべき殺人事件だ。
「あの人物に嘘は通用しない」――加賀恭一郎がきちっと理詰めで攻めていくシリーズ最新刊。8月の別荘地に裕福な家族が集まってくる。総合病院を経営する櫻木洋一と妻・千鶴、そのわがままな一人娘・理恵と婚約者・的場雅也。大企業の会長・高塚俊策とやり手の妻・桂子と会社の部下の小坂家3人。公認会計士の栗原正則と美容院経営の妻・由美子と中学生の娘・朋香。6年前から別荘地に移り住んだ未亡人の山之内静枝と姪夫婦で病院に勤務する鷲尾春那・英輔。そこで今年も恒例のバーベキュー・パーティが行なわれた。その夜、連続殺人事件の惨事が起きる。閑静な別荘地で、ある意味では、閉鎖された密閉空間での恐るべき殺人事件だ。
5人殺害、1人未遂――。殺されたのは櫻木洋一、高塚桂子、栗原夫妻、鷲尾英輔、未遂が的場雅也。ところがすぐに「俺が犯罪者だ」「生きている意味を感じないので、死刑になりたい。自分を蔑ろにした家族への復讐」と桧川大志という男が名乗り出て逮捕される。しかしそれ以上何も語らない。また被害家族との関係も全く見出せなかった。
事件に巻き込まれた家族たちは、真相を自分たちで解き明かそうとし、遺族が別荘地に集まり、検証会を実施することになる。鷲尾春那に頼まれ、長期休暇中の刑事・加賀恭一郎もそれに参加することになる。そして参加者には、「あなたが誰かを殺した」という手紙が送られていたことがわかる。疑心暗鬼の被害家族、次第にわかってくるそれぞれの家族の複雑な内情・・・・・・。そして事件の真相を加賀恭一郎が整理し、分析し、核心に迫っていく。いつもながら見事な東野圭吾の世界。
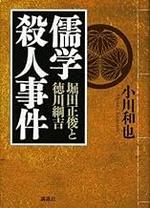 ミステリー小説ではない。歴史学者による実証研究の書。「堀田正俊と徳川綱吉」が副題。第5代将軍綱吉の時代(在職1680〜1709年)。元禄14年(1701)の江戸城内の「松の廊下」事件のほかにもう1件、貞享元年(1684)8月28日、大老・ 堀田正俊が若年寄・稲葉正休に脇腹を刺されて死亡した。赤穂浪士の話ばかりが有名だが、江戸城内で大老が刺し殺されるという大事件だ。こんな事件がなぜ起きたのか――。この殺人に綱吉の意志が働いていた。堀田正俊は、綱吉の度が過ぎるほどの犬愛護、それに落ち度があった者への厳しい処刑、恐怖政治、能役者の幕臣への登用など、諫言を繰り返したという。それを疎ましく思っていた綱吉は、ついに正俊の大老辞職を迫り、それが拒まれ殺害に至ったという説を立証している。
ミステリー小説ではない。歴史学者による実証研究の書。「堀田正俊と徳川綱吉」が副題。第5代将軍綱吉の時代(在職1680〜1709年)。元禄14年(1701)の江戸城内の「松の廊下」事件のほかにもう1件、貞享元年(1684)8月28日、大老・ 堀田正俊が若年寄・稲葉正休に脇腹を刺されて死亡した。赤穂浪士の話ばかりが有名だが、江戸城内で大老が刺し殺されるという大事件だ。こんな事件がなぜ起きたのか――。この殺人に綱吉の意志が働いていた。堀田正俊は、綱吉の度が過ぎるほどの犬愛護、それに落ち度があった者への厳しい処刑、恐怖政治、能役者の幕臣への登用など、諫言を繰り返したという。それを疎ましく思っていた綱吉は、ついに正俊の大老辞職を迫り、それが拒まれ殺害に至ったという説を立証している。
そこには、「綱吉の政治の是非(明君か暗君か)」「正俊が目指す仁政の実現と綱吉との食い違い」、何よりもよって立つ「儒学」に対する考え方の根本的違いが深刻な亀裂となったと分析する。近年になって、生類憐みの令が「仁政の実現」と言う評価があるが、「百件を優に超える法令によって、民衆の生活に立ち入り、厳しい処罰や取り締まりによって達成される仁政とはいったい何であろうか」と言う。正俊の著作「颺言録(ようげんろく)」には、仁政思想、明君たるべき将軍像が描かれている。綱吉を立てて書いたために、虚実が混ざっている。「民は国の本」「日本版貞観政要を意識」「仁政は父母の心で子たる民衆に望むこと」「命令や法律に頼らず、将軍自ら率先して人徳を示し、人々の心を感化して風俗を変えることこそ仁政である」「老子に『大国を治むるは小鮮を烹るが如し』とあるように、大国を預かる君主は、民衆の行いを逐一気にして介入し、その行いを正そうとするような小心翼々とした構えではいけない」などが描かれているいる。また綱吉は「儒学好き」で大名相手に講義をよくしたといわれるが、「儒学は修己治人の生きた学問、活学であって、儒学を講釈することと、儒学によって民衆を治めることはイコールではない」と解説している。綱吉の厳罰主義や、政治のやり方、講釈する儒学に、荻生徂徠、熊沢蕃山、新井白石などもそれぞれの立場で厳しい目を注いだ。正俊は諫言によって、綱吉の逸脱を正し、明君像近づけようとしたが、綱吉はそれを憎み、疎んじて大老職引退を迫り、それを拒否したことによって、事件が起こったと分析する。
正俊は、自分の死を予感していた節があり、それゆえに「颺言録」の完結を急いだようだ。綱吉を支えたのはたった4年。堀田正俊が殺され、綱吉のブレーキ役がいなくなり、生類憐れみの令、恐怖政治が進んでしまったようだ。きわめて面白い、示唆するところ大の著作。

