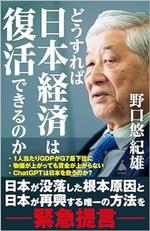 「日本経済は、今後さらに深刻な問題に直面する。長期的には高齢化が進行し、日本経済の成長にネガティブな影響を及ぼす。これに対応するため、外国人労働者の受け入れ拡大や新しい技術の開発が求められる。直近の問題としては、スタグフレーションの恐れがある。海外からインフレが輸入されるが、実質賃金は伸びないという『インフレと経済停滞の共存』だ」「本書では、これらの問題を『付加価値』という概念を中心に説明していく」「金融緩和を続けていれば、そのうち何とかなる、などという幻想を捨てることが必要だ。低金利と円安を続け、その上補助金をばらまいているだけでは、日本企業の体力はますます弱まる。こうした事態を防ぐため、新しい技術を積極的に取り入れることが必要だ(デジタル技術、生成AI)」と総合的に分析、提言をする。
「日本経済は、今後さらに深刻な問題に直面する。長期的には高齢化が進行し、日本経済の成長にネガティブな影響を及ぼす。これに対応するため、外国人労働者の受け入れ拡大や新しい技術の開発が求められる。直近の問題としては、スタグフレーションの恐れがある。海外からインフレが輸入されるが、実質賃金は伸びないという『インフレと経済停滞の共存』だ」「本書では、これらの問題を『付加価値』という概念を中心に説明していく」「金融緩和を続けていれば、そのうち何とかなる、などという幻想を捨てることが必要だ。低金利と円安を続け、その上補助金をばらまいているだけでは、日本企業の体力はますます弱まる。こうした事態を防ぐため、新しい技術を積極的に取り入れることが必要だ(デジタル技術、生成AI)」と総合的に分析、提言をする。
「日本の地位低下の原因は円安。円安に安住して、改革の努力を怠った」「金融緩和と円安政策を進めたことが、日本企業の技術革新力を喪失させた。技術開発力の衰退が日本衰退の最大の原因。日本銀行はそう思わないだろうが」「問題が生じれば、すぐ補助金を出すが(ばらまき政策)、何の役にも立たず、企業が補助金に依存する体質を作り出し、企業を弱くしている」「時価総額の世界のトップ100社に入るのはトヨタだけ。100社の中で『テック』が25社、医薬品産業が12社もあるが、日本は遅れている。新しい資本主義とはハイテク産業の事だ。アメリカでは、企業の新陳代謝が起きている」・・・・・・。
「成長を牽引してきた日本の製造業だが、就業者が減り(中国の工業化などで打撃)、人減らしで維持しただけで、技術開発やビジネスモデルの改革は行ってこなかった」「賃金は労使交渉で決まるのではない。賃金が上がらないのは付加価値が増加しないから。賃金は労働の存在量、資本量、技術進歩で決まる」「産業別・規模別の賃金格差をもたらすのは、分配率でなく資本装備率の差」「小規模企業や対人サービス業の賃金が上がらないのは、生産性(一人当たりの付加価値)が低いからであり、それは資本装備率が低いからだ」「2000年以降、医療・福祉を除けば、日本の産業構造はほぼ固定化してしまっており、産業構造の転換が進まず、構造や政策が製造業中心の時代から変わっていない。アメリカでは、IT企業が急成長、大きな構造変化が起きた」・・・・・・。
「貿易収支が20兆円の赤字に。赤字拡大の直接の原因は、資源価格高騰と円安」「スタグフレーションの恐れがある。物価引き下げによる実質賃金の引き上げを目標とすべきだ」「今後、高齢化の進行に伴って、社会保険の財政自体がひっ迫するので、少子化対策で社会保険料率の引き上げは筋違いだ。法人税の増税を検討すべきだ。増大する社会保障費を賄うためには、消費税率引き上げが必要」と言う。
「異次元金融緩和は物価上昇を目標にしたが、マネーストックは増えず失敗した。円安への安易な依存が企業の活力を奪い、円安政策から脱却できなくなった」「過剰な金融緩和の是正が日銀新体制の課題」「マイナンバーカード『迷走』曲ーー健康保険証を廃止していいことがあるのか。利用者の利便ではなく、カード普及だけが目的となっている。マイナンバーの利用範囲拡大のポイントは預金口座」「この問題は、結局のところ、国民が国を信頼するかどうかにかかっている」・・・・・・。
「日本経済衰退の原因は、IT革命に対応できなかったこと」「デジタル化投資こそ、日本が目指すべき道」「生成AIの登場という大変化が生じている。ChatGPTの基礎になっているトランスフォーマー技術の成長に見るアメリカの強さ」・・・・・・。
低金利と円安を続け、補助金をばらまいているだけでは、日本の企業は体力をますます落とす。新しい技術を積極的に取り入れ、日本を再興せよ、と言う。
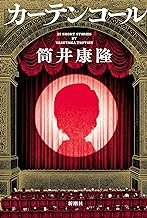 「これが最後の作品集になるだろう」と言う巨匠・筒井康隆さんの最近の25編を集めた作品集。いずれも8ページ程度と短い。しかしキレは抜群で鮮やか。右に左に、上下にぶん回される。極めて面白い。
「これが最後の作品集になるだろう」と言う巨匠・筒井康隆さんの最近の25編を集めた作品集。いずれも8ページ程度と短い。しかしキレは抜群で鮮やか。右に左に、上下にぶん回される。極めて面白い。
最初の「深夜便」や「花魁櫛」――男と女。シャレが効いていて絶妙。男は鈍、女は不可思議。
「白蛇姫」や「コロナ追分」――ブラック・ユーモアの中の普通では言えないギャグ、不謹慎パロディー。巻き込まれて、ひどい替え歌をつい歌ってしまう。日本はどうなったの、そんな世界へ連れていかれる。最後の「附・山号寺号」も凄まじい。やばい現実を突きつけられもする。
息子さんの死に触れている「川のほとり」は寂しさや優しさが迫ってくる。「羆」――今年は人里に熊が出るが、こんな生き生きとした表現の童話だったら、映像にはるかに勝る。「楽屋控」や「プレイバック」ーー自分自身の事だから、人や物の本質を鋭角的に捉えてグサっとくる。「美食禍」――飽食の時代を時間軸を逆転させて切る。「離婚熱」――男には、一様に離婚熱というものがあって、なぜだかそうした実害のない不満だけで、離婚したくてしかたがなくなる時期がある。それはもう離婚熱としか言いようがない、灼けつくような離婚願望なんですよ。
「手を振る娘」――短編なのに、その世界を作り上げる見事さ。「最初におれを見たとき、なんで手なんか振ったんだろうね」。その店主の答え絶妙。「夜来香」――戦争が終わる上海の繁華街の喧騒の中にある孤独や寂しさと、「夜来香」の歌声。「塩昆布まだか」――100歳夫婦、こんななるなぁ!
「プレイバック」も「カーテンコール」も名だたる役者総出演。みんな生き生きと生きている。
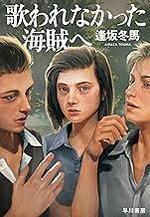 1944年から1945年戦争終結に至るドイツ――。ナチ体制下におけるエーデルヴァイス海賊団の少年少女は、いかなる思いを持って戦ったか。そして大人たちは・・・・・・。極限状況に追い込まれた時、人は何を考え生きようとするのか。政治的レジスタンスを超え、人間存在次元から問いかける魂を鷲掴みにする感動的作品。
1944年から1945年戦争終結に至るドイツ――。ナチ体制下におけるエーデルヴァイス海賊団の少年少女は、いかなる思いを持って戦ったか。そして大人たちは・・・・・・。極限状況に追い込まれた時、人は何を考え生きようとするのか。政治的レジスタンスを超え、人間存在次元から問いかける魂を鷲掴みにする感動的作品。
追いつめられ、残虐、過酷な統制を敷くヒトラー体制下のドイツ。父を処刑され居場所をなくしていた少年ヴェルナーは、ヒトラー・ユーゲントに戦いを挑むエーデルヴァイス海賊団を名乗る少年少女に出会う。町の名士の息子・レオンハルト、武装親衛隊将校の娘・エルフリーデ。その後加わる爆弾を愛好する少年・ドクトル。彼らは、愛国心を煽り、徹底した統制を図り、自由を奪い、密告を横行させ、ユダヤ弾圧を強行する体制に反抗する行動をとる。やがてヴェルナーたちは市内に建設されたレールの先に何があるかという不審を抱く。大人たちは車両を整備する操車場だと言い張り、口を閉ざす。ヴェルナーらは線路をたどる行動に出る。そこで強制収容所を発見、監視兵に足蹴にされる囚人たちがロケット兵器などを生産している死と強制労働の現場を目撃する。そこに着く貨物列車からは囚人服を着せられた人たちとともに、死体が異臭を放っていた。地獄絵図を見たのだ。衝撃を受けた彼らだが、やがてドクトルが見つけてきた巨大な長延期爆弾で、線路のトンネルと橋梁を爆破する計画を立てるが・・・・・・。
少年少女の純粋な感性と、したたかとも欺瞞ともいえる大人の生き方を対比。過酷な戦乱の中での「歌」という文化の力。この2つが鋭角的に絡み合って最後の1ページまで緊迫した展開が、ぐいぐいと胸に迫ってくる。ハンナ・アーレントのアドルフ・アイヒマンの「悪の凡庸さ」がまず想起させられる。ヴェルナーは、「(大人たちは)あそこに強制収容所があり、人が殺されていることもうすうす気づいている。でも、だからこそ、気づくことを恐れている。他の誰かに嘘だと言われて、喜んで騙されていく」と思い、エルフリーデは、「私たちは何も見なかった、私たちは何も聞かなかった、私たちは、ただ自分たちが生きられるよう精一杯頑張っただけ。そうやって、他人をごまかして、自分をごまかして、本当の自分に向き合うのを避けて一生を送ることになる。私は嫌だ、私は見た、私は聞いた、私は人の焼ける臭いを嗅いだんだ。その責任を果たす」と叫ぶ。しかしシェーラー少尉は、「およそ青年は、道を踏み外しやすく、己の中の衝動によって人生を誤るものだ。けれども、戦争は、人を正しい道を歩ませてくれる」と戦争を合目的的に論理づけ、女性教師のアマーリエは、「ヴェルナー。自分が反体制的な人間だと考えているのなら、それを表に出すのは、もう少し後でもいいと思うのよ。私がそうであるように。どのみちもうすぐ、この戦争は負けて終わる」と言う。大人のおぞましい姿に、少年少女は吐き気がこみ上げてくるのだ。「爆破するしかない。俺たちが本物の人間であるために。そのためなら命などは惜しくない」と、ナチを憎み、エーデルヴァイス海賊団という居場所に居心地の良さを覚えるのだった。それはまた、政治的レジスタンスとは違い、「自分たちはただ、愉快に生きようと思っていただけで、あそこに強制収容所があることが気に入らなかっただけなのに」とヴェルナーは述懐する。それが"筋金入りのレジスタンス"ではなく、エーデルヴァイス海賊団だったのだ。さらに政治的支援がかき消され、処刑に追い込まれたレオンハルトが「武器や弾薬で戦うのはもう無理だ。だから市民に呼びかけて、ここを包囲してくれ。そして僕らの歌を歌ってくれ。それで僕を助けるんだ」「敵と味方の区別を無効化して、歌の下に人を集めることができる。文化の力で僕を助けてくれ。文化が、野蛮に勝つところを見せつけてくれ」と叫ぶ。ナチは、そして戦争は、ファシズムは、文化をなぎ倒す。野蛮に対し、文化の力で、まっとうな人間力で勝利する。「歌われなかった海賊へ」の表題は、武器袋弾薬ではない戦う力が、文化であることを少年少女の戦いに託して訴えている。強烈なボディーブローだ。力感と精神性のみなぎる作品。
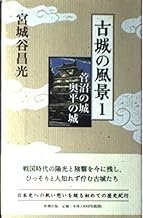 2004年の発刊。「菅沼の城 奥平の城」が副題。「戦国時代の陽光と陰翳を今に残し、ひっそりと人知れず佇む古城たち」「日本史への熱い想いを綴る初めての歴史紀行」と帯にあるが、著者と私の故郷でもある東三河の城を中心にした歴史が描かれている。小学校1年生の時に校庭となっていた新城城のお堀にグラジオラスを植えたことを今でもはっきり覚えている。
2004年の発刊。「菅沼の城 奥平の城」が副題。「戦国時代の陽光と陰翳を今に残し、ひっそりと人知れず佇む古城たち」「日本史への熱い想いを綴る初めての歴史紀行」と帯にあるが、著者と私の故郷でもある東三河の城を中心にした歴史が描かれている。小学校1年生の時に校庭となっていた新城城のお堀にグラジオラスを植えたことを今でもはっきり覚えている。
飯田線に野田城という駅があった。元亀3年(1572)12月、三方原で家康軍を破った武田信玄は翌年、宇利峠を越えて2万以上の大軍で菅沼定盈が籠る野田城を攻めた。守るはわずか400余人。徳川信康(岡崎城主)を誘い出す手もあり、織田信長との決戦を三河でするための兵站としての野田城を取っておきたいと信玄は思ったのではないかと言う。しかし野田城は1ヵ月も持ちこたえた。信玄にとって最後の戦いとなったのだ。私の生まれたのは新城で、新城小学校が新城城址だ。全国を見ても、堂々とした城門を今なおもっている小学校は他にないのではないか。築城したといわれる奥平信昌は、天正3年(1575)の長篠城を守り抜いた城主であり、家康の長女・亀姫が嫁いだことでも名高いが、家康は「長篠城では、みすぼらしい」と思い、新たな城を築かせたのではないかと言う。信昌と亀姫の間には4男1女が生まれ、宇都宮10万石、姫路18万石などを領したというが、亀姫の威力であったようだ。奥平氏の本拠は、今の群馬県吉井町にあるようで、それがやがて三河の作手に移ったという。今橋城(吉田城)を築いたのは牧野古白。今川の家臣である牧野一家は牛久保あたりに住んでいたが、永正2年(1505)に今川氏親から三河の国に新城を築き治めよと言われ、牧野古白が今橋城を築いた。
この東三河の地は、今川、岡崎の松平、渥美の戸田、さらには武田など、激しい攻防の中に常にあった。やがて徳川の時代になって、この地の者が全国に遣わされ、重大な任を負うことになる。
 世界最高峰の文学作品である「源氏物語」を著した紫式部と、日本史上最高の権力を長期間にわたって保持した藤原道長とのリアルな生涯を、確実な一時資料のみによって時系列的に復元する。確実な一次資料ということは、「後世に『紫式部』と称される女性の正式な呼称は『藤原為時の女』であり、本名は不明」「藤原彰子に女房として出仕した後は、おそらくは『藤式部』という女房名で呼ばれたものと思うが、(「栄花物語」「兼盛集」「河海抄」)、諱は彰子や朋輩の女房たちも知らなかったのではなかろうか」など厳密に読み解く。
世界最高峰の文学作品である「源氏物語」を著した紫式部と、日本史上最高の権力を長期間にわたって保持した藤原道長とのリアルな生涯を、確実な一時資料のみによって時系列的に復元する。確実な一次資料ということは、「後世に『紫式部』と称される女性の正式な呼称は『藤原為時の女』であり、本名は不明」「藤原彰子に女房として出仕した後は、おそらくは『藤式部』という女房名で呼ばれたものと思うが、(「栄花物語」「兼盛集」「河海抄」)、諱は彰子や朋輩の女房たちも知らなかったのではなかろうか」など厳密に読み解く。
「紫式部は、道長の援助と後援がなければ『源氏物語』も『紫式部日記』も書けなかったのであるし、道長は紫式部の『源氏物語』執筆がなければ、一条天皇を中宮彰子の許に引き留められなかったのである。道長家の栄華も、紫式部と『源氏物語』の賜物であると言えよう」「その意味では、『道長なくして紫式部なし、紫式部なくして道長なし』ということになる」と語る。本書を読めば、そのことが鮮明にわかる。
平安宮廷の権力闘争、摂関をめぐる争いは凄まじい。まず道長にとって一条天皇を産んだ姉の詮子の存在は大きかった。花山天皇が986年、出家入道し7歳の一条天皇が即位する。そして道長は宇多天皇の三世孫・倫子と結婚。倫子は永延2年(988)に彰子(後に一条天皇中宮)、正暦3年(992)に頼通(後に摂政・関白)、正暦5年(994)に姸子(後に三条天皇中宮)、長徳2年(996)に教通(後に関白)、長保元年(999)に威子(後に後一条天皇中宮)、寛弘4年(1007) に嬉子(後に敦良親王妃)と、2男4女を出産。激しい権力闘争の中で、女子を入内させ、揺るがない摂関政治を築いていくことになる。疫病による兄の関白藤原道隆、それを継いだ兄の藤原の道兼の連続死により、長徳元年(995)に道長はいきなり政権の座に就く。一条天皇生母の詮子の意向が強く働いたと言う。しかし一条天皇の定子への寵愛が深く、彰子も成人に達しておらず、道長と一条天皇との微妙な関係が始まっていく。やがて定子は皇后、彰子は中宮になる。そこに「源氏物語」がある。「『源氏物語』という物語は、初めから道長に執筆を依頼され、料紙などの提供を受け、基本的骨格についての見通しをつけて起筆したものと推定される。道長の目的が、この物語を一条天皇に見せること、そしてそれを彰子への寵愛につなげるつもりであったことは言うまでもなかろう」と解説する。紫式部が彰子の許にいつ出仕したかは明らかでないようだが、寛弘3年(1006)だと言う。源氏物語は、それ以前に書き始められていたようだ。
「定子サロンと全く違う彰子サロン」――「清少納言を非難し、定子が遺した敦康への皇位継承を拒絶し、『枕草子』で謳歌されている定子サロンを否定することは、紫式部から知らず知らずににじみ出た政治的感覚であり、また彰子後宮の雰囲気でもあったのであろう」と言っている。極めて面白い。
寛弘8年(1011)、25年にわたった一条天皇が死去、三条天皇の時代となるが、道長と三条天皇の確執が始まる。皇統が違いもあるが、道長は姸子を中宮にさせる。2人の関係が悪化し、皇太后となった彰子の政治的役割は増加し、三条が頼りとした「賢人右府」藤原実資が、彰子との取り次ぎ役として紫式部を使った。実資と紫式部は「よほどの信頼関係」と言う。知識人同士という面もあったのだろうか。長和5年(1016)、三条天皇が譲位して後一条天皇が即位し、道長は権力の頂点に立つ。道長の望月の世だ。「『源氏物語』の後宮世界、特に冷泉帝の後宮をめぐる『源氏物語』の記述は摂関期の政治史を貫く後宮原理をあまりにも鮮やかに描いている」と言う。凄まじい権力闘争のドラマと、「『源氏物語』以降、この国、いや世界はこれほどの文学作品を生み出してはいないのだし、道長以降、日本ではこれほどの権力を持った政権担当者は現れなかった」――。確かにその通りだ。それを凝縮した濃密な著作。

