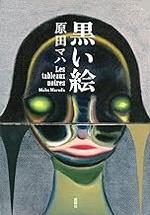 原田マハの6つの短編集。2007~2008年が4編、2022~ 2023年が2編。著者が「ようやく封印を解いて世に出す"ノワール"小説集」と言い、帯には「アートの暗部を炙り出す禁断の小説集」「禁じられた遊び、爛れたエロス、閃く殺意」とある。「これまでの原田マハさんとは違う」と言う声があるようだが、芸術において人間の始原的な愛や性欲や夢幻の世界が狂気となって噴出するのは至極当然のことであろう。「リボルバー」「風神雷神」「たゆたえども沈まず」に書かれたゴッホやゴーギャン、日本の名だたる絵師を見れば、生々しい人間の狂気を見ざるを得ない。
原田マハの6つの短編集。2007~2008年が4編、2022~ 2023年が2編。著者が「ようやく封印を解いて世に出す"ノワール"小説集」と言い、帯には「アートの暗部を炙り出す禁断の小説集」「禁じられた遊び、爛れたエロス、閃く殺意」とある。「これまでの原田マハさんとは違う」と言う声があるようだが、芸術において人間の始原的な愛や性欲や夢幻の世界が狂気となって噴出するのは至極当然のことであろう。「リボルバー」「風神雷神」「たゆたえども沈まず」に書かれたゴッホやゴーギャン、日本の名だたる絵師を見れば、生々しい人間の狂気を見ざるを得ない。
「深海魚」――高校生の瀬川真央は友達も彼氏もいない。学校ではひどいいじめに遭っていた。そんな真央がいつも逃げ込めるのは押し入れで「海の底」。そこで見る夢はたまらなく淫靡で、流花との禁じられた遊びが・・・・・・。
「楽園の破片」――ボストン美術館の講演会でスピーチをする予定の高木響子は、乗った急行列車が遅れて焦る。もうひとりのスピーカーのレイとは7年間の不倫関係があった。・・・・・・「ゴーギャンは、タヒチに永住する気はなかった。楽園だったからだ。対極にある現実があってこそ、楽園は楽園たりうる。現実と楽園を行き来する危ういボートに、ゴーギャンはカンヴァスと筆とイーゼルとを持ち込んだ。彼は楽園に安住できなかったのだ」「私たちは楽園に似たもの、あるいはその破片を生涯大切にして、憧れ続ける運命なのだ」・・・・・・。
「指」――東京にある私大の日本美術史博士課程2年の私は、家庭を持つ彼の研究室で助手をしている。5月のある週末に室生寺に来て、釈迦如来坐像の端麗で清らかな指を共に見る。「だから・・・・・・中指で、触って欲しいの」・・・・・・。
「キアーラ」――神戸の大学で教鞭を執る修復家の亜季。1997年9月のイタリアの大地震で、アッシジの聖人フランチェスコの遺体が眠る聖フランチェスコ大聖堂の天井のフレスコ画が崩れ落ちた。亜季は呼ばれて修復作業を行うことになるが・・・・・・。
「オフィーリア」――芥川龍之介の「地獄変」をもとにして、絵の中に閉じ込められたオフィーリアから見た世界。日本の画家の家に運ばれた「オフィーリア」は成金男のおぞましい姿や浮気現場を見る。・・・・・・「静かに沈んでゆく。悲しく、残酷な、これ以上ないほど美しい瀕死の瞬間」「それはすなわち、絵にすること。絵の中に閉じ込め、永遠を生きさせること」・・・・・・。
「向日葵奇譚」――超売れっ子で演技に定評がある役者・山埜祥哉の舞台の脚本を手がける塚本。狂気と悲劇の画家ゴッホを主人公に描こうとする。そこに1枚の奇妙な写真に出会う。後ろ姿のゴッホの写真を見ると、狂気や天才ではないゴッホが見えてきて、塚本は脚本を一晩で書き直す。
いつもの原田マハの世界と違っている――そうは全く思えない。
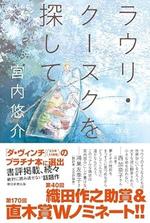 1977年に生まれた4人の少年少女はどう生きたか。舞台は、バルト三国の中で最も北側のエストニア。ソビエトの中にあり、生活は厳しかったが、ゴルバチョフのペレストロイカ、エリツィンの台頭、ソ連崩壊、エストニア独立・・・・・・。エストニア独立は1991年、ラウリ達が14歳の時だ。国家とは、民族とは。国家そのものの激震のなか少年少女はどう生きたのか。それを実に清々しいほどの透明感に満ちて淡々と、夢と挫折と友情を描く感動作。しかも今の世界に先駆けたデジタル国家への変貌を絡めた立体感ある作品だ。
1977年に生まれた4人の少年少女はどう生きたか。舞台は、バルト三国の中で最も北側のエストニア。ソビエトの中にあり、生活は厳しかったが、ゴルバチョフのペレストロイカ、エリツィンの台頭、ソ連崩壊、エストニア独立・・・・・・。エストニア独立は1991年、ラウリ達が14歳の時だ。国家とは、民族とは。国家そのものの激震のなか少年少女はどう生きたのか。それを実に清々しいほどの透明感に満ちて淡々と、夢と挫折と友情を描く感動作。しかも今の世界に先駆けたデジタル国家への変貌を絡めた立体感ある作品だ。
ラウリ・クースク――父が持ち込んだ電子計算機に興味を持ち、6歳にしてプログラムを完成させ、ロシア語を学んでやがて、ロシアの大学に行く希望をもっている。父はシベリアに送られたことがありロシアが大嫌い。
イヴァン――レニングラード出身で中学からのラウリの同級生、プログラミングの天才。カーテャ――中学からラウリの同級生の女性でパルチザンの孫娘。この3人がとても親しく友情を持ち互いにプログラミングを競う。そしてアーロンという小学校からの同級生でラウリをいじめる奴が交差する。さぁ、国家の激動にさらされた3人はどうなったか。そして、アーロンは・・・・・・。違う国になったイヴァンは・・・・・・。
1919年、ベルリンの壁崩壊。嬉しくないのかとカーテャに問われ、憂鬱を感じているラウリは答える。「国をまたいでイヴァンに出会えたのはソビエトがあるおかげだし、情報科学を学べるのもそう。将来はモスクワへ行きたいし、体制が崩れるかもしれないっていう想像は、僕には怖いよ」「(おじさんがぽそりと言う)俺たちの国から出て行け」「寮への帰り道、カーテャがラウリの手を握った。反対の手をイヴァンが握った」・・・・・・。しかし、ソビエトの政変、エストニアの独立運動は3人を切り裂いていく。そしてソ連の「黒ベレー」がエストニアにも侵入しようとする動きになる(1991年1月12日、リトアニアの「血の日曜日」事件)。3人は引き裂かれバラバラの動きになってしまう。
数年後、プログラミングの道から離れたラウリのもとに、少年の頃に接したライライ(タルトゥ大学教授)が会いに来る。「この国はまだまだだけれど、近い将来、情報通信技術の国に生まれ変わる。でも現状では人材が足りない。あなたみたいに、呼吸するようにプログラムをかける人を私たちは必要としている」と、学校でのインターネット環境整備やマイナンバーカードやインターネット投票の実現を目指すと言い、さらに「国とは領土ではなくデータであると考える。占領されても国と国民のデータは維持できる。わたしたちは情報空間に不死をつくる」と誘うのだった。
「わたしたちは独立回復にあたり、それぞれにアイデンティティーを選び直した。ラトヴィアはバルトというアイデンティティーにこだわりました。リトアニアは、北欧、バルト、中東欧をつなぐ、文明の十字路のような役割。わたしたちエストニア人は、フィンランドに近いこともあってか、北欧の一員としてのアイデンティティーを選択しました」「エストニアは、占領時代から職人たちが質の高いデザインを生み出して、"ソビエトのなかのヨーロッパ"と称されてきました」・・・・・・。国の崩壊、国家の独立、民族としてのアイデンティティーと誇りが相乱れるなか、「裏切り者」「出て行け」の怨讐のなか、3人の絆を温かく優しく描き切る。そしてサイバー攻撃やコンピューター犯罪、ブロックチェーン、暗号資産、ロシアのウクライナ侵攻など今日的課題についても描いている。
親友と会う。理由はいらない。「話題なんかなくたっていい。2人で空でも見てればいいのさ」「この国で、光のある道を生きろとは言えない。だから、せめて、お前さんはまっすぐ、したたかに生きてくれよ。まっすぐ、したたかに」・・・・・・。国家の嵐の中でも、上品で情のしみ通った作品。
 誰でも微分・積分を学んだが、また誰でもあれはどう役立ったのかと思うのも事実だ。「私以上に微分・積分を語れる人はいない」と言う著者が、数式を使わず、図やイラストを中心に解説する。微分積分は、「未来予測の数学」であり、「物事が今後どうなるのかを計算によって導き出すこと」「未来のために、今やるべきことをはっきりさせること」という役割をもつと言う。
誰でも微分・積分を学んだが、また誰でもあれはどう役立ったのかと思うのも事実だ。「私以上に微分・積分を語れる人はいない」と言う著者が、数式を使わず、図やイラストを中心に解説する。微分積分は、「未来予測の数学」であり、「物事が今後どうなるのかを計算によって導き出すこと」「未来のために、今やるべきことをはっきりさせること」という役割をもつと言う。
微分は「微小に分けることで、計算を簡単にする」、積分は「分けて計算したものを積み重ねて元に戻す」ものだ。積分は、紀元前5000年ごろから始まった古代エジプト文明で、ナイル川の水位を確認する「ナイロメーター」に原型が見て取れる。古代ギリシャで生まれた「取りつくし法」から「長方形でグラフを埋め尽くして面積を求める」積分の考え方が生まれ発展した。積分の正体とは「グラフの面積を求める計算」だった。微分は砲弾の軌道を正確に知りたいという戦争と大砲から生まれた数学で、16、17世紀ごろ始まる。グラフの接線を求める計算、グラフの傾きを求めることだ。微分と積分は、お互いに逆向きの計算になっている「微積分学の基本定理」だ。
現代社会で、天気予報、人口予測、放射性物質の放射線量予測、飛行機の空気抵抗・揚力計算、道路のクロソイド曲線、ロケットの推進方向や速度のコントロール、コロナなど感染症の広がりの予測、日々変動する株価の予測などあらゆる場面で使われていることを紹介している。現代社会を支えている微分・積分であることがよくわかる。ちなみに天文学者・ケプラーは、酒樽に入ったワインの量を測ろうとして、積分という世紀の大発見に至ったと言う。
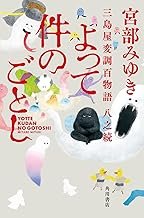 「青瓜不動」の1年前の「三島屋変調百物語八之続」。「賽子と虻」「土鍋女房」「よって件のごとし」の三話。江戸の袋物屋・三島屋の黒白の間で、人を招き、「語って語り捨て、聞いて聞き捨てる」百物語。主人の伊兵衛が酔狂で始め、最初の聞き手は姪のおちか、今は次男の小旦那・富次郎が引き継いでいる。
「青瓜不動」の1年前の「三島屋変調百物語八之続」。「賽子と虻」「土鍋女房」「よって件のごとし」の三話。江戸の袋物屋・三島屋の黒白の間で、人を招き、「語って語り捨て、聞いて聞き捨てる」百物語。主人の伊兵衛が酔狂で始め、最初の聞き手は姪のおちか、今は次男の小旦那・富次郎が引き継いでいる。
「賽子と虻」――。餅太郎の故郷は上州宇月藩の畑間村。母ちゃんが死んで、父、兄、姉との貧しい家だが、働き者で仲良しだった。自慢の姉が大きな商家かの一人息子に見初められ嫁になることになった。ところが誰かに恨まれて呪いをかけられる「虻の呪い」で生死を彷徨うことになる。姉を救うために"呪いの大虻"を餅太郎は飲み込み意識を失う。気づくと、さらわれた先の旅籠の里は神々が集う賭場で、餅太郎は下働きをすることになる。そこでも義侠心をふるい、燕の神を命がけで助けようとする。この土地には「ろくめん様」という土地神様がいて、鳥にも虫にも穀物にも神様があり、人はその加護を必要としていたのだ。苦しいことばかりの「11の時に笑い方を忘れました」と言う餅太郎の驚くべき話とは・・・・・・。
「土鍋女房」――。兄の喜代丸は渡し船を操っている渡し守。三笠の渡しは粂川の河口にあって、さらに下流では海苔の養殖が盛ん。三島屋に来たのは、その妹おとび。おとびが言うには、喜代丸にたいそう良い縁談があるのに、頑として受け付けない。家に持ち込まれた土鍋があって、その中に女がいて、喜代丸と夜な夜な話し合っている恐ろしい光景を見る。それはどうも粂川の水神様のようで・・・・・・。
「よって件のごとし」――あまりに信じ難く、恐ろしい途方もないことの次第をお城に送る申立書をしたためる際、文書の締めくくり「よって件のごとし」の文の上に汗が滴り筆先が震えたと言う。それほど恐ろしい出来事が語られる。語ったのは浅川真吾と妻・花代。浅川家は奥州久崎藩の2つの村を束ねる肝煎りで、中ノ村に住む。立冬の朝、浅川家の屋敷のすぐ裏手にある凍った夜見ノ池から土左衛門が浮かび上がる。白濁した目、よだれをたらした面妖な土左衛門は死んでるどころか、人に噛み付く"ひとでなし"と呼ぶ化け物。噛まれたらそのものがまた化け物の"ひとでなし"になる。池の向こうには奥州江崎藩南部の貧しい羽入田村があり、黄泉ノ池があった。ここでは、5年から10年に1度は"ひとでなし"が次から次といっぺんに増大する大変な厄禍があった。そこから逃れてきた若い娘の花江(後の花代)から話を聞き、浅川宗右衛門(真吾の父)ら中ノ村の者たちが池に潜って羽入田村に乗り込み化け物退治に奮戦する。そこで地の底の深いところに棲んでいる醜くて臭いけだもの「腐れ鬼」とも戦う。この化け物に噛まれたものが"ひとでなし"と化すのだ。激しい戦いにの果てに勝つのだが・・・・・・。コロナ禍と異常気象の中で書かれた小説なのか、江戸時代以前は怪異、災害、疫病、死、神仏が生活そのものに密着していたことを改めて思う。とにかく恐ろしい話。富次郎はあまりの展開にどう絵を描くか悩む。おちかの出産が近い。
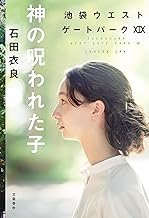 「池袋ウエストゲートパークXIX」――。次々と変貌する社会。その現場で出てくる新たな事件。マコトとタカシが痛快に解決するシリーズ第19弾。私にとってなじみの大塚、池袋、常盤台などが出て来て実感が増す。
「池袋ウエストゲートパークXIX」――。次々と変貌する社会。その現場で出てくる新たな事件。マコトとタカシが痛快に解決するシリーズ第19弾。私にとってなじみの大塚、池袋、常盤台などが出て来て実感が増す。
「大塚ウヰスキーバブル」――。JR大塚駅南口の商店街にあるお気に入りバーに来たマコト。そこに来た半グレ風の男は、国産のヴィンテージウイスキーを買い漁っているウイスキーバイヤー。なんと今はウイスキーバブル。響の30年物は今では100万円だという。バーの親父はなんと1本8000万という高値のついたウィスキーを持っており、脅しをかけられていた。
「<私生(サセン)>流出」――。推し活ブームのなか、私生活を追い回し過激な推し活をする危険なファンの私生(サセン)。芸能事務所の女社長から2人の悪質な私生に手を焼いていると相談を受ける。
「フェイスタトゥーの男」――。板橋区、豊島区、練馬区で三件立て続けに発生した連続強盗団。一日あるいはほんの2、3時間で100万もゲットする闇サイトの高額バイトに小心の若者が巻き込まれ、あげくに監禁される。タカシの腕が冴えわたる。
「神の呪われた子」――。神自身の生まれ変わりという天国の木教会。教祖は54歳。本や会費、高額有料イベントなどで金を集める上に、17、18歳の女性を妃候補として選抜するやりたい放題。宗教2世の切羽詰まった声をマコトが聞き立ち上がる。

