 「橋」にまつわる10の短篇集。「駅」については世界の小説、映画などで名作が多い。人の出会いと別れのドラマとなる場であるからだ。江戸時代、「橋」はまさに出会いと約束と別れの象徴的な場となっていた。
「橋」にまつわる10の短篇集。「駅」については世界の小説、映画などで名作が多い。人の出会いと別れのドラマとなる場であるからだ。江戸時代、「橋」はまさに出会いと約束と別れの象徴的な場となっていた。
このたび、「橋ものがたり」の中の冒頭にある傑作「約束」が、杉田成道監督・脚本によって映像化された。人の心の美しさ、橋や風景の何とも言えぬ映像美に心を洗われ涙した。藤沢周平の原作と脚本と映像を観て、芸術の素晴らしさを改めて感じた。
錺職人のもとに奉公していた幸助は、8年の年季がやっと明け、帰ることになった。幸助とお蝶は幼馴染み。「わたし・・・・・・幸ちゃんの、お嫁さんになる」と皆んなの前で言ったほどの仲。5年前、二人は年季が明けるその日、刻は暮六ツに、萬年橋で会う約束をしていた。しかし、互いに強く想いながらも、幸助には人に言えない秘密があり、お蝶にも辛い身の上の変化があった。そして約束の橋の上で・・・・・・。「できるさ。二人とも少しばかり、大人の苦労を味わったということなんだ」「お蝶が泣く声は、真直幸助の胸の中に流れこんでくる。幸助は自分も少し涙ぐみ、長い別れ別れの旅が、いま終ったのだ、と思った」。とても良い。
「小ぬか雨」「小さな橋で」「吹く風は秋」はこれまでに映像化されている。「小ぬか雨」――娘らしい華やかな思い出もないまま育ったおすみは、一人住まいをしている。下駄職人の勝蔵との縁談も決まっていたが、野卑な男で好ましい男ではなかった。ある夜、おすみの家に、若い男が「喧嘩をして追われているのでかくまってほしい」と駆け込んでくる。男は女を殺して追われているという。・・・・・・「もっと早く、あんたのような人に会っていればよかった。そうじゃなかったから、こんな馬鹿なことになってしまった」と若い男・ 新七は言う。・・・・・・「行ってしまった。新七が残していった傘を拾い上げ橋を戻りながら、おすみはそう思った。・・・・・・この橋を渡っててはならなかったのだ」。
「小さな橋で」――父が博打で姿を消し、姉も妻子持ちの男と駆け落ち、母は疲れ果て飲み屋の常連客の男にすがろうとする。十歳の少年・広次は嫌気がさしていたが、ある日、男に追われている父と偶然再会する。「吹く風は秋」――親分を裏切って、江戸を離れていた壺振り師の弥平は、老境に差し掛かり人生の区切りをつけようと、決死の覚悟で江戸への橋を渡る。そこでぼんやりと夕陽を眺めるおさよという女郎に出会う。なぜか心を惹かれた老博徒は・・・・・・。
「思い違い」「赤い夕日」「殺すな」などとても良い。「氷雨降る」「まぼろしの橋」「川霧」など、いずれも江戸の庶民の人情けが伝わってくる。
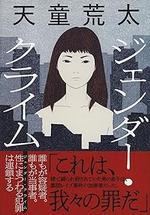 裸で縛られ、土手下に無残にも転がされた男性の殺人事件。その遺体には、「目には目を」というメッセージが残されていた。その男性・佐東正隆の息子・進人は、過去に集団レイプ事件の加害者だった。大学生四人が一人の女子大生をカラオケルームで酔わせて暴行、逮捕されたが、起訴は見送られた。加害者と被害者の間で示談が成立し、被害者が裁判所で証言しないというパターンだ。今回の猟奇殺人事件、集団レイプ事件と関係があるのか。恨みを買っているとしても、なぜ親が無残な姿で殺されるのか。捜査本部(帳場)が設置され、刑事で柔道の猛者の鞍岡直矢は、警視庁の切れ者・志波倫吏とコンビを組み、事件を探っていくことになる。世に晒され、今もなお苦しみ続けている被害女性とその家族。その兄・ 端本竜介が恨みから殺人を犯したのではないかと捜査は動き出すが・・・・・・。次々と現れる容疑者、そして明かされる被害者・加害者の関係者の悲しい過去や苦しみ。怒涛の広がりを見せて壮絶な新たな殺人へと傾れ込んでいく。このジェンダー・クライム(性にまつわる犯罪)の消し難く打ち続き、連鎖する苦しみの深さを描き出す力作。
裸で縛られ、土手下に無残にも転がされた男性の殺人事件。その遺体には、「目には目を」というメッセージが残されていた。その男性・佐東正隆の息子・進人は、過去に集団レイプ事件の加害者だった。大学生四人が一人の女子大生をカラオケルームで酔わせて暴行、逮捕されたが、起訴は見送られた。加害者と被害者の間で示談が成立し、被害者が裁判所で証言しないというパターンだ。今回の猟奇殺人事件、集団レイプ事件と関係があるのか。恨みを買っているとしても、なぜ親が無残な姿で殺されるのか。捜査本部(帳場)が設置され、刑事で柔道の猛者の鞍岡直矢は、警視庁の切れ者・志波倫吏とコンビを組み、事件を探っていくことになる。世に晒され、今もなお苦しみ続けている被害女性とその家族。その兄・ 端本竜介が恨みから殺人を犯したのではないかと捜査は動き出すが・・・・・・。次々と現れる容疑者、そして明かされる被害者・加害者の関係者の悲しい過去や苦しみ。怒涛の広がりを見せて壮絶な新たな殺人へと傾れ込んでいく。このジェンダー・クライム(性にまつわる犯罪)の消し難く打ち続き、連鎖する苦しみの深さを描き出す力作。
重層的なサスペンス小説であるとともに、主テーマは「ジェンダー・クライム(性にまつわる犯罪」。「性被害はまだ軽く見られている。それは『魂の殺人』であり、人の一生をダメにする」「被害に遭った女性は、家族までいわれなきバッシングを受け、住所や仕事先もネットでさらされて日本にいられない状況になる」「被害者のみならず、加害者自身やその家族の一生をも壊していく。世にさらされ、責められ続け・・・・・・」「私たちは無意識のうちに、女という性を軽く見てはいないか。たかがと思う心があるからではないか。一人の人間の人生を壊し、魂を殺すのも同然の、酷い犯罪が行われたのだと意識があれば・・・・・・。この国の根っこにある、我々の・・・・・・。我々の罪ですよ」と言う。また本書では、妻や子への虐待がいくつも出てくる。また、「奥さん」「ご主人」という言葉遣い、この社会に受け継がれてきた男女間の差別やジェンダーをめぐる旧来からの「男らしさ」「女らしさ」をめぐる課題をも提起している。さらに加害者の「だから・・・・・・もう、俺のしたことを許せよ。もう許して欲しかった・・・・・・もう、終わりにして欲しかったんだ」という苦しさから逃れたい心情が語られる。親などから感情的に責められ続ける苦しさ、謝罪して区切りをつけたい複雑な心境が吐き出される。「謝罪」とは何か。重いテーマが問い続けられる小説。
 「明治国家と権力」が副題。明治国家で圧倒的な政治権力を有し、明治日本を"支配"した最高実力者の山県有朋(1838~1922)。その力の背景には長州閥陸軍や山県系官僚閥と明治天皇からの信頼があった。幕末から明治、大正の時代とリーダーを、山県に即して見ると極めて興味深い姿が見えてくる。
「明治国家と権力」が副題。明治国家で圧倒的な政治権力を有し、明治日本を"支配"した最高実力者の山県有朋(1838~1922)。その力の背景には長州閥陸軍や山県系官僚閥と明治天皇からの信頼があった。幕末から明治、大正の時代とリーダーを、山県に即して見ると極めて興味深い姿が見えてくる。
長州藩、松下村塾の尊王思想の中で育った山県有朋。久坂玄瑞、高杉晋作等の死後、勝海舟が長州藩の5指に数えた木戸孝允、広沢真臣、伊藤博文、井上馨、山県有朋らが台頭する。そして明治――陸軍卿・内相として、徴兵制・地方自治制を導入し体制の安定に尽力する。「西郷の悲劇的な運命に直面して、山県の近代軍建設への使命感はいっそう強まっていった。情念ではなく、法治国家の枠組みの中で駆動する軍隊、つまりは官僚制的軍隊の建設こそがこれからの日本には必要なのだという確信である」と言う。1877年10月、東京に凱旋した山県は広大な邸宅・椿山荘を拠点とする。西郷隆盛が横死し、木戸孝允が病没、大久保利通も凶刃に倒れ、政治の第一線に伊藤博文と山県、大隈重信が立つことになる。山県の軍事革命観は、「強兵あって初めて『国民の自由や権利』がある。軍事力の後ろ盾がなければ、経済成長もおぼつかない」という富国強兵論であり、対外膨張論とは一線を画すものであった。また自由民権運動が藩閥政府を専制政府とみなしている限り、板垣率いる自由党の人民武装論とは徹底対決する。
1889年、内閣総理大臣となる。首相として民党と対峙し、時に提携し、日清戦争では第一軍司令官として、日露戦争では参謀総長として陸軍を指揮した。その間に枢密院議長を務め、長州閥陸軍や山県系官僚閥を背景に、最有力の元老として、長期にわたり日本政治を動かした。激動する時代の中で、これほど長く政治の中枢にあり続け、ポピュリズムに堕すことなく突き進んだ生涯は驚嘆すべきものだ。苦渋の決断も日常であったであろう。日露戦争の決断、「この時、山県も伊藤もそして明治天皇も『懸崖に臨む』、すなわち、切り立った崖の淵に立って谷底を覗き込む心境であった」と描く。その頃からはまた長州の後輩、桂太郎や児玉源太郎との不和が顕著になってくる。「明治の終焉――1905~12年」「世界政策、デモクラシーとの対峙――1912~18年(大正政変、桂太郎の離反、山県系官僚閥の変容」などが描かれる。
「山県の権力基盤は官僚制(陸軍)にあった。山県は陸軍、議会(政党勢力)、内閣とのあいだで、巧みにバランスをとりながら、自らの政治権力を行使していった。敵対勢力は、当初は自由党、次いで、対外硬派や社会主義勢力だった。山県にとってそれは国家防衛そのものであり、敵対勢力はそれを『公私混淆』と非難した」「日露戦争までの山県の陸軍軍備拡張案は比較的抑制されていた」「現実外交では山県の意見は相当抑制的であった」「山県は大衆から超然としていたがゆえに、ポピュリズムとは無縁だった。そのため、対華21ヵ条要求のような露骨な帝国主義外交、あるいは革命外交と距離を置くことができた」と言う。
現在の世界を見るときに、「山県の死から100年を経て、彼は再び召喚されつつあるように見える」と結んでいる。「国の形」がいま大きく問われているからだ。
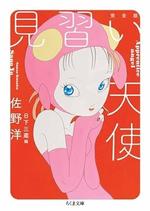 佐野洋さん(1928~2013年)の作家活動は55年、実にその間の短篇の総数は1200篇に及ぶ。そのなかで、「見習い天使」もの17篇と「見習い天使補遺」6篇の23篇を名作短篇集の完全版として復刊。よくぞここまで、鮮やかで、ユーモラスで、人間世界の小ずるさ、欲や業を描くかと、ついクスっと笑ってしまうショート・ミステリ。
佐野洋さん(1928~2013年)の作家活動は55年、実にその間の短篇の総数は1200篇に及ぶ。そのなかで、「見習い天使」もの17篇と「見習い天使補遺」6篇の23篇を名作短篇集の完全版として復刊。よくぞここまで、鮮やかで、ユーモラスで、人間世界の小ずるさ、欲や業を描くかと、ついクスっと笑ってしまうショート・ミステリ。
「意表をつくアイデア」「日常に溢れる夫婦や会社での感情のズレ」「小市民の抱く小欲・小願望」「人間につきまとう先入観の陥穽」「相次ぐどんでん返し」「鮮やかなオチの切れ味」「文章にしないで、読者に思考の時空を与える絶妙さ」・・・・・・。見事というほかない。
「三丁目の夕日」よりもちょっと後、昭和30年代の後半に差し掛かる頃の風景が目に浮かぶ。「楽しいテレビ」「いっぱいになっている駅の待合室」「おしゃべり好きなB ・ G」「スリにやられた手取り13万2千円ボーナス」「専業主婦が観る"よろめきドラマ"」「ピースと新生」「交通事故死の多さ」「浮気、誘惑、嫉妬――家族の縛りの強さ」「初めて見る10万円の札束」・・・・・・。もう死語となったものばかりだ。しかし懐かしい。
「誘拐犯人(人間の裏の裏まで作り上げている)」「モデル・ガン殺人事件(推理小説作家及ばぬ悪知恵の発達した人間というもの)」「最初の嫉妬(妻の嫉妬を見たかった夫)」「女の条件(使い込みをした男の寝言)」「大きな獲物(うまく仕掛けたつもりでやられた刑事)」「ご報参上(東京弁解コンサルタントを使った夫と妻)」「始めと終り(部長夫人とスリの名人)」――。いずれもどんでん返しに次ぐどんでん返し。鮮やかというほかない。
 ノンフィクション作家・佐々涼子さん初のエッセイ&ルポルタージュ作品集。この10年の作品から厳選したもの。心を揺さぶられ感動した。静かで丁寧に深く生と死を見つめる姿が心に沁みる。しかも、「あとがき」で佐々さんは今、悪性の脳腫瘍「グリオーマ」に罹り、「この病気の平均寿命は14か月といわれている」と言う。「グリオーマは『希少がん』と呼ばれているが、『希少』は、私には『希望』に見えてくる」「誰かが私を導き夜明けを照らしてくれるだろうか。・・・・・・そして遺された人たちには、その限りある幸せを思う存分、かみしめてほしいのだ」と言っている。
ノンフィクション作家・佐々涼子さん初のエッセイ&ルポルタージュ作品集。この10年の作品から厳選したもの。心を揺さぶられ感動した。静かで丁寧に深く生と死を見つめる姿が心に沁みる。しかも、「あとがき」で佐々さんは今、悪性の脳腫瘍「グリオーマ」に罹り、「この病気の平均寿命は14か月といわれている」と言う。「グリオーマは『希少がん』と呼ばれているが、『希少』は、私には『希望』に見えてくる」「誰かが私を導き夜明けを照らしてくれるだろうか。・・・・・・そして遺された人たちには、その限りある幸せを思う存分、かみしめてほしいのだ」と言っている。
さらに亡くなったお母さんは難病にかかり、「約10年間、母は24時間、父に介護され、下の世話をされ、入浴の介助をされて、人の手を借りながら生きてきた」と語り、「死」と、向き合いながら生きてきた。そして遺体や終末期医療等、多くの「死」を取材してきている。すべての取材に、描くエッセイに、生死の世界が現場から生々しく、しかも温かく、自身の実感を込めて開示される。開示悟入、明らかに観る諦観だ。「『長生きして幸せ』、『短いから不幸せ』、といった安易な考え方をやめて、寿命の長短を超えた『何か』であってほしい」「私たちは、その瞬間を生き、輝き、全力で愉しむのだ。そして満足をして帰っていく。・・・・・・だから、今日は私も次の約束をせず、こう言って別れることにしよう。『ああ、楽しかった』と」――そう言っているが、佐々さんの健康・長寿を心より祈るものである。
短いエッセイが続く。「『こんな私は嫌でしょう?』とお父さんに聞いたら、それでも生きていてほしいと言ったのよ(「死」が教えてくれること)」。「私は死に方を知らないが、きっと体は知っている。----だから命のことは体にゆだね、まかせていればいいのではないだろうか(体はぜんぶ知っている)」。「(アルコール依存症の治療で)こちらが無理やり直そうとするとたいてい失敗しますね。医師が治すんじゃないんです。まず本人が今のままではだめだと自覚しないと。・・・・・・依存症患者もある種の断念をくぐって、受容に至るのかもしれない。つまり一度『死ぬ』のだ(諦念のあと)」。「父は母の分まで幸せになろうと決めているのだろう。幸福でいるためには時に強い意志が必要だ(幸福への意志)」。「日本が実習生を安い労働力だと思っているなら、私はベトナムからの実習生はあと数年で来なくなると思うの。日本はどうなっちゃうんだろうって思うわ(ハノイの女たち)」。「終末医療の取材では亡くなりゆく人が、私にだけ胸の内を明かすこともあった。今ならわかる気がする。近くにいる人に言えば、その人にも苦しみを背負わせてしまう。・・・・・・街にはそういう距離の人がいる。飲み屋の店主、タクシーの運転手、かかりつけの医師に看護師・・・・・・(いつもの美容師さん)」。日本経済新聞の連載が多いが、確かに、なるほどと思うばかりだ。
「片方の手ぶくろたち」「誰にもわからない」では、「どうか、目の前にいる人を大切にしてほしい」「いくら自分の外側を探しても答えは見つからない。自分の内側に戻って自分なりの生き方を見つけよう。今を生きなさい。自分の内側に戻りなさい」と言う。
「ルポルタージュ」では、外国人技能実習生を指導する日本語学校の現場をひたすら歩く。特に「ダブルリミテッド」の問題。日本語の言語体験が圧倒的に少ないまま小中学校を過ごし高校生になっている現実。抽象的概念の言葉は理解不能。親の言葉さえわからない子供はどうして生きていけるのか。「あんなにシャカリキに自分たちと向き合ってくれた日本人がいた、と思い出してもらえたら、私はそれだけで満足なんです」と奮闘している日本人女性をルポしている。また生と死、宗教的なるものを求め続ける世界の旅、バブル時代の若者がどうなったのかを巡る旅。サリン事件の若者たちに触れつつ、「閉じ込められたものは何でも腐る。空気も、水も、人の集団も」「やることがあるだろう、人の中へ帰れと」と語っている。
本当に心に沁み入る作品集。

