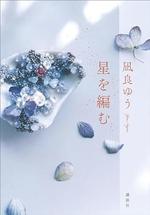 「汝、星のごとく」で語りきれなかった愛の物語。「春に翔ぶ」「星を編む」「波を渡る」の3篇がある。
「汝、星のごとく」で語りきれなかった愛の物語。「春に翔ぶ」「星を編む」「波を渡る」の3篇がある。
「春に翔ぶ」――。瀬戸内の島で出会った櫂と暁海の愛の物語が前作。「ぼくの過去は石を投げられる類のものです。でもぼくは後悔していない。・・・・・・ぼくたちは、生きる権利がある」「わたしは愛する男のために人生を誤りたい。わたしはきっと愚かなのだろう。なのにこの清々しさなんだろう」――。この世界には、生きることの不自由さが充満している。その不自由さを、自らの人生を自ら決め、自ら選ぶ。自らの人生は自らを生きるしかない。そうした前作のテーマを、2人を支える教師・北原を通してより深く描いたのが今回の「春に翔ぶ」だ。「情は人のためならず」と言い続けた北原の父。世間的には"善人"ではあるが、自分は常に後回しにされ続けたと不満と怒りをため込んでいた26歳の高校教師・北原。市内で有名な明日見病院の一人娘・菜々と出会う。菜々は北原の高校の生徒だったが体調が悪く悩みを抱え込んでいた。なんと彼女は妊娠をしていて・・・・・・。北原は驚くべき決断をする。「心地よかった。ぼくは初めて、自らの意思で、誰にも忖度せずに、自らの生き方を選んだのだ。愚かしい選択ではあったが、それがぼくと言う人間だったのだ」・・・・・・。
「星を編む」――。青埜櫂は小説を、久住尚人はイラストを描き、原作と作画のコンビで人気となった。しかし尚人の淫行疑惑をでっち上げられ、連載は打ち切り、既刊は絶版となる。そして尚人は自殺、その後櫂は病死する。櫂の才能を見出していた柊光社のヤングラッシュ編集長・植木渋柿は、櫂たちの漫画を復活させ、未完に終わった物語を完結させようと企画する。また薫風館のS a l yu編集長の二階堂絵理は櫂の小説を刊行しようとし、互いに連絡を取る。才能という名の星を輝かせようと魂を燃やす。落胆させることが次々に起きるが、「追いかけるのをやめたら、それが本当の夢の終わりだ」「美しく理想どおりに整った愛などない」「わたしも植木さんもみんなも、それぞれの場所で頑張っている。わたしもまだやれる」・・・・・・。光り輝く櫂と尚人の魂を愛し、編んで、物語を必要としてる人たちへとつなげること、「星を編む」に進んでいく。仕事、夫と妻、それぞれの感情の襞が実に情感をもって描かれる。
「波を渡る」――。暁海、北原などのその後の人生が描かれる。櫂の「汝、星のごとく」が映画化される。「暗がりで発光するスクリーンの中に、あのころの櫂くんがいた。あのころの暁海さんがいた。あのころの僕がいた。尚人くんが、植木さんが、二階堂さんが、みなそれぞれの人生を精一杯生きていた。客観的に見れば愚かで、歯がゆくだからこそ愛しい・・・・・・」「(互助会形式とはいえ)暁海さんと結婚したときは、教師と元教え子が・・・・・・眉をひそめる人が多くいた。学生時代まで遡って櫂くんとの三角関係を邪推する人もいた。・・・・・・しかし、それぞれが個であり、自らの人生を生きているだけであり、それを他へ啓蒙したことはない」・・・・・・。
「けっして、自分の人生の手綱を手放さないこと、世間の正しさに背いても自分を貫かなければいけないときがあること」――それを愛の物語によって、静かに丁寧に優しく描いている。
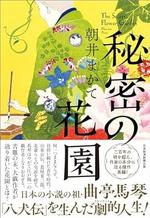 「南総里見八犬伝」の曲亭馬琴。「私は唐土の『水滸伝』に匹敵する小説を書きたかったのだ」「史実の種を見出し、文章を耕して種を蒔き、大いなる虚を育てる。それが稗史小説たるものの、執筆作法であり、読む面白さであり、作そのものの真だ」――狷介、不遜とも言われた馬琴の生涯を生々しい息遣いと素顔の中から描く。
「南総里見八犬伝」の曲亭馬琴。「私は唐土の『水滸伝』に匹敵する小説を書きたかったのだ」「史実の種を見出し、文章を耕して種を蒔き、大いなる虚を育てる。それが稗史小説たるものの、執筆作法であり、読む面白さであり、作そのものの真だ」――狷介、不遜とも言われた馬琴の生涯を生々しい息遣いと素顔の中から描く。
「私はその型から脱却したい。虚実の按配を変えて、歴史をより深く考証する。・・・・・・誰も読んだことのない天衣無縫の物語を紡ぎたい」「『ならおれも、挑むとしよう』と北斎は湯帷子の袖を肩まで捲りあげた」――「椿説弓張月」の北斎とのコンビ絶妙。
「(山東京伝の言葉が耳に入った)あたしは馬琴と交わって20年だが、近頃はますます気韻高く、結構なことさ。見事に山嶺に登り詰めたね。でもなにゆえ、時には山麓に下りて遊ばないのかねえ。麓から嶺を見上げたら、絶壁も断崖も、よく見えるものを・・・・・・増上慢だと非難されたような気がした。いかに師であろうともはや志が違うのだと思い知り、肚の底が冷えた」・・・・・・。「京伝の通夜、葬儀にも行かなんだ。・・・・・・わしは、一人で誰の力も借りずに、日本一の戯作者になりおおせた、そう思いたかった。狷介、不遜と謗られようとも、一個の作者として屹立したかった。京伝の師恩を踏みつけてでも」・・・・・・。
「渡辺華山よ、胸の中で呼びかけた。なにゆえ自制せなんだ。・・・・・・『八犬伝』を読んで気づかなんだのか。わしとて、昨今の政には存念がある。『八犬伝』で勧善懲悪を貫き通すは、悪の本性を問いたいがためだ。それは一個の無頼、蛮勇とは似て非なるもの、最も憎むべきは権力の悪ぞ。八犬士はその非道、無能、無慈悲と闘い続けておる。権力を持つ者こそが、仁義礼智忠信孝悌の珠を持たねば、天下が収まらぬではないか」・・・・・・。馬琴の息遣いと心の中が伝わってくる。
馬琴の人生は、波瀾万丈。大名の家臣の家に生まれたが、若き主君・松平八十五郎君に仕えるが、これが粗暴極まりない男で生傷が絶えず出奔。放浪の末、当代一の戯作者山東京伝の門をたたき、更に蔦屋十三郎の店に奉公して戯作の道に踏み出す。やがて独自の小説、読本作家として立ち、人気を博するようになる。しかし、妻はいつも苛々、不平不満、不機嫌で馬琴に当たり散らす。頼みの息子は医者として士官できるが病弱、出仕も滞りがちだ。板元とのトラブルは日常茶飯のこと。締め切りに追われて、体を酷使して、書き上げる毎日。その中で息子と共に庭の花園で草花を育てるのは、かすかな楽しみであった。
馬琴の素顔、日常の哀歓と凄まじい創作意欲が伝わってくる作品。
 激変するアジア情勢――外務省中南米局長、外務報道官、駐ベトナム大使、駐ベルギー大使・ NATO日本政府代表を歴任した著者が、「国を理解するには歴史から始めよ」の教えを胸に、アジアの潮流を歴史から読み解く。見識の詰まった面白い著作。経済・軍事大国になった中国の動向が最重要だが、近隣アジア諸国の思惑はそれぞれ複雑で違いを見せる。「食は民の天なり」を地で行く東南アジア。中国、韓国との関係は重要だが、長期的に見れば「 ASEAN諸国との関係発展こそ一段と重視すべき」と言う。
激変するアジア情勢――外務省中南米局長、外務報道官、駐ベトナム大使、駐ベルギー大使・ NATO日本政府代表を歴任した著者が、「国を理解するには歴史から始めよ」の教えを胸に、アジアの潮流を歴史から読み解く。見識の詰まった面白い著作。経済・軍事大国になった中国の動向が最重要だが、近隣アジア諸国の思惑はそれぞれ複雑で違いを見せる。「食は民の天なり」を地で行く東南アジア。中国、韓国との関係は重要だが、長期的に見れば「 ASEAN諸国との関係発展こそ一段と重視すべき」と言う。
「『異文化の衝突』の視点から見る日韓関係」――。同文同種とされたようだが全くそれは幻想。尚文軽武vs武士道精神、崇儒排仏vs神仏習合、派閥党争vs和の精神。このように全く違うのだと言う。
「合従vs連衡の時代に入った東アジア」「永楽帝と習近平を隔てる600年の歳月」「習近平が『皇帝』になった日」「中国におけるナショナリズムと『民族』」などで、古代中国の歴史、儒家、漢族中心主義のナショナリズムなどを対比しつつ現在の中国が述べられる。「東南アジアに浸透する中国の影響力」として、関係の深まりとともに、蓄積される ASEANの懸念が描かれる。
「日中越トライアングルへの視点」――。元寇と日露戦争の逸話、ベトナム庶民の嫌中感情の高まりとベトナム共産党の親中姿勢。ベトナム内政のコロナ禍の二大汚職事件、驚天動地の国家主席辞任劇、日越関係50周年と今後の展望が現場に即して語られる。
そしてインド。大国インドの歴史は複雑で厳しい。「カシミール問題」「パキスタン問題」「ヒンドゥー教とイスラム教」「高まる中国の脅威と経済依存」「武器とエネルギーと原子力のロシアとの関係強化」「ソ連邦の崩壊がもたらした印米接近」「モディ首相のグローバルサウス構想とその盟主」「インドのナショナリズムとヒンドゥー教至上主義の共鳴」・・・・・・。
現地、現場と歴史の時間軸の人間・文化論を交えての現在のアジア情勢分析は説得力を持っている。
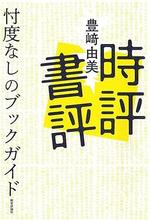 「忖度なしのブックガイド」が副題。まさにその通り忖度なし、「傲慢なもの」「強く大きく権力的なもの」「昭和のがさつで無神経なおじさんなるもの」にNOを突きつける。自由自在、快刀乱麻のメッタ斬り、大乱闘もいとわない。2020年から2023年初めまでの約3年、起きた事象、事件、騒動等についての時評、それに加えてピタッとはまる一冊を紹介する。さらに「2020年バカ強い福岡ソフトバンクホークスのベストナイン」「2022年箱根駅伝優勝の青山学院の10人」「2023年、前年のワールドカップ日本代表のイレブン」「2023年、WBC日本代表チーム」に見立てて、それぞれ小説を紹介する。それも世界の小説だから驚く。読んだ小説も確かにあるが、ほとんど初めて知るもので、触発されて何冊か買い込んだ。
「忖度なしのブックガイド」が副題。まさにその通り忖度なし、「傲慢なもの」「強く大きく権力的なもの」「昭和のがさつで無神経なおじさんなるもの」にNOを突きつける。自由自在、快刀乱麻のメッタ斬り、大乱闘もいとわない。2020年から2023年初めまでの約3年、起きた事象、事件、騒動等についての時評、それに加えてピタッとはまる一冊を紹介する。さらに「2020年バカ強い福岡ソフトバンクホークスのベストナイン」「2022年箱根駅伝優勝の青山学院の10人」「2023年、前年のワールドカップ日本代表のイレブン」「2023年、WBC日本代表チーム」に見立てて、それぞれ小説を紹介する。それも世界の小説だから驚く。読んだ小説も確かにあるが、ほとんど初めて知るもので、触発されて何冊か買い込んだ。
「芸能人や政治家の炎上発言をモーパッサンの『脂肪の塊』で考える」「『分断』や『世代間対立』を煽る言説に負けない小説」「帝政ローマ時代から現代まで変わらぬセクハラ事例に喝!」「自分の中の『おじさん』発見器になってくれる松田青子の『持続可能な魂の利用』」「推すことの『救いと絶望』を示す『推し、燃ゆ』」「女ゆえに味わわされた屈辱や怒りや恐怖に連帯する小説」「カズオ・イシグロVSイアン・マキューアンで読むAI小説」「糸井重里に韓国文学の傑作、チョ・セヒの『こびとが打ち上げた小さなボール』を読んでほしい」「太田光は得がたいトリックスター、ブラジルのマリオ・ヂ・アンドラーヂの『マクナイーマ つかみどころのない英雄』」「私なりの追悼・石原慎太郎」「『鎌倉殿の13人』にハマっていた方にオススメしたい古川日出男版『平家物語』」「プーチンのようなモンスター理解に文学の力を借りよ、ウラジーミル・ソローキンの『親衛隊士の日』」「コラムではなく小説集で小田嶋隆を追悼する」「『正しさ』に疲れたら、絶品ダメ人間小説で笑おう、ジョン・ケネディ・トゥールの『愚か者同盟』」「年のとり方がわかりません!『作家の老い方』」・・・・・・。
まさに「忖度なしのブックガイド」。凄い。
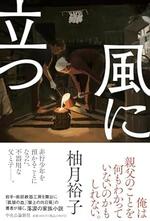 「仕事、人生、時代にいろんな風が吹く。穏やかなそよ風もあれば、激しい暴風もある。追い風、逆風もあるが、人はそれらに翻弄される。それらに立ち向かうために、必要なものは何か。どんな風にも動じない、強さが必要だ」「強くなるために必要なものは、忍耐、負けん気、信念と思うが、私が思うのは少々違う。たとえば怒り、嘆き、たとえば悔恨――それらをすべて受け止められたとき、強くなれるように思う」・・・・・・。
「仕事、人生、時代にいろんな風が吹く。穏やかなそよ風もあれば、激しい暴風もある。追い風、逆風もあるが、人はそれらに翻弄される。それらに立ち向かうために、必要なものは何か。どんな風にも動じない、強さが必要だ」「強くなるために必要なものは、忍耐、負けん気、信念と思うが、私が思うのは少々違う。たとえば怒り、嘆き、たとえば悔恨――それらをすべて受け止められたとき、強くなれるように思う」・・・・・・。
問題を起こして、家庭裁判所に送られてきた少年を一定期間預かる制度の補導委託。盛岡市で南部鉄器工房を営む72歳になる親方・小原孝雄は突然、「補導委託で少年を預かる」と言い出す。不器用な職人の父とその息子の悟。悟は、孝雄に遊んでもらったこともないし、いつもぶっきらぼうで態度も冷たく、「親父は昔から自分勝手な人間だ」と思ってきた。それが非行少年・春斗を預かることになったという。「なぜだ。何を考えているのか」と悟は戸惑う。しかも預かった少年は感情も少なく、突然、ガス爆発のように暴れたりもする。春斗は有名高校に入っており、父親は弁護士だという。毎週土曜日に宅急便を出しに行くが、何をしているのか不信が増す。しかし、父・孝雄は自分にはしたこともないような優しさで春斗に接し、先輩職人の健司も妹の由美も温かい。「親父は何を考えているのか」「親父はどういう人間だろう」「春斗は何に苦しんでいるのか、何が春斗をそこまで追い詰めているのか」と思うなか、事件が起きる・・・・・・。
「勉強しなければ、ちゃんと生きていけなくなってしまう」と言う親に「春斗くんはいま、すでにちゃんと生きていますよ」と言う孝雄。その孝雄は「もう、辛い思いをしたくなかったから職人になった」と、つぶやく。「耕太を見てきた私は、貧しさがどれほど人を不幸にするのか知っています。だから、あなたが春斗くんに苦労はさせたくない、と願う気持ちも痛いほどわかる。ただね、耕太が村を離れる時に言った言葉を思い出すと、あなたの言うとおりにしても、春斗くんが幸せになるとは思えないんですよ。耕太は、どんなに貧しくてもいいから、俺は姉ちゃんにいてほしかった――そう言いました」「耕太は泣きながら、もしこれから先、自分に家族ができたら本人のしたいようにさせる。選択肢がない人生が、いかに辛いかを知っているから、自分の子供には自由に生きてほしい、そう言って涙を流しました」・・・・・・。
岩木山、南部鉄器、チャグチャグ馬コ、宮沢賢治の「グスコーブドリの伝記」など、岩手を舞台に親と子の愛情と感情のすれ違い、津波にさらわれて「自分だけ生き残って幸せでいいのか」との葛藤、「風に立つ」ように背中をそっと支える温かい心の大切さを、丁寧に丁寧に描いている感動作。

