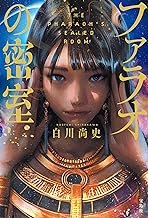 2024年第22回「このミステリーがすごい!」大賞受賞作。古代エジプトの時代。上級神官書記のセティは半年前、先王の葬送の儀の準備中に起こった王墓の崩落事故で命を落とす。冥界で審判を受け、心臓に欠けがあるので審判を受ける資格がないとされ、現世で心臓のありかを探すことになる。期限はわずか3日。現世に蘇ったミイラが、自分の心臓の欠片を探すという奇想天外な話だ。容疑者は元同僚のアシェリとジェドと思われ、当代随一のミイラ職人の親友タレクの協力を求める。敵味方相乱れるが、エジプトの主神を太陽のアテンと定め他の神々への信仰を禁じた先代王、それに倣う現在の王、神官を束ねる神官長・メリラアの深謀、書記長を務める父・イセシとの確執、奴隷の少女・カリらが複雑に絡み合い真相に迫っていく。さらにまた、葬送の儀のさなか、先王のミイラがピラミッドの玄室から忽然と消失し、外の大神殿で発見される。
2024年第22回「このミステリーがすごい!」大賞受賞作。古代エジプトの時代。上級神官書記のセティは半年前、先王の葬送の儀の準備中に起こった王墓の崩落事故で命を落とす。冥界で審判を受け、心臓に欠けがあるので審判を受ける資格がないとされ、現世で心臓のありかを探すことになる。期限はわずか3日。現世に蘇ったミイラが、自分の心臓の欠片を探すという奇想天外な話だ。容疑者は元同僚のアシェリとジェドと思われ、当代随一のミイラ職人の親友タレクの協力を求める。敵味方相乱れるが、エジプトの主神を太陽のアテンと定め他の神々への信仰を禁じた先代王、それに倣う現在の王、神官を束ねる神官長・メリラアの深謀、書記長を務める父・イセシとの確執、奴隷の少女・カリらが複雑に絡み合い真相に迫っていく。さらにまた、葬送の儀のさなか、先王のミイラがピラミッドの玄室から忽然と消失し、外の大神殿で発見される。
「自分にナイフを刺したのは、いったい誰なのか」「心臓の欠片はどこにあるのか、誰が何の理由でそうしたのか」「先王のミイラ消失事件の真相は?」・・・・・・。緊迫感ある壮大な物語が展開されるが、3日間の期限の中で真相究明を果たそうとする「走れメロス」を想起させる友情物語でもあり、エジプトを救わんとする指導者たちの決死の行動物語でもある。さらに、その奥に、「あのままアテンが巣くう太陽が大きくなれば、現世も冥界も関係なく、エジプトは滅びるだろう」と、熱暑の地域における「魔物の太陽」「異形の太陽」たる太陽神への恐怖が描かれる。宗教と自然と人間の哲学だ。その意味も含めてこのミステリーはすごい。
 「比較分析が示す変容」が副題。現在の経済的、文化的、政治的状況に潜んでいる民主主義の危機について、民主主義研究の第一人者であるプシェヴォスキが判断の手立てを示す。著者は「民主主義とは、人々が選挙を通じて政府を選択し、好ましくない現政権を排除できる相応の可能性を持つという政治的な取り決めのことである」とその立場を示す。そしてギンズバーグとヒュクのいう3つの「民主主義の基本的な述語」たる競争的選挙、表現や結社の自由の権利、法の支配から言えば、「選挙が非競争的か」「権利が侵害されているか」「法の支配が崩壊してるか」ということになる。
「比較分析が示す変容」が副題。現在の経済的、文化的、政治的状況に潜んでいる民主主義の危機について、民主主義研究の第一人者であるプシェヴォスキが判断の手立てを示す。著者は「民主主義とは、人々が選挙を通じて政府を選択し、好ましくない現政権を排除できる相応の可能性を持つという政治的な取り決めのことである」とその立場を示す。そしてギンズバーグとヒュクのいう3つの「民主主義の基本的な述語」たる競争的選挙、表現や結社の自由の権利、法の支配から言えば、「選挙が非競争的か」「権利が侵害されているか」「法の支配が崩壊してるか」ということになる。
具体的に、これまで民主主義崩壊の経験を持つドイツ・ワイマール共和国と1970年代のチリ、逆に危機にあっても、民主主義が維持された1960年代のフランスとアメリカを取り上げ分析する。そこから見えてくるのは、「最も顕著なのは所得水準。短期的な経済危機は民主主義の脅威とはならないが、長期にわたる所得の停滞は崩壊を招く」こと。さらに「大統領制の脆さ」と「暴動とストライキは民主主義を弱体化させるが、反政府デモに関しては暴力的でない限りそのような恐れは無い」と分析する。
そして現在、何が起きているのか。その危機の兆候として、「既存政党の衰退」「外国人排斥的、人種差別的、ナショナリスティックな政党の台頭」「民主主義への支持の低下」の3点を挙げる。特に中道有権者の投票率低下が、右派ポピュリズムの台頭につながっている可能性を指摘する。
考えられる原因として、「経済――所得の停滞(雇用の減少と低賃金のサービス業増加)、不平等、流動性」「分断――分極化、人種差別、敵意」を挙げている。
いかなる社会、いかなる場面でも対立があり、紛争がある。政治制度は紛争を、①構造化し②緩和し③ルールに則った調整を行う――ことで、秩序を立てて処理するものだ。その意味で選挙こそが、政治的安定のための要とすることだ。民主主義が危機に陥らないためには、「人々が選挙を通して政府を選択する」「選挙を軸として、昨日の敗者が明日には勝者となるかもしれないという期待値が満たされていること」が大事である。そのために危機の意味を冷静に分析し、その回避の道を考察することの重要性を指摘している。
 児童養護施設で育った山科翔太は、地元の先輩から誘われ、「カタラ」という会員制クラブの従業員になる。ここは若く見栄えの良い男たちが、言葉巧みに路上で女性をひっかけて店に来させ、挙句は借金まみれにした後に風俗に落とすことを目的とする半グレが経営する店だった。そこで有名私大に通いながら同じ仕事をする辻井海斗と親しくなる。2人は効率よく女性を誘うためにコンビを組んで成績を上げ、ついに関連の店を含めトップテンにのし上がる。しかしある日突然、カタラグループのトップや店のマネージャーと共に、翔太は逮捕される。公衆衛生または公衆道徳上、有害な業務につかせる目的で職業紹介や労働者の供給を送ってはならないという職業安定法第63条違反だ。世間で大きな話題にもなったこの「カタラグループ事件」で翔太は3年懲役の実刑、少年院入所歴のあることも響いたのか、執行猶予はつかなかった。海斗はその頃、体調が悪く出社しておらず、家柄も良かったせいか、事情聴取さえされなかった。
児童養護施設で育った山科翔太は、地元の先輩から誘われ、「カタラ」という会員制クラブの従業員になる。ここは若く見栄えの良い男たちが、言葉巧みに路上で女性をひっかけて店に来させ、挙句は借金まみれにした後に風俗に落とすことを目的とする半グレが経営する店だった。そこで有名私大に通いながら同じ仕事をする辻井海斗と親しくなる。2人は効率よく女性を誘うためにコンビを組んで成績を上げ、ついに関連の店を含めトップテンにのし上がる。しかしある日突然、カタラグループのトップや店のマネージャーと共に、翔太は逮捕される。公衆衛生または公衆道徳上、有害な業務につかせる目的で職業紹介や労働者の供給を送ってはならないという職業安定法第63条違反だ。世間で大きな話題にもなったこの「カタラグループ事件」で翔太は3年懲役の実刑、少年院入所歴のあることも響いたのか、執行猶予はつかなかった。海斗はその頃、体調が悪く出社しておらず、家柄も良かったせいか、事情聴取さえされなかった。
本書は「翔太の罪」と「海斗の罰」の2部で構成される。「翔太の罪」――3年後出所するが何もかもうまくいかない。「どうせ俺はカタラの人間で、前科者でヤクザなんだ」――前科がついて回ったのだ。そして、デリヘル嬢を乗せて待つステップワゴンのドライバーとなる。そんな時、モーパッサンの短編「脂肪の塊」を読む沙季という不思議なデリヘル嬢に出会う。そして外国の小説を翔太は読むようになる。コンラッドの「闇の奥」、アンナ・カヴァンの「氷」・・・・・・。そして「俺の罪は重い」――。翔太の運命は、子供の頃からの生命の奥底の深き闇へと突き進み、思いもよらぬ展開を見せていく・・・・・・。
一方で「海斗の罰」――。事件を免れた海斗は広告代理店最大手のアドルーラーの花形である営業企画部に所属する。そこで東京都、政府が後押しする新しい世界都市博の「シティ・フェス推進準備室」のナンバー2に抜擢される。利権渦巻くなか、広告塔のタレントのスキャンダル、パワハラ、政財界の接待やバックマージン、当初案の設計変更・・・・・・。半グレ集団の連続詐欺事件を含む最近の事件を想起させる事件の対処に、海斗は翻弄され我が身を振り返ることもできない。昔の半グレとの付き合いが復活し、ついに破綻に追い込まれる。
黒と白と灰色の世界。黒と白はわかりやすいが、問題は灰色の世界だと抉り出す。「平然と人様を踏みつけにする。しかも自分じゃわかってねえ。ナチュラルに薄汚ねえクソをまき散らす」「灰こそが、半グレの灰こそが、より人間的な分だけ邪悪なんだ。これは悪とは少し違う。悪じゃない。邪悪なんだよ」・・・・・・。翔太と海斗は再び会うが、心はなかなか交わらない・・・・・・。
しかし最後、海斗は視線を海へ向ける。「夕暮が闇に呑まれる半暮刻に、波が嗤うようにざわめき始めた」と何ともいえぬ余韻を残し描いている。そしてもう一つ、印象的なのは人の命を変える本の力だ。
 全くその通りで、こういう角度でわかりやすく解説しているのは、重要で面白い。経済ばかりではなく、政治の現場では常にあり悩むところだ。西部邁さんは「ポピュリズム」と「ポピュラリズム」を分けよと言ったが、民衆の声を受け取ることと、民衆に媚びる事は違うというのはよく整理されていると思う。論理ではなく空気で決まる情緒的な日本社会に、最近のSNS時代が加わり、なかなか「ちょっと待って」と熟議することが難しくなっている。だからこそ、存在感ある思考し哲学ある政治家の出番だと言うことだ。
全くその通りで、こういう角度でわかりやすく解説しているのは、重要で面白い。経済ばかりではなく、政治の現場では常にあり悩むところだ。西部邁さんは「ポピュリズム」と「ポピュラリズム」を分けよと言ったが、民衆の声を受け取ることと、民衆に媚びる事は違うというのはよく整理されていると思う。論理ではなく空気で決まる情緒的な日本社会に、最近のSNS時代が加わり、なかなか「ちょっと待って」と熟議することが難しくなっている。だからこそ、存在感ある思考し哲学ある政治家の出番だと言うことだ。
この30年余の日本の政治・経済・社会――。「地価を下げることこそ正しい」「銀行救済に税金投入はけしからん」「日本はものづくり国家、額に汗して働け」「弱い中小企業は皆救うべきだ」「堕落した官僚は懲らしめろ」「金融政策はあらゆる手段を」「高齢者は弱者、皆で助けよう」「人口減少は国家的危機」「拙速な改革は避けよ」という9つの「正義」のバブルが紹介され分析されている。公共事業悪玉論も構造改革ブームも「政治家はまず身を切る改革」についても触れている。「4文字熟語に気をつけよ」と、石川好さんが言ったことを思い出す。富国強兵、鬼畜米英から構造改革に至るまで、ピタッとはまる4文字熟語にやられてしまったのは日本の常だ。しかも、有識者やメディアまでが奔流となる。
「地価を下げることこそ正しい」の「正義」は、劇薬だった総量規制や地価税の導入によって収めはしたが、バブル崩壊の損失を大きくし、「公的資金の投入はけしからん」の大合唱は不良債権処理を長引かせた。公共事業悪玉論も財政再建論の槍玉に上がり、インフラのストック効果と防災・減災・ 老朽化対策をないがしろにした。「高齢者は弱者」「堕落した官僚を懲らしめよ」も、歪みをもたらせている。一つ一つのテーマが、極めて現実的で、この30年の我が人生とダブっているだけに実感を持って感じる。日本人論でもあるかもしれない。
4文字熟語に気をつけよ、「正義」がブームになるときに気をつけよ、冷静な分析を心がけよ。本書は「デジタル敗戦」「人口減少・少子高齢社会」の今こそ、日本の停滞を招かぬよう、その教訓を抉り出していいる。過剰な「物語」が、長期停滞の闇を再び招かぬよう・・・・・・。
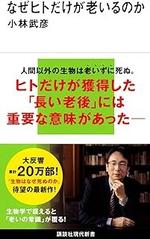 前著の「生物はなぜ死ぬのか」は、生物はなぜ誕生し、なぜ死ぬのか。生物はどのように死に、ヒトはどのように死ぬのかを、「生物」「生命科学」から論及した。「死は生命の連続性を維持する原動力」「死とは進化、つまり『変化』と『選択(たまたまその環境で複製しやすい、増えやすいものが選ばれて残る)』を実現するためにある。『死ぬ』ことで生物は誕生し、進化し、生き残ってくることができた」「進化が生物を作った」と言う。
前著の「生物はなぜ死ぬのか」は、生物はなぜ誕生し、なぜ死ぬのか。生物はどのように死に、ヒトはどのように死ぬのかを、「生物」「生命科学」から論及した。「死は生命の連続性を維持する原動力」「死とは進化、つまり『変化』と『選択(たまたまその環境で複製しやすい、増えやすいものが選ばれて残る)』を実現するためにある。『死ぬ』ことで生物は誕生し、進化し、生き残ってくることができた」「進化が生物を作った」と言う。
最初にできたのはRNAやアミノ酸といった有機物。RNAは将来親から子へと受け継がれる情報、つまり遺伝子となる物質(遺伝物質) 。アミノ酸は生物の体を構成するタンパク質の材料となる。RNAは壊れやすい性質を持っており、作られては壊されるが、その壊れることは、材料を供給することになり、分解=「死」がある限り動き続けることになる。加えて、すべての生物、すべての細胞が持っている最も基本的な細胞内の小器官「リボソーム」が、あたかも「調理人」のようにタンパク質を作る。さらにRNAの一部が変化してできたと思われる壊れにくいDNAが誕生、遺伝子としての地位をRNAから譲り受けた。「分解= 死ぬ」は、進化に必須で、RNA分子に例えれば「老化とは複製するよりも、分解が起こりやすくなった状態のこと」と言う。
不思議なことがある。「ヒトとバナナの遺伝子は50%同じ」「チンパンジーとヒトは遺伝子はなんと98.5%同じ」で、先祖が同じで別れたことを示していると言う。そして「老いる」ことについては「人間以外の生物は老いずに死ぬ」「サケは産卵に適した場所を経験的に知っており、川に戻って産卵・放精して、ピンピンコロリで死ぬ(子孫を残すまでは死なない=結果的に子孫を残す生物が生き残ってきた)」「野生の生き物は基本的に老化しない。『食べるー食べられる』の世界では老化した動物は、たちまち食べられて死ぬ」「哺乳類は体が大きい方が長生きで、ゾウはがん抑制遺伝子P53がなんと20個もある」と言うのだ。
「加齢とともに徐々にDNAが壊れて、遺伝情報(設計図)であるゲノムがおかしくなる。その結果、細胞の機能が低下し、老化して死ぬ。またDNAが壊れてくると、細胞がそれを感知して、積極的に細胞老化を誘導する」「ヒトの老化の原因は、新しい細胞の供給能力の低下、つまり幹細胞の老化の影響が大きい。これが臓器や組織の機能が低下を招く。もう一つは、細胞が入れ替わらない臓器の細胞の老化で、脳と心臓だ」・・・・・・。
面白いことに「ヒトの寿命は50〜60歳」と考えると言う。理由は、「遺伝情報(ゲノム)がほぼ同じのゴリラやチンパンジーの寿命が50歳前後」「哺乳動物の総心拍数20億回仮説」「ヒトバー55歳位からがんで亡くなる人数が急増。野生の哺乳動物でがんで死ぬものはほとんどいない」と言っている。興味深い話だ。
そこで「なぜヒトは老いるようになったのか」だ。「ヒトだけが」・・・・・・。子供が産めなくなると、すぐ死んでしまうのが普通で老後は無いのだが、ヒトとシャチとゴンドウクジラだけが老後がある。寿命の延長には「おばあちゃん仮説(おじいちゃん仮説)」がある。長寿遺伝子の進化があり、子育てに貢献したおばあちゃん、体力だけでなく知識・技術・経験や集団をまとめる長老の力(おじいちゃん)がある。「シニア」がいる集団は有利だった、シニア量産の正のスパイラルに突入したと指摘する。政治家は本来、そうした能力・経験・知識と集団をまとめる人間性であれと言っている。生物学的には「なぜ人だけが老いるのか」ではなく、老いた人がいる社会が選択されて生き残ってきたと言う。
こうしたことから、「経済も人口も縮小傾向の日本にあって『復活の切り札』はシニア」だと強調する。そのためにも病気を減らし「ピンピンコロリ」的な生き方をしようと提唱する。そのために「ゲノムの脆弱部位、老化細胞除去」研究をしていると言う。
そして超高齢者の価値観は「物質主義的・合理的」な世界観から「宇宙的・超越的」世界観に変化していることを生かせと結んでいる。死を意識し、公共を意識する老年的超越によって、人生は楽しい幸せを感じるものになる、社会も喜ぶ。ヒトだけが獲得した「長い老後」には重要な意味があったと言うのだ。

