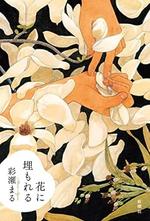 驚くような、そして大胆かつ繊細な短編小説集。恋が身体を変えていく。「花」「指」「くぼみ」などが、愛や恋にしなやかに絡んでくる。「実在」よりも、量子力学的世界が描かれるようにも思った。
驚くような、そして大胆かつ繊細な短編小説集。恋が身体を変えていく。「花」「指」「くぼみ」などが、愛や恋にしなやかに絡んでくる。「実在」よりも、量子力学的世界が描かれるようにも思った。
「花に眩む」――著者の2010年の作品。「しまの肌にはツリガネニンジンの花が咲く。・・・・・・陰気で鮮やかさのない、つまらない花だと言ってはぷつぷつと毛穴から吹き出た芽を引き抜いた」「私の肌には、センニチコウの花が咲く」「高臣さんが芽を整えているのは、首や手足の先などのはたから見える部分だけで、背中やへそのまわりや腿の辺りにはやわかなハトムギの葉が茂っている」――。「私が高臣さんの子供を産んだのは、春のはじめのあたたかい風が吹く季節で、年に一度の出産のシーズンだった。どこの家も、濡れた白い赤ん坊で溢れていた。多い人は生涯で20人近くの子供を産む。私は1度に3人の子を産んだ」――なんとも不思議な物語だ。
「なめらかなくぼみ」――彼の身体よりも、ソファーの肌触りを愛する女。「リビングの壁を見た瞬間、母親は私を床に落とした。・・・・・・きっとみんな、確かだと思っていた腕から滑り落ちた経験があるのだ。だから、安心して体を預けられるものが欲しくなる。言う通りになる他人、拒む手段を奪った肉体、将来の約束、不安をなだめてくれる体温を、確保しようとする」「そのソファは、安心するでしょう」。愛を失って抱かれていた腕から落とされ、安心していた場所から遠ざかるのに対し、今日も暖かくて柔らかい場所が欲しいというのは、誰にもあるようだ。
「ニ十三センチの祝福」――妻と別れた男が、同じアパートに住む女の靴を直してあげる。女は猫背のグラビアアイドルだった。「加納さん、私はできは悪いけど、夢の女なんです。男の人の、毎日しんどいなぁ、こんな姉ちゃんに触りたいなぁ、きっとやーらかくて気持ちいいんだろうなあってイメージを形にして、いい夢見てもらうのが仕事なの・・・・・・」「なにもいらない。もらったんだ。飯、一緒に食うの楽しかったよ」」・・・・・・。
「マイ、マイマイ」――これもまた不思議な話。愛すると、身体のどこかに石ができる。その身体から出た美しい石を交わし合う恋人たち。
「マグノリアの夫」――劇団に所属する郁人は、物語の起伏に合わせて、木蓮の一枝からの花を旺盛に咲かせたり、反対に病んでしなびたりと変わった役を演じることになる。彼は有名作曲家の日与士幻馬の隠し子だった。妻の脚本家の陸は、演技を見て郁人の心にある純粋なアンビバレントな意地の感情の根っこに触れた思いをするのだった。
新鮮さと熟練の冴えを合わせ持つ5つの短編集。
 方言学、社会言語学の篠崎晃一東京女子大学教授が選んだ212語。学生時代に愛媛出身の先輩が「風呂にはまる」と言って驚いたことがある。また宮崎県に行って「よだきー」がよく使われて、気候の良い宮崎らしいことを感じたこともある。東京の「肉まん」が大阪では「豚まん」であり、肉とは牛肉のこと。また方言ではないが、東京のエスカレーターには左側に、大阪では右側に立つこともいつも不思議に感じていたことだ。本書で、富山県では「おごってくれる」ことを「だいてくれる」と言い、「先生、だいてくれるんですか?」という恐ろしい言葉が書かれているが、富山の人に聞いてみると本当だと言う。紹介されている「離合困難(すれ違い困難)」は、現実にある標識だ。
方言学、社会言語学の篠崎晃一東京女子大学教授が選んだ212語。学生時代に愛媛出身の先輩が「風呂にはまる」と言って驚いたことがある。また宮崎県に行って「よだきー」がよく使われて、気候の良い宮崎らしいことを感じたこともある。東京の「肉まん」が大阪では「豚まん」であり、肉とは牛肉のこと。また方言ではないが、東京のエスカレーターには左側に、大阪では右側に立つこともいつも不思議に感じていたことだ。本書で、富山県では「おごってくれる」ことを「だいてくれる」と言い、「先生、だいてくれるんですか?」という恐ろしい言葉が書かれているが、富山の人に聞いてみると本当だと言う。紹介されている「離合困難(すれ違い困難)」は、現実にある標識だ。
愛知県の私は、授業の後の休み時間を「放課」と言うが、全国では「長休み、中休み」「大休憩、昼休憩」と言ってることを初めて知った。本書には出ていないが、私の東三河では、「じゃん」「だら」「行くまいか」が最も使われている方言で、洒落ていると思うのは、朝日がまぶしい時に「ひずるしい」と言う。「日出ずるらしい」からきたと言われている。お湯が「ちんちんに沸く」と言う。
「津軽じょっぱり」は「情張り」からきており、「土佐のいごっそう」「肥後もっこす」と並んで、"日本3大頑固"といわれていると言う。「うざったい」は、東京多摩地方の伝統的な方言のようで、小さなものがたくさん群がることを表す「うざる」から来ており、今の若者言葉とは意味がずれているようだ。山梨で「からかう」と言うのは、困難を打開するために知恵を出しいろいろ手をつくす、ということのようだ。京都の「おーきに」は「大きなり」が元の形で、程度の甚だしい様子で「おーきにありがとう」の後半が省かれていると言う。「佐賀のがばいばあちゃん」の「がばい」は、たくましいとか豪快なではなくて、「とても」というものだと言う。
どの方言もだんだん使われなくなっていると思うが、故郷に帰ると、やっぱりそんな言葉遣いになってることに気づくものだ。
 「心をつかむ44のヒント」が副題。演説やスピーチというより、会話力、会話の妙や楽しみ方、空気を変えるタイミング絶妙の言葉など、阿川さんの自身の豊富な経験から示してくれるコミニュケーション術。貴重なヒントが満載。
「心をつかむ44のヒント」が副題。演説やスピーチというより、会話力、会話の妙や楽しみ方、空気を変えるタイミング絶妙の言葉など、阿川さんの自身の豊富な経験から示してくれるコミニュケーション術。貴重なヒントが満載。
「何を話したいか。それが問題。もっと積極的に『話したい』テーマやエピソードがあったら会話ができる」「インタビューをする際、質問は1つだけ用意する。質問を10も20も用意していたら、2つ目の質問をいつ切り出そうかとタイミングを伺ってしまう。つまり、相手の答えをろくに聞いていない」――国会の質疑でも典型的だ。
「会話とは"しりとり話題合戦"」 ――間違いなく会話はキャッチボールだと思う。演説ではないし、演説をしたら嫌われる。「相手の話に共感し、反応する」「助け舟を出すことを心がける(三宅久之、ハマコウさんの話)(今日はまたいちだんと。さっきの話の続きは?)」・・・・・・。「モテる男は聞き上手(石田純一さん、自分の話はしないでまず女の子の話を聞くことかな)」「人の話は90%が自慢と愚痴である(東海林さだおさんの名言)」と言う。「相手との距離感をつかむ」――この人には本音を話せるという距離感と興味ある中身をさらけ出す姿勢が政治家には特に大事だと思う。「会合では、1番下っ端にしゃべらせる」「話題に窮したら病気自慢」・・・・・・。
「女性で大事なのは共通の悩み」「いつもにこやかなのは良い(不機嫌や怒っているはダメ)」「おしゃべりは女にとってストレス解消」「末っ子には特有の能力があるようだ(周囲の人間に愛されて、上手に甘えて仕事です成果を上げている。ポジティブ、甘え上手、屈託がない)」「専門用語でなく、相手に合わせた平易な言葉を使う(わかりやすいことが大事)」「心に響く言葉選びを心がける」「人は他人の不幸話に魅了される(立派な話には興味がない。むしろ自虐ネタ)」「認知症の母と話す――最初イライラ、そして受け入れる」・・・・・・。
これらはまさに人間学だ。
 「メディアが隠す事実」が副題。前著「イスラム2.0」では「イスラム教は平和な宗教という通説があるが、2000年以降、ジハード主義が世界中で急速に拡大した背景にあるのは、イスラム2.0であると考えている」「イスラム教徒と共生するためには、多様性社会への粘り強い知的営為の努力が必要」と言っている。
「メディアが隠す事実」が副題。前著「イスラム2.0」では「イスラム教は平和な宗教という通説があるが、2000年以降、ジハード主義が世界中で急速に拡大した背景にあるのは、イスラム2.0であると考えている」「イスラム教徒と共生するためには、多様性社会への粘り強い知的営為の努力が必要」と言っている。
昨年10月からのガザでの戦闘――。「"弱者は正義、弱者こそ善"という観念が世界を席巻している」「強者たる権力者は支配者なので常に悪人である」を、世界で最もうまく利用しているのが、イスラム過激派テロ組織ハマスだと言う。「我々パレスチナ人は、占領者イスラエルによって虐殺されている弱者である」と。
主張は鋭角的、直截的だ。「そもそもハマスはパレスチナの代表ではない。パレスチナ人を武力で抑えつけて支配しているテロ組織だ」「ハマスはイスラエルという国を殲滅することを目指すテロ組織である」「パレスチナ人を人間の盾に利用しながら、弱者を守る戦士の顔で、イスラエルの民間人を標的にした無差別攻撃をかけた」「イスラエルの軍事作戦の標的は、パレスチナ人の民衆ではなくハマスである」「ハマスはガザ全体をテロ基地にして、住民を盾に立てこもる卑劣なやり方をしている」・・・・・・。
これに対して、メディアは「圧倒的軍事力を持つ強者」としてのイスラエルと、ガザという「天井のない監獄」に閉じ込められ、逃げ場を失った「哀れな弱者としてのパレスチナ人」という非対称性を強調していると言う。「どっちもどっち」論ではない。「私たちはテロを容認してはならない」と言う。そして「当初、日本はハマスの行為をテロと非難せず主権国家であるイスラエルに『自制』を要求する声明を出したことはおかしい」と指摘、それは「全方位嫌われ外交」を招いている。アラブ諸国のハマスへの対応を見よ。イランなどはどう動いているかを見よ、と激しく言う。
顕在化した事件の背景には、常に内在する歴史性があり、宗教にも人間存在そのものの本質をめぐる確執がある。地政学とも相まって根は深い。背後にある構造、構造的暴力の複雑性を剔抉することが不可欠だ。今年に入って、この地域では「ヒズボラ」や「イスラム国」の動きもある。「ウクライナ」も2年になる。大変な、そして重要な年となっている。
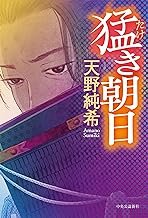 「朝日将軍」木曽義仲の猛き生涯を描く。真っ直ぐで鮮烈であるだけにもの悲しい。「驕る平家を打倒し、人が人として生きられる世を創る」ことを目指した木曽義仲は、兵を挙げてわずか4年足らずで滅びていく。芥川龍之介は「木曽義仲論」で言う。「彼は其炎々たる革命的精神と不屈不絆の野快とを以て、個性の自由を求め、新時代の光明を求め、人生に与ふるに新なる意義と新なる光栄とを以てしたり。彼の一生は失敗の一生也。彼の歴史は蹉跌の歴史也。彼の一代は薄幸の一代也。然れども彼の生涯は、男らしき生涯也」「彼の一生は短かけれども彼の教訓は長かり」と言う。しかし盛者必衰といってもあまりにももの悲しい。
「朝日将軍」木曽義仲の猛き生涯を描く。真っ直ぐで鮮烈であるだけにもの悲しい。「驕る平家を打倒し、人が人として生きられる世を創る」ことを目指した木曽義仲は、兵を挙げてわずか4年足らずで滅びていく。芥川龍之介は「木曽義仲論」で言う。「彼は其炎々たる革命的精神と不屈不絆の野快とを以て、個性の自由を求め、新時代の光明を求め、人生に与ふるに新なる意義と新なる光栄とを以てしたり。彼の一生は失敗の一生也。彼の歴史は蹉跌の歴史也。彼の一代は薄幸の一代也。然れども彼の生涯は、男らしき生涯也」「彼の一生は短かけれども彼の教訓は長かり」と言う。しかし盛者必衰といってもあまりにももの悲しい。
木曽谷を本拠とし信濃の国で屈指の勢力を誇っていた武士・中原兼遠の養子として育った駒王丸。兼遠の息子たち次郎兼光、四郎兼平、五郎兼行との兄弟として過ごすが、実は「駒王丸殿はいずれ、信濃を束ねる御大将となられる方」「源氏の棟梁・源為義の次男・源義賢の子」であった。保元の乱、平治の乱を経て世は平家の天下。「俺は、貴族の世でも武士の世でもない新しい世を創りたい。人が人として生きられる。俺は平家討つ」――木曽義仲は拠点を東の佐久に移し兵を挙げる。関東では、伊豆の頼朝が挙兵し、勢力を広げ始めていた。やがて京を出陣した平家の頼朝追討軍7万が駿河に入り、富士川の西岸に陣を布いたが、戦して撤退する。平清盛が死に、信濃を固めた木曽義仲達は、越後との横田河原合戦で勝ち、義仲の勢力は一気に広がる。頼朝は平家と雌雄を決する前に、義仲を討たねばならないと考える。源氏の棟梁は、世に2人も必要ないのだ。そして両者の激突をかわすため、義仲の嫡男・ 義高を頼朝の息女・大姫の婿として事実上の人質として差し出すことになる。
義仲は進むしかなかった。平家を倒し義高を取り戻すその日までは何があろうと立ち止まるわけにはいかない。倶利伽羅峠で平家軍を破り、西へ進む義仲の軍は膨れ上がっていく。そして京都に入り、とうとう平家を西へ追い落とした。しかしそこは「魔都」だったのだ・・・・・・。
法皇は、「頼朝と義仲は、いずれ必ず決裂する」「木曽、鎌倉、平家、平泉。この4者が互いを牽制しあい、結果として均衡を保つ。武士の中に、突出した力を持つものが現れることは王家のためにならない」と頼朝に使者を送るなど画策する。平家軍は、再び東上を始める。京都には飢饉で食べ物がなく、「木曽の山猿に、不作法者にどうして支配されるのだ」「あんたらが来てからうちも京も無茶苦茶や」の声が充満し、7万といわれた木曽軍も落ち目と見ると離れていく武士が次々離れ、見る影もなくなった。
そして「全軍、力を振り絞れ。目の前の敵を切り崩し、皆で故郷へ帰るぞ!」・・・・・・。巴御前、樋口兼光、今井兼平、落合兼行、楯親忠、葵 ら仲間との信頼は凄まじい。それ故の体を張った戦い振りは目に浮かぶようだ。

