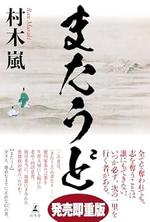 田沼意次は賄賂にまみれた悪徳政治家だったのか――その実像を第9代将軍徳川家重に見出され、第10代将軍徳川家治の信頼の下、邪念なく戦い続けた改革者として描く。意次の胸に常にあったのは、「この者は<またうど>の者なり」と家重からいただいた言葉(あの動かぬ手で懸命に書き付けてくれたもの)であった。「またうど」とは「全き人。愚直なまでに正直な信(まこと)の者」ということだ。
田沼意次は賄賂にまみれた悪徳政治家だったのか――その実像を第9代将軍徳川家重に見出され、第10代将軍徳川家治の信頼の下、邪念なく戦い続けた改革者として描く。意次の胸に常にあったのは、「この者は<またうど>の者なり」と家重からいただいた言葉(あの動かぬ手で懸命に書き付けてくれたもの)であった。「またうど」とは「全き人。愚直なまでに正直な信(まこと)の者」ということだ。
田沼意次が家治に仕え舵取りを任されたこの時代――江戸の大火、浅間山の噴火、飢饉に打ち毀し、商人の台頭と貨幣経済の黎明期。困難と激動が続いた。「意次には確信がある。五十年後か百年後か、意次のやりかけたことはいつか必ず実を結ぶ。蝦夷地の開発も印旛沼、手賀沼の干拓も、貸金会所も南鐐ニ朱銀も――。そのとき意次はこの世にはいない。だが、己のしようとしたことは間違っていない。その未来が意次にははっきりと見える。だから罵られ、禄を奪われても意次はへこたれるまい。意次はまたうどだ」・・・・・・。
身分の低い者も実力さえあれば登用し、交易に役立つ俵物を手に入れるため、蝦夷地開発に乗り出す。江戸税制の改革者として商人にも課税。新しい5匁銀を鋳造し金貨と銀貨が同じ曲尺の上にある貨幣だとする貨幣経済の道を開く。「付け届け」は多かったが、全く無頓着で開封することさえなかった。そこには"まいまいつぶろ"家重に仕え、何一つ受け取らなかった大岡忠光の姿を目のあたりにしていたからだった。
汚職政治家の汚名を着せられた田沼意次は思う。「人はなぜ身に余る位や物を望むのか。この世には御役を果たすほど愉しいことはない」と。この嘆息こそが意次の本心であったと本書は描く。懸命にただただ仕事をし、「付け届け」を放置していたのだ。これが後に仇となるなるのだが・・・・・・。
しかし突然、家治の死によって、老中を罷免され領地まで失う。家治の嫡男・家基が18歳で事故死しており、権政は一橋家の治済の子息が第11代将軍・徳川家斉となる。これに白川藩の松平定信が老中としての実権を握り、意次らの改革を何から何までひっくり返したのだ。
意次は逍遥として受け止める。「全てを奪われても、志を奪うことは誰にもできない。いつか必ず、次の一里を行くものがある」と。

