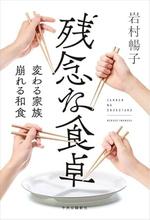 「変わる家族 崩れる和食」が副題。「令和の米騒動」が騒がれ、備蓄米が焦点となっているが、大事な事は背後にある社会自体の構造変化を見ることだ。農業生産自体が高齢化等の構造変化にさらされ、一方で消費の現場では・・・・・・。岩村暢子さんは、「普通の家庭の『和食』は崩れ」「白いご飯は味がないので苦手」「食べ物をあまり噛まないで食べる、『柔らかなもの』を嗜好する人々が増加」「米の朝食は4人に1人。白いご飯を出すと面倒。味噌汁はあってもなくてもいい」「『一汁三菜』って知らない」となっていると本書での徹底調査によって指摘する。確かにその通り。前著の「ぼっちな食卓」で剔抉しているように、「家族バラバラで食事」「朝昼晩3食のリズムのない家族」「親自身に自由とお金と無干渉の考え方」に変わり、家族が崩れ、その食卓も和食が崩れている。
「変わる家族 崩れる和食」が副題。「令和の米騒動」が騒がれ、備蓄米が焦点となっているが、大事な事は背後にある社会自体の構造変化を見ることだ。農業生産自体が高齢化等の構造変化にさらされ、一方で消費の現場では・・・・・・。岩村暢子さんは、「普通の家庭の『和食』は崩れ」「白いご飯は味がないので苦手」「食べ物をあまり噛まないで食べる、『柔らかなもの』を嗜好する人々が増加」「米の朝食は4人に1人。白いご飯を出すと面倒。味噌汁はあってもなくてもいい」「『一汁三菜』って知らない」となっていると本書での徹底調査によって指摘する。確かにその通り。前著の「ぼっちな食卓」で剔抉しているように、「家族バラバラで食事」「朝昼晩3食のリズムのない家族」「親自身に自由とお金と無干渉の考え方」に変わり、家族が崩れ、その食卓も和食が崩れている。
その調査は凄まじいものだ。「食卓」を定点観測。1998年より原則年1回で現在も継続中。総計413人の主婦へのアンケート、8,673食の食卓日記、15,611枚の食卓写真の収集、主婦への詳細面接データはのべ700時間を超える。現代の「食の乱れ批判」というアプリオリな批判目的ではなく、あくまで今日までの社会の変化、人間の変化を時間軸を持って恣意を排して見る。家族、食卓の変化を時系列を正確に測ってみるという全く類例のない調査、そして分析だ。
「一汁三菜」型食事の減少、しかも「焼きそばとおにぎり」「スパゲティーとサンドイッチと肉まん」のように「主食重ね」が増えている。「消える『さしすせそ』と和風調味料」「給食で初めて煮物を食べる子どもたち(家庭で煮物は減っている)」「魚料理も週一回」・・・・・・。さらに、「箸が消えていく(フォークで刺したりスプーンで口に入れたり)」「マグカップの味噌汁・洋皿のご飯」「食器が売れなくなり、お子様ランチに使うような仕切り皿を大人も」「食卓はフリーデスク」「家庭の鍋料理は減った。家族が揃って食卓につき、みんなで同じ料理を食べる機会は減った」・・・・・・。
そして「『好き』を立てれば『和食』は立たず。家族の好物に和食なし」「噛まない。流し込み食べが増え、和食が衰退」「子供にラーメンやパスタ、パンなど、ご飯や味噌汁ではない簡単な食事を与えることが多くなっている」・・・・・・。
「和食遺産は相続放棄?」――。「母親からの伝承料理は大変そうで、私は無理」「結婚前、お米を研いだこともなかった」「ニ世帯同居の交わらない台所と食卓」・・・・・・。
本書に載せられた膨大な写真の生々しさ。日本社会の変化、日本人の変化は著しく、まさに「残念な食卓」「変わる家族、崩れる和食」そのもの。土砂ではないが、深層崩壊の危機にある。食卓が、家族が、人間が、日本社会が・・・・・・。

