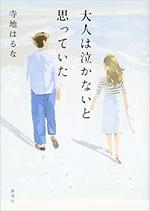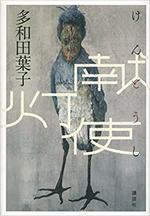 日本の近未来。大きな災厄に見舞われ、東京からほとんどの人が逃げ、しかも日本は極端な鎖国政策をとる。108歳の誕生日を迎えようとしている作家の義郎は、同世代の人と同様、肉体は十分元気、死を奪われた存在だ。しかし若い者ほど体力はなく、動きも遅く、猫背で髪も薄く、季節が変わるたびに身体は変調をきたすほど弱い。歯は退化してパンも噛むのが大変で、"健康"な子供はいない。野生動物もいなくなり、蜘蛛とか鴉、ミミズしかいない。東京には車も走っていない。
日本の近未来。大きな災厄に見舞われ、東京からほとんどの人が逃げ、しかも日本は極端な鎖国政策をとる。108歳の誕生日を迎えようとしている作家の義郎は、同世代の人と同様、肉体は十分元気、死を奪われた存在だ。しかし若い者ほど体力はなく、動きも遅く、猫背で髪も薄く、季節が変わるたびに身体は変調をきたすほど弱い。歯は退化してパンも噛むのが大変で、"健康"な子供はいない。野生動物もいなくなり、蜘蛛とか鴉、ミミズしかいない。東京には車も走っていない。
義郎と共に住んでいるのは曾孫の無名。現在の延長線の未来とはほど遠い、異次元の日常の世界・時空が開示される。男女の性の区別が曖昧となり、あらゆる風習がひっくり返り、何が正しいか判断がつかない。とても考えつかない想像を絶する日本の近未来だ。
義郎は「献灯使」という歴史小説を書いたが、埋めてしまっていた。そして、義郎は115歳、無名は15歳になった。もう無名は自分では歩けない。義郎は丈夫で、朝の犬との"駆落ち"から食事をつくり、働き続ける。そして無名は「献灯使」に選ばれ、インドのマドラスに密航することになるが・・・・・・。
2011年の福島原発事故を受けて書かれたと思われる「献灯使」「韋駄天どこまでも」「不死の鳥」などデストピアの5編。この11月、全米図書賞に選ばれた。
 「教場」の長岡弘樹さんが、18の短編で紡ぐミステリー。人間の思い込み、視覚・聴覚をもってする限界と歪み、加えて自分自身の置かれている状況と境涯――それらが真実を覆い隠す。一寸した心遣いを嗅ぎ取るには、変化を覚知し、耐えるための心の準備がいかに大切か。そんな心の襞をきわめて精緻に鮮やかに描く。
「教場」の長岡弘樹さんが、18の短編で紡ぐミステリー。人間の思い込み、視覚・聴覚をもってする限界と歪み、加えて自分自身の置かれている状況と境涯――それらが真実を覆い隠す。一寸した心遣いを嗅ぎ取るには、変化を覚知し、耐えるための心の準備がいかに大切か。そんな心の襞をきわめて精緻に鮮やかに描く。
18編それぞれが全く違った問題設定にも感心する。「声探偵」「苦い厨房」「風水の紅」「ヴィリプラカの微笑」「仮面の視線」「曇った観覧車」「不義の旋律」「意中の交差点」「色褪せたムンテラ」「遠くて近い森」「虚飾の闇」「レコーディング・ダイエット」「父の川」「嫉妬のストラテジー」「狩人の日曜日」・・・・・・。たしかに「驚きと余韻の残る結末」だ。
 副題は「レフト3・0の政治経済学」。「もう成長はいらない」「財政再建が最重要」という声が日本の左派には根強いが、欧州の左派では「デモクラティック・エコノミー」「反緊縮運動」が起きている。英国労働党のコービンなどが支持を集めている例も顕著だ。「日本のリベラル・左派の躓きの石は『経済』という下部構造の忘却にあった」と指摘する。「経済にデモクラシーを!(ブレイディみかこ)」「ソーシャル・リベラリズムの構築に向けて(北田暁大)」「日本に左派の反緊縮運動を!(松尾匡)」と、"左派"といわれた3氏が語る。刺激的だが、当然といえば当然だ。
副題は「レフト3・0の政治経済学」。「もう成長はいらない」「財政再建が最重要」という声が日本の左派には根強いが、欧州の左派では「デモクラティック・エコノミー」「反緊縮運動」が起きている。英国労働党のコービンなどが支持を集めている例も顕著だ。「日本のリベラル・左派の躓きの石は『経済』という下部構造の忘却にあった」と指摘する。「経済にデモクラシーを!(ブレイディみかこ)」「ソーシャル・リベラリズムの構築に向けて(北田暁大)」「日本に左派の反緊縮運動を!(松尾匡)」と、"左派"といわれた3氏が語る。刺激的だが、当然といえば当然だ。
「下部構造を忘れた左翼」「再分配と経済成長は対立しない」「短期の成長と天井の成長(長期成長)を混同するな」「経済成長を需要・供給のどちらの側から見るか」「文化的な移民反対よりも経済的な動機(生活への不安)が大きかった(コービンの労働党の躍進)」「右か左かの問題ではなく、上か下かの問題が出ている」「反緊縮運動は新自由主義と既存の中道左派を批判して"大きな政府"による手厚い社会政策を提唱」「緊縮こそ欧州の災いの種。いまこそニューディール政策を」「レフトは新しくバージョンアップせよ(来たるべき3・0に向けて)」「金融緩和と規制緩和は全く関係がない」「世界中で生じる左と右のねじれ」「真のポピュリズム(民衆主義)に向かって」「ケインズ経済学と新自由主義」・・・・・・。
アベノミクス、自公連立の公明党の役割等々、3氏の対談にふれつつ考えた。
 「日本の近代を問う」という膨大なテーマは「近代日本の病理を最深部から問う」ということだ。西洋文明への羨望と脅威から始まった明治は、昭和の敗戦に帰結し、平和と議会制民主主義の戦後は経済的豊かさの半面、軽薄な哲学不在の時代をももたらしている。明治が西洋文明を受容するなか、「日本とは、日本人とは何か」が間歇泉のように常に吹き上がる時代であったように、その後も「西洋対アジア」「豊かさと空虚」「ナショナリズムとパトリオティズム」「国家と個人」「権威・文化としての天皇と権力の天皇」「文明と文化」「思考と肉体」「議会制民主主義とファシズム」等、格闘が繰り返されてきた。現代はその格闘が減衰していることこそが問題だと私は思う。
「日本の近代を問う」という膨大なテーマは「近代日本の病理を最深部から問う」ということだ。西洋文明への羨望と脅威から始まった明治は、昭和の敗戦に帰結し、平和と議会制民主主義の戦後は経済的豊かさの半面、軽薄な哲学不在の時代をももたらしている。明治が西洋文明を受容するなか、「日本とは、日本人とは何か」が間歇泉のように常に吹き上がる時代であったように、その後も「西洋対アジア」「豊かさと空虚」「ナショナリズムとパトリオティズム」「国家と個人」「権威・文化としての天皇と権力の天皇」「文明と文化」「思考と肉体」「議会制民主主義とファシズム」等、格闘が繰り返されてきた。現代はその格闘が減衰していることこそが問題だと私は思う。
「思想家とは、時代を『診る』医者である」と先崎さんはいう。時代の変化相のなかで、個人の孤立と不安を察知し、時代への違和感を持ち続けること。人間の複雑さ、不可解さを抱きしめ、思考停止の裁断を戒める骨太の誠実さを持つこと。本書では、福澤諭吉、中江兆民、高山樗牛、頭山満、保田與重郎、丸山眞男、江藤淳、竹内好、橋川文三、吉本隆明、三島由紀夫、網野善彦、高坂正堯ら錚々たる骨太の思想家23人を抽出して論じ、さらに自ら「明治と現代」を論述する。鮮やかな「近代日本の思想史」となっている。