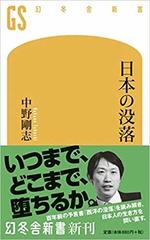 2018年の今年は、シュペングラーの「西洋の没落」が出てちょうど100年。「西洋の没落」は単線的進歩史観を切る。ゲーテがファウストで示した限界を超えて永遠、無限空間に向かおうとする西洋文化の魂が、18世紀に頂点を示して19世紀、20世紀と没落し、21世紀には西洋文化は末期症状を迎えると予言した。本書はそれを読み解き、現代の世界が直面している諸問題を剔抉する。すさまじい知の力業だ。
2018年の今年は、シュペングラーの「西洋の没落」が出てちょうど100年。「西洋の没落」は単線的進歩史観を切る。ゲーテがファウストで示した限界を超えて永遠、無限空間に向かおうとする西洋文化の魂が、18世紀に頂点を示して19世紀、20世紀と没落し、21世紀には西洋文化は末期症状を迎えると予言した。本書はそれを読み解き、現代の世界が直面している諸問題を剔抉する。すさまじい知の力業だ。
シュペングラーの予言は根源的で、驚くほど現代を照射する。そして、本書は「現代を照射している」とだけ言っているのではなく、「政治のポピュリズム」も「金融」「技術」の問題も、通説に流れて問題設定自体ができていないことを鋭角的に指摘する。ベルクソンの「問題は正しく提起された時、それ自体が解決である」ということであり、「リベラリズム」の軽薄さをも暴く。
「経済成長の終焉、アジアの台頭」「グローバル・シティの出現、地方の衰退そして少子化」「"ポスト・トゥルース"の政治とポピュリズム」「リベラリズムの破綻」「人間と技術――機械の支配と技術の拡散、際限なき人間の欲望」「金融の支配、貨幣の独裁」「貨幣と財政――"商品貨幣論と信用貨幣論"から見る財政問題」「予言の方法――西洋中心の進歩史観を破壊した転回の基軸はゲーテの『人間精神の形態学』」「覚悟存在(知性)と現存在(生命全体)の相克が繰り広げる栄枯盛衰のリズム」――。
さて今の日本。上記の通り、いずれからも日本(先進諸国も)は逃れられず、西洋の没落の運命に巻き込まれている。「没落の運命を受け入れざるを得ない時が来たようだ。ただし、それは悲観や諦念に陥るということではない。シュペングラーのように、徹底して懐疑し、執拗に批判する能力と精神力を身につけるということである」という。没落する世界を直視し、生き抜こうとする猛き覚悟ということだ。
 日本史というと、「武将の武勇伝」や「英雄の物語」にどうしても偏る。その時、民衆はどう生きたのか。いつも「戦争の被害者」か。それだけではない「たくましい民衆」の姿、「生き延びる民衆」「加害者としての民衆」「チャンスとしての戦乱」の姿を、国際日本文化研究センターの学者が、語り、討論する。面白い。
日本史というと、「武将の武勇伝」や「英雄の物語」にどうしても偏る。その時、民衆はどう生きたのか。いつも「戦争の被害者」か。それだけではない「たくましい民衆」の姿、「生き延びる民衆」「加害者としての民衆」「チャンスとしての戦乱」の姿を、国際日本文化研究センターの学者が、語り、討論する。面白い。
日本史上、最大の敗戦である「白村江の戦いと民衆」(倉本一宏氏)――。唐の軍勢は国家軍、倭国軍は豪族軍の寄せ集めで地域の農民を連れての出兵。西日本の豪族は疲弊し、壬申の乱の勝敗にも影響を与えた。「応仁の乱と足軽」(呉座勇一氏)――。応仁の乱で初めて登場する足軽には「合戦で活躍する軽装の歩兵部隊」と「略奪に精を出す悪党・強盗」の二面性がある。土一揆、徳政一揆にも関連。慢性的な飢饉状態と治安悪化で毎晩強盗が放火。1400年代の京都を襲った土一揆のひどさと、応仁の乱でこれらが足軽となって略奪行為をした。
「オランダ人が見た大坂の陣」(フレデリック・クレインス氏)――。戦場から避難する民衆、焼き払われた大坂の姿。大坂の陣とアントワープの大虐殺。「禁門の変――民衆たちの明治維新」(磯田道史氏)――。京都の大半が丸焼けとなる大事件。長州の潜伏ゲリラを恐れて、会津や薩摩が火をつける。借家がなく、金を貸すものがいない。京都が首都になれなかった理由が明かされる。鉄砲焼けで火の海となった京都と、京都守護職・松平容保による雇用政策(会津小鉄や五条楽園)・・・・・・。
「とにかく生き残らなければならない民衆」の姿、戦乱にも災害にも「生き延びなくてはならない民衆」の姿が浮き彫りにされる。
 清冽な余韻が残る。葉室麟、最後の長編小説ということもあろう。他の小説まで思い出し、生老病死の人生の生き方に思いが及ぶ。
清冽な余韻が残る。葉室麟、最後の長編小説ということもあろう。他の小説まで思い出し、生老病死の人生の生き方に思いが及ぶ。
舞台は激しい政争の江戸幕府。5代将軍綱吉、6代将軍家宣、7代将軍家綱の元禄、宝永、正徳の時代。権勢を振るった柳沢吉保、それを退け「正徳の治」を推し進める新井白石ら、そしてその背景として松之廊下の刃傷事件・赤穂浪士討ち入り事件と怨讐が描かれる。赤穂浪士を賞讃する世間の空気、「前の将軍家(綱吉)は御台所の信子様に殺され、御台所はすぐに自害した」との江戸の噂、刃傷事件の背後にある政争、討ち入り後の吉良家への厳しい仕打ち・・・・・・。そうした濁流に巻き込まれて生きる元小城藩士・雨宮蔵人、妻・咲弥、娘・香也、吉良家の家人・冬木清四郎、蔵人の従兄弟・清厳、越智右近(家宣の弟、松平清武)、刺客となる隠密等々。生死をかけた攻防は、息苦しいほどだ。
「色も香も昔の濃さに匂へども植ゑけむ人の影ぞ恋しき」「春ごとに花のさかりはありなめどあひ見むことはいのちなりけり」「君にいかで月にあらそふほどばかりめぐり逢ひつつ影を並べん」――蔵人と咲弥の交した歌に、思いの深さ、堅固さ、絆が表われる。「おのれが大切に思うもののために身を捧げる覚悟」「ひとは皆、おのれにとっていとしき者のために生きている」「わが剣はひとの思いを守るためにある」「勝てぬとわかっていても、臨まねばならぬ戦いがひとにはある」「勝つとわかっている戦いしかしない者は、武士ではない」・・・・・・。
幕府の暗闇のなかで、清冽な精神と絆、生きざまを描いたいかにも葉室麟の本領を感じさせる長編。
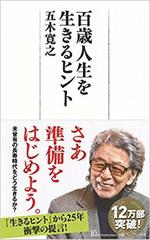 「人生50年」「60歳還暦」「人生70古来稀なり」――。それらを前提につくられてきた人類の価値観やシステム。それが今、ひっくり返って突然のように「人生100年時代」がやってきた。ここで意識を変えよう、恐れるに足らず、備えを共に考えてみよう。「百歳人生を生きるヒント」を85歳の五木さんが"つぶやき"、提示している。これまでの人生観や死生観の転換。新しい生き方、新しい哲学を打ち立てることだ。
「人生50年」「60歳還暦」「人生70古来稀なり」――。それらを前提につくられてきた人類の価値観やシステム。それが今、ひっくり返って突然のように「人生100年時代」がやってきた。ここで意識を変えよう、恐れるに足らず、備えを共に考えてみよう。「百歳人生を生きるヒント」を85歳の五木さんが"つぶやき"、提示している。これまでの人生観や死生観の転換。新しい生き方、新しい哲学を打ち立てることだ。
「さあ準備をはじめよう」「"人生50年"から"人生100年"への大変換」「後半の人生は"下山"の思想」として50歳から10歳ごとに人生を見直す。「50代の事はじめ――長い下り坂を歩く覚悟、寄りかからない覚悟」「60代の再起動――群れから離れる覚悟、孤独の中で見えてくるもの、諦める(明らかに究める)」「70代の黄金期――60代にも増して生命の躍動感を覚える、学びの楽しさに目覚める、年代にあわせた食養生、幸せの期待値を下げる」「80代の自分ファースト――嫌われる勇気をもつ、周囲や群れの掟に迎合しないで自分に忠実に生きる、死の影を恐れない覚悟、明日のことを思い煩うな」「90代の妄想のすすめ――回想世界・郷愁世界に遊ぶ、見える世界から見えない世界の住人に」――。そして「この取るに足らない一日が百年つづいて、私たちの命を、次の次元にはこんでくれるかもしれないと思うと、この世もなかなか味わい深いものだと感じることができる」と語る。
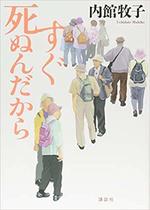 人生100年時代。今、最も取り組むべき大事なテーマ――70代、80代をどう生きるか。とくに夫を失った一人暮らしの70代、80代女性はどう生きるか。内面のつぶやきも含めて実にテンポよく描く。時間を経るごとに左右に揺れ動きながら逡巡し、心がしだいに収斂していく。生々しく、面白い。
人生100年時代。今、最も取り組むべき大事なテーマ――70代、80代をどう生きるか。とくに夫を失った一人暮らしの70代、80代女性はどう生きるか。内面のつぶやきも含めて実にテンポよく描く。時間を経るごとに左右に揺れ動きながら逡巡し、心がしだいに収斂していく。生々しく、面白い。
78歳の忍ハナ。10年前に実年齢より上に見られた「70ちょっと事件」にショックを受ける。以後、外見こそ大事と「外見磨き」に精を出し、今や若く、美しい。そんなハナは、酒屋を商ってきた夫の岩造にとって自慢の女房だ。ところが、仲の良かったその岩造が突然他界し、心が沈む。それに追い討ちをかけるように、愛人、隠し子まで発覚する。足下が崩れるような衝撃をハナは受け、怒りと喪失感がのしかかる。
「『すぐ死ぬんだから』というセリフは、高齢者によって免罪符である。それを口にすれば、楽な方へ楽な方へと流れても文句は言われない。・・・・・・80代中心の集まりに出たことがある。免罪符のもとで生きる男女と、怠ることなく外見に手をかけている男女に、くっきりと二分されていた。外見を意識している男女ほど、活発に発言し、笑い、周囲に気を配る傾向があった」「重要なのは品格のある衰退。衰え、弱くなることを受けとめる品格を持つこと。"若い者に負けない""何としても老化を止める。アンチエイジングだ"とあがくことは品格のある衰退ではない」――。
70代、80代をどう生きるか。おそらく100人100色、桜梅桃李。家族構成、家族や友人が近くにいるかどうか。住まい住居の有無、年金・預金等の経済状況、健康状態・・・・・・。本書のテンポと明るいタッチのなかで、読者は皆、考えさせられるに違いない。面白い。

