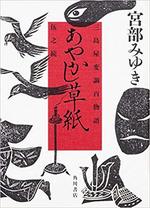 三島屋変調百物語伍之続。江戸・神田の筋違御門先で袋物を商う三島屋で、風変わりな百物語を続けるおちか、側には従兄の富次郎やお勝。三島屋の変わり百物語は、聞いて聞き捨て、語って語り捨て、心のわだかまり、澱が吐き出される。素朴で人情味ある江戸の町人文化は、生老病死や怪異とも隣り合わせでもある。
三島屋変調百物語伍之続。江戸・神田の筋違御門先で袋物を商う三島屋で、風変わりな百物語を続けるおちか、側には従兄の富次郎やお勝。三島屋の変わり百物語は、聞いて聞き捨て、語って語り捨て、心のわだかまり、澱が吐き出される。素朴で人情味ある江戸の町人文化は、生老病死や怪異とも隣り合わせでもある。
「開けずの間」――塩断ちが元凶で「行き違い神」を呼び込んだ悲惨で悲しい物語。「だんまり姫」――亡者を起こす変わった声「もんも声」をもつ女が、女中となって大名家の過去の悲しい事件と向き合う。そこには呪か毒で殺害された"一国様(お次様)"の"怨"が行き場を失っていた。そして加代姫に声が戻るのだ。「あやかし草紙」――100両という破格の値段で写本を請け負った武士の数奇な運命、寿命を縮める冊子と、おちかの決断。それに「面の家」「金目の猫」の5篇。江戸のゆったり流れる時間と人情のなかに生ずる"怪談"だが、むき出しの人間の悲しみ、愚かさ、支えあい、縁と業などが伝わってくる。江戸社会が生み出した"怪談""怪異"は身近な所にあるが、その解決の仕方も江戸社会。
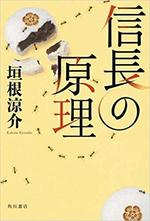 信長研究、本能寺の変の真実――。歴史は勝者の歴史となりがちだが、信長、光秀と本能寺の変は、学際的研究も小説・ドラマでも語り尽くされている感がある。しかし、本書はきわめて面白い。歴史の事象、事件を追うというより、信長の内面、それを取り巻く佐久間信盛、林秀貞、柴田勝家、丹羽長秀、滝川一益、羽柴秀吉、明智光秀らの信長に対する恐怖、不安、懊悩の内面を徹底して描く。裏切る松永弾正や荒木村重の虚無・意地等の心象はド迫力で迫ってくる。武将の働き方についての「1:3:1の蟻の法則」。「武将をも所詮は虫けらとしか見ぬ信長への恐怖と絶望」「神仏を否定しても存在する森羅万象の法」「異次元の信長の思考と及ばぬ家臣の距離」‥‥‥。考えさせられること多き力作。
信長研究、本能寺の変の真実――。歴史は勝者の歴史となりがちだが、信長、光秀と本能寺の変は、学際的研究も小説・ドラマでも語り尽くされている感がある。しかし、本書はきわめて面白い。歴史の事象、事件を追うというより、信長の内面、それを取り巻く佐久間信盛、林秀貞、柴田勝家、丹羽長秀、滝川一益、羽柴秀吉、明智光秀らの信長に対する恐怖、不安、懊悩の内面を徹底して描く。裏切る松永弾正や荒木村重の虚無・意地等の心象はド迫力で迫ってくる。武将の働き方についての「1:3:1の蟻の法則」。「武将をも所詮は虫けらとしか見ぬ信長への恐怖と絶望」「神仏を否定しても存在する森羅万象の法」「異次元の信長の思考と及ばぬ家臣の距離」‥‥‥。考えさせられること多き力作。
さて「信長」と「本能寺の変」――。「怨恨説」「野望説」「長宗我部征伐阻止、土岐氏存続説」「信長の家康殺害計画と光秀・家康同盟説」「唐入り阻止説」など、数多くの説があるが、本書では信長に追い詰められていく光秀の内面がぐいぐい描かれる。「頼りとする斎藤利三への切腹命令」「家康殺害の密命と領地替え」「長宗我部征伐」‥‥‥。「ときは今 あめが下しる 五月哉」は「下なる」との解釈同様、五月雨の情景を詠んだもので、謀反の意味はないとしているが、利三、秀満は備前の諺「一人ならば心安んじ、二人ならまだ良し。三、四人は穏やかならず。五人にては、まず洩れ落ち候」によって、「外に洩れ出ることは必定」と「決起するしかない」と腹を決める。
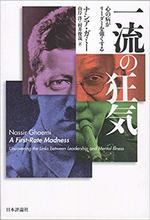 「心の病がリーダーを強くする」が副題。「危機の時代にあっては、精神的に正常なリーダーよりも精神的に病んだリーダーの指揮の下にあるほうが私たちはうまくやっていける」「典型的な平時のリーダーは理想主義的で、世の中や自分に幾分楽観的にすぎ、苦しみや痛みに鈍感であり、つらい経験をしたことがない」「危機の時代の偉大なリーダーは、たいてい優れた知性をもち、身体的に健康を損なっていることが多い。生い立ちは恵まれているが、葛藤に満ちた家庭状況・・・・・・パーソナリティ特性と生い立ちの状況は、躁病やうつ病のような精神疾患、あるいは気分高揚性のような異常な気質とも相関が認められる」「彼らの弱さこそが彼らの強さの秘密なのだ」という。時代の危機と格闘した偉大なリーダーの精神分析に踏み込む。しかもホモクリット(平凡人)がリーダーであれ、一般大衆であれ、大失敗をすることを示すことにより、精神疾患をもつ人への偏見を寛容に変えるという人間学の変更をも志向する。きわめて大胆、ユニークで興味深い。
「心の病がリーダーを強くする」が副題。「危機の時代にあっては、精神的に正常なリーダーよりも精神的に病んだリーダーの指揮の下にあるほうが私たちはうまくやっていける」「典型的な平時のリーダーは理想主義的で、世の中や自分に幾分楽観的にすぎ、苦しみや痛みに鈍感であり、つらい経験をしたことがない」「危機の時代の偉大なリーダーは、たいてい優れた知性をもち、身体的に健康を損なっていることが多い。生い立ちは恵まれているが、葛藤に満ちた家庭状況・・・・・・パーソナリティ特性と生い立ちの状況は、躁病やうつ病のような精神疾患、あるいは気分高揚性のような異常な気質とも相関が認められる」「彼らの弱さこそが彼らの強さの秘密なのだ」という。時代の危機と格闘した偉大なリーダーの精神分析に踏み込む。しかもホモクリット(平凡人)がリーダーであれ、一般大衆であれ、大失敗をすることを示すことにより、精神疾患をもつ人への偏見を寛容に変えるという人間学の変更をも志向する。きわめて大胆、ユニークで興味深い。
例えばケネディ。アディソン病に長期間苦しみ、一方では気分高揚性の気質(豊富なエネルギー、性欲亢進、仕事への熱中、社交性、危険を冒すこと)をもつ。連日のように薬づけ、ステロイドづけ。ケネディ大統領在任1000日の後半、医師団が理に適ったステロイド乱用を抑え込み、弱々しい前半のケネディではなく輝かしい成果をあげた。また、ヒトラーはかなり重い双極性障害をもっていた。「1937年までの間は障害はよい方向に作用し、カリスマ性、不屈の態度、独創性を高める方向に作用したが、それ以降、連日の静脈内注射によるアンフェタミン投与のせいで躁とうつのエピソードがひどくなり、リーダーとしての能力が損われた」という。さらにチャーチルの重篤な反復性のうつ病(気難しく、攻撃的、自信の絶頂にいるか、ひどいうつの底にいるか)、リンカンの重いうつ病(うつは、現実的なものの見方と共感能力を彼に授けた)、ガンディーやキングのうつ病と共感能力の強い結び付き・・・・・・。
「ネガティブな面や危険性も十分認識したうえで、精神疾患というものが人類の最高の特質の証拠でもあることを人々が理解するようになっていくだろう」と著者はいい、訳者の村井氏は本書の意義と試みを認めつつ「疾患のもつ偉大な力を強調しすぎることは・・・・・・狂気に対しての落とし穴もある」「双極性障害とうつ病を同列にみている点にも日本の精神科医は違和感をもつ方も多いだろう」という。しかし、いずれにしても面白い刺激的な書だ。
 なんとも奇妙、荒唐無稽な物語。しかし、なぜか心持良いのは、主人公・朝霧夕霞が元気で優しい、情に厚く、突っ込んでいく魅力ある女性であるということ。こういう女性はたしかに居る。
なんとも奇妙、荒唐無稽な物語。しかし、なぜか心持良いのは、主人公・朝霧夕霞が元気で優しい、情に厚く、突っ込んでいく魅力ある女性であるということ。こういう女性はたしかに居る。
就職に失敗し続けていた夕霞が国土交通省の臨時職員募集の貼紙を見つけ、採用されたのが、国土交通省国土政策局の「幽冥推進課」。ここの仕事は、道路、橋、都市などインフラ整備にあたって、「この世に未練があって、土地や建物から離れられなくなっている地縛霊を説得し成仏させること」だという。職員も辻神課長、火車先輩、百々目鬼女史しかおらず、皆妖怪。つまり夕霞は初の人間職員だ。
1章ではビルの屋上から飛び降りた無名のアイドル藍田ミサ、2章では長期出張を終え自宅へ車で帰る際、トンネルから無灯火で出てきたトラックと正面衝突した山田篤弘、3章では150年前の慶応年間、橋を守るための人柱となった少女(姫)――。いずれも未練を残してその地から離れられないでいる。
夕霞はそれに体当たりで挑むのだ。
 ネット社会の急進展は、社会も人間も変質させている。たしかに便利ではある。しかし、デジタルテクノロジーの進化はめざましく、私たちの生活に介入し、いつの間にか多くの個人情報が集積され、「世論は操作」され、「いいね!は悪用」され、「偽ニュースに誘導」され、危険にさらされるという。「イギリスのEU離脱」や「アメリカ大統領選」でも現実にそうした動きが顕わとなった。世論がより操作される時代になったのだ。「世の中のデジタル革命に対する用意が不足している」「ネット上のニュースで何が本当で何が偽ニュースであるのか、見分けるためのメディアリテラシーの教育が必要になってくる」「ここ数年(2014年のウクライナ危機)の異変に気付け」「個人データが収集されてビッグデータとして売られ、"換金化される"ネット資本主義が民主主義を、人と人との関係を変形させていることに注意せよ」「一番の防衛は無視することだが、簡単なことではない」・・・・・・。生々しい現実が報告され、「操作される世論と民主主義(本書の副題)」への警告が発せられる。
ネット社会の急進展は、社会も人間も変質させている。たしかに便利ではある。しかし、デジタルテクノロジーの進化はめざましく、私たちの生活に介入し、いつの間にか多くの個人情報が集積され、「世論は操作」され、「いいね!は悪用」され、「偽ニュースに誘導」され、危険にさらされるという。「イギリスのEU離脱」や「アメリカ大統領選」でも現実にそうした動きが顕わとなった。世論がより操作される時代になったのだ。「世の中のデジタル革命に対する用意が不足している」「ネット上のニュースで何が本当で何が偽ニュースであるのか、見分けるためのメディアリテラシーの教育が必要になってくる」「ここ数年(2014年のウクライナ危機)の異変に気付け」「個人データが収集されてビッグデータとして売られ、"換金化される"ネット資本主義が民主主義を、人と人との関係を変形させていることに注意せよ」「一番の防衛は無視することだが、簡単なことではない」・・・・・・。生々しい現実が報告され、「操作される世論と民主主義(本書の副題)」への警告が発せられる。
「ビッグデータは監視し、予測し、差別する」「データブローカーという新しい産業」「ソーシャルメディアから流出する膨大な個人データ」「ビッグデータとアルゴリズムを応用したデジタル資本主義のもとでは、顧客ごとの価格が設定される(定価がなくなる)」「IoTは監視機器でもある」「『心理分析』データを使った選挙広告キャンペーン」「迷っているスイングボーター有権者を取り込む戦略」「小グループへの個別広告(マイクロターゲット広告)」「背後にいる天才プログラマーの富豪(ロバート・マーサー)」「ソーシャルメディアは敵か、味方か」「ツイッターとボット」「ロシアのサイバー作戦が欧米のポピュリズムを扇動する」「IoTで高まるハッキングの脅威」「ポスト冷戦時代はサイバー戦争時代」「デジタル時代の民主主義と国民投票」「ネット利用者が一般化するなか、ネット社会には"異なる事実"が存在することを認識せよ」「厳しいドイツのヘイトスピーチ法」「拡散した流言飛語は人道危機に発展」・・・・・・。
「捏造され、誘導され、分断される」時代の危険性と脆弱性を真剣に考えなければならない。

