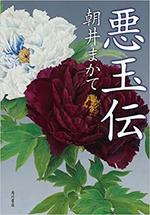 吉宗や大岡越前をも巻き込んだ"辰巳屋一件""辰巳家疑獄"――。大坂の炭問屋・木津屋の吉兵衛のもとに、兄が急死したとの訃報が伝えられる。放蕩三昧であった吉兵衛が生家の辰巳屋に戻り、葬儀をはじめとして実家をまとめようとするが、兄の養子・乙之助を操り、やりたい放題の大番頭・与兵衛の大反撃にあう。事態は相続争いに発展。自ら逃げ出したはずの乙之助が、なんと奉行所に訴状を出す。裏には与兵衛、さらに泉州の廻船問屋・唐金屋与茂作(乙之助の父)がいた。大坂の奉行所では当然ながら訴状は退けられたものの、次には江戸の御箱にまで訴えを投げ入れる。江戸の将軍・吉宗や大岡越前守忠相をも巻き込む騒動になるが、牢に入れられた吉兵衛は頑として罪を認めない。
吉宗や大岡越前をも巻き込んだ"辰巳屋一件""辰巳家疑獄"――。大坂の炭問屋・木津屋の吉兵衛のもとに、兄が急死したとの訃報が伝えられる。放蕩三昧であった吉兵衛が生家の辰巳屋に戻り、葬儀をはじめとして実家をまとめようとするが、兄の養子・乙之助を操り、やりたい放題の大番頭・与兵衛の大反撃にあう。事態は相続争いに発展。自ら逃げ出したはずの乙之助が、なんと奉行所に訴状を出す。裏には与兵衛、さらに泉州の廻船問屋・唐金屋与茂作(乙之助の父)がいた。大坂の奉行所では当然ながら訴状は退けられたものの、次には江戸の御箱にまで訴えを投げ入れる。江戸の将軍・吉宗や大岡越前守忠相をも巻き込む騒動になるが、牢に入れられた吉兵衛は頑として罪を認めない。
「一町家の跡目争いが、何でここまで大事になってますのや」「町人風情の跡目争いで、何ゆえお武家様が命を落とさんとなりまへんのや」――。「大坂」対「江戸」、「銀」と「金」の貨幣の競り合い、吉宗の治世と賄賂、「大坂」対「泉州」など、背景には時代そのものの構造が投影され、各人の思惑が交錯する。凄惨きわまりない酷い仕打ちを受けながら、妥協もしない、屈しない、信念をいささかも曲げない吉兵衛だが、「何故に強情にそんなに頑張ったのか」「悪玉とは何か」「どれだけの人の人生を不幸に巻き込んだかが悪党の度合いか」等々の哲学的問いも漂い、迫力ある小説となっている。
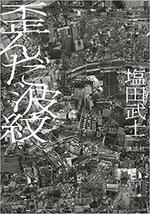 5つの短編が合流する。「情報に騙されるな。意図的な悪意に満ちた戦略的なものもある」ことを示唆する。ネット時代は情報洪水の時代――。真実もあれば、誤報・虚報、フェイクニュースがあふれ、なかには意図的に虚報を流し続ける集団もいる。既成の新聞、テレビ、よりセンセーショナルな週刊誌等があるなか、それに対して個人が情報発信するネットは従来の世界を一変させている。「レガシー・メディアの信用を低下させる」「第4権力マスメディアに対する第5権力」「正しいより面白い、人の役より自分の役に立つ」・・・・・・。情報に対する考え方が根本的に変わってきている。そのなかで記者たちはどう動くか。一般市民はどうするか。「記者は現場やで」「浅瀬に留まるな」との声が響く。
5つの短編が合流する。「情報に騙されるな。意図的な悪意に満ちた戦略的なものもある」ことを示唆する。ネット時代は情報洪水の時代――。真実もあれば、誤報・虚報、フェイクニュースがあふれ、なかには意図的に虚報を流し続ける集団もいる。既成の新聞、テレビ、よりセンセーショナルな週刊誌等があるなか、それに対して個人が情報発信するネットは従来の世界を一変させている。「レガシー・メディアの信用を低下させる」「第4権力マスメディアに対する第5権力」「正しいより面白い、人の役より自分の役に立つ」・・・・・・。情報に対する考え方が根本的に変わってきている。そのなかで記者たちはどう動くか。一般市民はどうするか。「記者は現場やで」「浅瀬に留まるな」との声が響く。
「黒い依頼」――地方紙の記者が、フェイクニュースを作ってしまう。誤報ではなく虚報の悪に堕していく話。「共犯者」――かつて同僚であった記者仲間・垣内が自殺した。その直前、電話をしてきたが、相賀が気付いたのは死んだ後だった。残された遺品を調べてみると、かつての「サラ金」地獄の取材資料・切り抜きがあり、その背後には1人の女教師の人生を狂わした誤報記事があり、なんと自らが関係していたことに驚愕する。「ゼロの影」――元記者の野村美沙が勤めている語学学校のビルで盗撮事件が起き、男が逮捕されたが、なぜか原稿は闇に葬られ、警察も沈黙したまま。報じないこともまた誤報だが、裏に潜んだ秘密とは。「Dの微笑」――コンビを組んでいた相方が売れていくのに嫉妬した男が、捏造記事・ニュースをつくる。それを暴いた記者がまたウェブメディアにそれを流すというドンデン返しの話。これまでと違うネット時代。「書き手がその都度媒体を選ぶ。それが『マス以後』の世界だ」という。記者を鳥籠から解き放つ解放感・歪んだ微笑が生ずる怖さ。「歪んだ波紋」――これまでの4話が合流する。意図的に虚報を流し続け、フェイクニュースの作り方まで指南する集団「メイク・ニュース」に、安田・桐野・徳田らが加わっており、三多園が率いる「ファクト・ジャーナル」も標的にされる。彼らの意図とは・・・・・・。
 「近江商人、温州企業、トヨタ、長期繁栄の秘密」が副題。「売り手よし、買い手よし、世間よし」の「三方よし」の近江商人。小さな領地から飛び出し、多店舗展開、店員は信頼できる同郷人、相互扶助と共存共栄、社会貢献で広げていく。世界最強の田舎商人集団で欧州に一大コミュニティーとネットワークをつくる温州人。日用消費財に狙いを定め、加工業と卸・小売業で栄える強靭な相互扶助システムをつくって繁栄を築く。そして高い競争力を維持するトヨタのサプライチェーン。
「近江商人、温州企業、トヨタ、長期繁栄の秘密」が副題。「売り手よし、買い手よし、世間よし」の「三方よし」の近江商人。小さな領地から飛び出し、多店舗展開、店員は信頼できる同郷人、相互扶助と共存共栄、社会貢献で広げていく。世界最強の田舎商人集団で欧州に一大コミュニティーとネットワークをつくる温州人。日用消費財に狙いを定め、加工業と卸・小売業で栄える強靭な相互扶助システムをつくって繁栄を築く。そして高い競争力を維持するトヨタのサプライチェーン。
そこにあるのは、同じコミュニティーのメンバー間で共有される「同一尺度の信頼」と、そこから派生し協力し合う「準紐帯」。長期にわたる参加者同士の相互作用によって、強靭な企業コミュニティーが進化していく。その目に見えない共通財(関係資本)、「コミュニティー・キャピタル」の重要性を指摘する。近江商人も温州人も時代の変化のなかで、凝集性の負の側面にもさらされ、血縁・地縁を超える新たな信頼関係の構築が飛躍のためには不可欠となる。トヨタのサプライチェーンも、アイシン火災事故や東日本大震災時のルネサス那珂工場の復旧等で、その信頼・準紐帯はより強化されることになる。企業等の長期繁栄のための「コミュニティー・キャピタル論」が具体的に展開される。
 結婚して20年、52歳の加能鉄平は、たまたま妻にかかってきた弁護士からの電話に出て、驚愕の事実を知る。妻・夏代が伯母から34億円もの遺産を相続し、それが現在総額で48億円にもなっているというのだ。リストラ、左遷、そして今、身内の会社でも閑職に追いやられていた鉄平にとって、衝撃であるとともに、人生そのものを揺さぶられることになる。「なぜ妻はこれを隠し、手をつけないできたのか」――。それだけでなく、別居する長女の妊娠、長男の同棲等、鉄平の知らない秘密が次々に明らかになる。加えて大爆発事故を起こして加速する社内抗争。「俺だけが知らない。どいつもこいつも勝手ばかりして」との心の空洞は「俺はいったい何をしようとしているのか」へと人生そのものの根源的問いかけへと進んでいく。
結婚して20年、52歳の加能鉄平は、たまたま妻にかかってきた弁護士からの電話に出て、驚愕の事実を知る。妻・夏代が伯母から34億円もの遺産を相続し、それが現在総額で48億円にもなっているというのだ。リストラ、左遷、そして今、身内の会社でも閑職に追いやられていた鉄平にとって、衝撃であるとともに、人生そのものを揺さぶられることになる。「なぜ妻はこれを隠し、手をつけないできたのか」――。それだけでなく、別居する長女の妊娠、長男の同棲等、鉄平の知らない秘密が次々に明らかになる。加えて大爆発事故を起こして加速する社内抗争。「俺だけが知らない。どいつもこいつも勝手ばかりして」との心の空洞は「俺はいったい何をしようとしているのか」へと人生そのものの根源的問いかけへと進んでいく。
「人生」「夫婦」「男女」「家族」「愛」「信頼」・・・・・・。大事件、大災害、生死の極みにはじめて顕わになる人間のコアー・核心。幸福感における男の「煩悩即菩提」、女の「生死即涅槃」の差異を浮かび上がらせている。
 たしかに江戸の町は、賑やかで粋で、色彩鮮やかで、自由で"とっぽい"。商人も職人も、こんなものを売り買いしていたのか、それで商売が成り立っていたのか。江戸の季節や祭りとのかかわり、風習などがのびやかにに描かれて楽しい。
たしかに江戸の町は、賑やかで粋で、色彩鮮やかで、自由で"とっぽい"。商人も職人も、こんなものを売り買いしていたのか、それで商売が成り立っていたのか。江戸の季節や祭りとのかかわり、風習などがのびやかにに描かれて楽しい。
8つの短編よりなっているが、「ぞっこん(看板書き栄次郎の筆)」「千両役者(贔屓客の心)」「晴れ湯(湯場のお晴)」「莫連あやめ(義姉の正体とは)」「福袋(当時からあったのか大食い大会)」「暮れ花火(枕絵が昔の恋を照らす)」「後の祭(神田祭の祭掛の大変さ)」「ひってん(卯吉と寅次が山ほどの櫛を拾うことに)」――。
歌丸さんらにやってもらったかのような"読む落語"となっている。江戸風情があふれる。

