 宇宙のリズム、生命のリズム、月の盈ち虧け、海の波、心拍・呼吸、舞踊のリズム、世阿彌の「序破急」、「鹿おどし」の構造――。「無意識がもたらす正確さ、断絶が増幅する流動、死を含むことで生きる生命、いずれを見ても逆説的というほかないが、この逆説性こそがリズムの本質である」という。宇宙論、生命論の本質に迫るまさに「リズムの哲学ノート」に身震いする思いだ。常に、仏法の「法概念」「諸法実相 如実知見」を考えながら読んだが、難解のなかにも開けるものがあり、嬉しい思いがした。言語絶する世界に踏み込む凄い著作だ。
宇宙のリズム、生命のリズム、月の盈ち虧け、海の波、心拍・呼吸、舞踊のリズム、世阿彌の「序破急」、「鹿おどし」の構造――。「無意識がもたらす正確さ、断絶が増幅する流動、死を含むことで生きる生命、いずれを見ても逆説的というほかないが、この逆説性こそがリズムの本質である」という。宇宙論、生命論の本質に迫るまさに「リズムの哲学ノート」に身震いする思いだ。常に、仏法の「法概念」「諸法実相 如実知見」を考えながら読んだが、難解のなかにも開けるものがあり、嬉しい思いがした。言語絶する世界に踏み込む凄い著作だ。
「認識と行動の新しい関係を示唆する考察はすでに哲学界にも少なからず現れている。典型的なのがポランニーの暗黙知論であり、それに先立つベルクソンの自由論であった。・・・・・・暗黙知の主体は理性でも意識でもなく、訓練され習慣づけられ、それ自体『自主的秩序』と化した身体であった。・・・・・・またベルクソンの自由は意志の選択とは正反対に、危機に臨んで純粋持続が自生的に発動する現象であった。・・・・・・そして本稿では長い考察を一貫して、認識の主体を身体そのものと見なすとともに、認識の主体と客体の二項対立も乗り越えようと努めてきた・・・・・・」「リズムの特性の第一はそれがもっぱら顕現する現象であり、ひたすら感知することはできても、それを造りだすことはできないという事実である。そしてその第二の特色はそれを感じることが喜びであり、その認識が解放感に直結しているという不思議である。たしかにすべて知ることは喜びを伴うが、リズムを知ることの歓喜は次元を異にしている」・・・・・。
リズムを体感しながら生きる。みずからが「運ばれていること」を深く感知する。ベルクソン、ポランニーを経て、最後の「人間至上主義を超えて」に至って、満たされた感がする。
 仏の歴史と文化と伝統、神と人間と教会、欧州の戦乱・攻防――。その激しくも深く蓄積されてきた思想・哲学と社交の中から抉り出された人間学。ルイ14世の時代に生きた文人ラ・ロシュフーコーの「マクシム」(辛辣な人間観察を含んだ格言、箴言)が紹介される。まさに「言葉の短刀」。ラ・ロシュフーコーとともに、パスカル、ラ・フォンテーヌ、ラ・ブリュイエール、E・M・シオランをも含めて、鹿島茂氏でなければできない圧倒的な力業の"悪のマクシム"。"社交する人間"で、他人には短刀かもしれないが、自分には「お前そんなカッコつけているけれど・・・・・・」とズバッと心の中を荒々しく掴まれるようだ。
仏の歴史と文化と伝統、神と人間と教会、欧州の戦乱・攻防――。その激しくも深く蓄積されてきた思想・哲学と社交の中から抉り出された人間学。ルイ14世の時代に生きた文人ラ・ロシュフーコーの「マクシム」(辛辣な人間観察を含んだ格言、箴言)が紹介される。まさに「言葉の短刀」。ラ・ロシュフーコーとともに、パスカル、ラ・フォンテーヌ、ラ・ブリュイエール、E・M・シオランをも含めて、鹿島茂氏でなければできない圧倒的な力業の"悪のマクシム"。"社交する人間"で、他人には短刀かもしれないが、自分には「お前そんなカッコつけているけれど・・・・・・」とズバッと心の中を荒々しく掴まれるようだ。
「人間は自己愛(ドーダ)に生きる動物であり、どんなに自己愛と無縁に思われる言動にも必ず自己愛が潜んでいる。『マクシム』はドーダから始まりドーダで終わる究極のドーダ論だ」という。「人はパンのみに生きるにあらず。褒め言葉にこそ生きるのである」「"面倒くさい"は日本人を律する最高のルールである」「人間の営為のすべては気晴らしにすぎない。楽しい労働もつらい仕事も、遊びも戦争も。気晴らしだけが人間を無為と倦怠という最悪の事態から救い出してくれる」「ドーダは死よりも強し」「好奇心も善行も虚栄心にほかならない」「『理性による承認』がなされたとき、初めて人は自尊心の十全たる満足を得る」「人々が感心する徳は2つしかない。勇気と気前のよさである(生命と金銭という2つのものを軽視しているから)」「ホームグローン・テロリストにある"極悪非道ドーダ"」「自我は『他人の栄光』が許せない」「妬み、嫉み、恨みは生命力の根源」「情念の最大の敵は『面倒くさい』」「自己愛はおのれを破壊もする」・・・・・・。
「耳をふさぎたくなる270の言葉」と副題にあるが、本当に(本当だから)グサッとくる。
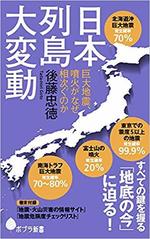 本書を読んでいるさなかに大阪北部地震が起きた。ついこの間は土木学会が、首都直下地震、南海トラフ地震、三大湾の巨大高潮、三大都市圏の巨大洪水を対象として「南海トラフ地震の20年累計の経済被害は1240兆円」「首都直下地震では731兆円」などという衝撃的な報告書を出した。東日本大震災、熊本地震から今回まで、日本を襲う大地震は確実に増え、活動期にあるようだ。
本書を読んでいるさなかに大阪北部地震が起きた。ついこの間は土木学会が、首都直下地震、南海トラフ地震、三大湾の巨大高潮、三大都市圏の巨大洪水を対象として「南海トラフ地震の20年累計の経済被害は1240兆円」「首都直下地震では731兆円」などという衝撃的な報告書を出した。東日本大震災、熊本地震から今回まで、日本を襲う大地震は確実に増え、活動期にあるようだ。
本書は日本の地底では何が起こっているのか、巨大地震や火山の噴火がどういう構造から起きているのかを、理学的見地から解き明かしている。「いま日本の地底で何が起こっているのか」「日本を襲う地震・噴火のメカニズム」「地底を知ることで見えてくるもの」「地震予知はどこまでできるのか」「地震の国・日本に住む私たちに、いまできること」の5章から成る。
2億5000万年前の超大陸「パンゲア」、海底だったヒマラヤとインドの北上、活断層の可視化、地底探査、海底電位差磁力計、コンピュータ・シミュレーション・・・・・・。きわめて興味深い。
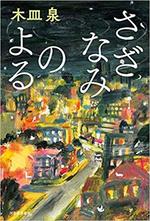 43歳、小国ナスミがガンで亡くなる。ガンは長い闘いであるだけに、人はある意味では強くなり、突き抜ける部分もある。「だからぁ死ぬのも生きるのも、いうほどたいしたことないんだって」――。もともと明るく、真っすぐ。
43歳、小国ナスミがガンで亡くなる。ガンは長い闘いであるだけに、人はある意味では強くなり、突き抜ける部分もある。「だからぁ死ぬのも生きるのも、いうほどたいしたことないんだって」――。もともと明るく、真っすぐ。
「ナスミは、好江の話をいつも自分のことのように聞いて、腹の底から怒り、バカみたいに喜んでくれた。腹立たしいことも、時間が経てば、二人は犬がじゃれあうようにそのことで大笑いした」。加藤由香里が上司からひどい仕打ちをしたことを知って2発、顔面に見舞ったりもした。「私がもどれる場所でありたいの。誰かが、私にもどりたいって思ってくれるような、そんな人になりたいの」「清には、ナスミと話したファーストフード店を思い出す。二人が悲しみの真っ只中にいたことを。あれは、悲しいけれど、少し甘酸っぱい時間だった」「あげたり、もらったり、そういうものを繰り返しながら生きてゆくんだ」・・・・・・。
ナスミは一人で死んで逝ったが、家族や友人一人一人には、さまざまな感情が渦巻く。感謝したり、涙したり、微笑ましく思い出したり、今の自分の中にナスミが住んでいることに気付いたり、夜はさざなみのように寄せてくる。


