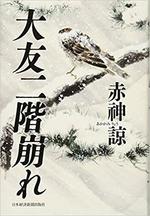 天文19年2月(1550年)、豊後大友家で起きた「二階崩れの変」――。当主・大友義鑑(よしあき)は後継となっていた長男・義鎮(よししげ)(後の大友宗麟)を廃嫡せんとし、愛妾の子・塩市丸に家督を譲ろうとする。家臣は義鑑派と義鎮派に分裂、熾烈なお家騒動へと発展する。そして義鑑と塩市丸は襲撃され落命する。家中での勢力争い、功名の競い合い、謀略の充満するなか、ひたすら大友家への「義」を貫こうとする義鑑の腹心である吉弘鑑理(あきただ)(義鎮の義兄でもある)と、運命的な出会いから楓との愛を貫く弟・吉弘鑑広(あきひろ)の姿を描く。
天文19年2月(1550年)、豊後大友家で起きた「二階崩れの変」――。当主・大友義鑑(よしあき)は後継となっていた長男・義鎮(よししげ)(後の大友宗麟)を廃嫡せんとし、愛妾の子・塩市丸に家督を譲ろうとする。家臣は義鑑派と義鎮派に分裂、熾烈なお家騒動へと発展する。そして義鑑と塩市丸は襲撃され落命する。家中での勢力争い、功名の競い合い、謀略の充満するなか、ひたすら大友家への「義」を貫こうとする義鑑の腹心である吉弘鑑理(あきただ)(義鎮の義兄でもある)と、運命的な出会いから楓との愛を貫く弟・吉弘鑑広(あきひろ)の姿を描く。
戦国武将の戦いや「二階崩れの変」自体がテーマではなく、吉弘鑑理・鑑広兄弟の内面の苦闘と葛藤、二人の「義」と「愛」へのこだわり、それゆえに生じた運命的結末が息苦しいほど迫ってくる。とくに「義」――。「この紹兵衛、やっとお仕えすべき主にお会いでき申した。変節常なき乱世で、己を顧みず、いかなる時も義を重んじられる殿に心底惚れましてございまする」「乱世なればこそ、義を貫かねばならぬのじゃ。不義を謗られるよりは、愚昧なりと嘲られるほうがよい。義は滅びぬ。義を貫かば、必ず後に続く者が出る」――。それに対して「愛」の鑑広の才から見ると「それは平時の話。乱世に義を貫くなぞ、愚の骨頂にございまする。義を貫いて滅びるは、ただの愚か者にござる」「昔から鑑理の人のよさは救いがたかった。鑑理が今生きてあるのは、人の"悪い" 鑑広が支えたおかげだろう」・・・・・・。
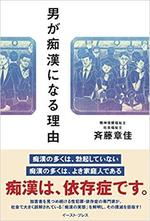 満員電車で日常的に痴漢が横行する日本。その汚名を返上し、誰もが安心して電車に乗れるようにするためには、「なぜ痴漢をするのか」「痴漢をすることで何を得ているのか」「どうすればやめられるか」を実態を把握して対策に乗り出すことが不可欠だという。
満員電車で日常的に痴漢が横行する日本。その汚名を返上し、誰もが安心して電車に乗れるようにするためには、「なぜ痴漢をするのか」「痴漢をすることで何を得ているのか」「どうすればやめられるか」を実態を把握して対策に乗り出すことが不可欠だという。
痴漢をする男性の多くは人間関係を苦手としている。「コミュニケーションが不得手で他者を尊重できない性質が、ストレスのはけ口を弱い者に求め、相手を征服、支配したいといった形で露呈するのが痴漢行為」だという。「平成28年中、東京で強姦は約140件、強制わいせつは約800件、痴漢は約1800件発生」と警視庁はレポートするが、数字に表われるのは氷山の一角。被害女性の9割近くが泣き寝入りをするというのが実態のようだ。
痴漢のリアルな実態は「四大卒で会社勤めをする働き盛りの既婚者男性」「痴漢は依存症。アルコール、ギャンブルと同じ」「痴漢を突き動かしているのは性欲だけではない。多くは勃起していない」「仕事、人間関係などのストレスがきっかけ、ストレス対処が下手」「痴漢はいじめに似て、女性がいやがることをし、追い詰め、傷つけ、征服し、優越感をもつ、男尊女卑の価値観がある」「"痴漢をしてもOKの女がいる"という歪み」「スリルとリスクがともなう"ゲーム"性を求める」「痴漢は"派手めの女性、勝ち気そう、頭がよく仕事ができそうな、毅然とした女性"を敬遠する。"逆らわない、黙っていそう、幼い感じの女性"をターゲットにする」「厳しく取り締まり、迅速に逮捕する有効な手段を社会全体で考えるべき」「逮捕されても"実刑にならない""示談ですむ"と再犯が多い」「痴漢は再犯率がずば抜けて高い」「"失敗した""家族等に迷惑をかけた"と反省しても被害者に申し訳ないと思い至っていない」「集中的治療プログラムの必要性」・・・・・・。再発防止の治療計画等を具体的に示している。
 前著「未来の年表」は、少子高齢社会にあって西暦何年に何が起きるかを「人口減少カレンダー」を作成して俯瞰した。統計は、データのとり方によって異なるものだが、前提も含めて相当綿密に分析してカレンダーに仕上げる力業に感心した。今回は違う。人口減少・少子高齢化が人々の暮らしにどのような形で降りかかってくるかを、生活に即して明らかにしている。そして、あわせて「今からでも始められる対策」を提示した。
前著「未来の年表」は、少子高齢社会にあって西暦何年に何が起きるかを「人口減少カレンダー」を作成して俯瞰した。統計は、データのとり方によって異なるものだが、前提も含めて相当綿密に分析してカレンダーに仕上げる力業に感心した。今回は違う。人口減少・少子高齢化が人々の暮らしにどのような形で降りかかってくるかを、生活に即して明らかにしている。そして、あわせて「今からでも始められる対策」を提示した。
焦点は、「高齢者の高齢化」「独り暮らしの貧しい高齢者」の急増、女性高齢者の増加だ。しかも年間出生数は100万人を切ったのに比し、死亡数は134万人(2017年)。2040年頃には167万人に及ぶ予測だという。「あなたの住まいで起きること(家庭内事故の増大、大都市のマンションの廃墟化・スラム化)」「あなたの家族に起きること(8050問題、貧乏定年)」「あなたの仕事で起きること(中小企業の後継者不足、親が亡くなると地方銀行がなくなる)」「あなたの暮らしに起きること(人手不足、商品が届かなくなる、灯油難民)」「女性に起きること(定年女子が"再就職難民"に、高齢女性の万引き問題)」・・・・・・。
戦略的にどう縮むか、そして人口減少・少子高齢社会、AI・IoT・BT・ロボットの急進展、エネルギー・地球環境問題の3つの構造的変化にどう立ち向かうか。
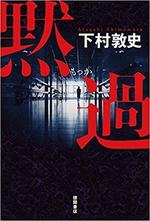 きわめてパワフルな力作。ミステリー性も面白い。テーマはしっかりして、問題提起が読後も残る。臓器移植、積極的安楽死、動物の生命と人間の生命の差異、異種移植というこれからの重大問題・・・・・・。要するに生命倫理をどう考えるか、それをサスペンスとして人間の究極の愛と生命の問題として問いかける。
きわめてパワフルな力作。ミステリー性も面白い。テーマはしっかりして、問題提起が読後も残る。臓器移植、積極的安楽死、動物の生命と人間の生命の差異、異種移植というこれからの重大問題・・・・・・。要するに生命倫理をどう考えるか、それをサスペンスとして人間の究極の愛と生命の問題として問いかける。
4篇と最後の一篇で成る。別々と思わせて4篇が最後の「究極の選択」に合流し、どんでん返しとなる。構成も刺激的だ。
第一篇の「優先順位」は臓器移植問題。意識不明の患者が病室から消えるという衝撃的な謎。次の「詐病」は厚労省事務次官が、"パーキンソン病"を演ずる。消極的安楽死ではなく、積極的安楽死問題が提起される。第三篇の「命の天秤」。舞台は感染対策をしっかりやっている養豚場。ところがある日突然、母豚の胎内から子豚が消えてしまう。動物愛護団体と種による命の選別問題。そして次は「不正疑惑」。真面目な学術調査官が「人間として赦されないことでした」として自殺に至る謎。そして最後の「究極の選択」。「異種移植は人類史上、最も罪深く、最も希望を孕んだ医療だろう」「命の倫理とは一体何だろう」と、真実の追求は、生命倫理、医学、家族愛等々の根源的問題へと収斂していく。
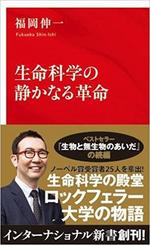 「生物と無生物のあいだ」「動的平衡」の福岡伸一さんが、ロックフェラー大学のノーベル賞受賞者たちと「生命科学」の最先端について対談する。そして最近の「社会的利益を実現し得る学問」への偏重に警鐘を鳴らす。そして、「生命科学の本質に立ち戻れ」「生命科学の本質は、生命とはいかなるものか、生命とはいかにして生命たりえているのか、そのHOWを解き明かす営みにあるはずだ」という。対談等のなかで、黙々と気の遠くなるような実験・研究を繰り返す研究者の日々が浮き彫りにされ、その謙虚、自然体、正確へひたむきな追求作業と科学の限界ギリギリを見つめて格闘する真摯な態度に感銘する。
「生物と無生物のあいだ」「動的平衡」の福岡伸一さんが、ロックフェラー大学のノーベル賞受賞者たちと「生命科学」の最先端について対談する。そして最近の「社会的利益を実現し得る学問」への偏重に警鐘を鳴らす。そして、「生命科学の本質に立ち戻れ」「生命科学の本質は、生命とはいかなるものか、生命とはいかにして生命たりえているのか、そのHOWを解き明かす営みにあるはずだ」という。対談等のなかで、黙々と気の遠くなるような実験・研究を繰り返す研究者の日々が浮き彫りにされ、その謙虚、自然体、正確へひたむきな追求作業と科学の限界ギリギリを見つめて格闘する真摯な態度に感銘する。
対談は印象深い。「ロックフェラー大学という『科学村』の強み」「誰もが公正に扱われるチームづくり」「将来のリーダーを見つけ出す嗅覚」「科学における最大の障害は無知ではなく、知識による錯覚」「どれだけ目立って、インパクトを与えられるか」など、いずれも傑出した人間の境地を感じさせる。
テーマは「生命とは何か」「生命科学は何を解明してきたのか?」だ。生命科学史上、20世紀最大の発見はジェームズ・ワトソン、フランシス・クリークのWCによる「DNAの二重らせん構造の解明(二重とは相補性による情報の担保)」。「遺伝子の本体はDNAである」としてその端緒を切り開いたオズワルド・エイブリー。そして脳がどのように世界をコード化しているかという大発見に至ったデイビッド・ヒューベルとトーステン・ヴィーゼル(HW)。
「奔放で真摯な研究姿勢は、今の私の身体に深く染みついている」と福岡さんは語る。そしてGP2(グリコプロテイン2型)遺伝子を追い、ついに生命を動的平衡と捉えるに至った戦いの歴史を語る。膵臓、消化酵素、情報の解体たる消化、消化管は生命の最前線・・・・・・。じつに興味深い。

